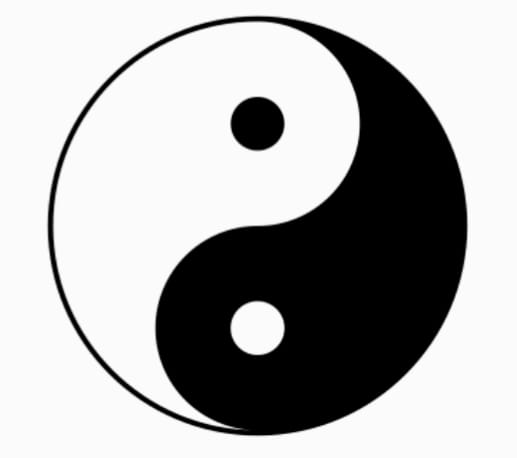
『妙見信仰』の起源
前回の妙見総本宮⛩️千葉神社で紹介した『妙見さま』について深掘り
歴史ミステリーの投稿。少し長めですが🙏興味のある方は御覧下さい。
✨✨✨ ✨ ✨✨✨
妙見信仰は中国の道教の信仰の一つで、天の中心にある北極星を崇める。
神道や仏教と習合しながらも、風水や五行といった古代中国独特の世界観を祭り
群馬・妙見寺、千葉・千葉神社、大阪・星田妙見宮、九州・足立山妙見宮など全国で「妙見さん」と言われ親しまれている。
【道教】
数千年の歴史がある中国の道教は、森羅万象、この世の理から人の生死や日常まで、理論学説と実践術が幅広く存在している。
道(タオ)、天帝、尊神、神仙思想にはじまり、延命長寿・不老不死、道徳教、天文学、陰陽五行、易術、風水、気学、薬学、仙術、符術、太極拳、気功術まで、
中国独特の歴史的な世界観や文化を包括しているパラダイム(常識値)であり、宗教だけには収まらない。
なので中国人は太極拳をやっているからと言って「道教徒」とは言わない。
道教の一部は二千年程前から宗教化が進んできたが、「宗教」と一言で言いきってしまうには未だ疑問もあり、西洋的な神を求める崇拝型宗教とは同じではない様だ。
元々東洋は、西洋の様に神そのものを求める宗教と違い、(神も含めて)森羅万象・宇宙の理を求めていた自然科学的なものだった。
その後の政策や宗教環境の変化により神々の存在が強く求められていくが、道教だけでなく、仏教も自然科学的な面があり(俱舎論)
宇宙の姿を克明に伝えている。
ブラックホールは黒龍、
銀河は蓮、
バルジは須弥山、
イベントホライズンは金輪際、
ボイドは虚空など、

当時の人々の言葉で宇宙の姿を理解しようとしていた事は確かだ。(観測でなく想像だけだと思うが😅何故か似ている)聖徳太子がこの世のことは全て「虚仮である」と語ったことも、理論物理学の「ホログラム宇宙論」を一言で現した様な言葉と言えなくもない。
【太極(太元)陰陽を生じ、四像八卦を生じる】

道教が言う「太元」とは万物の始まりの事で、「道」タオの本質であるという哲学だった。後に、宗教環境の変化に合わせ、哲学上の太元を ⇒ 太元尊神と呼び人格化して崇拝の対象となる様に創造主(万物主)という宗教的な存在にした。
道教は宗教環境の変化に合わせてこの様に、崇拝対象とする神々が生み出されていった。
妙見信仰も、元々は神ではなく北極星そのものが信仰対象だった。
中国では北極星を北辰と言い、
インド仏教の北斗七星の神である
『妙見菩薩』が中国に伝わると、
道教の『北辰』北極星の信仰と合わせて『北辰妙見』となった。
妙見さまは、仏教と道教の混合神だ。
千葉の千葉神社は妙見信仰の総本宮だが、妙見信仰はもともと西からはじまった説もあり東西の起源が分かれる。

(千葉神社)
大阪の星田妙見宮は、9世紀頃(800年~)空海の修法によって七曜の星(北斗七星)が降臨し祭られたという由緒で、
千葉の千葉神社は、一条天皇の眼病平癒の由緒があり西暦1000年に開山した。
平安時代初期(800年頃)と、
平安時代中期(1000年頃)、平安文化の特徴的な信仰の一つだ。
世界の宗教は太陽神ラー、アポロン、天照大神、ヴィシュヌなど、太陽を人格化して神話を作るが、
道教は人格化した神も作りつつ方位や天体そのものを祀っているのが面白い。
天体の中心で唯一動かない星、北極星=「北辰」、を『星の王』として祀り、天の中心である北辰は、日(太陽)・月・星を掌握し、人の死も司ると考えられていた。
【妙見信仰の始まり】
ウィキペディアでは、妙見信仰は飛鳥時代に百済・高句麗の渡来人によって日本にもたらされたと考えられている様だ。
これが、妙見信仰の始まりだろうか?
飛鳥時代と言えば、中国に百済・高句麗が滅ぼされた時代で、日本に多くの百済・高句麗人が渡来して来た。
しかし自国が滅ぼされた直後に、憎き敵国の信仰をわざわざ伝えたりしたのだろうか🤔
三蔵法師がインドから仏典を持ち帰ったばかりで、まだインド仏教と道教の神が習合していたとも思えず、
ようやく密教経典が編纂され始めた頃でもあり、早くも信仰対象として日本に伝わっていたとは考えにくい。
(※インドの密教よりも、何故か役行者の修験道の方が早く日本に広がり役行者が齎した可能性は考えられる🤔)
そして飛鳥時代の遣唐使など僧が伝えたていたのは、中国道教との混合仏教などではなく、三蔵法師がインドから持ち帰り伝えられた直伝の『法相宗』だった。
もっと以前の【北辰】とは、まだ妙見信仰ではなく天の中心であることから【天帝】を指して言う場合もあり政治用語の比喩として使われていた様だ。
信仰というより道教思想の知識として日本に伝わっていた様で、飛鳥時代の天武天皇は、道教の知識に通じていて
「真人」(仙人となった最高位の人のこと🧿)などの道教の呼称も政治的に用いていたので、高句麗系の天武天皇が、道教の知識としての「北辰」も日本に持ちこんだのかもしれない。
天武天皇は、陰陽寮という中務省の道教専門部署を初めて設置したが、「天文を讀み占星術を行い暦を作る」など国家の秘儀を扱う機密機関だった。
奈良時代になり、高句麗系の渡来人が東国に追いやられてしまった後、中央から目の届きにくい環境の中で、
政府直属レベルの道教の知識があった高句麗系の王族や博士、子孫の人々によって、もっと実用的な必要から妙見信仰は始まったのではないだろうか。
中国の神々は、時代が下った後に仏教勢力や貴族勢力に対抗する為に、武士勢力が積極的に用いた信仰である。
そうした意味では、中国の道教は仏教でも神道でもない第三勢力的な立ち位置であり、「妙見さま」は日本で最初に東国の武人が広めた中国系の信仰なのだろう。
【平将門】
平安時代は「武士」という存在はなく、まだ「つわもの(兵)」と呼ばれていた。
桓武天皇の子孫の高望王は「平氏」という姓を賜り臣籍降下し、清和天皇の子孫は源氏となり、地方で兵(つわもの)を動かす役割を担っていた。
その中の一氏族である千葉氏が妙見さまを氏神としたのも、戦さの度に祈願し、勝利をおさめたからという由緒があり、勝利の神としての信仰から広められたのだ。
苦戦時には「妙見菩薩により、七星剣を授けられた」と謳い軍を鼓舞して起死回生を図った。
(妙見信仰は、西日本の七夕、東日本の七星剣と、特徴が別れるのはその為なのだろうか🤔)
平安中期は「この世をば、我が世とぞ思う…」と詠んだ藤原道長の時代で、藤原貴族が中央を独占支配し、地方の任官・腐敗にも軋轢が生じる様になり、争乱が多発する様になった時代でもある。
兵(つわもの)を動かす機会が多くなるが、権勢の影響は更なる軋轢を生みだし天皇側も藤原朝廷を抑えよう様と心を砕いていた。
一条天皇が、わざわざ東国の香取神社の摂社でしかない千葉氏の「妙見さま」に病気平癒を祈り、「北斗山金剛授寺』と言う寺号を贈り開山させたのも千葉氏を支援する口実だったのかもしれない。
藤原氏が中央の要職を占めていた為に、他の貴族(天皇の降下貴族など)は差別され地方の兵になるしかなかった様な時代だ。
『つわもの』と言う呼び方も、本来は強者ではなく、
『兵は不詳の器(うつわ)=
武器を使うのは立派な人間のする事ではない』と言う意味の
「うつわ者」が語源らしく、謂わば蔑称だ。
一条天皇はその地方の天皇の子孫(つわもの)である千葉氏を何故、支援したのか。何故、千葉氏だったのか?
西日本の七夕と結びつけて考えられている妙見信仰と違い、
東日本の「妙見さま」は、千葉氏が勝利を祈願し、平将門と結びつけて考えたものでやや趣きが違う。
地方では人々は国司の横領の為、重税に苦しみ盗賊が横行していた。
しかし、中央は治安悪化を野放しにしたままであり、国司の利権争いも激化していった。
遂に平将門の乱や藤原純友の乱が起き、平将門は東国の人々の為に立ち上がったが、鎮圧に派兵された藤原秀郷や他の平氏に敗れてしまった。
平将門の兵の多くは圧政に苦しめられていた農民であった為、繁農期になり人々が農作業に戻って少数になったところを急襲された。

(平将門)
千葉氏の始祖である下総の平良文は、平将門の同族であり密かに平将門を助け、表向き朝廷側に立ちつつも将門の討伐には直接参加はしなかった様だ。
やがてその子孫の平忠常も圧政に対し反乱を起こした。
政情にもよるが、地方の人々の味方は、中央の敵である。中央は地方の利権争いを制御できず、平将門は闘争の渦に巻込まれていったが、中央からはたとえ反乱者の様に扱われていても、
戦で亡くなった東国の人々の御魂を安んじる為に、
生き残った人々が祈りを捧げたいという願いは当然あったのだろう。
平将門の家紋は妙見菩薩から授かったとされていた。
千葉氏も堂々と「平将門」を祀ることは出来なかった為、
表向きは「妙見さま」にして平将門を影祀りして、各地に広げていったのかもしれない。
 川崎⛩️馬絹神社
川崎⛩️馬絹神社
(平将門の側近だった興世王が討たれた時、里人たちがその馬の衣を拾って馬絹神社に収め、表向きは興世王ではなく熊野の神として祭った)
妙見さまは天の中心であることから「天御中主」という神道の神とも習合されて祭られているが、
天御中主は日本神話では創造主なのでどちらかと言えば、中国の「太元」=物事の始まりである根源的存在=太元「太元尊神」の方が近いと思う。が、
東国では「天御中主」も、アラハバキや国常立神など古い神さまの影祀りの御神名なっていることも多い。
平安中期は、つわもの(兵)の地方への土着の始まりと、中央からの任官の争乱の時期だったが、
その後、平安後期には
中央の権勢から離れ地方への土着が進み、つわもの(兵)から武士の時代へと変化していった。
中央を藤原氏に実効支配されてしまったこの時代。天皇側も、表向きは道教の神に祈りつつ
藤原朝廷を切り崩そうと
千葉氏が祭った
『妙見さま』(平将門)に願をかけたのかもしれない。

長い話しを
お読み頂きありがとうございました🙏
✨✨✨ ✨ ✨✨✨



















