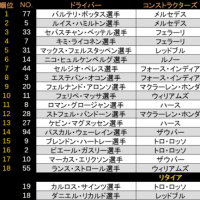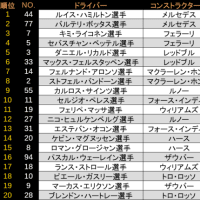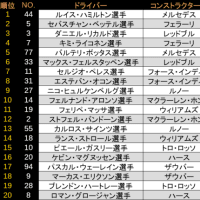Linuxのソフトウェアと言うのはGPLライセンスのモノが多く
GPLライセンス(ソースコードを公開する義務付けのあるもの)
で公開されており、コンパイルをして最新版のソースを使う事
も可能なんですが、開発言語を理解して要る場合、ソフトウェ
アの学習においてもいい教材が多く存在しているいい時代に
なっています。
こうした内容かrあ、Linuxディストリビューションには作業が
いきなりできるソフト群が揃ったパッケージが存在するのです
が、
■ UbuntuStudio
■ AV Linux
http://www.bandshed.net/avlinux/
などを使うと、マシンスペックはある程度上げておかないとダ
メですが、マルチメディア系のオープンソースのソフトがパッ
ケージングされています。
こうしたモノを日本語で使う場合には日本語ローカライズを
自分で行う必要があるので、日本語でインストールをしてもIM
Eやフォントの部分で日本語が存在していないので、日本語フォ
ントのインストール作業やiBusの設定もしくは別のIMEの導入
などを検討するなどの設定や日本語キーボードの設定などの
設定が必要になります。つまり、作るもオンがSTLやColladaや
FBXのような3D形状やCineonやOpen EXRなどのシーケン
シャルだったり、RAWやTiffなどの画像だったり、PCMなど音
声ファイルや、SMFによるMIDIや任意の形式の動画での書き
出しをする場合や編集作業だと全く日本語入力の登場する場所
はないですからほぼ影響は発生しません。
まぁ、あるとすれば日本語フォントを使った画像や3Dフォント
程度でしょうか。
結果的に、そうしたものが必要ないのは日本語ローカライズさ
れたものなんですが、ある程度割り切って使うとあまり影響がな
いものだと言えます。
軽快に動くものだと、
■ Knoppix
があるわけですが、LXDE環境なので、x64環境だと当然のように
軽く、x86-32でも軽く動くので、ローカル駆動で非ネット接続環境
でも軽く動く状態があります。
ネットに接続しない場合だと、不要なネットサービスをすべて削
除すればいいので、WINDOWS XP SP3よりも軽くなる状態が
あります。とりあえず、Knoppixをローカルオンリーでインストー
ルソフトだけで使った場合におけるメモリー消費は256MB以下
でGPUがIGPである場合には、メモリー消費量が増え、IGPの割
り当ての上限まで行くので(これはGPUの詳細を見ると確認可能)
増えてしまいますが、GPU実装かんきょづあとそうした内容が存
在しないので、メモリー消費量は相当抑える事が出来ます。
オープンソースのソフトは基本的にクロスプラットフォームで、
MAC OS-XのようにLinuxのモノがそのまま使える環境もあり
ますから、当たり前にOSに関係なく使えるものが存在しいて
います。
現在は、オフィースソフトもオープンソースのソフトが存在し、
■ Libre Office
を使うと、
■ ワープロ
■ 表計算
■ プレゼンテーション
■ ドロー系ツール
■ 数式エディタ
■ データベース
を使用する事が出来ます。つまり、上位のオフィースソフトと同じ
ソフトのパッケージングになっています。マイクロソフトオフィース
のようにゲーミングPCで処理するとGPUの処理能力を使って高
速になる物ももありますが、個人が使う上だと、当たり前に使える
状態があります。
と言っても、これに関してはJA福岡がマニュアル作成などもし
ており、ダウンロードをして機能を学ぶ事が出来ます。
■ JA福岡市
http://www.ja-fukuoka.or.jp/libre/
20世紀と違って、オフィースソフトと言うと現在は
■ 各社のアカウントを取得してクラウドを使う
(WINDOWS 10のものもそれ)
と言う方法もあり、簡素なモノだと、Googleのスプレッドシートを
使えば表計算が可能ですし、スマホやタブレットでもソレは可能
なので、時代錯誤があると既に終わり切っているわけですが、O
SSの利用についても結構前からそうした流れが公的機関でも
存在していますから、20世紀で頭が止まってる状態だったり、
数十年遅れてる状態だと現実と相当かい離しているので、そう
した痛々しい間違いを真に受けないようにする必要があります。
とりあえず、BASEがあるので、データベースを構築できるの
ですが、マイクロソフトオフィースのVBベースのBASICを使った
マクロとLibre Basicは互換性がないので(昔のマイコン時代の
BASICにおける方言のようなものがある。)その部分だけは注意
が必要なので、
【 プログラミングが出来る場合のみ関係してくる 】
のですが、ワープロや表計算をライトユーザー的に文字打ち状態で
入力する部分については単なるソフトに慣れてるか否か程度の話な
ので、この差はほとんど発生しません。ただし、データベースを構築
して【 アプリケーションを作る場合 】だとLibre BASICにおける
マクロの学習の必要が出てきます。ただし、これについてもJA福岡
市のサイトで配布しています。
レガシーなPCを日ネット接続の端末として使う場合だと、Kmop
pixを使うか、もしくは、ネットでLXDEを打¥運ロードしてデスクトップ
マネージャーをにするなどの方法があるのですが、基本的に、ソフト
の部分でもそうしたもがあ存在しています。現状で存在するソフトだと
■ 画像・オフィース
■ Libre Office(オフィースソフト)
一通りそろったオフィースの統合環境
■ Gimp 2.818(フォトレタッチ)
https://www.gimp.org/downloads/
平面処理においてフォトレタッチとペイントの
双方が可能なソフト。3Dレイヤーのないフォ
トショのようなイメージ。Script Fuによって機
能追加も可能。 アドオンも不K軸数存在してい
る。
■ Inkscape(ドロー系ツール)
パスを使ってシェイプを生成し、蛾図を作るドロー系ツール。
GIMPのようにドットを配置するラスターグラフィックではなく、
座標wおベジェ曲線で補間してラインを構築するベクターグ
ラフィックっ系ツールなんド絵、イラストレーターライクなソフト。
■ Krita
オープンソースのペイントツール。アニメーション機能も実装。
写真関連
■ RAW Therapee
オープンソースのRAW現像ソフト
多くの形式に対応。
■ Hugin
複数の写真からパノラマ画像の制作が可能な
ステッチソフト。マーカー調整で精度を上げること
も可能
■ Luminance HDR
http://qtpfsgui.sourceforge.net/
EVを変えて撮影した写真からHDRを作成する
トーンマッピングソフト
(*) TIFFやBMPをレイヤーを使って編集する場合にはGIMPを
使う事になります。合成前の素材制作がこれです。
動画編集・3DCG
■ Blender
動画編集・コンポジションなどが可能な3DCG統合
環境。ゲームエンジンを実装しており、ゲーム制作も
可能。(ただし、GPLライセンス)
音声は7.1chのハイレゾ対応。
(*)環境によって最新版のインストールが不能な
ので、Previous Versionから旧バージョンを
選択する事になります。ちなみに、ネットブッ
クは2.69で、Core i5 650だとIGPの場合、
2.7系でも少し前のバージョンまでになります。
■ MaheHuman
キャラクター生成ソフト
波形編集・作曲
■ Audacity
無制限トラック、無制限アンドゥ・リドクが可能な
非破壊系エンジン実装の波形編集ソフト。
VST Plugin対応で、エフェクトの追加が可能。
ノイズと波形を生成でき、エフェクトと形状変形に
よって音声を作れるため、ソフト単体で音を作成
可能。
オプションでサラウンド(サラウンド分のモノラルを
当ててそれを再再生用のチャンネルに割り当てる
事でサラウンドに出来る。7本のモノラルトラックだ
と7chのサラウンドが作れる。)
■ LMMS(DAW)
VSTi/VST Pluginの利用できるDAW。音源を
使った作曲だけでなく音声ファイルを読み込んで
曲作りも可能。また、ループ素材も複数用意され
ており、ASIDライクにループ音源で作曲が可能。
MIDI+音源と録音したオーディオでミックスが出
来る。イメージ的にはFL Studioっぽいつくり。
■ Ardour(DAW)
動画トラック対応のDAW。ログインしないとダウ
ンロードできないものの多機能なソフト
■ MuseScore(五線譜の譜面制作ソフト)
クロスプラットフォームで複数のパートの譜面を記
述が可能な譜面制作ソフト
PDFやMIDIの書き出しだけでなく、Sound Font
で音を鳴らし、オーディオでの書き出しにも対応。
■ Tux Guitar(TAB譜制作ソフト)
https://sourceforge.net/projects/
JAVA実行環境が必要なものの、TAB譜の打ち込み
が可能なソフト。コードやフレット票の譜面場への追
加が可能で、各減のコードや本数の変更が可能。
■ Hydrogen(シーケンサ)
http://www.hydrogen-music.org/hcms/
ループ素材用のドラムパターンを作成可能
別途ドラムキットをダウンロードする事によって
音を追加が可能で、個別にチューンも可能。
MIDIとCDDA音質のPCMでの書き出しが可能。
Linux環境だとオープンソースんお動画編集ソフトに
■ Kdenlive
なども存在している為、大抵のことは可能になっているわけですが、
基本的に、オープンソースのソフトをインストールするだけでも相当
色々できるようになっています。
ネット接続なしで使える条件だと、Ardourは消えるのですが、そ
ウした選択肢があります。また、クロスプラットフォームでオープンソー
スのモノには、ゲームエンジンも存在しており、
■ Godot Engine
様々なプラットフォーム向けに開発が行える2Dと
3Dに対応したゲームエンジン。
PlayStation 3やPlayStation Vitaといったゲ
ーム機用のゲームを開発できる。2014年1月に
オープンソースプロジェクト(1.0)となったソフト。
ライセンスはMIT Licenseを利用する。
2Dゲーム開発ではあらゆる解像度に対応でき
るスケーリング機能を持つほか、高機能なアニメー
ション編集機能も備える。
3DゲームではMax、Maya、Blenderなどから3D
モデルをインポートでき(Blenderのパス形状もCo
lladaでインポート可能。)、HDRレンダリング、スケ
ルトン作成などもサポートする。
Pythonベースのスクリプト言語やC++で任意のオ
ブジェクトの振る舞いをカスタマイズ可能。シミュレー
ション機能や2D/3Dでのアニメーション化、デバッガ
なども備える。
■ ALEPH One
【 日本語プロジェクトサイト 】
https://ja.osdn.net/projects/marathon/
一人称視点シューティング(FPS)ゲーム「Marathon 2」の
ソースコードをベースとしたゲームエンジン。
Marathon 2のほか、「Marathon」と「Marathon Infinity」、
それらの修正版に対応する。
Aleph Oneとこれらのゲームデータはすべて無料で配布
されており、SourceForge.netなどからダウンロードできる。
ライセンスはGPL 3。
■ Playground
http://www.klab.com/jp/press/detail/id=4676
スクフェスなどの同社の開発実績のあるゲームエンジン。
なども存在しています。戦時うtプログラミングにはソフトノコストがか
からない時代になっていると書きましたが、
■ NetBeans IDE
JAVA,C++のビルドが可能な統合環境。
などもあります。基本的に、個人が作業をする場合だと、オープンソー
スのソフトである程度機能する場合が多いのですが、何でもかんでも
散財すればモノが出来るという発作もちだとどうしようもないのは確か
で、10万円のソフトを使って、それが存在しない文明レベルの場所で
しか通じないような無能も時に居ますから、結果的に、そうした間違い
に行き着かないようにする必要があるのは確かです。
とりあえず、Linuxの場合、g++が入ってるか否か(というか、Fedo
ra CoreのようなRedhat系の場合、パッケージの選択ができるので、
サーバオンリーにすると最小構成でインストールが出来たりするので、
ディストリビューションでインストール時の選択が変わってくる)で変わっ
てくるのですが、それが入ってる場合だと複数の開発言語の事項やコ
ンパイルが可能なので、Linuxを使うとフツーにC++のコンパイルはで
きる状態になっています。あと、オープンソースと言うとコマンドラインで
すが、IntelのC++というVC++とg++互換のようなのもあるようです
から選択肢は複数あるようです。(ただし、開発言語ですから、安定して
いて確実性のある選択にする必要があります。)
ソフトの選択と言うのも、個人が学習して使えるようにならない事には
どうしようもないのですが、コストをかけて機能が多ければ、無知で何をし
ていいのか解らない人間でもモノが作れると言う訳ではないですから、基
本的に、【 学習できて出来る様になる事がが大前提 】なんですが、
安西したら何か凄い事が出来てるという貧困の反動で散在が酷くなって
る痛々しい無能のようなのが時に存在していますが、あれをまねてもロク
な事になりません。つまり、何が貧困なのかと言うのあh金銭ではなく知
性や能力や生物的な構造なわけですが、そうした間違いはしないほうが
いいのは確かです。
基本的に優勝のソフトの用途と言うのは、ライセンスの縛りがなく、その
ソフトを使って制作したものを商用利用が可能だとか、映像制作でいうと
対応コーディックの内容などもあるので、そうした点で有償のパッケージ
ソフトなんですが、個人が業務でも何でもない条件で考えるとバンドルソ
フト及びオープンソースで対応する方法も存在しています。これとフリー
ウェアの組み合わせても結構いろいろできるようになっているのですが、
PC側にインストールするもので考えると、ノート製品の場合だと、ローカ
ルで利用できるモノを多くしておいたほうが場所を問わず作業できるの
でいいかなと思います。
とりあえず、オープンソースでない物を含めると、選択肢はもっと多く
存在しているのですが、ピックアップするだけでもこれだけの量が存在
しています。