
高校野球!
今日の第四試合は富山第一対木更津総合です。
なんか、おもしろそうな本を見つけました。
三線教室と共通する部分が多々ありそうです。
コラムを紹介しておきます。
↓
いきなり言い訳になってしまうが、高橋秀実作品の面白さをレビューで伝えるのは、実は難しい。構成は徹底的に練られ、すべての章、すべての文が有機的につながっていて、その一部を取り出したところで、本全体が醸す、なんともいえない、そこはかとない面白さを伝えることができず、もどかしい気分になる。
なので、こう書くしかない。本書はとびきりに面白い。近年の作品の中では、一番ではないだろうか。もちろん小林秀雄賞を受賞した『ご先祖様はどちら様』も面白いし、『おすもうさん』も、「R25」に連載していた『結論はまた来週』も素晴らしい。しかし、それらを越えて、本書が、なんというか、一番しっくりと来る面白さだと思う。もしこのレビューを読んで面白い本だなぁと思ったとしたら、この本は、その何倍も面白いことを保証する。
著者が今回取り上げるのは開成高校である。
開成高校といえば、なんといっても「東京大学合格者数第一位」。生徒の4~5割が東大に行く、「賢い学校」という印象がある。その野球部と聞けば、さぞかし弱いだろう、とまず想像してしまうのだが、東京都大会でベスト16まで勝ち進んだという。すごい。でも、なぜ? と疑問も湧き上がる。
本書のタイトルおよびサブタイトルによれば、「弱くても勝てるセオリー」があるらしい。きっと体 力や練習時間、設備などに劣る超進学校の面々が、数学や物理を応用し、頭脳プレーやら高度なサインプレーやらを駆使して勝ち上がってゆく、そんな本なのだろう、と想像したのが、実際にページを開いたら、そんな安易の想像はまったく間違っていた。
まず、開成高校が平成17年全国高等学校野球選手権大会の東東京予選の戦績を見てほしい。
1回戦 開成10ー2都立科学技術高校(7回コールド)
2回戦 開成13ー3都立八丈高校(5回コールド)
3回戦 開成14ー3都立九段高校(7回コールド)
4回戦 開成9 ー5都立淵江高校
5回戦 国士舘高校10ー3開成(7回コールド)
なんというか、ものすごく大雑把な感じがしないだろうか?緻密さに欠ける、というか、もっと言ってしまえば、「賢さ」をまったく感じさせないスコアだ。著者はこう書く。「野球は9回裏まで何が起こるかわからない」という決まり文句があるが、開成の野球には9回がないのである、と。
著者が開成高校の練習を見に行った際の、最初の感想を記しておく。
下手なのである。
それも異常に。
内野ゴロが野手の股の下を抜け、球拾いをしている選手の股も抜け、壁にぶつかるまで転がり続ける。フライの落下点を誤って後逸し、走塁すれば足がもつれそうになる。キャッチボールでさえエラーするので、いつ球が飛んでくるかわからず、百戦錬磨の著者をして、「危なくて気が抜けない取材」だったという。
レフトを守る3年生は言う。
「内野は打者に近い。近いとこわいです。外野なら遠くて安心なんです」
彼は固い地面もこわいそうで、ヘッドスライディングができないという。
ショートを守る2年生が言う。
「僕は球を投げるのは得意なんですが、捕るのが下手なんです」
著者が「苦手なんですね」と相槌を打つと、「いや苦手じゃなくて下手なんです」と答える。そして「苦手と下手の違い」について淀みなく説明する。野球ではなく、国語の問題か?と思う著者。ちなみに開成中学校の国語の入試問題は選択式は一切なく、すべて記述式だそうだ。
そしてサードの3年生は胸を張る。
「エラーは開成の伝統ですから」
エラーしまくると相手は油断する。エラーは一種の戦略でもあるのだ。
そして個人的に一番気に入ったのは、2年生のピッチャーのこの一言
「実は、僕は逆上がりもできないんです」
念のため書いておくが、小学2年生ではなく、高校2年生である。
そんな面々が集う開成高校野球部の青木英憲監督がポジションを決める基準は極めて簡単だ。
・ピッチャー/投げ方が安定している。
・内野手/そこそこ投げ方が安定している。
・外野手/それ以外。
向き不向きで決めようとしたら、全員が野球に不向き、ということになってしまう。 監督が言うには、「存在してはいけないチームになりかねない」のだ。
ピッチャーに関しては、勝負以前に、「相手に失礼にならないことを第一に考えている」と青木監督はいう。
「球がストライクゾーンに入らないとゲームになりませんから」
開成高校野球部には送りバントやスクイズはない。そもそもサインプレーがなく、監督は大声で指示を出す。サインプレーをし、スクイズで1点取っても、意味がない。なぜならていねいに1点取ったところで、その裏に相手に10点取られてしまうからだ。
「送りバントのような局面における確実性を積み上げていくと結果的に負けてしまうんです」とは聡明なる監督の弁である。
そんな開成高校野球部の戦略は以下のようなものだ。
まず、1番から6番まで、できる限り強い打球を打てる選手を並べていく。もっとも強い打者は2番。そして、ひたすら強振する。一番チャンスがあるのは8番、9番 からはじめるイニングで、彼らがうまいことヒットやフォアボールで出塁した場合だ。下位打線を抑えられなかったことで動揺する相手ピッチャーに1番が強振して長打、そして最強の2番打者が打つ。弱いチームに打たれたことにショックを受けている相手を逃さず、後続がとにかく振り抜いて連打を食らわせして大量点を取るイニングを作り、そのままドサクサに紛れて勝つ、のだそうだ。
超進学校の勝てるセオリーは「ドサクサ」なのである。そして、実際そうやって勝ち上がってきたことは、冒頭の戦績で見た通りだ。
しかし、そんな開成高校野球部に、異変が起こる。平成19年の東東京予選。最初の試合は10-0と、開成らしい勝ちを収めるものの、続く試合は5-3、さらにその年の準優勝校となった強豪の修徳高校相手に0-1と善戦して負けた。
ちゃんと「野球」になっているのである。著者曰く、守備がうまくなったという。エラーという開成高校野球部の伝統を、彼らは捨ててしまったのだ。しかしながら、「野球」になってしまえば、週に1度しか練習できない開成高校は非常に不利とも言える。同じ土俵に経てば、「ドサクサ」は通用しない。
試合中、「野球をしようとするな!」という青木監督からの罵声が飛ぶ。「ピッチャーをしようとするな!」とピッチャーに指示を出し、ヒ ットを打っても「なんだそのスイングは!」と激怒。思いきりのよい空振りには「ナイス空振り!」と褒め、「ドサクサ! ドサクサ!」と連呼する。勝ったある試合の後には「これじゃまるで強いチームじゃないか」と怒りまくる。極めつけは「大体、打つのは球じゃない、物体なんだよ」とのお言葉。ほとんど禅問答である。
加えて生徒たちの言葉も不可思議だ。
例えば、サードの藤田くん
「大事なのは反省しないってことだと思うんです」(中略)
「反省してもしなくても、僕たちは下手だからエラーは出るんです。反省したりエラーしちゃいけないなんて思うと、かえってエラーする。エラーしてもいい。エラーしても打ちゃいいやって思うとエラーしない。といってもエラーしますけど、下手だから」
結局どうやってもエラーするんじゃん、とガクッとくる。理路整然と、なおかつやけに遠回りし、冷静に自分を客観視し、さらには客観視する自分をも客観視しているみたいだ。面倒くさいまでにいろいろ考えているのである。
続いて試合中、セカンドベースを踏み忘れたとして審判にアウトにされた尾島くん。
「踏んだと思うんですけど、たぶん」(中略)
「でもそれはあくまでも審判が判断することですから、実は2塁ベースを回るところで砂埃が立ったんです。審判はベースに砂埃が立つと『踏んでない』と判断するんです。審判が見て『踏んだ』と思われなきゃいけないんで、それは反省しないといけないんです」
そして彼は砂埃が立った理由も事細かに分析してみせる。しかし、そこは「踏み忘れたと判定されたけど、本当は踏んだ!」と腹を立てるべきところじゃないのか?と疑問が湧く。著者は「何を言っているのかよくわからなかった」「彼は勝負というより野球のルールにおける審判の存在理由について論じているのだろうか」と戸惑いを隠さない。
彼らの多くが、自分自身のことを、ひとつの現象のように観察し、分析する。そして、考えすぎ、すべての動きがワンテンポ遅れ、試合中もいつも出遅れているように見えるのだそうだ。
著者は、それを「は」と「が」の違いとして分析している。部員の多くは、「僕は◯◯なんです」と言う。まるで人ごとのように自分を冷静に見る。その「は」を「が」に変える。それこそが青木監督の思いなのだろう。
思い切り球を叩く、というのも、『僕が』でなけばできないのだ。
と著者は言う。そして、以下は青木監督の言葉。
「チームに貢献するなんていうのは人間の本能じゃないと思います」
「思いっきり振って球を遠くに飛ばす。それが一番楽しいはずなんです。生徒たちはグラウンドで本能的に大胆にやっていいのに、それを押し殺しているのを見ると、僕は本能的に我慢できない。たとえミスしてもワーッと元気よくやっていれば、怒れませんよ。伸びやかに自由に暴れまくってほしい。野球は『俺が俺が』でいいんです」
実は青木監督は選手時代、常にチームに貢献することを考え、送りバント、セーフティーバントの練習ばかりしていたという。その経験を経て気づいたことを、選手たちに託しているのだ。
「大人になってからの勝負は大胆にはできません。だからこそ、今なんです」
本当にそうだと思う。自分の楽しさのために、ただ思いっきりバットを振る。そんな素晴らしく心地良い経験は、大人げない大人ならいざ知らず、多くの人にとってなかなかできない。東大をはじめとする有名大学に進み、将来、国や企業の要職につくような開成高校の子たちならなおさらであろう。
そして、最終章では、平成24年東東京予選大会でベスト16進出に挑む彼らの姿が描かれる。「は」を「が」に変えるため、選手たちは思いっきりバットを振る。彼らの空振りが空気を震わせるさまは感動的でさえあり、「爆発の予感」を感じさせるのだ……。
読了後、僕は、開成高校野球 部の部員たちをすっかり好きになってしまった。彼らが「異常な」野球を続けている限り、彼らをぜひ応援したい。そしてとりあえず、小学2年生の息子のプラスティックのバットを借り、何十年かぶりに、思いっきり、素振りをしてみたのである。
なお、開成高校野球部の部員たちのことを、「考えすぎ、すべての動きがワンテンポ遅れ、(中略)いつも出遅れているように見える」と書いたが、それって、他の著書で描かれる高橋秀実の性格そのものではないだろうか?ヒデミネさんがあの野球部のなかにいてもまったく違和感はない。その親和性の高さも、本書がとびきり面白い理由のひとつかも知れない。
今日の第四試合は富山第一対木更津総合です。
なんか、おもしろそうな本を見つけました。
三線教室と共通する部分が多々ありそうです。
コラムを紹介しておきます。
↓
いきなり言い訳になってしまうが、高橋秀実作品の面白さをレビューで伝えるのは、実は難しい。構成は徹底的に練られ、すべての章、すべての文が有機的につながっていて、その一部を取り出したところで、本全体が醸す、なんともいえない、そこはかとない面白さを伝えることができず、もどかしい気分になる。
なので、こう書くしかない。本書はとびきりに面白い。近年の作品の中では、一番ではないだろうか。もちろん小林秀雄賞を受賞した『ご先祖様はどちら様』も面白いし、『おすもうさん』も、「R25」に連載していた『結論はまた来週』も素晴らしい。しかし、それらを越えて、本書が、なんというか、一番しっくりと来る面白さだと思う。もしこのレビューを読んで面白い本だなぁと思ったとしたら、この本は、その何倍も面白いことを保証する。
著者が今回取り上げるのは開成高校である。
開成高校といえば、なんといっても「東京大学合格者数第一位」。生徒の4~5割が東大に行く、「賢い学校」という印象がある。その野球部と聞けば、さぞかし弱いだろう、とまず想像してしまうのだが、東京都大会でベスト16まで勝ち進んだという。すごい。でも、なぜ? と疑問も湧き上がる。
本書のタイトルおよびサブタイトルによれば、「弱くても勝てるセオリー」があるらしい。きっと体 力や練習時間、設備などに劣る超進学校の面々が、数学や物理を応用し、頭脳プレーやら高度なサインプレーやらを駆使して勝ち上がってゆく、そんな本なのだろう、と想像したのが、実際にページを開いたら、そんな安易の想像はまったく間違っていた。
まず、開成高校が平成17年全国高等学校野球選手権大会の東東京予選の戦績を見てほしい。
1回戦 開成10ー2都立科学技術高校(7回コールド)
2回戦 開成13ー3都立八丈高校(5回コールド)
3回戦 開成14ー3都立九段高校(7回コールド)
4回戦 開成9 ー5都立淵江高校
5回戦 国士舘高校10ー3開成(7回コールド)
なんというか、ものすごく大雑把な感じがしないだろうか?緻密さに欠ける、というか、もっと言ってしまえば、「賢さ」をまったく感じさせないスコアだ。著者はこう書く。「野球は9回裏まで何が起こるかわからない」という決まり文句があるが、開成の野球には9回がないのである、と。
著者が開成高校の練習を見に行った際の、最初の感想を記しておく。
下手なのである。
それも異常に。
内野ゴロが野手の股の下を抜け、球拾いをしている選手の股も抜け、壁にぶつかるまで転がり続ける。フライの落下点を誤って後逸し、走塁すれば足がもつれそうになる。キャッチボールでさえエラーするので、いつ球が飛んでくるかわからず、百戦錬磨の著者をして、「危なくて気が抜けない取材」だったという。
レフトを守る3年生は言う。
「内野は打者に近い。近いとこわいです。外野なら遠くて安心なんです」
彼は固い地面もこわいそうで、ヘッドスライディングができないという。
ショートを守る2年生が言う。
「僕は球を投げるのは得意なんですが、捕るのが下手なんです」
著者が「苦手なんですね」と相槌を打つと、「いや苦手じゃなくて下手なんです」と答える。そして「苦手と下手の違い」について淀みなく説明する。野球ではなく、国語の問題か?と思う著者。ちなみに開成中学校の国語の入試問題は選択式は一切なく、すべて記述式だそうだ。
そしてサードの3年生は胸を張る。
「エラーは開成の伝統ですから」
エラーしまくると相手は油断する。エラーは一種の戦略でもあるのだ。
そして個人的に一番気に入ったのは、2年生のピッチャーのこの一言
「実は、僕は逆上がりもできないんです」
念のため書いておくが、小学2年生ではなく、高校2年生である。
そんな面々が集う開成高校野球部の青木英憲監督がポジションを決める基準は極めて簡単だ。
・ピッチャー/投げ方が安定している。
・内野手/そこそこ投げ方が安定している。
・外野手/それ以外。
向き不向きで決めようとしたら、全員が野球に不向き、ということになってしまう。 監督が言うには、「存在してはいけないチームになりかねない」のだ。
ピッチャーに関しては、勝負以前に、「相手に失礼にならないことを第一に考えている」と青木監督はいう。
「球がストライクゾーンに入らないとゲームになりませんから」
開成高校野球部には送りバントやスクイズはない。そもそもサインプレーがなく、監督は大声で指示を出す。サインプレーをし、スクイズで1点取っても、意味がない。なぜならていねいに1点取ったところで、その裏に相手に10点取られてしまうからだ。
「送りバントのような局面における確実性を積み上げていくと結果的に負けてしまうんです」とは聡明なる監督の弁である。
そんな開成高校野球部の戦略は以下のようなものだ。
まず、1番から6番まで、できる限り強い打球を打てる選手を並べていく。もっとも強い打者は2番。そして、ひたすら強振する。一番チャンスがあるのは8番、9番 からはじめるイニングで、彼らがうまいことヒットやフォアボールで出塁した場合だ。下位打線を抑えられなかったことで動揺する相手ピッチャーに1番が強振して長打、そして最強の2番打者が打つ。弱いチームに打たれたことにショックを受けている相手を逃さず、後続がとにかく振り抜いて連打を食らわせして大量点を取るイニングを作り、そのままドサクサに紛れて勝つ、のだそうだ。
超進学校の勝てるセオリーは「ドサクサ」なのである。そして、実際そうやって勝ち上がってきたことは、冒頭の戦績で見た通りだ。
しかし、そんな開成高校野球部に、異変が起こる。平成19年の東東京予選。最初の試合は10-0と、開成らしい勝ちを収めるものの、続く試合は5-3、さらにその年の準優勝校となった強豪の修徳高校相手に0-1と善戦して負けた。
ちゃんと「野球」になっているのである。著者曰く、守備がうまくなったという。エラーという開成高校野球部の伝統を、彼らは捨ててしまったのだ。しかしながら、「野球」になってしまえば、週に1度しか練習できない開成高校は非常に不利とも言える。同じ土俵に経てば、「ドサクサ」は通用しない。
試合中、「野球をしようとするな!」という青木監督からの罵声が飛ぶ。「ピッチャーをしようとするな!」とピッチャーに指示を出し、ヒ ットを打っても「なんだそのスイングは!」と激怒。思いきりのよい空振りには「ナイス空振り!」と褒め、「ドサクサ! ドサクサ!」と連呼する。勝ったある試合の後には「これじゃまるで強いチームじゃないか」と怒りまくる。極めつけは「大体、打つのは球じゃない、物体なんだよ」とのお言葉。ほとんど禅問答である。
加えて生徒たちの言葉も不可思議だ。
例えば、サードの藤田くん
「大事なのは反省しないってことだと思うんです」(中略)
「反省してもしなくても、僕たちは下手だからエラーは出るんです。反省したりエラーしちゃいけないなんて思うと、かえってエラーする。エラーしてもいい。エラーしても打ちゃいいやって思うとエラーしない。といってもエラーしますけど、下手だから」
結局どうやってもエラーするんじゃん、とガクッとくる。理路整然と、なおかつやけに遠回りし、冷静に自分を客観視し、さらには客観視する自分をも客観視しているみたいだ。面倒くさいまでにいろいろ考えているのである。
続いて試合中、セカンドベースを踏み忘れたとして審判にアウトにされた尾島くん。
「踏んだと思うんですけど、たぶん」(中略)
「でもそれはあくまでも審判が判断することですから、実は2塁ベースを回るところで砂埃が立ったんです。審判はベースに砂埃が立つと『踏んでない』と判断するんです。審判が見て『踏んだ』と思われなきゃいけないんで、それは反省しないといけないんです」
そして彼は砂埃が立った理由も事細かに分析してみせる。しかし、そこは「踏み忘れたと判定されたけど、本当は踏んだ!」と腹を立てるべきところじゃないのか?と疑問が湧く。著者は「何を言っているのかよくわからなかった」「彼は勝負というより野球のルールにおける審判の存在理由について論じているのだろうか」と戸惑いを隠さない。
彼らの多くが、自分自身のことを、ひとつの現象のように観察し、分析する。そして、考えすぎ、すべての動きがワンテンポ遅れ、試合中もいつも出遅れているように見えるのだそうだ。
著者は、それを「は」と「が」の違いとして分析している。部員の多くは、「僕は◯◯なんです」と言う。まるで人ごとのように自分を冷静に見る。その「は」を「が」に変える。それこそが青木監督の思いなのだろう。
思い切り球を叩く、というのも、『僕が』でなけばできないのだ。
と著者は言う。そして、以下は青木監督の言葉。
「チームに貢献するなんていうのは人間の本能じゃないと思います」
「思いっきり振って球を遠くに飛ばす。それが一番楽しいはずなんです。生徒たちはグラウンドで本能的に大胆にやっていいのに、それを押し殺しているのを見ると、僕は本能的に我慢できない。たとえミスしてもワーッと元気よくやっていれば、怒れませんよ。伸びやかに自由に暴れまくってほしい。野球は『俺が俺が』でいいんです」
実は青木監督は選手時代、常にチームに貢献することを考え、送りバント、セーフティーバントの練習ばかりしていたという。その経験を経て気づいたことを、選手たちに託しているのだ。
「大人になってからの勝負は大胆にはできません。だからこそ、今なんです」
本当にそうだと思う。自分の楽しさのために、ただ思いっきりバットを振る。そんな素晴らしく心地良い経験は、大人げない大人ならいざ知らず、多くの人にとってなかなかできない。東大をはじめとする有名大学に進み、将来、国や企業の要職につくような開成高校の子たちならなおさらであろう。
そして、最終章では、平成24年東東京予選大会でベスト16進出に挑む彼らの姿が描かれる。「は」を「が」に変えるため、選手たちは思いっきりバットを振る。彼らの空振りが空気を震わせるさまは感動的でさえあり、「爆発の予感」を感じさせるのだ……。
読了後、僕は、開成高校野球 部の部員たちをすっかり好きになってしまった。彼らが「異常な」野球を続けている限り、彼らをぜひ応援したい。そしてとりあえず、小学2年生の息子のプラスティックのバットを借り、何十年かぶりに、思いっきり、素振りをしてみたのである。
なお、開成高校野球部の部員たちのことを、「考えすぎ、すべての動きがワンテンポ遅れ、(中略)いつも出遅れているように見える」と書いたが、それって、他の著書で描かれる高橋秀実の性格そのものではないだろうか?ヒデミネさんがあの野球部のなかにいてもまったく違和感はない。その親和性の高さも、本書がとびきり面白い理由のひとつかも知れない。











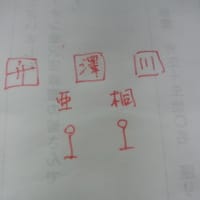








おもしろかったです。
川原師匠が指摘するように三線でも通ずるところが多々ありました。
それを5点ほど列挙します。いつも勝手な持論でしかも長文ですいません。
(1)試合では練習のつもりで投げろ・・・。というがそれができない。
「練習のつもりで」と思うことがすでに練習とは違っている。
某君は、「右肘を少し曲げて投げてみよう。」と思って投げる。
確かに練習の時にはそのような具体的なテーマを持って練習するわけだから・・。
三線も家で練習していると上手だけど皆の前だとまるっきり弾けない。
じゃ「練習のつもりで」と思ってみても効果なし。
具体的に「七の音だけでも正確に弾こう」とか考えて弾くと練習と同じに弾けるかも・・。
(2)エラーで反省はしない。
開成高校はエラーが伝統なので「エラーしちゃいけない」なんて思わない。
三線も同じですね。我々はアマチュアなのでエラーして当たり前、エラーしても反省しない精神が大切かと。
(3)監督曰く「野球はゲームにすぎない。やってもやらなくてもいいこと。単なるムダ。」
一般には、高校野球は人格形成、精神修養など様々に効用を述べたがるけれども、この監督の割り切りには感心します。
三線もそのように割り切れば、もっと楽しめそうです。
(4)素振りは戻しを早く正確に。
この監督は、バットを振ることより戻すことばかりを指導しています。
「正確に戻せるということは、正確に振っているということだ。」と。
三線も、初心者はバチを振りぬいて次の弦へ止めるのがなかなかできない。
これは戻しが正確でないからかと思ったりしています。そこで、
私は最近、初心者には「四上中」を掛け音で弾く練習を奨励しています。
これだと正確に戻せます。
(5)ムダな練習はしない。
開成高校は、野球部の専用グランドはなく週一回しか練習できないので、必要なことだけ集中して練習する。
ピッチャーはストライクを投げること。バッターは強振すること。のみ。
バントだの、ダブルプレーだの小賢しいことは練習しない。
シンプルでいいですね。
三線も難しいこと考えずに、いい音出すことだけシンプルに追及すればいいのかと・・。