各地の集落に「庚申塔」の石仏が建っている。あまりにも見慣れた風景なのか地域住民は特に関心を示さない。川連集落には秋田県内で最大と言われる「庚申供養塔」がある。県内を調べたわけではないが今から10数年前、地区の役をしていた頃一つの電話があった。象潟町の本藤さんと言った。川連の集落を回っていたら「庚申供養塔を見つけた。新しいしめ縄があり奉りをしたらしいので詳しいことを聞きたい」ということだった。毎年5月地域の講でまつりがおこなわれ、その祭りを司る宮司さんを紹介した。下記はその時の秋田魁新報の記事だ。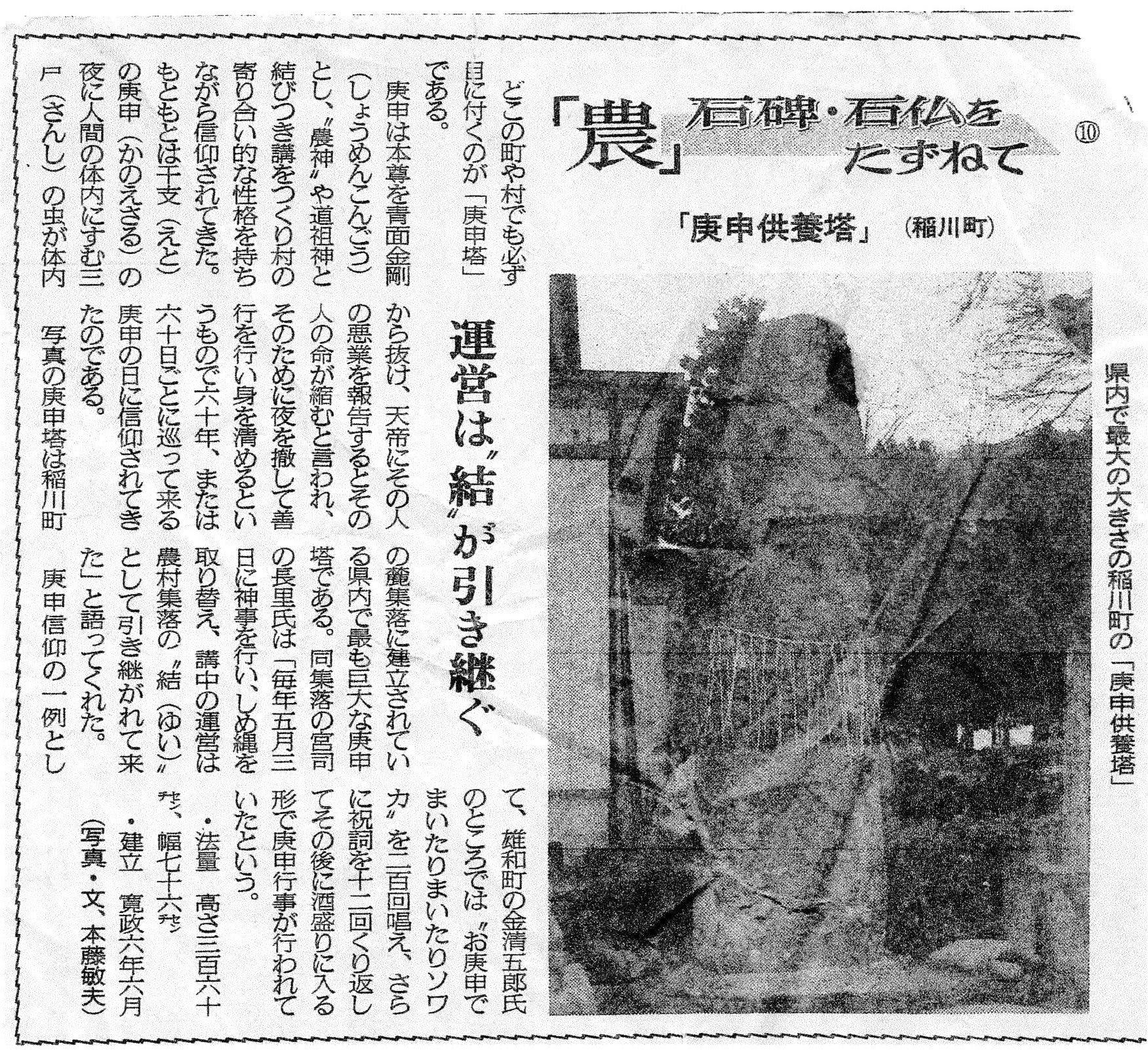
秋田魁新報「農」石碑・石仏をたずねて 「庚申供養塔」(稲川町)
この記事によれば秋田県内で最も巨大な庚申塔だと記されている。法量(仏像の大きさ。立高・座高を髪際から測り、丈六・半丈六・等身などとよぶ) 高さ360㎝ 幅76㎝ 建立寛政6年6月(1796)とある。風化が激しく現在は建立年月日の判読は困難になっている。この石と同じ石質の石は集落内にはない。推定で2トンもあろうと想われる巨大な石をどこから運んだのだろうかと興味は尽きない。石碑の文字の庚の部分に斜めに亀裂があり、セメントで補修されている。いつの頃にどのようにして修復補修されたのか知っている人は集落にいない。一部に陸羽地震、明治29年(1896)説もあるが確かなことかわからない。
川連「庚申供養塔」2013.4.16
庚申供養塔とは大辞泉によれば「庚申(かのえさる)の日、仏家では青面金剛または、神道では猿田彦の神を祭り、徹夜する行事。この夜眠るとそのすきに三尸(さんし)が体内から抜け出て、天帝にその人の悪事を告げるといい、また、その虫が人の命を短くするともいわれる。村人や縁者が集まり、江戸時代以来しだいに社交的なものになった」とある。仏教で「青面金剛童子」や「帝釈天」、神道では「猿田彦」の名で庚申塔が建っている。
八坂神社境内にも「青面金剛童子」150㎝、95㎝、75㎝三体ある。寛政4年(1792)建立「寿命長久」は当時の人々の不老長寿の祈りのしるしと云われている。上野の八幡神社に「庚申供養塔」高さ150㎝、「青面金剛童子」高さ140㎝がある。こちらは天明5年(1785)に建立されている。さらに市道野村~川連と上野からくる十字路に約70㎝ほどの「庚申塔」がある。建立年はわからない。この場所にかつて通称「宿の番小屋」が建っていた。
八坂神社「青面金剛童子」三体 2013.7.15
県内最大と云われる「庚申供養塔」、八坂神社内の「青面金剛童子」も寛政年代の建立。
八坂神社はかつては現在地から約400mほど離れた所にあったと云われている。秋田佐竹藩主の臣で横手城の岡本代官が来村の際「立派な社を造るように」と命じられ、社殿が創建されたと言い伝えがある。2011年豪雪で損傷した八坂神社。一部解体したら二つの「束」に墨で寛政12年(1800)の文字と川連村 大工棟梁 虎吉の名があった。八坂神社の寛政12年の創建が明らかになった。 大雪被害補修の八坂神社 中央の左のブナの横の石塔が「青面金剛童子」2011.08.28
大雪被害補修の八坂神社 中央の左のブナの横の石塔が「青面金剛童子」2011.08.28  束の文字 寛政十二歳 かのえ申 八月二一日 2011.08.28
束の文字 寛政十二歳 かのえ申 八月二一日 2011.08.28
湯沢市稲庭町の約5mもある巨大な「青面金剛童子」塔は寛成12年(1800)で、「青面金剛童子」では秋田県内最大のものでないかといわれている。川連「庚申供養塔」から6年後建立。稲庭町の「青面金剛童子」と川連の「庚申供養塔」は6㌔程しか離れていない地域で、なぜ巨大さを競って建立したのだろうか。
この庚申(かのえさる)の日というのは、暦に従って60日おきにめぐってくる。たいていの年は、一年に6回、庚申の日がある。旧暦では平年は353~356日、閏年は383~385日あるので、年によっては、一年に庚申が5回しかなかったり、逆に7回あったりするということも起こる。これらは、それぞれ「五庚申の年」「七庚申の年」などと呼ばれて、人々によって特別に意識されていた。寛政の七庚申は寛成3年の年。寛政12年は60年一回の庚申(かのえさる)の年。
「五庚申の年は不作、七庚申の年は豊作」と言われている。七庚申も不作との説もあり、五庚申や七庚申の年に「庚申塔」、「青面金剛童子」を立てるという習わしが、東北地方にあったとされる。川連の「庚申供養塔」は六庚申の年、稲庭の「青面金剛童子」建立年は寛政12年(1800)の庚申の年だった。
庚申塔の造塔は、享保年間(1716~36)、安永年間(1772~81)、寛政年間(1789~1801)と3つのピークがあったとされる。文字塔では安永を境にしてその数を増そうとしている。安永年間までの文字塔 では、「庚申供養塔」としたものが多いのに対して、天明年間(1781~89)や寛政年間には、ほとんどの塔が「庚申塔」としているのが多いと一般的に云われているが川連の県内最大と云われる寛政6年建立のは「庚申供養塔」となっている。
「天明の大飢饉」(1782年から1788年)があった。天明3年3月12日(1783年)岩木山が噴火。同年7月6日浅間山も噴火する。東北地方の冷害や、悪天候は1770年頃から続いていたらしく、両山の噴火は、東北地方に壊滅的な打撃を与えた。東北地方の農村を中心に、餓死者が全国で数万人(推定で約2万人)と云われている。
この年代に集中して建立されたのに、「寛成の改革」との関連性があったのではないかと推論してみた。寛政の改革は、天明7年(1787)から寛政5年(1793)に松平定信によって行われた改革。田沼意次に代わり政権の座についたのは、8代将軍 吉宗の孫である松平定信でした。この松平定信が行った改革は吉宗による享保の改革を理想としたもので、非常に堅苦しいものだったと言われている。
寛政の改革は、どのような結果を生んだのか。「世の中に蚊ほどうるさきものはなし、ぶんぶといふて夜もねむれず」、「白河の清きに魚のすみかねて、もとのにごりの田沼こひしき」という落書が示すように、松平の政治は非常にクリーンでまじめだけど、賄賂などで濁っていた田沼の時代のほうがよっぽど生活しやすかった。あまりに厳しい統制で、不満が高まり、しかも改革自体が反動的なものであったために、松平定信は僅か6年で失脚。寛政の改革は失敗に終わる。
飢饉と改革の失敗は庶民の暮らしは一体どう影響したのだろうか。この時代「庚申供養塔」の建立、「八坂神社」の再建には川連集落、麓の住民には多くの浄財が課せられたこと想像される。庚申は60日毎。他「十八夜塔」、「二十三夜塔」は毎月訪れる。十五夜から八日過ぎた二十三夜の月は、真夜中頃に東の空から昇る。1日で約50分月の出が遅れるので真夜中まで一緒に行動を共にし、絆を確かめ合った。各地でこれらの石塔の建立がこの天明の飢饉から寛成時期前後に多いのはそれなりの理由があることなる。
抑圧されていた庶民に一揆が起こることを憂慮して、集会は悉く制限されていたと云われていたこの時代。庚申の日や十八夜、二十三夜の夜はこれらの塔の前で夜を徹して集まりに制限がゆるやかだったと云われている。もしかしたら各地に、この時代「庚申塔」の建立が多かったのは多くの庶民の反動の意があったのかもしれない。
県内最大と云われる「庚申供養塔」の前を通ると、210余年前の川連の暮らしを思い浮かべる。
今でも岩清水観音様の例祭の日に「庚申供養塔」にしめ縄を飾り、祝詞が奉納される。今年のまつりは5月11日だという。
最新の画像[もっと見る]
-
 50年後の道路再舗装
5ヶ月前
50年後の道路再舗装
5ヶ月前
-
 50年後の道路再舗装
5ヶ月前
50年後の道路再舗装
5ヶ月前
-
 50年後の道路再舗装
5ヶ月前
50年後の道路再舗装
5ヶ月前
-
 50年後の道路再舗装
5ヶ月前
50年後の道路再舗装
5ヶ月前
-
 50年後の道路再舗装
5ヶ月前
50年後の道路再舗装
5ヶ月前
-
 麓集落 戸数の減少
1年前
麓集落 戸数の減少
1年前
-
 麓集落 戸数の減少
1年前
麓集落 戸数の減少
1年前
-
 麓集落 戸数の減少
1年前
麓集落 戸数の減少
1年前
-
 麓集落 戸数の減少
1年前
麓集落 戸数の減少
1年前
-
 麓集落 戸数の減少
1年前
麓集落 戸数の減少
1年前

















