一年に一度の投稿・・・。
ちょうど、このブログを書き始めたのが10年前。
環境の取組みをはじめて、バックキャストで考える事、資源の採取から製造 利用 廃棄までというライフサイクルアセスメントという思考が大切な事を学ばせて頂いた。
読み返してみると、なんと 当時は夢だと思っていた事が確実にかなっている!
例えば・・・
地元の木で出来た印刷用紙やコピー用紙が作れるようになって 使えるようになって
多賀町の広報誌にまで活用してもらえるようになっていたり
古い建物を活かす住まいづくりにも取組んだり
すっかり忘れていたが CO2も半分削減したり
http://blog.goo.ne.jp/jjjko0313/e/34d00c5c26fc712290c4485e719700f2
何より、ほぼ100% 国産材を使った家づくりが出来るようになった。
(すべて、他力本願だけど(笑)感謝・感謝)
森林の方も、まだまだではあるが地元の木が流通するようになり
森林所有者の把握にむけて国が動き出したというニュースも目にした。
ライフサイクルアセスメントから考えると 森林や木材は資源の採取に対してどうかという「はじまり」の部分になる。
建築は「製造・利用」に対して、どうかという取組みになる。
耐震や省エネというのも その中の一つの要素だ。
ここが、今 工務店として取組んでいるところ。
そして、昨年 廃棄に対して あまりにも無頓着だったという事に気づかせていただいた。建物を廃棄する(解体する)に至るまでのアプローチが出来ていなかった…。
ちゃんと分別して捨てるという意味ではなくね。
作る時から考えなくてはいけないのに。
わかりやすい話だと「空き家」の問題もその一つ。
これは、物の作り方や流通とか自社で何とかなる問題ではないけれど
「空き家」になる前に、出来ることがあるのではないか、私たちの業界は空き家予備軍を今もつくり続けているのではないだろうか…とか、問題の深さ広さの現実を目の当たりにしつつ、手探り中。
と、いう事で 今までの活動プラス、「まもる。つなぐ。しまう。」という最終ステップに取組みたいと思っております。
ザックリしすぎの宣言ですが・・・











 やっぱりだめかしら?(笑)
やっぱりだめかしら?(笑)
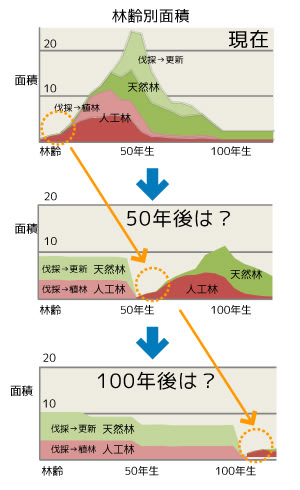
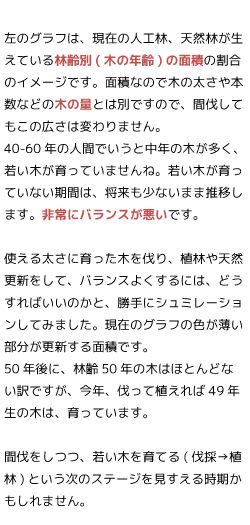










 な
な



