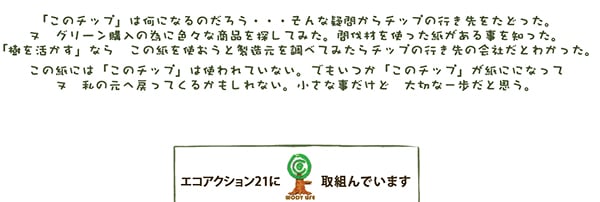この春に完成しました 写真の滋賀県の多賀中学校のランチルームにて
kikito 湖東地域材循環システム協議会
第5回 びわ湖の森ローカルシステム専門委員会が 7月31日(火)に開催されます。
http://www.kikito.jp/pjreport/certification/201207063346.html
この委員会や会場となるランチルームの建築に至る過程は、小さな地域の方にとって参考にして頂けるかもと思うと共に 色々な制度の問題点も浮き彫りにしてくれるのではないかと思い、少しご紹介したいと思います。
(個人的に書いております。私は、ただのkikitoの一メンバーにすぎません。あしからず)
この委員会では、地域の森林のCO2吸収と木材のCO2固定認証を検証して頂いて参りました。
今回は会場となる多賀中学校のランチルームのCO2固定認証も行われます。
「公共建築物等木材利用促進法」に基づき 多賀町の木材が使用され、滋賀県の森林税も利用された建物です。
1.びわ湖の森ローカルシステム専門委員会
森林のCO2吸収に関しては(カーボン)オフセット・クレジット(J-VER)制度というのがあり、通常は、都道府県J-VERプログラム認証というのを利用するのですが、ローカルとありますように「独自」になったのは、この制度が出来る前に始めた事とkikitoが存在する意味を考えた時に、民間の力を借りながら 私たちの身近な森を元気にしていくには公的な支援が入りにくい、民間の小さな面積の集まりである森林こそ 一番何とかしなければならないとの想いからです。
与えられた制度では 既にまとまりのある(公的な)森林の広い面積しか認められなかった事、又、クレジットを利用して頂く側も 大企業でないと参加できず、出来るだけ身近に利用して頂ける制度にしたいとも考えました。
CO2という見えないものを取り扱うのは、ちょっと胡散臭そうに思えるかもしれませんが、本音は山の事をあきらめたり、興味のない森林所有者やその跡継ぎの方と、川下の皆さんをつなげる為の「森や木の見える化」の為のひとつの取組みと、私は思っています。
町の人や若い人・企業などから興味を持ってもらえる事は、山の人にとって 少し森林が「キラキラ」見えてくるんですよね。
kikitoに関しましてはHPをご覧頂ければと思いますが、林業→建築までの地域の木に関わる業種で構成されています。公的機関ではないところがミソです。
2.公共建築物等木材利用促進法
通常、大きな公共工事はゼネコンが落します。設計も大きな事務所です。
すると、先に価格が決まり、下請け・孫請けに渡り 川下から利益を引いていくと 木材はたたかれ その木材を生産している「地域の森」には 真っ当な価格が還らないという事になります。
入札で落してから、建築業者は「地域材」を探しまわります。普段、大量に流通ストック・乾燥されていないものを短期で集めるのは至難の業です。地域の事情を考えると公共工事に使われる木材は、住宅建築とは違う寸法やスペック、民間の流通に支障をきたす発注などという問題も起こりかねません。
地域の木や日本の木は使われるけれども、例えば使う為に伐採した跡地に植林をする為の資金も残らないという事も起こります。地域で営みをしている製材所や大工、工務店、設計事務所も通常はカヤの外です。使えばいい というものではなく、地域の木を使うという事は、その森林や地域の人、伐り旬や乾燥期間など 今までの公共工事とは違う根回しの必要性を感じていましたところ、地元で しかも 私の母校で 全国に誇れる「公共工事」が行われました。
3.多賀中学校ランチルーム
設計は 多賀町のいくつかの設計事務所の協同体「設計同人社」です。大きな設計事務所でなくても、こういう形で地元の公共工事に参加できる資格を作られています。多賀で暮らしておられる設計事務所の方のプランは、とても「地域思い」だということを ひしっと感じました。
1.木材に関しては、町からの支給という形をとり、入札からはずした事。
この事により、町として守るべき地域の森林・林業にしわ寄せをせずにすみます。
2.地域の木が出せるかという事を森林側と話をつけて プランや工程を組んだこと。
3.建築家としてすばらしいと思ったのが、地域の木材で地域の大工さんにも加工できる工法を考えられたこと。
150×180×2M の木材を基準とし、かつ構造用合板の大きさに合わせた寸法でローコスト・ロングスパンが可能な「すだれ工法」を考えられました。町の予算 つまりは 自分たちの支払っている税金も有効に活用する事にも配慮されています。
県立大で多賀木匠塾をされている「設計同人社」中西先生を中心に「設計事務所」の仕事の範囲を超えて、取組まれている姿勢には、本当に感動たしました。
中西先生とは、湖東流域森林づくり委員会でご一緒です。
今回、このランチルームのCO2固定認証を受けようと提案されたのは、「設計同人社」とkikitoのメンバーでもある Aサイトさん。木材も kikitoのメンバーである大滝山林組合の木です。
大量に安定供給できない事が「日本の木を使わない理由」とされて、林業に変革を求められているのですが、建築側にも変わる事を求めてもよいのではないでしょうか。ちなみに、木造住宅でハウスメーカーがしめる割合は、たった15%ほどで、後、85%は 地域の工務店です。地域で公共工事が年間どれほどあるのかという事を考えても「建築からの歩み寄り」も必要だと、kikitoで「森林側」の皆様の実状を聞き、敵(笑)と見られがちな「建築側」も感じております。林業の方が、森林→原木市場までの事しか考えていなかったらこういう関係は築けなかったことと思います。