すごく、のんきなペースの更新ですが 今年も どうぞよろしくお付き合い下さいませ。
今日は、CMです。 色々なメディアで お知らせしているので 「しつこいんだよーー」と 思われる方もお見えかもしれませんが、お許し下さいませ。
明日 2012年1月14日(土)15日(日) と 滋賀県の多賀町多賀にて オープンハウスを開催します。
ここで、使われている何本かの木は ほんと近くの森の木です。
育てて頂いた山主さんも 生えていた場所も知っています。
長い時間をかけて、自社で伐採し天然乾燥させてきました。
杉・桧・地松・栗・欅・桜・もみ・栃・松・桐・漆・和紙・土・・・
合板も集成材も、滋賀の木や日本の木。
適したものがなければ、輸入木材もつかう。でも、ほとんどは この国で育った木。
適材適所と 大胆な「木づかい」。
木材と ひとくくりにする建築って おかしいと心から思える。
金属にも 鉄・アルミ・銅 とあるように それぞれの樹種はそこに適する性能として選ばれ、一番 適した形に加工され、家を構成する部材となる。
「近江の森と樹を活かす家づくり」
心から、取り組んでよかったと思える 住まいが完成しました。
明日14日(土)の朝の湖東地域の新聞に折込チラシが入ります。
チラシのPDFを含め、地図等は こちらをご覧ください。










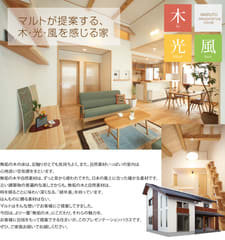
 。
。














