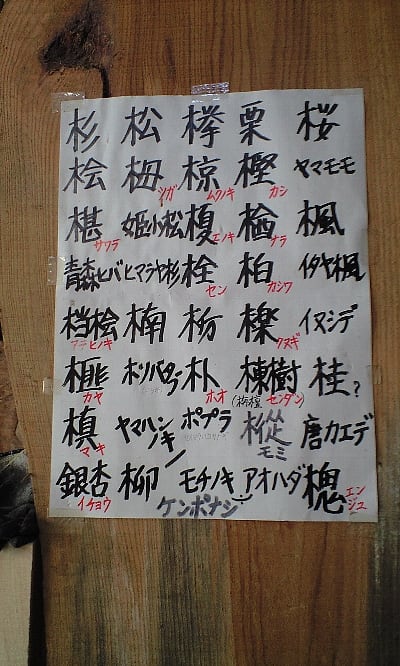消費者のニーズだとぉ。
山も守れだとぉ。
手入れができてないだとぉ。
植えすぎた だとぉー
と 山の人は 怒ったりしない。
自分たちも 悪かったと思っているし
そう 思わされているからだ。
でもね もう 山の人を責めるのはやめにして欲しい。
恩恵を受けてきたのは、日本の川下の消費者だ。
これ以上 コストダウンとか 安定供給だとか
努力が足りないとか 言ってはいけない。
後 数年したら
植えすぎて生態系を壊したとか
そのせいで花粉症になった とか 言っている
悪行にされていた 戦後の大造林が もう少し長い目や
更に悪くなっている地球の環境を思えば
感謝する日もくるのではないかと 思っている。
日本の森林の半分は、個人の山だ。
すでに 山がなくったって生きていける人が大半である。
うちの山がどうなろうと かってでしょと言われればそれまでだ。
上から ものをいう事だけは ほんと やめようね。
どうしても言いたい人は、真っ当に 日本の樹を使って
植林なり 手入れなりできる対価を払ってからに
しましょうね。
と 言っても そんな 具合にいかないのが
今の世の中である。
しかし 山の人にだけ しわを寄せるわけにはいかない。
と いう事で あーしたい こうしたい こうなればなぁと思っていたことが
ここにきて パタパタっと 動き出してきたの。
山も守れだとぉ。
手入れができてないだとぉ。
植えすぎた だとぉー
と 山の人は 怒ったりしない。
自分たちも 悪かったと思っているし
そう 思わされているからだ。
でもね もう 山の人を責めるのはやめにして欲しい。
恩恵を受けてきたのは、日本の川下の消費者だ。
これ以上 コストダウンとか 安定供給だとか
努力が足りないとか 言ってはいけない。
後 数年したら
植えすぎて生態系を壊したとか
そのせいで花粉症になった とか 言っている
悪行にされていた 戦後の大造林が もう少し長い目や
更に悪くなっている地球の環境を思えば
感謝する日もくるのではないかと 思っている。
日本の森林の半分は、個人の山だ。
すでに 山がなくったって生きていける人が大半である。
うちの山がどうなろうと かってでしょと言われればそれまでだ。
上から ものをいう事だけは ほんと やめようね。
どうしても言いたい人は、真っ当に 日本の樹を使って
植林なり 手入れなりできる対価を払ってからに
しましょうね。
と 言っても そんな 具合にいかないのが
今の世の中である。
しかし 山の人にだけ しわを寄せるわけにはいかない。
と いう事で あーしたい こうしたい こうなればなぁと思っていたことが
ここにきて パタパタっと 動き出してきたの。