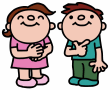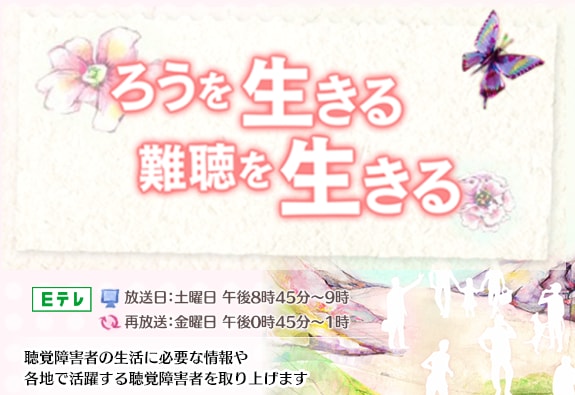パンフレット『みんなでつくる手話言語法』はご存知ですね。
まだ持ってない人はいませんか?
パンフレット『みんなでつくる手話言語法』は完売いたしましたが、本会事務局にまだ在庫があります。
私たちの先達が守り通してきた大切な宝である「手話」の法定化を実現するときがきています。
手話言語法って何?
ぜひこの本を読んで勉強しましょう。
A5判・56ページ 定価500円(税込)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
情報・コミュニケーション法の対象者は、
ろう者、難聴者、中途失聴者、盲ろう者などの聴覚障害者のほか、
視覚障害者、知的障害者、発達障害者など、
情報とコミュニケーションの支援が必要な
すべての障害者となる予定です。
選択と保障が中心となります。
コミュニケーション手段は、手話のほか、文字、触覚による
意志伝達などが含まれます。
ろう者がろう者の手話である言語を獲得し、
使用する権利のひとつとして、情報へのアクセスおよび
コミュニケーション手段の選択が位置づけられます。」
「手話言語法制定の取り組みはそれらの前提となる
ろう者の手話に焦点を当てています。
ろう者の立場から手話言語法制定を進め、
手話の法的な位置づけをしっかりとしたものに
することによって、他の法律もろう者の意志を
正しく反映するように導いていくことができます。」
(パンフレット『みんなでつくる手話言語法』より)
本会行事や市内の各手話サークルなどにて、再販売したいと思いますので、
よろしくお願いします。