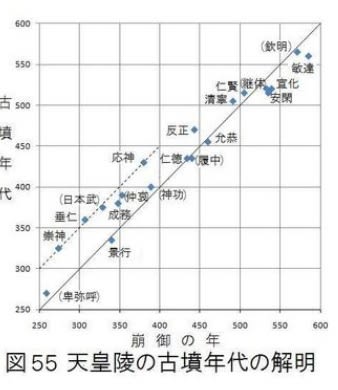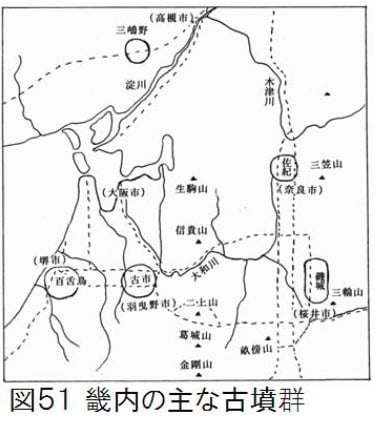新年あけましておめでとうございます。
初詣、神社についてです。
古代史豆知識(神社)で説明していますが
イザナギが産んだ三貴神 アマテラス、スサノオ、ツキヨミ
天皇家の祖先はアマテラスですので、天照大神を祀った伊勢神宮を頂点とした神宮
天皇家の分家となるスサノオを祀った出雲大社などが大社です。
神宮と大社では、鳥居や社殿などの作りも違います。
その他にも多くの神社があります。
お正月の休みを使って、是非、勉強してみましょう。
ここでは、各地の有名な神社を紹介してみます。
伊勢神宮(三重県伊勢市) 天照大神が鎮座されていて、日本を守っていただいています。
式年遷宮でも有名で最も歴史がある神社の本家です。
天皇家の三種の神器 八咫鏡が納めてあります。
社格の頂点にあります。
猿田彦神社(三重県伊勢)
ニニギ一行が天損降臨の際に、道案内した猿田彦大神が祀られています。
熱田神宮(愛知県名古屋) 天皇家の三種の神器 草薙剣(くさなぎのつるぎ)を祀る神社
もう一つの神器 勾玉は皇居にあるとされています。
天照の先代、イザナミ、イザナギが祀られてます。
出雲大社(鳥取県出雲市) こちらは大社の総本山
スサノオが祀られてます。
伊勢神宮が 高床式の穀物蔵の形から発達した「神明造」
出雲大社が 古代の住居の形から発達した「大社造」です。
宗像大社(福岡県宗像市) 誓約の神話で、アマテラスの勾玉からスサノオが産んだ女神(宗像三女神)が祀られています。
田心姫神(たごりひめかみ) 沖の島・沖津宮 (長女)
湍津姫神(たぎつひめかみ) 大 島・中津宮 (次女)
市杵島姫神(いちきしまひめかみ)宗像市・辺津宮 (3女)
スサノオから産まれた為、分家扱いの大社です。
平安神宮(京都市) 平安遷都を行った天皇であった第50代桓武天皇を祀る神社
幾度も焼失しており、現在の建物は明治時代に再建された。
春日大社(奈良県奈良市)旧 春日神社、中臣氏(のちの藤原氏)の氏神を祀る
厳島神社(広島県廿日市市)宗像三女神を祀る。平清盛により現在の海上に立つ大規模な社殿が整えられた。
太宰府天満宮、北野天満宮 天神様信仰で天満宮の総本山、菅原道真(菅原道真公、菅公)を祭神として祀る天満宮
鶴岡八幡宮(神奈川県鎌倉市)
源氏再興の旗上げをした源頼朝が完成させた。
三韓征伐の神功皇后と応神天皇が祀られています。
時の権力者は、スサノオなど強い神々を崇拝した様です。
八坂神社、稲荷神社(伏見稲荷)、住吉大社など多数の支社を持つ神社の形式が出来ます。
古くは、社格の高い神社は高貴な貴族の物だったのが、大衆化した証だと思います。
えびす神社は、七福神とインドの神様まで加わって縁起が良い神社です。
狛犬は、飛鳥時代に仏教と共に獅子の姿で伝わり、平安時代に左右に獅子と狛犬となったようです。
日光東照宮 江戸幕府初代将軍・徳川家康を神格化して祀られています。
幕末、明治維新では、明治神宮が造られます。
初詣に行かれたら、鳥居や社殿の作り、狛犬、しめ縄、ご神体など確認してみては如何でしょうか。
初詣、神社についてです。
古代史豆知識(神社)で説明していますが
イザナギが産んだ三貴神 アマテラス、スサノオ、ツキヨミ
天皇家の祖先はアマテラスですので、天照大神を祀った伊勢神宮を頂点とした神宮
天皇家の分家となるスサノオを祀った出雲大社などが大社です。
神宮と大社では、鳥居や社殿などの作りも違います。
その他にも多くの神社があります。
お正月の休みを使って、是非、勉強してみましょう。
ここでは、各地の有名な神社を紹介してみます。
伊勢神宮(三重県伊勢市) 天照大神が鎮座されていて、日本を守っていただいています。
式年遷宮でも有名で最も歴史がある神社の本家です。
天皇家の三種の神器 八咫鏡が納めてあります。
社格の頂点にあります。
猿田彦神社(三重県伊勢)
ニニギ一行が天損降臨の際に、道案内した猿田彦大神が祀られています。
熱田神宮(愛知県名古屋) 天皇家の三種の神器 草薙剣(くさなぎのつるぎ)を祀る神社
もう一つの神器 勾玉は皇居にあるとされています。
天照の先代、イザナミ、イザナギが祀られてます。
出雲大社(鳥取県出雲市) こちらは大社の総本山
スサノオが祀られてます。
伊勢神宮が 高床式の穀物蔵の形から発達した「神明造」
出雲大社が 古代の住居の形から発達した「大社造」です。
宗像大社(福岡県宗像市) 誓約の神話で、アマテラスの勾玉からスサノオが産んだ女神(宗像三女神)が祀られています。
田心姫神(たごりひめかみ) 沖の島・沖津宮 (長女)
湍津姫神(たぎつひめかみ) 大 島・中津宮 (次女)
市杵島姫神(いちきしまひめかみ)宗像市・辺津宮 (3女)
スサノオから産まれた為、分家扱いの大社です。
平安神宮(京都市) 平安遷都を行った天皇であった第50代桓武天皇を祀る神社
幾度も焼失しており、現在の建物は明治時代に再建された。
春日大社(奈良県奈良市)旧 春日神社、中臣氏(のちの藤原氏)の氏神を祀る
厳島神社(広島県廿日市市)宗像三女神を祀る。平清盛により現在の海上に立つ大規模な社殿が整えられた。
太宰府天満宮、北野天満宮 天神様信仰で天満宮の総本山、菅原道真(菅原道真公、菅公)を祭神として祀る天満宮
鶴岡八幡宮(神奈川県鎌倉市)
源氏再興の旗上げをした源頼朝が完成させた。
三韓征伐の神功皇后と応神天皇が祀られています。
時の権力者は、スサノオなど強い神々を崇拝した様です。
八坂神社、稲荷神社(伏見稲荷)、住吉大社など多数の支社を持つ神社の形式が出来ます。
古くは、社格の高い神社は高貴な貴族の物だったのが、大衆化した証だと思います。
えびす神社は、七福神とインドの神様まで加わって縁起が良い神社です。
狛犬は、飛鳥時代に仏教と共に獅子の姿で伝わり、平安時代に左右に獅子と狛犬となったようです。
日光東照宮 江戸幕府初代将軍・徳川家康を神格化して祀られています。
幕末、明治維新では、明治神宮が造られます。
初詣に行かれたら、鳥居や社殿の作り、狛犬、しめ縄、ご神体など確認してみては如何でしょうか。