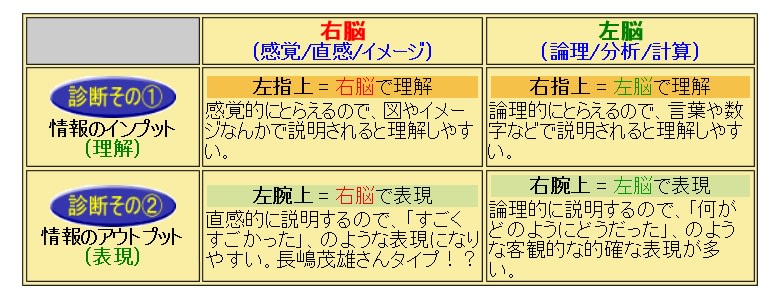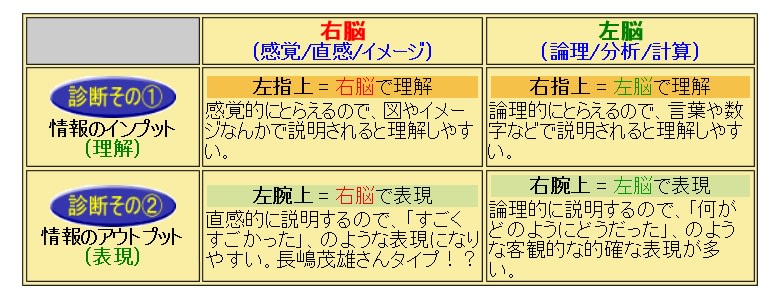卑弥呼は 日・巫女 だから、現在の巫女(上の写真)のようだった。
とイメージされている方が多いと思います。
では、もう一度、魏志倭人伝を読み直してみましょう。
・その国は、もとまた男子をもって王としていた。
・7~80年まえ倭国は乱れ、あい攻伐して年を歴る。
・すなわち、ともに一女子をたてて王となす。名づけて卑弥呼(女王:ひめみこの音を写したとみられる)という。
・ 鬼道につかえ、よく衆をまどわす。年はすでに長大であるが、夫壻(おっと・むこ)はない。
倭国大乱が180年頃まで、その後の王となる。年はすでに長大である
つまり、老婆です。
当時の寿命から4~50歳代?248年に死亡ですから、120歳?到底、考えられません。
・(卑弥呼が)王となっていらい、見たものはすくない。
つまり、卑弥呼が王となって間もなく死亡したのです。その後は、数代にわたり卑弥呼が密室にて祈祷を行ったのです。
もう少し、卑弥呼が魏に贈った貢物
・絳地(あつぎぬ)の交竜錦(二頭の竜を配した錦の織物)五匹
・絳地の粟(すうぞくけい:ちぢみ毛織物)十張・
・絳(せんこう:
あかね色のつむぎ)五十匹
・紺青(紺青色の織物)五十匹でもって、・・・
これらは、既に倭の国にあって、高貴な人々が身につけていた服です。
あかね色のつむぎ は、巫女の袴や和服の裏地を想像します。
二頭の竜を配した錦の織物は、結構派手ですね。
卑弥呼が魏から受け取ったもの
・紺地の句文錦(くもんきん:紺色の地に区ぎりもようのついた錦の織物)三匹
・細班華(さいはんかけい:こまかい花もようを斑らにあらわした毛織物)五張
・白絹(もようのない白い絹織物)五十匹
・金八両
・五尺刀二口
・銅鏡百枚
・真珠
・鉛丹(黄赤色をしており、顔料として用いる)おのおの五十斤
銅鏡百枚は、よく話題にあがりますが
・紺地の句文錦(紺色の地に区ぎりもようのついた錦の織物)
・細班華(こまかい花もようを斑らにあらわした毛織物)
・白絹(もようのない白い絹織物)
これらは、倭国には、無かった、或いは 貴重だった、或いは 中国でも高級品だったのでしょう。
白絹は、吉野ケ里でも見つかっています、後に蚕の栽培が始まったのでしょう。
巫女や和服の下着の部分でしょう。
ここで、疑問は、銅鏡
既に卑弥呼が鏡を使って祈祷を行っていたのか?
魏からもらった銅鏡を使ったのが始まりなのか?
銅鏡一枚が5kgとすると100枚で500kg
かなりの重量、運搬するのは大変です。
朝鮮半島までは、台車があったとしても、上陸してからは、人手になります。
一人が前後に一枚づつ背負ったとしても50人の行列
それから、卑弥呼の死後、台与の時代となります。
卑弥呼の死は、実際に誰かが無くなったのではなく、老婆による祈祷術が信頼を失った、権力が男王に移った年です。
・(倭人たちは)また卑弥呼の宗女(一族の娘、世つぎの娘)の壱与(台与)なるもの、年十三をたてて王とした
ここで、13歳の若い巫女となります。
・卑弥呼はすでに死んだ。大いに冢つかをつくった。径は百余歩・徇葬者(じゅんそう)のは百余人であった
卑弥呼一族による祈祷政治は効力を失った。遠く離れた土地に祈祷と殉職者の為の土地を作った。
これが前方後円墳でsる。
狗奴国(卑弥弓呼)との戦いの最中、既に卑弥呼一族は移住の計画を実行していたのではないでしょうか。
それが、奈良(橿原)の地です。卑弥呼一族の移動と同時に卑弥呼の死となります。
残った一部が台与です。つまり、現行若者勢力が台与の九州北部です。
年老いた巫女が住む土地が奈良と云う事になります。
奈良へ移動した祈祷信仰集団はその土地を邪馬台からヤマトと呼ぶようになります。
多分に、親魏倭王の金印も一緒に移動したでしょう。倭をヤマトと読むのも、その為です。
既に魏は滅亡(265年)、国を追われる立場になってしまう。
残された台与は晋へ朝貢しますが、これ云う功績は上げれませんでした。
かなり衝撃ですが、
こちらが朝鮮半島の巫女です。
卑弥呼は、こちらに近く。
台与が、現在の神社の巫女の始まりです。