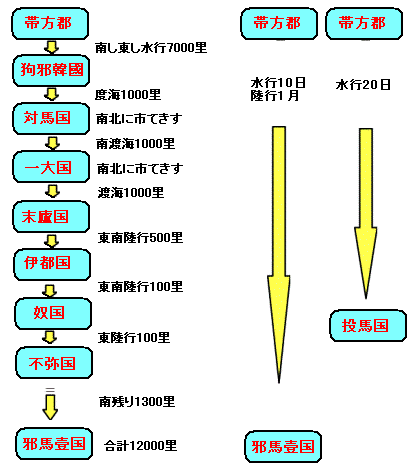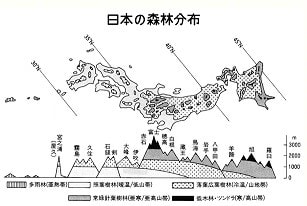銅鏡と一緒に考えてほしいのが
銅鐸・銅矛文化です。
銅鐸・・朝鮮半島に原型があり日本へ伝わる。
1世紀末ごろを境にして急に大型化する
近畿式は大和・河内・摂津で生産され、三遠式は濃尾平野で生産された。
近畿式は、近畿一帯を中心として、東は遠江、西は四国東半、北は山陰地方に、
三遠式は、東は信濃・遠江、西は濃尾平野を一応の限界とし、
例外的に伊勢湾東部・琵琶湖東岸・京都府北部の日本海岸にそれぞれ分布する。
2世紀末葉になると近畿式のみとなる。
3世紀になると突然造られなくなる。
つまり、弥生時代の後期の200年程間に普及して突然と無くなります。
銅矛・銅剣
弥生時代初期より、農耕、建築と共に青銅製の道具が大陸より持ち込まれる。
1世紀に倭国大乱にて青銅製の矛、剣が使われる、鉄製の武器が持ち込まれる。
大乱後は、巨大化し祭祀として、或いは権力者の埋葬時の葬飾品として使われる。
こちらも平原遺跡では、素環頭太刀となり葬飾品も鉄製の剣になり終焉となります。
青銅文化は、銅矛、銅剣、銅鐸共に3世紀(卑弥呼の時代)に無くなります。
同じ時代に吉野ケ里の様な環濠集落も突然に国を捨ててなくなります。
大陸で魏、呉が滅亡して大陸から鏡職人が倭国へ移住
三角縁神獣鏡を使われなくなった青銅器から作成します。
大陸でも三国志の時代が終わり乱れてしまます。
倭国でも、九州のみでなく
山陰、山陽(吉備)、近畿で大きな変化が繰り返された時代だったようです。
後のヤマト王権も大陸、朝鮮半島から人材を取り入れ律令制度、漢字、仏教が取り入れられます。
しかし、大化の改新以後は新仏分離など、神道国家体制へか舵取りを変換
日本神話を含む「古事記」伊勢神宮、出雲大社など神道制度の確立を行います。
銅鐸・銅矛文化です。
銅鐸・・朝鮮半島に原型があり日本へ伝わる。
1世紀末ごろを境にして急に大型化する
近畿式は大和・河内・摂津で生産され、三遠式は濃尾平野で生産された。
近畿式は、近畿一帯を中心として、東は遠江、西は四国東半、北は山陰地方に、
三遠式は、東は信濃・遠江、西は濃尾平野を一応の限界とし、
例外的に伊勢湾東部・琵琶湖東岸・京都府北部の日本海岸にそれぞれ分布する。
2世紀末葉になると近畿式のみとなる。
3世紀になると突然造られなくなる。
つまり、弥生時代の後期の200年程間に普及して突然と無くなります。
銅矛・銅剣
弥生時代初期より、農耕、建築と共に青銅製の道具が大陸より持ち込まれる。
1世紀に倭国大乱にて青銅製の矛、剣が使われる、鉄製の武器が持ち込まれる。
大乱後は、巨大化し祭祀として、或いは権力者の埋葬時の葬飾品として使われる。
こちらも平原遺跡では、素環頭太刀となり葬飾品も鉄製の剣になり終焉となります。
青銅文化は、銅矛、銅剣、銅鐸共に3世紀(卑弥呼の時代)に無くなります。
同じ時代に吉野ケ里の様な環濠集落も突然に国を捨ててなくなります。
大陸で魏、呉が滅亡して大陸から鏡職人が倭国へ移住
三角縁神獣鏡を使われなくなった青銅器から作成します。
大陸でも三国志の時代が終わり乱れてしまます。
倭国でも、九州のみでなく
山陰、山陽(吉備)、近畿で大きな変化が繰り返された時代だったようです。
後のヤマト王権も大陸、朝鮮半島から人材を取り入れ律令制度、漢字、仏教が取り入れられます。
しかし、大化の改新以後は新仏分離など、神道国家体制へか舵取りを変換
日本神話を含む「古事記」伊勢神宮、出雲大社など神道制度の確立を行います。










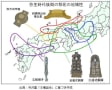

 の
の