江戸時代の司法制度
江戸時代の司法制度は、幕府が武家の棟梁として全国的な司法権を有したのに対して、各藩あるいは幕府の直轄地にたいしては、藩領・直轄領あるいはその家臣(一領一家中)に限られた司法権が与えられた。各藩の権限は司法権の全般に渡り、刑の種類や、執行についても各藩に任されていたのであるが、藩の司法権は幕府に監督され、その意味で幕府は上位機関として位置づけられる。また、藩を跨ぐ事件についても、刑事事件であれ、民事事件であれ、藩は幕府に対して吟味願を提出し、その事件の所属に基づいて寺社奉行・町奉行・勘定奉行がそれぞれ担当し、そのうち奉行所の手限を越える重大な事件に関しては、評定所を設けてこれを議し、仕置伺を草して老中に上申する仕組みである。
江戸時代の司法制度においては、たとえば白州における裁判が非公開であるとか、事件の捜査、捕縛あるいは取調べを行う部局と、事件を審理し、犯罪事実を認定し、刑罰を適用する部局が同一の機関においてなされるなどは、西洋世界の歴史的産物たる罪刑法定主義や三権分立を継受していないのであるから当然であるのだけれども、一方で注目すべき特徴もある。
先ほど評定所から上申された仕置伺であるが、老中はこれを仕置掛右奥筆に回付し、その当否について調査・検討させ、仕置掛右奥筆は幕府法である公事方御定書や過去の判例などを調べて、老中に提出するのであるが、これは幕府における司法官僚にほかならず、判例の蓄積とその検討を職務とすることにより、法的安定性を維持するための専門機関であると位置づけられよう。さらに、江戸時代の弁護人制度については、もちろん近代司法における弁護人制度は存在しないのであるが、奉行所の召喚や出訴のために出府したものに宿を提供する公事宿が、刑事事件においては、被糺問者の依頼を受けて書面を代筆したり、これに付き添って出廷し意見をのべたり、とりわけ取調べをおこなう吟味役人と被糺問者との間を周旋するための媒体として、幕府の側からは不可欠な存在であると認められていたことが注目される。
奉行所によって出府を命じられた者は、遠路はるばるその取調べを受けるために、江戸へやってくるだろう。おそらく裁判手続きに関してもよく分らず、不安なままに泊め置かれる宿において、出廷前の書類を世話してくれたり、裁判の進行については被告人の立場に立った教示をしてくれることは、藁にもすがる思いである被告人からすれば、大変力強いに違いにない。およそ庶民の権利を守るという着想からは少し外れているとはいえ、江戸時代の司法制度における弁護人の役割が宿泊施設に宿ってきたことは、じつに日本的であり興味深い。
以上
江戸時代の司法制度は、幕府が武家の棟梁として全国的な司法権を有したのに対して、各藩あるいは幕府の直轄地にたいしては、藩領・直轄領あるいはその家臣(一領一家中)に限られた司法権が与えられた。各藩の権限は司法権の全般に渡り、刑の種類や、執行についても各藩に任されていたのであるが、藩の司法権は幕府に監督され、その意味で幕府は上位機関として位置づけられる。また、藩を跨ぐ事件についても、刑事事件であれ、民事事件であれ、藩は幕府に対して吟味願を提出し、その事件の所属に基づいて寺社奉行・町奉行・勘定奉行がそれぞれ担当し、そのうち奉行所の手限を越える重大な事件に関しては、評定所を設けてこれを議し、仕置伺を草して老中に上申する仕組みである。
江戸時代の司法制度においては、たとえば白州における裁判が非公開であるとか、事件の捜査、捕縛あるいは取調べを行う部局と、事件を審理し、犯罪事実を認定し、刑罰を適用する部局が同一の機関においてなされるなどは、西洋世界の歴史的産物たる罪刑法定主義や三権分立を継受していないのであるから当然であるのだけれども、一方で注目すべき特徴もある。
先ほど評定所から上申された仕置伺であるが、老中はこれを仕置掛右奥筆に回付し、その当否について調査・検討させ、仕置掛右奥筆は幕府法である公事方御定書や過去の判例などを調べて、老中に提出するのであるが、これは幕府における司法官僚にほかならず、判例の蓄積とその検討を職務とすることにより、法的安定性を維持するための専門機関であると位置づけられよう。さらに、江戸時代の弁護人制度については、もちろん近代司法における弁護人制度は存在しないのであるが、奉行所の召喚や出訴のために出府したものに宿を提供する公事宿が、刑事事件においては、被糺問者の依頼を受けて書面を代筆したり、これに付き添って出廷し意見をのべたり、とりわけ取調べをおこなう吟味役人と被糺問者との間を周旋するための媒体として、幕府の側からは不可欠な存在であると認められていたことが注目される。
奉行所によって出府を命じられた者は、遠路はるばるその取調べを受けるために、江戸へやってくるだろう。おそらく裁判手続きに関してもよく分らず、不安なままに泊め置かれる宿において、出廷前の書類を世話してくれたり、裁判の進行については被告人の立場に立った教示をしてくれることは、藁にもすがる思いである被告人からすれば、大変力強いに違いにない。およそ庶民の権利を守るという着想からは少し外れているとはいえ、江戸時代の司法制度における弁護人の役割が宿泊施設に宿ってきたことは、じつに日本的であり興味深い。
以上










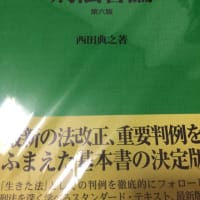
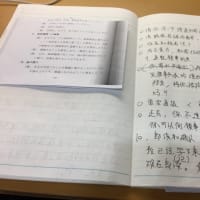
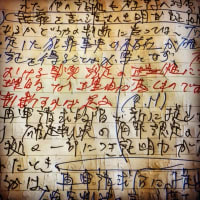

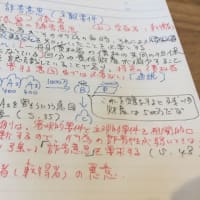
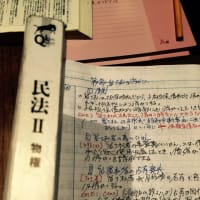
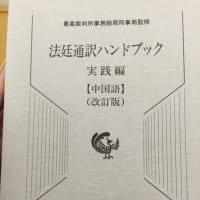
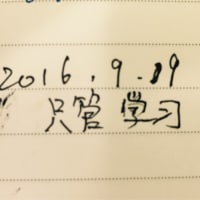

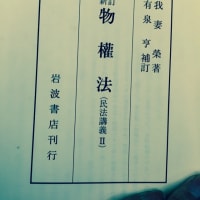
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます