ストーリー;マーキュリー・シューズ株式会社に奨学生として入社し、それいらい8年間にわたり靴のデザインをしていたドリュー・ベイラーは新製品で約10億円の損害を会社にもたらし、彼は解雇される。地球監査プロジェクトなど種々のプロジェクトにも断念でざるをえなくなったバーロウ会長は、彼に経済紙の取材をまかせ日曜日に報道される旨を告げる。自殺を図ろうとした日に、おりしも父親がケンタッキーで死亡。「失敗と大失敗」を痛感するとともに同僚の「最後の視線を通痛切に感じる。そして出てくる言葉は「大丈夫…」だけだった。8年間靴作りに挑戦してきた彼の部屋は案外綺麗だったが、荷物をすべて捨てて自殺未遂。親族がいるケンタッキーのエリザベスタウンに向かう。従兄弟のジェシーにいわせると「小さなことを50年間ずっといわれる」土地柄だということだったが、父親のミッチーは本当に地元の人間から親しまれていたようだった。ジェシーの滞在したブラウンホテルではおりしも結婚式の真っ最中。混乱している間に携帯電話をかけまくり、恋人エレンには別れを告げられ、妹ヘザーには母親の行動が妙なのでもどってきて欲しいと頼まれる。そして朝方まで携帯電話の会話につきあってくれたのは飛行機の中で知り合ったアテンダントのクレアだった。死んだ父親ミッチーの口癖「人生山あち谷あり」といった言葉をあちこちできくドリュー。携帯電話のクレアはナッシュビル空港から自宅にもどったばかり。二人は朝陽をみようと電話でおちあうことにする。パソコンと携帯電話の新たな形の純愛シーンの描写が綺麗。カリフォルニアの火葬率は約80パーセントということだったが火葬か土葬かで微妙に親族と母親の対立もドリューは感じるのだった。「南部は見かけとは違うのよ」とやや躁鬱気味の母親はいう。東京のエレベーターの中で偶然であったという二人はそれぞれ別に恋人がいたのだが、恋に陥りそれ以来母親と親族はうまくいっていなかったのだ。一方、レキシントンから棺をとりよせ、お葬式の準備は着々とすすむ。そして日曜日には自分の失敗が経済紙に大きく報道される…。「失敗、失敗、失敗…大失敗しても根性でしがみつくのが根性ってものよ」とクレアは励ます。それでも「最後の視線」におびえるドリュー。父親の葬式も無事に終了するとクレアがもってきたのは「大きな地図」とCDだった。「悲しみに屈するのは簡単。それよりは一人でどこかで踊って」というメッセージなどがついて、所要時間は42時間と11分。地図の最後の目的地は世界第二位のファーマーズマーケット。そこで彼は一つの選択をせまられる…
出演 ;オーランド・ブルーム、キルスティン・ダンスト、スーザン・サランドン
コメント ;音楽が好きな監督なのだなあと思う。火葬用のツボにも「KISS」の絵が書いてあるものがあったり、ジム・モリソン、「フリー・バード」、レオナード・スキナードなどいろいろなミュージシャンの名前に対してコラボレーションが施されている。
で、「物語」としてはやはり「死ぬこと」から「再生」へ、ということになるだろう。株式会社の破産にもつながる大失敗ではあるが、この場合には責任はふつう役員がとるべき課題であって一介のデザイナーがとるべき課題ではない。しかも新製品をいきなり大量に大生産するというのもメーカーとしては普通ありえない行動が。テストにテストを重ねてやっと市場に提供するのが新製品であるわけであって、なぜにここまで一人のデザイナーが責任を追及されるのかがそもそも不明だ。スーザン・サランドンがとつぜん舞台の上で「土曜日の夜」にあわせてタップを踊りだす場面が不可思議であると同時にこの女優の凄さを感じる。とにかく台詞が長い上に場面が場面。それをきっちり演じきってしまうのはやはり天才女優のゆえか。「土曜日の夜」にあわせてタップをゆっくり踊り始める場面が秀逸。ゆったりへたくそにしかし、貫禄をもたせて踊りながら見せる表情はやはり名女優というべきか。
(ノーマン・ロックウェル)
「2を好む」という設定の社長が飾っている絵画がノーマン・ロックウェルの絵。2000近い作品を書いたがそのうちのほとんどが火災で消滅して、残された絵画にはかなりの高値がついている。秘書も二人、ドアもチュニジアから取り寄せた2ドアということで靴会社の社長だけに「2」というか左右対称にこだわるという演出を狙ったようだ。
(ケンタッキー州)
地図でみると北西部にあたる地域。ケンタッキー州最大の都市がルイヴァイル…でこの映画が扱っている街になる。オーランド・ブルームが高速道路の出口を見誤り、インディアナ州に入ってしまう場面も面白い。所得や教育の水準はあまり全米でも高いほうではないとされている地域。カーネル・サンダースの銅像を前に、キルスティン・ダンスドが「ケンタッキーのジム・モリソンだわ」とつぶやくシーンも印象的。映画にはルイヴァル球場やリンカーンの名前もでてくるのだが、リンカーンもこのケンタッキー州の出身だ。南北戦争では北部についている。「リンカーンからロニー・ヴァン・ザントまで子供に教えている」という従兄弟の教育方針が面白い。レーナード・スキナードのミュージシャンだが、このレーナード・スキナードの影響をうけて従兄弟は「ラックス」というバンドをしていたという逸話が映画の伏線となっている。ダービー博物館も映画の中に登場。5月の第一土曜日におこなわれる「ケンタキー・ダービー」にちなんでの博物館と思われる。
(ローマの休日)
映画「ローマの休日」でオードリー・ヘップバーンが机の下の靴を探す場面とクレアがベッドの下の靴を探す場面とをオーバーラップ。ともに純愛路線でしかも階級社会から市民社会へ移行しているわけだが、時代の変化を乗り越えても「純愛」というのは普遍的というキャメロン・クロウのこれも演出か。
(オクラホマシティ サバイバルツリー)
市庁舎爆破事件のときにも生き残った木。映画の中でも生命力をたてる存在としてゆったりと画面の真ん中に位置して撮影されているのが印象的。この日差しをあびたサバイバルツリーのシーンはなかなか良かったなあ。
(フリー・バード)
レナード・スキナードの名曲。ジョン・レノンのほうではなく、映画の設定どおり「ラックス」はレナード・スキナードの極端な盛り上がりをみせる名曲でコメディチックな映画の場面を盛り上げる。
(夜のガソリンスタンド)
オーランド・ブルームとキルスティンダンストが向かい合う夏の夜のガソリンスタンド。虫の音が印象的だ。ジョージアで「学問と結婚している」というベンがやってくるキルスティン・ダンストは「私たちはいつでもだれかの穴埋めができる特殊な才能をもっているわ」とささやく。熱情的な台詞をささやこうとするオーランド・ブルームに対して「アイスクリーム…5分で溶けてしまう…」と切り返すキルスティン・ダンストが印象的。もともとかなり恥ずかしい台詞が多いのだが、ホテルの部屋で「大丈夫、何もしないから安心して」とささやくオーランド・ブルームはかなり型にはまっていてかっこいい。こういう台詞はかつて何かの映画でリチャード・ギアがつぶやいて以来、久しぶりに「はまる役者」が出てきたという感じだ。
(FIASCO)
オーランド・ブルームが世界第二位のファーマーズ・マーケットで手に取る雑誌のタイトル。別の雑誌が上にかぶさっているがクレアのこれは配慮だろう。「ライトハウス英和辞典」で調べてみると、アメリカでも英国でも「(計画などの)大失敗」という意味で用いられているようだ。「ファエスコウ」という発音か。
(ジェフ・バックリーのお墓)
1997年に31歳でミシシッピー川で溺死した伝説のロックシンガー。メンフィスに立ち寄ったときにオーランド・ブルームはクレアのアドバイスどおりお墓参りをする。ルートとCDが指定されたこのクレア独自の地図は客室添乗員という職業もさることながらアメリカ南部の名所めぐりといった観を呈してくる。メンフィスではさらにサン・スタジオにも行くが、これはジム・ジャームッシュの「ミストリー・トレイン」でも取り上げられた場所。一度もいったことがないのに違う映画でまた同じロケーションをみるのも面白い。おそらくミステリー・トレインにもでてきた電車が走る場所も違う角度から違う演出で映画に取り上げられている。
(ロレイン・モーテル)
キング牧師の演説シーンなどはよくドキュメンタリーでも引用されるがこの映画では博物館となっている現在のロレイン・モーテルを画面に登場させる。1968年にキング牧師が暗殺された場所だが、306号室の現状保存の状況や白黒の画面に映し出されている当時の公民権運動の様子など生々しいほどの演出。しかしオーランド・ブルームはそのロレイン・ホテルの前で父親の遺灰をばっとまく…。もしかすると日本人以上に今の若いアメリカ人には公民権運動やキング牧師というのは遠い存在になっているのかもしれない。
(「It would be something else…」)
(もし今の状況でなかったら)もっと違った二人でいたかもしれない…という受験英語では典型的な仮定法現在の会話。「穴埋めできる特殊能力を私たちは持っているわ」と話すクレアに対してオーランド・ブルームがつぶやく仮定法現在のこの台詞がなかなかいい。
(オーランド・ブルームにお茶を運んでくる女性)
エリザベスタウンで、談笑しているときにオーランド・ブルームにお茶を運んでくる女性がいるのだが、お茶が運ばれてきたこともわからず自分の世界に入ってしまうオーランド・ブルーム。映画の中では役名も何もない脇役の女性なのだが、自分に気が付いてもらえないという「寂しさ」をふっと表情にかげらせるのが非常にうまい。キャメロン・クロウ監督の演出なのかもしれないが非常に気になる脇役だ。「スパイダーマン2」でも主人公の部屋にケーキを運んでくる大家さんの娘がいて、二人でモクモクとケーキを食べているシーンが印象的だったが、こういう目に見えない物語が映画のはしっこで同時進行しているのが画面に見える演出は個人的に大好き。だれもが映画の主人公になれるわけでない…という寂しさを感じると同時にほっとする映画演出でもある。
(車は赤のレクサス)
レクサス…といって二人がぷっと笑うシーンがあるのだが、それだけ日本自動車がアメリカに日常的に使われていることを意味しているようだ。日本の国内新車販売台数は実は2007年1月時点で昨年よりも1割前後落ち込んでいる一方で、自動車メーカーの業績自体は一部の2つのメーカーを除いては増益。この業績の背景には北米での販売台数の増加が連結決算で組み込まれている結果といえる。国内の販売台数が減少する一方で輸出は増加傾向をたどっており、国内の消費性向がそれほど高くなったというわけでもないらしい。もちろんレクサスの販売をしているトヨタ自動車も増益だ。
(つたはコンクリートを破り、鮭は川を登る…)
クリエイターの辛さをたとえたものだが、こうした比喩をばねに主人公は自殺を思いとどまる…。でもなあ。クリエイターも予算と販売のリコールについてはやはりそれなりに責任は負うべきなので、すべてがすべて正当化されるわけでもない。むしろ死ぬことを思いとどまって、またやり直す…という意味でなら別の比喩を用いるべきではなかったか、という気がする。
出演 ;オーランド・ブルーム、キルスティン・ダンスト、スーザン・サランドン
コメント ;音楽が好きな監督なのだなあと思う。火葬用のツボにも「KISS」の絵が書いてあるものがあったり、ジム・モリソン、「フリー・バード」、レオナード・スキナードなどいろいろなミュージシャンの名前に対してコラボレーションが施されている。
で、「物語」としてはやはり「死ぬこと」から「再生」へ、ということになるだろう。株式会社の破産にもつながる大失敗ではあるが、この場合には責任はふつう役員がとるべき課題であって一介のデザイナーがとるべき課題ではない。しかも新製品をいきなり大量に大生産するというのもメーカーとしては普通ありえない行動が。テストにテストを重ねてやっと市場に提供するのが新製品であるわけであって、なぜにここまで一人のデザイナーが責任を追及されるのかがそもそも不明だ。スーザン・サランドンがとつぜん舞台の上で「土曜日の夜」にあわせてタップを踊りだす場面が不可思議であると同時にこの女優の凄さを感じる。とにかく台詞が長い上に場面が場面。それをきっちり演じきってしまうのはやはり天才女優のゆえか。「土曜日の夜」にあわせてタップをゆっくり踊り始める場面が秀逸。ゆったりへたくそにしかし、貫禄をもたせて踊りながら見せる表情はやはり名女優というべきか。
(ノーマン・ロックウェル)
「2を好む」という設定の社長が飾っている絵画がノーマン・ロックウェルの絵。2000近い作品を書いたがそのうちのほとんどが火災で消滅して、残された絵画にはかなりの高値がついている。秘書も二人、ドアもチュニジアから取り寄せた2ドアということで靴会社の社長だけに「2」というか左右対称にこだわるという演出を狙ったようだ。
(ケンタッキー州)
地図でみると北西部にあたる地域。ケンタッキー州最大の都市がルイヴァイル…でこの映画が扱っている街になる。オーランド・ブルームが高速道路の出口を見誤り、インディアナ州に入ってしまう場面も面白い。所得や教育の水準はあまり全米でも高いほうではないとされている地域。カーネル・サンダースの銅像を前に、キルスティン・ダンスドが「ケンタッキーのジム・モリソンだわ」とつぶやくシーンも印象的。映画にはルイヴァル球場やリンカーンの名前もでてくるのだが、リンカーンもこのケンタッキー州の出身だ。南北戦争では北部についている。「リンカーンからロニー・ヴァン・ザントまで子供に教えている」という従兄弟の教育方針が面白い。レーナード・スキナードのミュージシャンだが、このレーナード・スキナードの影響をうけて従兄弟は「ラックス」というバンドをしていたという逸話が映画の伏線となっている。ダービー博物館も映画の中に登場。5月の第一土曜日におこなわれる「ケンタキー・ダービー」にちなんでの博物館と思われる。
(ローマの休日)
映画「ローマの休日」でオードリー・ヘップバーンが机の下の靴を探す場面とクレアがベッドの下の靴を探す場面とをオーバーラップ。ともに純愛路線でしかも階級社会から市民社会へ移行しているわけだが、時代の変化を乗り越えても「純愛」というのは普遍的というキャメロン・クロウのこれも演出か。
(オクラホマシティ サバイバルツリー)
市庁舎爆破事件のときにも生き残った木。映画の中でも生命力をたてる存在としてゆったりと画面の真ん中に位置して撮影されているのが印象的。この日差しをあびたサバイバルツリーのシーンはなかなか良かったなあ。
(フリー・バード)
レナード・スキナードの名曲。ジョン・レノンのほうではなく、映画の設定どおり「ラックス」はレナード・スキナードの極端な盛り上がりをみせる名曲でコメディチックな映画の場面を盛り上げる。
(夜のガソリンスタンド)
オーランド・ブルームとキルスティンダンストが向かい合う夏の夜のガソリンスタンド。虫の音が印象的だ。ジョージアで「学問と結婚している」というベンがやってくるキルスティン・ダンストは「私たちはいつでもだれかの穴埋めができる特殊な才能をもっているわ」とささやく。熱情的な台詞をささやこうとするオーランド・ブルームに対して「アイスクリーム…5分で溶けてしまう…」と切り返すキルスティン・ダンストが印象的。もともとかなり恥ずかしい台詞が多いのだが、ホテルの部屋で「大丈夫、何もしないから安心して」とささやくオーランド・ブルームはかなり型にはまっていてかっこいい。こういう台詞はかつて何かの映画でリチャード・ギアがつぶやいて以来、久しぶりに「はまる役者」が出てきたという感じだ。
(FIASCO)
オーランド・ブルームが世界第二位のファーマーズ・マーケットで手に取る雑誌のタイトル。別の雑誌が上にかぶさっているがクレアのこれは配慮だろう。「ライトハウス英和辞典」で調べてみると、アメリカでも英国でも「(計画などの)大失敗」という意味で用いられているようだ。「ファエスコウ」という発音か。
(ジェフ・バックリーのお墓)
1997年に31歳でミシシッピー川で溺死した伝説のロックシンガー。メンフィスに立ち寄ったときにオーランド・ブルームはクレアのアドバイスどおりお墓参りをする。ルートとCDが指定されたこのクレア独自の地図は客室添乗員という職業もさることながらアメリカ南部の名所めぐりといった観を呈してくる。メンフィスではさらにサン・スタジオにも行くが、これはジム・ジャームッシュの「ミストリー・トレイン」でも取り上げられた場所。一度もいったことがないのに違う映画でまた同じロケーションをみるのも面白い。おそらくミステリー・トレインにもでてきた電車が走る場所も違う角度から違う演出で映画に取り上げられている。
(ロレイン・モーテル)
キング牧師の演説シーンなどはよくドキュメンタリーでも引用されるがこの映画では博物館となっている現在のロレイン・モーテルを画面に登場させる。1968年にキング牧師が暗殺された場所だが、306号室の現状保存の状況や白黒の画面に映し出されている当時の公民権運動の様子など生々しいほどの演出。しかしオーランド・ブルームはそのロレイン・ホテルの前で父親の遺灰をばっとまく…。もしかすると日本人以上に今の若いアメリカ人には公民権運動やキング牧師というのは遠い存在になっているのかもしれない。
(「It would be something else…」)
(もし今の状況でなかったら)もっと違った二人でいたかもしれない…という受験英語では典型的な仮定法現在の会話。「穴埋めできる特殊能力を私たちは持っているわ」と話すクレアに対してオーランド・ブルームがつぶやく仮定法現在のこの台詞がなかなかいい。
(オーランド・ブルームにお茶を運んでくる女性)
エリザベスタウンで、談笑しているときにオーランド・ブルームにお茶を運んでくる女性がいるのだが、お茶が運ばれてきたこともわからず自分の世界に入ってしまうオーランド・ブルーム。映画の中では役名も何もない脇役の女性なのだが、自分に気が付いてもらえないという「寂しさ」をふっと表情にかげらせるのが非常にうまい。キャメロン・クロウ監督の演出なのかもしれないが非常に気になる脇役だ。「スパイダーマン2」でも主人公の部屋にケーキを運んでくる大家さんの娘がいて、二人でモクモクとケーキを食べているシーンが印象的だったが、こういう目に見えない物語が映画のはしっこで同時進行しているのが画面に見える演出は個人的に大好き。だれもが映画の主人公になれるわけでない…という寂しさを感じると同時にほっとする映画演出でもある。
(車は赤のレクサス)
レクサス…といって二人がぷっと笑うシーンがあるのだが、それだけ日本自動車がアメリカに日常的に使われていることを意味しているようだ。日本の国内新車販売台数は実は2007年1月時点で昨年よりも1割前後落ち込んでいる一方で、自動車メーカーの業績自体は一部の2つのメーカーを除いては増益。この業績の背景には北米での販売台数の増加が連結決算で組み込まれている結果といえる。国内の販売台数が減少する一方で輸出は増加傾向をたどっており、国内の消費性向がそれほど高くなったというわけでもないらしい。もちろんレクサスの販売をしているトヨタ自動車も増益だ。
(つたはコンクリートを破り、鮭は川を登る…)
クリエイターの辛さをたとえたものだが、こうした比喩をばねに主人公は自殺を思いとどまる…。でもなあ。クリエイターも予算と販売のリコールについてはやはりそれなりに責任は負うべきなので、すべてがすべて正当化されるわけでもない。むしろ死ぬことを思いとどまって、またやり直す…という意味でなら別の比喩を用いるべきではなかったか、という気がする。










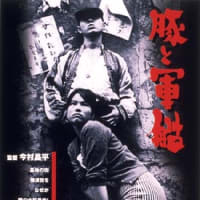



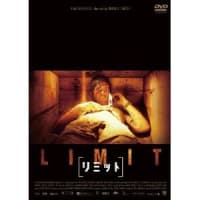





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます