大きな物語の終焉
「大きな物語」とは、フランスの哲学者ジャン=フランソワ・リオタール(1924-98)が『ポストモダンの条件』(1979)において提唱した。「大きな物語」とか「メタナラティヴ」とか訳されるが、意味は、絶対的な存在や真実によって保障される世のあらすじ。
かつての西洋文明の中では、キリスト教的神や後には理性という存在/性質が歴史の行方を決定付けていると思われていたが、このポストモダンな時代の中、もはやメタナラティヴの可能性はなくなった、とリオタールが主張したところから有名になった用語。
つまり、規範となる事柄がみずからの依拠する規則を正当化する際に用いる「物語、語り口narrative」のことを意味する。同書のなかでは、同じ意味として「メタ(=上位)物語metarecit」という表現が使われることもある。



(リオタールの主張する趣旨ーWEBコピペによる):従来人々は科学の正当性を担保するために「大きな物語」としての哲学を必要としてきた。この「哲学」とは、真偽や善悪を問う際の「基礎づけ」を担う知の領域を指している。
リオタールは、このような「大きな物語」に準拠していた時代を「モダン」、そしてそれに対する不信感が蔓延した時代を「ポストモダン」と呼んでいる。
つまりポストモダンとは、この基礎づけとしての「哲学」が有効性を失った、言い換えれば「大きな物語」が終焉した時代だという。1980年代以降に「ポストモダン」という言葉が浸透するにつれて、「大きな物語の終焉」というキャッチフレーズは、それ以前の時代からの断絶を強調するための格好の用語として広く人口に膾炙した。
しかし上記のように、そもそもこの言葉を広く知らしめた『ポストモダンの条件』において、「大きな物語」という言葉が科学の正当化をめぐる議論において用いられていたという事実は記憶にとどめておく必要がある。
(蛇足:ここでの「大きな物語」とは、近代社会がそれ特有の世界観と人間観によって社会・文化的コンテキストを維持・正当化するための物語を指している。「大きな物語」は大きくなくてもいい。つまり大きな物語とは、時間のスケールとか空間のスケールとか言葉のスケール等ではない。関連語としてmeta-narrative、grand narrative、Master Narrative, Model Story.などがある。
モデルストーリーとは一定のコミュニティのなかで機能する、人々がある現実を語ろうとするときに引用したり参照したりするモデルとなるストーリー。
マスターナラティブとはコミュニティをこえて社会的に機能するイデオロギーであり、文化的慣習や規範を表現するストーリーであるとともに、ときにポリティカリィ・コレクトな言説として表されるストーリーでもある。



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・21世紀論・アポリアー思考を放棄して袋小路に
米国の社会学者ウォーラーステイン教授の言葉(1990年頃):「これから半世紀近くの間、人類は厳しい混乱と不安の時代に直面する」。
現代文明は深刻なアポリア『袋小路、難問』に入り込んだとみる。
・2か月里山ボランティアを通しての孫娘からの手紙
・・・チェーンソーとか電ノコとかちょっとした工具も使えるようになった。椎茸とシメジの収穫時期の見極めもつくようになった。・・・どれもこれも実に些細なことだけれどもこういう素朴な作業をしている時こそああ自分が生きているなあ―としみじみ感じます。ここでの生活は食べる・働く・温まる・寝るの単調な繰り返しで余計なものがそぎ落とされてそのシンプルさが際立っているんです。鶏のお世話は平日週末関係なくしなければいけないので実質お休みは有りません。・・・
 現代の都会生活では、他愛もない便利さとか人付き合いに流されて、むしろ空虚な生き方をせざるを得なくなっている。こうだとすると、この手紙の感想は実に現代社会の問題点と忘れられた人間のあるべき姿を示唆しているように思える。
現代の都会生活では、他愛もない便利さとか人付き合いに流されて、むしろ空虚な生き方をせざるを得なくなっている。こうだとすると、この手紙の感想は実に現代社会の問題点と忘れられた人間のあるべき姿を示唆しているように思える。

・夢が語れる、それが人生というものです。夢が語れない、だったら人生の終着駅です
・教えることは他人の夢の実現に寄与することです
・私たちには夢がある
・愚かさは不幸の元、学びは豊かさの源、 学びは人生を豊かにする
・人生は遊び、学び、そして伝え合う旅である
-------------------------------------------
"Micro-cosmos cluster"の考察-(MICC)
ヒトはおのおの1個の宇宙であって、それが社会的集団と言われるような、所謂集まりを形成して、それがさらに大きな集団をなしている。例えれば磁石の磁区のようなもである、そして磁石そのものが Macro-cosmos をなしていると考える。その Macro-cosmos の相転移が起きると時代が変化したり、革命が起きたり、組織形態などの大変動をきたす。
さて Macro-cosmos において、その特性、特質、形質が個性を形成して時空を動いていくと考える。端的に言えば Macro-cosmos は小さな物語であり、それがcluster になって、大きな物語をなす。



































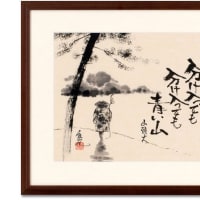

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます