宇宙・数学・AIー数学はどこからきたのか、数学とは何か、数学はどこへ行くのか
 ピタゴラス(ラテン語: Pythagoras、英: Pythagoras、紀元前582年 - 紀元前496年)、古代ギリシアの数学者、哲学者。
ピタゴラス(ラテン語: Pythagoras、英: Pythagoras、紀元前582年 - 紀元前496年)、古代ギリシアの数学者、哲学者。
■数学(Mathematics)とは
数・量・図形などに関する学問である。
数学は、一般に形式科学に分類され、自然科学とははっきり区別される。方法論の如何によらず最終的には、数学としての成果は自然科学のように実験や観察によるものではない。
現代における数学の研究は「岩波数学辞典」によると以下の分野がある。:
部門名
I 数学基礎論,数理論理学
II 集合,位相
III 代数学
IV 整数論
V 群と表現論
VI 代数幾何学
VII 幾何学
VIII 微分幾何学
IX 位相幾何学
X 解析学
XI 複素解析学
XII 関数解析学
XIII 微分方程式
XIV 特殊関数
XV 数値解析
XVI 応用解析
XVII 確率論
XVIII 統計数学
XIX 離散数学,組合せ論
XX 情報科学における数学
XXI 最適化理論
XXII 力学,物理学
XXIII 数学史
■中島啓(京都大学大学院理学研究科)、「数学と物理学の絡み合い」、大阪大学理学部「理学への招待」WEB記事、2006 年7 月7 日 (抜粋)
歴史的な理由
・物理は, 数学を用いて記述される.
・一方, 数学は物理に動機付けされて発展する.
現在の理由
・日常から離れているため(e.g. 弦, ブラックホール,ビックバン),実験ではチェックできないので, 数学的な論理の整合性のみが理論の正しさを保証する
・論理の整合性だけでは面白いことが見付けられない.
・物理的な直観が, しばしば面白い数学的な理論を作る.
数学の厳密性
数学は, 普遍的にどこでも正しい。正しいことは常に正しい.(昔の理論が否定されることがない.)
数学は実験で見る必要がない. 実験できないことでも, 数学は記述する力を持っている.
数学は, 直観とは関係ない. 日常とはかけ離れた世界でも, 記述可能である.
したがって, 極小の世界(e.g. 弦) でも, 宇宙でも, ブラックホールでも, 数学にさえなれば, どこでも正しい理論が作れる.
論理だけでは, 意味があることができない. 面白いことが見付けられない.
・新しい理論・定理を見付けるのには, 論理だけでは不十分. 直観が必要
物理的な直観が新しいことを見付けるのにしばしば役に立つ. (歴史的にもそうである.)
特に現在では
・数学的に厳密な裏付けのない場の量子論に基づいて, 豊かな数学が生み出されてきた.
物理的な直観
場の量子論の特徴
・無限個の自由度を持つ. (無限個の粒子を取り扱う.)
・無限次元の幾何を,(数学的な裏付けのある)有限次元の幾何のように取り扱う.
・場の量子論は数学的に厳密な正当化はなされていない. (e.g. ファインマンの経路積分)にもかかわらず, 20 世紀後半から場の理論は大成功をおさめてきた.
数学への侵略(さまざまな予想)
・数学的な不変量を, 物理的な観測量として定義し, その性質を調べる.
・ミラー対称性
・弦理論の研究からリーマン面の幾何学へ. (すべてのリーマン面を同時に考え調べる。
・さらに数論の世界へ(双対性からラングランズ予想を導く)
粒子の生成・消滅をすべて調べる
モジュライ空間(沢山のものを集めて,その全体に幾何学的な構造を入れた空間)
弦理論では,すべてのリーマン面を同時に取り扱うから,モジュライ空間の幾何学と自然に結び付く.
量子力学では, 粒子の全ての経路について考える必要がある. (ファインマンの経路積分)
すべての経路の全体のなす空間(=path space) が重要になる.
場の量子論では, すべての場の全体のなすモジュライ空間が大切になる.
■外園康智、宇宙が先か数が先か、数理の窓、WEB記事 2020-2-26 (抜粋)
宇宙の全ての現象をただ一つの数式で表すことは理論物理学の最大の目的である。しかし幸運にその一つの数式を見つけたとして、次になぜその数式であり、別のものではないのかと問われたら、答えに詰まるだろう。今でも相対性理論や量子力学の数式の中に、いくつかの基本手数があるが、なぜその数値なのかは説明できない。
物理法則は数学の構造の分(数)だけあって、その構造に支配された宇宙が論理的に存在すると考えるのが数学的宇宙仮説である。素粒子物理学における物質の最小単位はクォークや超ひもをもとにしているが、どんな実在を仮定しても最終的には電荷、色荷、スピン及び質量など数的特徴以外は残らない。宇宙の外的存在は数学しかなく、宇宙が先か数が先かの議論は数が先だが答えである。
■砂田 利一(明治大学)、数学の発展と展望、WEB記事、2017-2-9(抜粋)
数学の将来を語る場合,人工知能(AI)と数学の関係は無視できない。既にAI はプロの碁と将棋の棋士を打ち負かし,さらに人間のみが関われると考えられていた分野へAI が進出する勢いは加速しつつある.
人工知能がどこまで発展し,数学研究に影響するのかは,予測不可能と思われる。無理にいうと,「何でもあり」、「言いたい放題」の予測ということになりかねない.
確かなことは,問題解決におけるコンピュータの使用は増えていくだろうし,中でもシミュレーションでは増々大きな力を発揮するだろう.
しかし,100 年後の未来はどうなっているか.AI の学習機能が進歩し,機械に知能と呼べるものが備わったとき,数学者はどのように付き合っていくべきなのか。
SF映画,「2001 年宇宙の旅」,「アイ,ロボット」,「A.I.」のような映画に登場する人工知能は「問いかけ」を自由に行うが,それが近未来に起きうることなのか,あるいは永遠に起きないのか.
現時点では,「問と答」という人間と機械とのやりとりを考えたとき,問いかけは人間の得意技であり,答えるのは機械のほうが断然勝っている.すなわち,問いかけのためには,問題意識を持つ必要があり,問題意識は経験や外的影響,さらにセンス,美意識に深く関係している.AI は美意識を持つことができるか。
さらに宇宙の問題がある.我々は何故ここにいるのか,何故宇宙を知り、その調和を語ることができるのか.宇宙は何故「知性」あるいはその根源にある「意識」というものを生み出したのか.自由意志」(もしそのようなものがあるとすれば)は,宇宙の物理法則とはどのような関係があるのか.AI は自由意志を持ちうるのか。
自由意志の問題も,宇宙の構造問題と同じく神学に深く関係し,その歴史は古い. しかし現在でも,自由意志に関係する決定論,非決定論の正否には決着がついていない.
ドイツの生理学者エミール・デュボア・レーモン(1818-1896、78歳没)が言うように,例え宇宙のすべての法則を知りえたとしても,この疑問に答えられる者はいないのかもしれない。宇宙は有限か無限かについても答えられないし,AI がどこまで発展するのか,自由意志が実際にあるのかどうかにも答えられない.
 (Emil Heinrich Du Bois-Reymond)以下Wikipedia から引用
(Emil Heinrich Du Bois-Reymond)以下Wikipedia から引用
■「我々は知らない、知ることはないだろう」ラテン語: Ignoramus et ignorabimus, イグノラムス・イグノラビムス)は、人間の認識の限界を主
張したラテン語の標語。
19世紀末、ベルリン大学教授の生理学者エミール・デュ・ボア=レーモンによって、「ある種の科学上の問題について、人間はその答えを永遠に知りえないだろう」という意味で使用された。レーモンの主張は、当時のドイツ語圏において「イグノラビムス論争」と呼ばれる議論を引き起こした。
1880年の講演『宇宙の七つの謎』において、デュ・ボア=レーモンは科学には大きい7つの謎があるとした。それら7つの謎のうちの4つ(※印)は、単に現時点において謎であるだけでなく、永久に解決不可能な問題であろうとした。
1.物質と力の本性(※解決不可能)
2.運動の起源(※解決不可能)
3.生命の起源
4.自然の合目的的性質・効率的性質
5.単純な感覚的性質の起源・意識の起源(※解決不可能)
6.理性の起源、言語の起源
7.自由意志(※解決不可能)
■これに応じて、数学者ダフィット・ヒルベルトは「我々は知らねばならない、我々は知るであろう」 と応じた。
 ダーヴィット・ヒルベルト(David Hilbert)、 1862年1月23日 - 1943年2月14日 81歳没、ドイツの数学者。「現代数学の父」と呼ばれる。
ダーヴィット・ヒルベルト(David Hilbert)、 1862年1月23日 - 1943年2月14日 81歳没、ドイツの数学者。「現代数学の父」と呼ばれる。
1930年、ダフィット・ヒルベルトは、ケーニヒスベルクで行われた講演『自然認識と論理』において、デュ・ボア=レーモンの言葉を批判的に参照しつつ次のように述べた。
我々[数学者]にイグノラビムス[不可知]はない、また私が思うに、自然科学にもイグノラビムスはない。馬鹿げたイグノラビムスに対し、我々のスローガンはこうなるだろう。「我々は知らねばならない、我々は知るであろう」(Wir müssen wissen — wir werden wissen)。このように講演を締めくくった後で、ヒルベルトは声を上げて笑ったと伝えられている。
 ヒルベルトの墓碑:「我々は知らねばならない、我々は知るであろう」
ヒルベルトの墓碑:「我々は知らねばならない、我々は知るであろう」













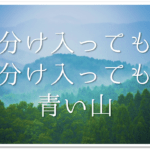













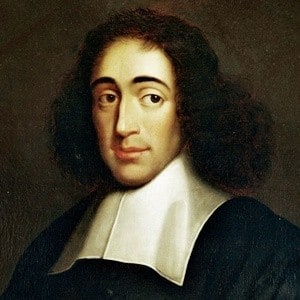
 ヒルベルトの墓碑(Wir mussen wissen ? wir werden wissen)
ヒルベルトの墓碑(Wir mussen wissen ? wir werden wissen) ピタゴラス(ラテン語: Pythagoras、英: Pythagoras、紀元前582年 - 紀元前496年)、古代ギリシアの数学者、哲学者。
ピタゴラス(ラテン語: Pythagoras、英: Pythagoras、紀元前582年 - 紀元前496年)、古代ギリシアの数学者、哲学者。 (Emil Heinrich Du Bois-Reymond)以下Wikipedia から引用
(Emil Heinrich Du Bois-Reymond)以下Wikipedia から引用 ダーヴィット・ヒルベルト(David Hilbert)、 1862年1月23日 - 1943年2月14日 81歳没、ドイツの数学者。「現代数学の父」と呼ばれる。
ダーヴィット・ヒルベルト(David Hilbert)、 1862年1月23日 - 1943年2月14日 81歳没、ドイツの数学者。「現代数学の父」と呼ばれる。

