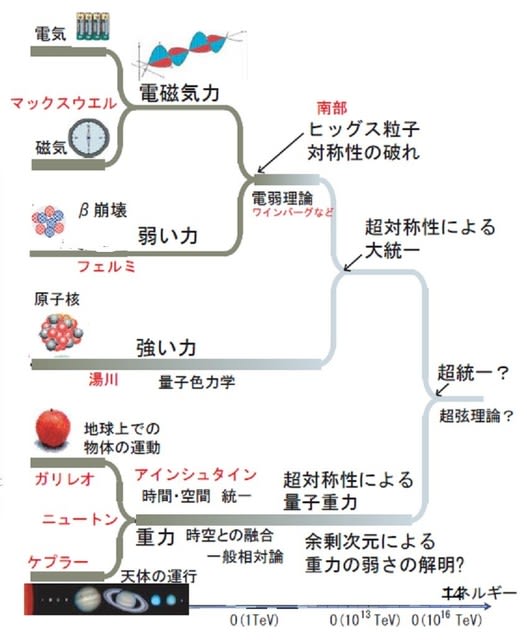脳トレ宇宙論 第34話 人類の見果てぬ夢-宇宙

・星空は美しい
星空は文句なく美しい そして 宇宙は神秘に満ちている。
星空は理屈抜きに美しく 純粋に魂を揺さぶり高揚するものがあり 未知なる宇宙への夢や憧れが重なっている。
さらに理屈を知ることが出来れば その美しさをもっと楽しめる。
宇宙はこんなに精緻にできている。宇宙は正確無比にして完璧である。自然の法則は素晴らしい。そして法則を理解できる理性を持った人間もまた素晴らしい。
・驚くほど良く見える天体望遠鏡には、人を感動させる力がある。
「見える」ではなく、「本格的に見える」から感動する。月の切り立ったクレーター、土星の見事な輪、木星のきれいな縞模様、・・・それらを見て、子供たちが走って伝えまわり、大人ですら声を上げて驚く。この反応は、中途半端な 「見える」 望遠鏡とは全く違う。
・見たものだけが語れることー宇宙飛行士の世界の手触り
宇宙飛行士が月にたどり着いたとき、窓から見えた地球を「マーブルの大きさ」と表現する。はじめはその美しさ、生命観に目を奪われていたが、やがて、その弱弱しさ、もろさを感じるようになる。感動する。宇宙の暗黒の中の小さな青い宝石。それが地球だ。その美しさは写真とは異なり、実際に見た者でなければ絶対に分からない、と彼らは口を揃える。
・科学の発展
科学は思索だけで成立することはない。
科学の強みは理論が事実によって保証される。
極微の世界、極限の世界では、それを知るのはもはや日常的な感覚や知性では不十分で、数学的表現のみがそれを精確に表しうることは明らかである。
科学にとって大切なことは理論を作るよりも、まず事実を観測することである。
事実の観察には鋭い感受性、精密な感覚が必要なほか、道具を作る、機械を作るという物質的な条件も必要である。
学問、科学の伝統、知識の成果、蓄積がないと研究は始まらない。加えて、常識、通説、通念に疑問を持ち、違うのではないかという批判をもち続けることが大切である。
先人の発見した科学を学ばずに自分の頭だけで考えることには限界がある。
専門の研究者の長い年月の思索と体験を通して学問は進歩する。
・天文学の発展ー未知との遭遇、宇宙の神秘へ、そして神秘から科学へ
天文学の魅力は天体現象の多様性、不思議さ・神秘性・超越性、無限の可能性があるからである。太古の昔から、人は夜空を見上げ、きらめく星々に神秘を感じ、宇宙の秘密を解く手掛かりを探し求めてきた。古代、神話や伝説に結びつけられていた宇宙の姿を天才たちの登場により徐々に宇宙の謎が解明されていく。
天文学はその起源をたどると、はるか紀元前から星々の観測が行われている、極めて古い学問である。人類史においても、その発展が人類全体の認識を大きく変えてきた。
事実は小説よりも奇なりと言われるが、現代宇宙論で展開されている理論の多くは想像以上に突飛なものであり、SFよりも奇なりといえるものさえある。
宇宙とは常識的に想像できる範囲を超えたものであり、宇宙を想像することは壮大で常識を超えた宇宙の視点で思考をすることでもある。
20世紀に入って、宇宙の基本的構成要素は銀河であること、つまり「銀河からなる宇宙」という描像が確立してまもなく、アインシュタインにより一般相対性理論が提出された。一般相対性理論は科学者に宇宙全体を探る理論を提供したと言える。宇宙がビッグバンによって138億年前に誕生し、現在も膨張を続けていると言われる現代の宇宙像は、一般相対性理論を使って宇宙を探求することから生まれてきた。一般相対性理論を直接証明するブラックホールの存在が今まで理論上「あるだろう」ということだったが、一般相対性理論誕生から100年以上が経過して初めてその「実在」が証明された。
ブラックホールの成果は宇宙の始まりの解明にも繋がり、銀河の形成に影響を与えるなど、天文学において大変重要かつ画期的なものである。このように天文学は壮大な学問で我々人類共通の謎にアプローチし続けており、常にホットな学問である。また同時に、なぜ自分たちが今という時代に生きているのかについても思いを馳せさせる。
若い頃の夢-相対性理論を数式で理解したいという夢。物理学を勉強した者は誰でも、いつか自分もこの偉大な理論を数式で理解できるようになれればと夢見る。自分には無理だと最初から諦めてしまう人が殆どだろう。しかし必ずしも物理そのものは決して難しくない。 ただ理解に達するために資料を調べ、考える時間が異常に長いことはよくある。
現在でも「宇宙」「ブラックホール」「重力波」など知らなくても生きていける。社会に出て直接これらを使うことはないかも知れない。しかしこれらを知らないで生きるのと、知って生きるのとではその人の活動、ひいては人生が違ったものになる。というのは宇宙進化の軌跡及び未来についての人類文明の曙から現代に至るまでの思考過程は、科学を含むあらゆる人間活動における複雑困難な問題解決の強力な指標となり参考になり得るものが豊富に存在するからである。
・時間・空間・人間
時は過ぎ去り、空は広がり、人は考える、時間とは何か 空間とは何か。哲学的に思索し、科学的に考え 文字で書き 芸術で表現し、音楽を奏で、疑問は次から次へと続き、解き明かすべく解答が次々とよせられ永遠に続く人類の見果てぬ夢である。
さて天文学や宇宙論に限らずあらゆる学問、自然科学も社会科学も数学も、さらに宗教は勿論、哲学や文学、芸術は、その根本にこの人類最大の謎を解き明かしたいという衝動、願望、情熱が憧憬のように息づいている。
その典型的かつ衝撃的な作品を残した画家ポール・ゴーギャンは1897年、作品《我々はどこから来たのか 我々は何者か 我々はどこへ行くのか》を描いた。ゴーギャンが晩年に問いかけたこの疑問はすべ ての人間に問いかけている。そして、天文学もそのことを追求してきて、同じ問いに 辿り着いているともいえる。
「なぜ宇宙があるのか?(Why is there a universe?)」
「なぜ世界があるのか?(Why is there a world?)」
「なぜ無ではないのか?(Why not nothing?)」
存在とは何か。宇宙はどのようにして出来上がり、どのような構造をしているのか。そして自分は何者なのか、どこから来てどこへ行くのか。 また生命とは何か。生きる意味はどこにあるのか。 この命題に対する答えを、あなたは持っているだろうか? 答えを持たなくても、人は生きていくことが出来る。忙しくしていれば、これらの問いに心をくだくことさえも忘れてしまうことだろう。けれども、ふと立ち止まった時に沸き上がってくる生きる上での根本的問いかけでもある。
・我々はどこへ行くのか
現代は科学や機械文明の進展や成果によって、皆が上を向いた生活に明け暮れているようある。世界中は刻苦精励の根性や気概が薄らいでいくようであり、人間所在の影が薄くなっている。いわゆる近代化が急速度に進む中で、気が付いてみると人間不在の仕組みの中に我々みんなが落ち込んでいるということになりかねない。今の不安はそこにある。近代的に合理化された機械や仕組みの社会に埋没してしまった人間をもう一度救い出す理念が必要ではなかろうか。
科学と科学技術の発展は、杜会を科学技術に向かってさらに加速させる。好むと好まざるとに拘わらず、その知識と技術は実在し、我々はそれを積極的に吸収し利用するか、あるいは無知のまま留まるかの二者択一に迫られることになる。
・科学技術が人間社会において単なる増幅器だとすると、テクノロジーは人類の貧困を救わない、何を増幅すのかを問わざるをえないし、技術以外に必要なものを問う。ミシガン大、外山健太郎。
・現代に響く思考停止へ警鐘ードイツ出身の政治哲学者ハンナ・アーレント
自分がやっていることの意味を深く考えない行為、自分のやっていることの意味を考えない普通の人が、途方もない災厄を引き起こす。アーレントが「悪の陳腐さ」と呼ぶ考え方は現代の様々な社会事件を捉える上でも有効だ。これに対抗するには、個人個人が自分と対話しながら、行いの意味を問い続けるしかない。
・アポリア・思考を放棄して袋小路へー米の社会学者、ウオーラーステイン
現代文明は深刻なアポリア(袋小路、難問)に入り込んだと見る。グローバル化が進めば進むほど、狭くなった地球上での富の格差が広がるばかりだ。科学は核のように環境を後戻りできない形で変えてしまう力を持つ技術を生み出し、一方では生命は大切だと言う人類が共有してきた価値観や規範は大きく揺らいでいる。
事態を一層複雑にしているのは、そうした今日的な問題に取り組む哲学や思想も袋小路に迷い込んでしまった事だという。哲学や思考の無力が実感され、社会の中に一種の思考の放棄ともいえる現象が広がっている。
個人が脳を鍛えれば何か問題が解決するというのは幻想である。人間を部分ごとに考えていては、いつまでも袋小路からは抜け出せない。生きる喜びを持つ本来の人間を取り戻すためには、立ち止まって全体を振り返ることが大切なはずだ。
・大きな物語、冬の精神が次の時代開くーポストモダン思想を代表するフランスの哲学者レオタール
もう大きな物語の時代は終わった。今の時代の顕著な変化は歴史の進歩や人間の解放という近代が目指してきた大きな物語を人々が信じなくなったことなのだ。大きな物語が消えるとともに、その担い手だった知識人の時代は終わった。正義や理想といった、人類にとって共通の目標や普遍的な価値観
も失われたという。これからは人々は断片化した自分たちだけの小さな物語の中で生きるしかなくなった。
大切なのは物事をただありのまま見るのではなく、それはいかにしてそうなったかを見ることだ。春が近づく気配を予感しながら希望の季節をただ待ち続けるだけでなく、あえて寒風に身を晒す。今が困難な冬の時代だからこそ、厳しい冬の精神を持たなければならない、とサイードは考えた。
21世紀のいま、人類共通の大きな理想ではなく自分たちだけの閉ざされた物語を美化する動きが広がっている。無意識のうちに集団志向に流れる空気もある。孤立を恐れずに逆風に向かい、熱狂や集団思考から遠ざかる。冬の精神が受け継がれた時に初めて、次の時代の新しい物語は見えてくる。
・ブッダの声ー「世界は美しいもの、人の命は甘美なもの」
今や文明の発達は、人間の寿命を引き延ばし、一人ひとりが自分の余生と終の生をいかに過ごすかを真剣に考えねばならない時代となった。自分の一生をどのように生きればよいか、その問いかけは無限の答えがあり、過去の賢者の言葉や神託なども思い浮かばれよう。
仏教を開いたブッダは、人生は苦である、と説いた。生老病死のすべてが苦である、すべては移ろいゆく、よって精進努力せよと。
やがて悟りを得たブッダは最晩年「世界は美しいもので、人の命は甘美なものだ」と表現したとある。なぜか安堵感を与える言葉である。
(宇宙は精緻にできている。宇宙は正確無比にして完璧である。自然の法則は素晴らしい。そして法則を理解できる理性を持った人間もまた素晴らしい。ーーーこれに通じるブッダの言葉である)
・世界は意味があるわけでもないし不条理であるわけでもない。ただ単にそれは存在するだけだ。仏作家、ロブ・グリエ。