脳トレ宇宙論 第4話 星空は美しい
星空は文句なく美しい
星空は理屈抜きに美しい。純粋に魂を揺さぶり高揚する。そして宇宙は神秘に満ちている。未知なる宇宙への夢や憧れが重なっている。さらに理屈を知ることが出来れば、その美しさをもっと楽しめる。
・天の川 見果てぬ夢に かける橋(森谷真理)
・天の川 わたるおたふく 豆一列(加藤楸邨)
荒波すさぶ夜の日本海。はるかな闇の中に佐渡の島影が黒々と横たわり、その中天高く銀河が横切って、初秋の冴えた夜空に光っている。「荒海」と「佐渡」で陰鬱な日本海の特質を形象化し、これに銀河を配した雄大な宇宙的把握の中に、おのずから人間の卑小感、寂寥感がこもっている。また芭蕉は佐渡を、重罪人遠流の哀史を背景に悲しく眺めている。その哀愁が大自然の把握に漂っている。
漆黒の闇
月明かりの無い夜は文字通り「漆黒の闇」。星座や天体に興味の無い人でも、天の川の凄さにはきっと感動する。訪れる人が最初に驚くことは、深い山と自然、そして夜が深まればやって来る漆黒の闇。我々現代人が、夜いかに明るい場所で暮らしているかを痛感させられる。月が出ていれば、その明るさにも驚く。そして頭上には、都会では決して見ることのできない星空が広がる。満天の星空というありきたりな表現では言い表せないほどの光り輝く無数の星に感動を覚えずにはいられない。星を見るために暗いところを求めてやってきたのだが、想像以上に暗い。そして単独1人でいると、励ましてくれる人もいなければ、明かりを灯してくれる人もいない。静寂の暗闇に1人でいるというのが急に恐ろしくなってくる。
 漆黒の闇に浮かぶ地球と月 NASA
漆黒の闇に浮かぶ地球と月 NASA
良く見える天体望遠鏡には人を感動させる力がある
月の切り立ったクレーター。土星の見事な輪。木星きれいな縞模様・・・それらを見て、子供たちが走って伝えまわり、大人ですら声を上げて驚く。この反応は、中途半端な 「見える」 望遠鏡とは全く違う。「見える」ではなく、「本格的に見える」から感動する。
空に向かいカメラを構え、天空写真を撮影して月が沈むのを待った。「けっこう明るい!」と思わず驚嘆する。月が思ったより強い光で私たちを照らしている。夜といえども月や街の明かりで割と明るい。星を撮影するには、月が沈むのを待たないと星の光がかすんでしまう。
口径30センチの大きな天体望遠鏡を取り出して月を見る。月は手が届きそうなほど近く、ざらざらしたクレーターやウサギの模様がくっきり見え、触ることができそうなほどだ。 静寂の中、天体望遠鏡に携帯電話のカメラレンズを近づけて撮影した。月のクレーターやウサギの模様がはっきり見える。時々虫の声や国道を通るトラックの音が聞こえる以外は本当に静かだ。今ここに存在しているのは空と私だけ。そう考えると“下界”での日常がだんだん遠い出来事になっていくのを感じた。今まで夜はひたすら深夜番組ばかり見ていたが、「野外にこんなにすてきな景色があるのに、あんな小さな部屋にこもっていたのか」としみじみと感じる。
やがて月が山陰に沈むと、辺りはぐっと暗くなり、空のスクリーンの主役は星たちに変わる。降り注ぐような無数の星くずの中からオリオン座やおおいぬ座、冬の大三角形などが次々に姿を現し「私を撮って!」と言わんばかりに瞬く。感動して「天然のプラネタリウムだ」と頓珍漢な感想!。
天の川が見えない人口、欧州60%、北米80%
全世界の夜空を網羅した最新の光害マップが公表され、世界人口の80%以上、そして米国と欧州の人口の99%が、人工光の影響下に暮らしていることが分かった。また世界人口の3分の1以上、ヨーロッパの人々の60%、北米の人口のほぼ80%が天の川を肉眼で見られないことも分かった。シンガポールでは、全国民があまりに明るい環境で暮らしているため、天の川を見ることができない。クウェート、カタール、アラブ首長国連邦でも状況は同様だ。一方、チャド、中央アフリカ共和国、マダガスカルに住む人々の75%は、ほぼ自然本来の空(背景光が空全体の明るさの1%未満)の下に暮らしている。
この15年ぶりに作成された全世界の「光害マップ」は、イタリアのティエーネにある光害科学技術研究所(ISTIL)の研究者(ファビオ・ファルキ)が2016年6月、世界各地で見られる夜空の質を示した新たな調査結果であり、35000カ所以上にわたる地上から観測結果と、地球観測衛星スオミNPPが2014年から6カ月間で収集したデータから作った。
前回の光害マップから、地球上の夜空がどうなっているかの手がかりが得られたが、今回判明した数値は衝撃的である。かつては夜空を眺めることで、文学や哲学、科学、宗教が生まれた。漆黒の夜空を流れる天の川は、はるか昔から人間にインスピレーションを与え続けてきた。古代エジプト人は夜空に牛乳がたまっていると言い、ヒンドゥーの神話では空で孤を描くその姿を、泳ぐイルカとなぞらえた。またガリレオ、アリストテレス、ゴッホをはじめとする無数の科学者、哲学者、芸術家が、天の川を見上げながら思索にふけったと言われている。
それなのに、私たちは星空とのつながりを失ってしまった。新たな世代は、もう夜空の美しさを楽しむことができない。 数十年前は自宅近くで眺められた満天の星が、今や特別な場所まで行かなければ見られない。それでも、人々は星空を眺めることがいかに貴重であるかを認識し始め、今や星空はお金を出して見に行くものになりつつある。地球全体を眺め、本来は暗い夜を過ごすための能力が、現代のライフスタイルに蝕まれていることを考えると、私たちがいかに『明るい夜』に慣れきってしまっているかがわかる。
 もうすぐ漆黒の闇
もうすぐ漆黒の闇
暗い夜を取り戻すために化学物質、粒状物、一酸化炭素などの汚染物質のほか、光による汚染も同様に、減らしていくことが必要である。 おそらく大都会に住んでいる人たちにとっては、夜空を眺めてもスモッグに覆われた空はぼんやりと霞んでいて、街中の灯りの洪水が星のきらめきをすっかり隠してしまっているので、空には何も見えないかもしれない。でも、少しだけ都会を離れて空気の澄んだところに行ってみると、夜空にはけっこうたくさんの星がちりばめられていることを実感して、新鮮な驚きを覚える。そして、人があまりいない山や海に出かけてみれば、夜の空には思いもかけないほどの数の光がぎっちりと詰まっていて、その驚異の世界がまるで自分に強く迫ってくるような感じがして、大きな感動を覚えることであろう。



























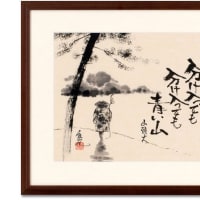

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます