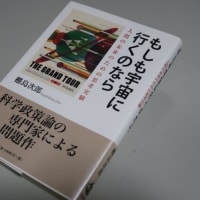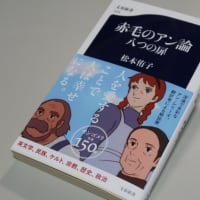☆『石となった死』(香原志勢・著、弘文堂、1989年)☆
何の因果か心疾患を持って生まれてきた身上ゆえに、若い頃から「死」というものを身近に感じて生きてきた。もう少し正確にいうと、そんな想いとともに生きてきたはずだと思っていた。がしかし、そう思い込みたかっただけなのかもしれない、と最近は思い直している。たしかに健常者と比べれば不自由なことも多々あったし、そもそも病因が生命に直結している心臓にあるということで、死との距離感が近いと感じても不思議はない。他人事のように客観視すれば、そのように思い込みたい気持ちも理解できそうだ。
しかし、歳を重ね、実際に老いが加速しはじめ、身体や生活面での不自由度も現実的に日に日に増してくると、若い頃に身近に感じていた死というものが、何と観念的で実態(あるいは実体)の伴わないものだったのだろうと思う今日この頃である。
そんなある日、何とはなしに本棚を眺めていて、タイトルがちょっと気になり本書を手に取った。奥付を見ると平成元年(1989年)12月10日発行の初版本。アマゾンの購入履歴にも出てこないので、どこかの書店で買ったのだろうがまったく覚えがない。
ページをパラパラとめくってみると、そもそも読んだ覚えもない。著者の香原志勢さんは著名な自然人類学者で、『人類生物学入門』(中公新書)や『人体に秘められた動物』(NHKブックス)は興味深く読んだ覚えがあるのに、不思議なことに本書は覚えがないのである。この二冊は本棚の手の届くところに並んでいた。その流れで買った本なのかもしれない。
本書はまた「叢書・死の文化」の中の1冊なのだが、同叢書中の『終末期医療』(大井玄・著)、『遺伝管理社会』(米本昌平・著)、『巨大事故の時代』(高木仁三郎・著)の三冊は買った覚えがある。完全に読み終えたかどうかはわからないけれど。その三冊は目の届く場所にはなかったが、無くしていなければ本棚か押入れのどこかにあるはずだ。ひょっとしたら、その叢書シリーズの流れで買った本だったのかもしれない。
さて、本書は出版から30年以上も経っているわけだが、中身はまったく古さを感じさせなかった。もちろん細かな事実を現在の事実を照らし合わせれば異なる部分もあるのだろうが、著者の主張は至極まっとうであり、観念的に死を論じただけの著作とは一線を画している。
そんな魅力の一つには、著者が生物学を基盤とした自然人類学の研究者であったことが大きくはたらいているのだろうと思う。そしてもう一つには、著者が経験してきた多彩とでも表現すべき死との出逢いにあるにちがいない。多彩な死との出逢いは、職業上での出来事のみならず個人的な事件にも及んでいる。
1950年、著者は大学院(東京大学理学部人類学教室)在学中にアメリカ(在日占領軍総司令部、いわゆるGHQ)の要請で、朝鮮戦争での米軍戦死者の個人識別の「アルバイト」に参加した。本書の第一章「死神が見えた頃」は「大学院学生向きの高級アルバイトのつもりで引き受けたが、事柄はそんななまやさしいものではなかった」というまさしく生々しい描写からはじまる。
本章のサブタイトルは「戦死体の個人識別とエンバーマー」となっていて、すでに「エンバーマー」という言葉が使われていたのに少し驚かされた。余談ながら、個人的にはタレントの壇蜜さんが「エンバーマー」の資格を取得していたことからその名称と業務を知った。いずれにしても、著者が人類学を専攻していたからこその死との出逢いだったといえるだろう。
著者はまた何人もの近親者の死を看取っている。戦前の1936年の秋にまだ16歳だった長姉を結核性髄膜炎で亡くした。仕事がら多数の遺体を見てきた著者が言うには、長姉の死顔かもっともきれいだったそうである。著者は「聖少女」とも表現しているが、「その年頃の娘の死顔を他に一つも見ていない」からなのかもしれないと述懐している。
やがて時局は本格的な戦争の時代へと突入し、東京をはじめ日本国内各地が空襲され、いやが上にも身近で遺体と対面せざるを得ない人たちが増えていく。1945年5月の東京大空襲で45歳の母親と重度身体障害者(肢体不自由)であった13歳の妹の二人を著者は亡くした。ふつうに葬儀や火葬などできるはずもなく、父親とともに廃墟の中で二人を荼毘に付した。この様相の描写は感動を誘うなどと軽々しく書くことはできず、著者の淡々とした筆致はむしろ逆に、読む者の脳裏にさまざまな感情を想起させ、こころの奥底に何かを焼き付けてくるかのようだ。
さらに敗戦後の1945年11月に、著者の三歳上で19歳の姉を栄養失調で亡くした。著者は「何も恥じることのない戦争犠牲者」と書いているが、まったく同感である。近年、地震などの災害に関連して「災害関連死」という言葉(概念)が使われるようになったが、戦争こそが最大の「災害関連死」を生み出していると言わざるを得ない。さらに問題なのは、その「災害」が自然由来ではなく人間の愚行によるものであることだ。
ここまで著者の個人的な死との出逢いばかり書いてきたが、人類学者としての話題も豊富に語られている。たとえば死の意義に関連して、ネアンデルタール人が遺体に花を添えた埋葬をしていたことについて「ザ・ファースト・フラワー・ピープル(最初に花を愛でた人びと)」として紹介している(この事実関係については近年異論もあるようだが)。
上記シャニダール洞窟での発掘に関連して驚くべきことも紹介されていた。落石事故によって死亡したと思われる人骨も発見されたのだが、それを精査したところ骨折した左腕に治療した痕があり、彼は落石事故後に身体障害者として生きながらえたにもかかわらず、再び災禍によって事故死したものと考えられるという。当時は仲間の扶助がなければ彼は生きていけなかったと想像され、著者はネアンデルタール人の人間性の開花の証しと見ている。障害者として余計なことを一言付け加えれば、ネアンデルタール人にももとる現代人の多さに暗澹とさせられる。
著者がいうように、われわれは生と死を対立概念として捉えている。しかし、生がなければ死はありえない。だから無生物に死はない。また、生と死もどちらも抽象概念だが、生は時の流れに伴う「時間的概念」であるのに対して死は時の流れの中の一点という「時刻的概念」であるという。
著者のこの主張を踏まえて思うに、どちらも抽象概念であっても、死は一瞬という時刻的概念であるがゆえに、より抽象度が高く観念的にならざるを得ないのではないだろうか。死を脳死とするか心臓死とするか、あるいは他の指標を用いるかは社会的に決めざるを得ないのは、死の一瞬を捉えることの困難さに基づいているように思われる。
このことは「老い」と死の関係についてもいえるのではないだろうか。老いは死とイコールではないにもかかわらず、老いが積み重なって死に至るとわれわれは考えがちである。しかし、いつ死の一瞬が訪れるのかは予測のしようがない。老いはあくまで生の領域に属しているので、老いの実態を捉えることは一応できることになる。しかし、死は実態として捉えられないからには観念として捉えるほかはない。
だからといって、頭の中で観念をいじくり回していても埒が明かない。やはり実体としての生き物である身体のことを考慮すべきではないか。死は観念ではあるけれども、観念論だけで対峙するのではなく、単なる観念論を超えて、いま一度考えてみるべきではないか。著者である香原さんの主張、あるいは本書の主旨と異なるかもしれないが、自らの読後感をまとめればそこに行き着きそうだ。
タイトルの「石となった死」は化石の連想からきていることは容易に想像がつくだろうが、化石や石と化した骨には過去の生き物の姿や行動が記録されているのだという。著者は自らの職業を「石の中に生物の死を見つけ、その死からさらに生物の生き方を読みとる学者」としている。日々老いと向かい合いながら生と死について考えざるを得ない今日、本棚で本書が目に止まったことは僥倖のようにも思えてくる。
細かな事実関係はさておき本書の内容に古さは感じないと前述した。その一方でテクノロジーは本書の出版当時とは比較にならないほど長足に進歩している。その影響を受けて、今日の死生観は根本から揺らいでいるように思われる。それは死の観念自体の揺らぎにもつながっているのではないだろうか。そんな時代だからこそ、原点にもどってみる必要があるように思う。その意味では、本書は「故きを温ねて新しきを知る」ための韋編三絶の書といえるだろう。
本書が執筆されていた時点で、著者の香原志勢さんと栄養失調で亡くなった姉の上の姉が存命であり、また父親は1982年に脳梗塞で85歳の生涯を閉じたられたとのこと。ウィキペディアによると香原さんご自身は2014年11月16日に肺炎により86歳で死去されたという。本書との出逢いに感謝しつつ、謹んでご冥福をお祈りする次第である。

何の因果か心疾患を持って生まれてきた身上ゆえに、若い頃から「死」というものを身近に感じて生きてきた。もう少し正確にいうと、そんな想いとともに生きてきたはずだと思っていた。がしかし、そう思い込みたかっただけなのかもしれない、と最近は思い直している。たしかに健常者と比べれば不自由なことも多々あったし、そもそも病因が生命に直結している心臓にあるということで、死との距離感が近いと感じても不思議はない。他人事のように客観視すれば、そのように思い込みたい気持ちも理解できそうだ。
しかし、歳を重ね、実際に老いが加速しはじめ、身体や生活面での不自由度も現実的に日に日に増してくると、若い頃に身近に感じていた死というものが、何と観念的で実態(あるいは実体)の伴わないものだったのだろうと思う今日この頃である。
そんなある日、何とはなしに本棚を眺めていて、タイトルがちょっと気になり本書を手に取った。奥付を見ると平成元年(1989年)12月10日発行の初版本。アマゾンの購入履歴にも出てこないので、どこかの書店で買ったのだろうがまったく覚えがない。
ページをパラパラとめくってみると、そもそも読んだ覚えもない。著者の香原志勢さんは著名な自然人類学者で、『人類生物学入門』(中公新書)や『人体に秘められた動物』(NHKブックス)は興味深く読んだ覚えがあるのに、不思議なことに本書は覚えがないのである。この二冊は本棚の手の届くところに並んでいた。その流れで買った本なのかもしれない。
本書はまた「叢書・死の文化」の中の1冊なのだが、同叢書中の『終末期医療』(大井玄・著)、『遺伝管理社会』(米本昌平・著)、『巨大事故の時代』(高木仁三郎・著)の三冊は買った覚えがある。完全に読み終えたかどうかはわからないけれど。その三冊は目の届く場所にはなかったが、無くしていなければ本棚か押入れのどこかにあるはずだ。ひょっとしたら、その叢書シリーズの流れで買った本だったのかもしれない。
さて、本書は出版から30年以上も経っているわけだが、中身はまったく古さを感じさせなかった。もちろん細かな事実を現在の事実を照らし合わせれば異なる部分もあるのだろうが、著者の主張は至極まっとうであり、観念的に死を論じただけの著作とは一線を画している。
そんな魅力の一つには、著者が生物学を基盤とした自然人類学の研究者であったことが大きくはたらいているのだろうと思う。そしてもう一つには、著者が経験してきた多彩とでも表現すべき死との出逢いにあるにちがいない。多彩な死との出逢いは、職業上での出来事のみならず個人的な事件にも及んでいる。
1950年、著者は大学院(東京大学理学部人類学教室)在学中にアメリカ(在日占領軍総司令部、いわゆるGHQ)の要請で、朝鮮戦争での米軍戦死者の個人識別の「アルバイト」に参加した。本書の第一章「死神が見えた頃」は「大学院学生向きの高級アルバイトのつもりで引き受けたが、事柄はそんななまやさしいものではなかった」というまさしく生々しい描写からはじまる。
本章のサブタイトルは「戦死体の個人識別とエンバーマー」となっていて、すでに「エンバーマー」という言葉が使われていたのに少し驚かされた。余談ながら、個人的にはタレントの壇蜜さんが「エンバーマー」の資格を取得していたことからその名称と業務を知った。いずれにしても、著者が人類学を専攻していたからこその死との出逢いだったといえるだろう。
著者はまた何人もの近親者の死を看取っている。戦前の1936年の秋にまだ16歳だった長姉を結核性髄膜炎で亡くした。仕事がら多数の遺体を見てきた著者が言うには、長姉の死顔かもっともきれいだったそうである。著者は「聖少女」とも表現しているが、「その年頃の娘の死顔を他に一つも見ていない」からなのかもしれないと述懐している。
やがて時局は本格的な戦争の時代へと突入し、東京をはじめ日本国内各地が空襲され、いやが上にも身近で遺体と対面せざるを得ない人たちが増えていく。1945年5月の東京大空襲で45歳の母親と重度身体障害者(肢体不自由)であった13歳の妹の二人を著者は亡くした。ふつうに葬儀や火葬などできるはずもなく、父親とともに廃墟の中で二人を荼毘に付した。この様相の描写は感動を誘うなどと軽々しく書くことはできず、著者の淡々とした筆致はむしろ逆に、読む者の脳裏にさまざまな感情を想起させ、こころの奥底に何かを焼き付けてくるかのようだ。
さらに敗戦後の1945年11月に、著者の三歳上で19歳の姉を栄養失調で亡くした。著者は「何も恥じることのない戦争犠牲者」と書いているが、まったく同感である。近年、地震などの災害に関連して「災害関連死」という言葉(概念)が使われるようになったが、戦争こそが最大の「災害関連死」を生み出していると言わざるを得ない。さらに問題なのは、その「災害」が自然由来ではなく人間の愚行によるものであることだ。
ここまで著者の個人的な死との出逢いばかり書いてきたが、人類学者としての話題も豊富に語られている。たとえば死の意義に関連して、ネアンデルタール人が遺体に花を添えた埋葬をしていたことについて「ザ・ファースト・フラワー・ピープル(最初に花を愛でた人びと)」として紹介している(この事実関係については近年異論もあるようだが)。
上記シャニダール洞窟での発掘に関連して驚くべきことも紹介されていた。落石事故によって死亡したと思われる人骨も発見されたのだが、それを精査したところ骨折した左腕に治療した痕があり、彼は落石事故後に身体障害者として生きながらえたにもかかわらず、再び災禍によって事故死したものと考えられるという。当時は仲間の扶助がなければ彼は生きていけなかったと想像され、著者はネアンデルタール人の人間性の開花の証しと見ている。障害者として余計なことを一言付け加えれば、ネアンデルタール人にももとる現代人の多さに暗澹とさせられる。
著者がいうように、われわれは生と死を対立概念として捉えている。しかし、生がなければ死はありえない。だから無生物に死はない。また、生と死もどちらも抽象概念だが、生は時の流れに伴う「時間的概念」であるのに対して死は時の流れの中の一点という「時刻的概念」であるという。
著者のこの主張を踏まえて思うに、どちらも抽象概念であっても、死は一瞬という時刻的概念であるがゆえに、より抽象度が高く観念的にならざるを得ないのではないだろうか。死を脳死とするか心臓死とするか、あるいは他の指標を用いるかは社会的に決めざるを得ないのは、死の一瞬を捉えることの困難さに基づいているように思われる。
このことは「老い」と死の関係についてもいえるのではないだろうか。老いは死とイコールではないにもかかわらず、老いが積み重なって死に至るとわれわれは考えがちである。しかし、いつ死の一瞬が訪れるのかは予測のしようがない。老いはあくまで生の領域に属しているので、老いの実態を捉えることは一応できることになる。しかし、死は実態として捉えられないからには観念として捉えるほかはない。
だからといって、頭の中で観念をいじくり回していても埒が明かない。やはり実体としての生き物である身体のことを考慮すべきではないか。死は観念ではあるけれども、観念論だけで対峙するのではなく、単なる観念論を超えて、いま一度考えてみるべきではないか。著者である香原さんの主張、あるいは本書の主旨と異なるかもしれないが、自らの読後感をまとめればそこに行き着きそうだ。
タイトルの「石となった死」は化石の連想からきていることは容易に想像がつくだろうが、化石や石と化した骨には過去の生き物の姿や行動が記録されているのだという。著者は自らの職業を「石の中に生物の死を見つけ、その死からさらに生物の生き方を読みとる学者」としている。日々老いと向かい合いながら生と死について考えざるを得ない今日、本棚で本書が目に止まったことは僥倖のようにも思えてくる。
細かな事実関係はさておき本書の内容に古さは感じないと前述した。その一方でテクノロジーは本書の出版当時とは比較にならないほど長足に進歩している。その影響を受けて、今日の死生観は根本から揺らいでいるように思われる。それは死の観念自体の揺らぎにもつながっているのではないだろうか。そんな時代だからこそ、原点にもどってみる必要があるように思う。その意味では、本書は「故きを温ねて新しきを知る」ための韋編三絶の書といえるだろう。
本書が執筆されていた時点で、著者の香原志勢さんと栄養失調で亡くなった姉の上の姉が存命であり、また父親は1982年に脳梗塞で85歳の生涯を閉じたられたとのこと。ウィキペディアによると香原さんご自身は2014年11月16日に肺炎により86歳で死去されたという。本書との出逢いに感謝しつつ、謹んでご冥福をお祈りする次第である。