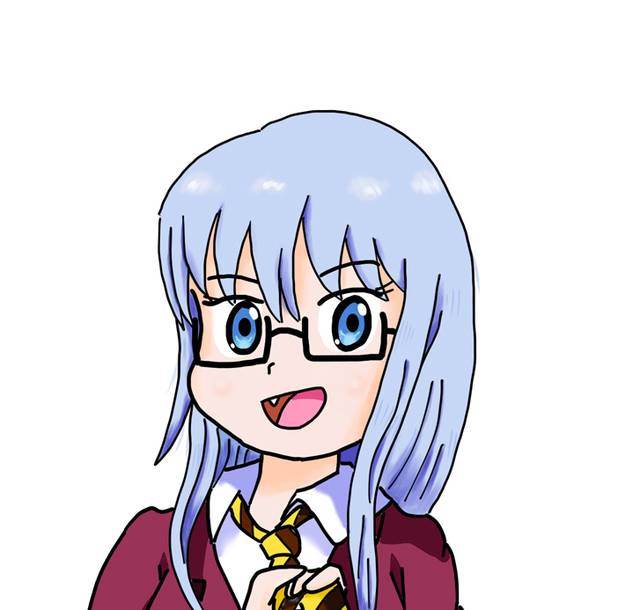最近ミニがモデルチェンジした?ようだ。お洒落な車として感性の高い人たちにはなかなかの人気である。まぁ、高いけど・・ 現在BMWが手がけるミニは5種類のモデルが輸入されいる。1.6リッター・ターボエンジン搭載モデルの「ミニ・クーパーS」と1.6リッターNAエンジン搭載モデルの「ミニ・クーパー」、1.4リッターNAエンジン搭載モデルの「ミニ・ワン」、それとコンバーチブルとワゴン?タイプのクラブマンの5モデルである。
一番ベーシックな「ミニ・ワン」の6速ATモデルに試乗した。こういうコンパクトカーは素のベーシックモデルが一番美味しいのだ。特に輸入車は国産車のように廉価モデルの質を落とすようなことは無いのでその車が持つ基本的な性格がそこにすべて現れるのだ。上級モデルのエンジンを強化したり、サスをスポーツタイプに引き締めたものもそれなりに良いがわしはそういうのはあまり好かん。出来ればMTモデルに乗りたかったが「ミニ・ワン」のMTモデルはほとんど輸入しておらず注文を受けてから本国に発注するそうだ。従って注文してから納車になるまで3〜4ヶ月かかる。ひどい話だ。
さて「ミニ・ワン」の1.4リッターエンジンは実はBMWとプジョーの共同開発のエンジンで最新のプジョー207にも積まれている。最近は欧州メーカーも開発費が巨額になるエンジンなんかを共同開発するのが流行っている。基本スペックは皆同じだがメーカーによって味付けはかなり違うようだ。BMWの場合はかなり高回転まで回して面白い!という味付けだそうだ。(プジョー207にも乗って比較しないと本当のところはわからないけど)
で、乗ってみた感触は「この大きさの車ならこのエンジンで十分じゃん」であった。エンジンに負荷をかけるため常時エアコンをONにした状態で街中、高速と走ってみた。信号待ちから発進するときはかったるさを感じる(セールスによるとわざとそういうふうにしてるそうだ。なぜそんなことするのかよくわからんが)が一度スピードさえ乗ってしまえば何の不満も無い。まぁ、これは国産のコンパクトカーでも同じだろうが。
驚いたのは高速道路を走ってみたとき。これがまぁよく走る。特に追い越し加速はまったくストレスを感じない。動力性能的には1.4でなんら問題ない。特に6速という多段ATがエンジンの力を目一杯引き出してるんだろう。しかもビシ!っとした直進安定性はわしのレガシィB4と比べても全然遜色ない。さすがはBMW直系の車だ。この2,465mmと短いホイールベースで時速140k以上出してこの直進安定性の凄さには舌を巻いた。
乗り心地も「ワン」の175/65 15インチの標準タイヤと標準サスの組み合わせはかなり良い感じ。ピッチングもほとんど感じないし、サスの柔らかい当たりがかなり乗り心地をよくしている。セールスさんによると「クーパーS」や「クーパー」はこの「ミニ・ワン」よりは明らかに乗り心地が堅いそうだ。助手席に乗る人によっては苦情が出ることもあるそうな。まぁ、そこは人による好みの問題なので否定する気は無い。わしの好みは「ワン」の方だと言うことだ。
総じて良く出来た車である。インテリアのデザインも遊んでいて超個性的。質感も高いし非常におっしゃれー!!である。ただ高速走行時に出た変な風きり音だけはちょっと気になった。時速120k〜140kあたりでフロントガラス左サイドから出た音である。最初は左サイドのウィンドウから出てるのかと思ったがどうも左ワイパーが浮いて?音が出てるらしい。セールスさんに聞いたらこれはミニに共通の現象らしい。まぁ、法定速度守ってたら出る音じゃないけどね。
またカタログを見ていたらオプションが物凄く多い。それもエクステリアの部品もさることながらインテリアに関してトリムなどいろんなカラーや柄を選べる。全部メーカーオプションであるが自分だけのカスタム化が可能である。見てるだけで楽しいカタログだがいざ実際に選ぼうとすると頭が痛くなるくらいである。もっとも調子に乗ってオプション付けまくってたらとんでもない金額になるけどね。そういう意味ではまさしく趣味!!の世界の車である
一番ベーシックな「ミニ・ワン」の6速ATモデルに試乗した。こういうコンパクトカーは素のベーシックモデルが一番美味しいのだ。特に輸入車は国産車のように廉価モデルの質を落とすようなことは無いのでその車が持つ基本的な性格がそこにすべて現れるのだ。上級モデルのエンジンを強化したり、サスをスポーツタイプに引き締めたものもそれなりに良いがわしはそういうのはあまり好かん。出来ればMTモデルに乗りたかったが「ミニ・ワン」のMTモデルはほとんど輸入しておらず注文を受けてから本国に発注するそうだ。従って注文してから納車になるまで3〜4ヶ月かかる。ひどい話だ。
さて「ミニ・ワン」の1.4リッターエンジンは実はBMWとプジョーの共同開発のエンジンで最新のプジョー207にも積まれている。最近は欧州メーカーも開発費が巨額になるエンジンなんかを共同開発するのが流行っている。基本スペックは皆同じだがメーカーによって味付けはかなり違うようだ。BMWの場合はかなり高回転まで回して面白い!という味付けだそうだ。(プジョー207にも乗って比較しないと本当のところはわからないけど)
で、乗ってみた感触は「この大きさの車ならこのエンジンで十分じゃん」であった。エンジンに負荷をかけるため常時エアコンをONにした状態で街中、高速と走ってみた。信号待ちから発進するときはかったるさを感じる(セールスによるとわざとそういうふうにしてるそうだ。なぜそんなことするのかよくわからんが)が一度スピードさえ乗ってしまえば何の不満も無い。まぁ、これは国産のコンパクトカーでも同じだろうが。
驚いたのは高速道路を走ってみたとき。これがまぁよく走る。特に追い越し加速はまったくストレスを感じない。動力性能的には1.4でなんら問題ない。特に6速という多段ATがエンジンの力を目一杯引き出してるんだろう。しかもビシ!っとした直進安定性はわしのレガシィB4と比べても全然遜色ない。さすがはBMW直系の車だ。この2,465mmと短いホイールベースで時速140k以上出してこの直進安定性の凄さには舌を巻いた。
乗り心地も「ワン」の175/65 15インチの標準タイヤと標準サスの組み合わせはかなり良い感じ。ピッチングもほとんど感じないし、サスの柔らかい当たりがかなり乗り心地をよくしている。セールスさんによると「クーパーS」や「クーパー」はこの「ミニ・ワン」よりは明らかに乗り心地が堅いそうだ。助手席に乗る人によっては苦情が出ることもあるそうな。まぁ、そこは人による好みの問題なので否定する気は無い。わしの好みは「ワン」の方だと言うことだ。
総じて良く出来た車である。インテリアのデザインも遊んでいて超個性的。質感も高いし非常におっしゃれー!!である。ただ高速走行時に出た変な風きり音だけはちょっと気になった。時速120k〜140kあたりでフロントガラス左サイドから出た音である。最初は左サイドのウィンドウから出てるのかと思ったがどうも左ワイパーが浮いて?音が出てるらしい。セールスさんに聞いたらこれはミニに共通の現象らしい。まぁ、法定速度守ってたら出る音じゃないけどね。
またカタログを見ていたらオプションが物凄く多い。それもエクステリアの部品もさることながらインテリアに関してトリムなどいろんなカラーや柄を選べる。全部メーカーオプションであるが自分だけのカスタム化が可能である。見てるだけで楽しいカタログだがいざ実際に選ぼうとすると頭が痛くなるくらいである。もっとも調子に乗ってオプション付けまくってたらとんでもない金額になるけどね。そういう意味ではまさしく趣味!!の世界の車である