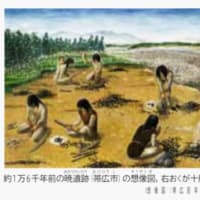八戸市博物館。青森県八戸市根城。
2022年10月1日(土)。



国史跡・丹後平(たんごたい)古墳群は、馬淵川の支流・土橋川に面した標高90~100mのなだらかな丘陵に位置する主に7世紀後半から9世紀後半の飛鳥時代中頃から平安時代前期にかけての「末期古墳」とよばれる100基以上の円墳の群集墳である。八戸ニュータウンの開発に伴い、発掘調査が行われた。
東北北部においては,岩手県南部の胆沢町の角塚古墳などの例外的な存在はあるが,6世紀までに古墳が波及することは基本的になかった。これは弥生時代以降,稲作が定着した東北南部以南と,一定期間の定着が認められるものの継続部以北との間に生じた歴史的な歩みの大きな相違が,そのまま引き継がれたものである。
しかし,こうした東北北部においても, 7世紀後業以降,8・9世紀代を中心として末期古墳とよばれる群集墳が築かれていく。その背景には,7世紀中頃から,城柵を築いての軍事的介入を含め,東北北部を律令支配下におこうとする古代国家の活動がある。東北北部の群集墳の築造は,こうした活動の活発化にともない,律令制下の人々と接触することのあった在地の勢力が,東北以南の墓制を採用するにいたったものと考えられる。
その意味で,東北北部の群集墳は,日本における異文化間の交流という重要な歴史的課題にかかわる素材となる。本州北端部に位置し,しかも大規模な古墳群であることから,きわめて重要である。




古墳はいずれも直径約5m程度で、最大のものは15号墳の全長9mである。埋葬施設はすべて木棺を直葬したものであるが,棺をおさめる土坑の手前に,横穴式石室の羨道部に由来すると思われる通路状の張り出しをもつものが多い。木棺を土坑にそのままおさめるもののほか,棺床に礫を敷くもの4基、木炭を敷くもの5基がある。

埋葬施設に収められる副葬品や墓前祭祀に用いられた供献品が出土する。
副葬品には方頭(ほうとう)大刀、直刀、蕨手刀、鉄鏃(てつぞく)などの武器類・馬具をはじめ、132個の勾玉など約1800個の玉類、鉄製・錫製の釧(くしろ)などの装身具類がある。周溝から発見される供献品には、意図的に壊された土師器、須恵器とともに、玉類、鉄器、和同開珎、帯金具などがある。
国内に出土例がない朝鮮半島の新羅で製作された「金装獅噛三累環頭大刀柄頭(きんそうしがみさんるいかんとうたちつかがしら)」と呼ばれる黄銅製の刀の柄飾りをはじめ、東北地方に特徴的に分布する蕨手刀や錫釧・多量の勾玉やガラス玉などの豊富な出土品は、律令制が及ばなかった北日本における「蝦夷(えみし)社会」でのエミシの族長たちの実態や墓制の在り方を考える上で価値が高い。
蕨手刀・錫釧・多量の玉類は、東北地方の末期古墳群に共通してみられる。錫釧は北海道でも出土し、北方との交流を示す遺物ともいわれている。また、銙帯金具(かたいかなぐ)や和同開珎(わどうかいちん)は、律令国家との関係がうかがえる資料である。
丹後平古墳群出土品は、文献上の記述にあらわれない八戸地域の当時の社会や墓制、律令政府との関係性を示すまとまった資料である。
円墳や土坑墓から出土した副葬品や墓前祭祀に用いられた土器の一括が重文に指定されている。


金装獅噛三累環頭大刀柄頭(きんそう/ しがみ /さんるい/ かんとうたち /つかがしら)。
墳丘規模の大きい15号墳から出土した金銅製の獅噛式三累環頭大刀の把頭は,獅噛環頭と三累環頭とを組み合わせた類例のないもので,6世紀前半から中頃の朝鮭半島の製品と考えられている。柄頭部分は黄銅製(真鍮製)の鋳造品で、三累環には文様を毛彫りし、金象嵌が施されている。中央には歯をむき出した獅子が表現され、表面は鍍金されている。

この柄頭は、発掘当時は内外を通して同類のものはなかったが、その後、韓国全羅南道羅州市の「伏岩里三号墳」の横穴式石室から、丹後平古墳群での出土より数年早くこの大刀が発見されていたことが明らかになった。本古墳群では柄頭だけであるが伏岩三号墳では刀身に着いた状態で出土した。全体の長さは84㎝。この韓国の遺跡の築造年代は6世紀後半と推定されている。