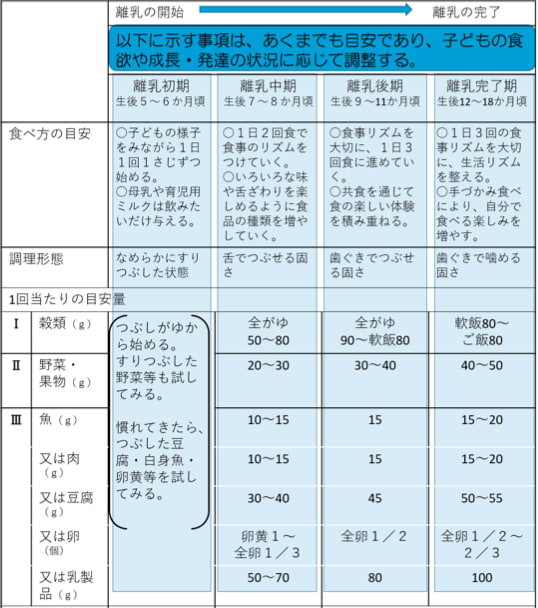ふたたび魚アレルギーのアップデート。
第23回食物アレルギー研究会で、
近藤康人Dr(藤田医科大学ばんため病院)によるレクチャーを聴講しましたので、
メモを残しておきます。
近藤先生のレクチャーは今までに何回も聞いたことがありますが、
理論派というか、重箱の隅をつつくような内容で、
いつも驚かされ、
「そ、そこまで必要ですか?」
と聞きたくなる私です。
今回は診断のコツと食事指導を中心に話されました。
▢ 魚アレルギーの年齢別症状傾向
・乳幼児期は皮膚症状中心
・学童期以降はアナフィラキシーや口腔アレルギー症状も見られるようになる
▢ 魚アレルギーの内訳
・真の魚アレルギー
・ヒスタミン中毒
・アニサキスアレルギー
▢ ヒスタミン中毒
・魚が死ぬとヒスタミン産生菌が繁殖する。
・魚肉中のヒスチジン(アミノ酸の一種)が菌により分解されてヒスタミンになる。
・ヒスタミンを多量に含む魚を食べた直後~1時間以内に、
吐き気、顔面紅潮、発汗、頭痛、発熱、蕁麻疹などを起こす。
・ヒスタミン感受性には個人差がある。成人より小児の方が影響を受けやすい。
・ヒスタミン過敏症状は調理法により変わる。アルコールや酸(レモン、酢)を一緒に接種すると吸収が促進される。
▢ ヒスタミンの性質
・ヒスタミンは加熱調理しても壊れない。
・凍結中は安定している。
・冷凍中は増えないが、解凍すると酵素の作用により増える。
・10℃よりも25℃~35℃で増えやすい。
▢ 魚肉中のヒスチジン含有量
・赤身魚で多い
(例)キハダマグロ、ブリ、カツオ、マカジキ、マサバ、メバチ、カタクチイワシ
・白身魚で少ない
(例)アンコウ、マダイ、イシガレイ、メバル、マフグ、ヒラメ、メカジキ
※コイは白身魚ではあるが多め
▢ 魚アレルギーの主要アレルゲンはβ-パルブアルブミンである。
・β-パルブアルブミン:Gad c 1, Onc m 1, Sal s 1等:陽性率60-90%
・アルドラーゼA:(省略):13-37%
・β‐エノラーゼ:(省略):10-56%
・コラーゲンーα:Lat c 6, Sal s 6:陽性率22%
▢ パルブアルブミン(PA)
・ほぼすべての魚種の筋肉中に広く存在する
・両生類や鳥類の筋肉中にも存在するCa結合性蛋白質
・加熱や酸の処理に安定
▢ アレルギーは白身魚の方が起きやすい
(赤身魚)回遊魚は絶えず大量の酸素を必要とすることから、筋肉中にミオグロビンを多く持つため、赤身になる。
(白身魚)身動きせずに獲物を待ち伏せして狩猟する白身魚は、赤身魚に比べると、酸素の消費量はとても低いため、筋肉は赤身魚ほどミオグロビンを含まないため、白身になる。
▢ パルブアルブミン(PA)含有量
(PA高値)キンメダイ、トビウオ、ウスメバル、アカムツ、マアジ、イサキ、マダイ、アカカマス
(PA低値)ギンザケ、メカジキ、カツオ、メバチマグロ、キハダマグロ
★二つ前の項目(千貫祐子Dr)紹介のPA含有量データと比較してみましょう;
マアジ(11.6-19.7)
ハモ(5.7-13.7)
ウナギ(10.2)
メバル(8.9-9.8)
アカアマダイ(3.9-9.6)
キンメダイ(6.9)
イサキ(4.4-6.8)
トビウオ(2.8-6.5)
マイワシ(2.6-3.4)
マサバ(2.4)
メバチマグロ(0.33)
カツオ(0.25)
トラフグ(0.1‐0.2)
ハモ(5.7-13.7)
ウナギ(10.2)
メバル(8.9-9.8)
アカアマダイ(3.9-9.6)
キンメダイ(6.9)
イサキ(4.4-6.8)
トビウオ(2.8-6.5)
マイワシ(2.6-3.4)
マサバ(2.4)
メバチマグロ(0.33)
カツオ(0.25)
トラフグ(0.1‐0.2)
・・・あれ、アカウオ関連のメバルが近藤Drの紹介データには入っていませんね。こんな風に比較しないとわからないことがあります。
▢ ほかの魚との交差反応性
・魚アレルギー患者が別の魚を食べたときにアレルギーを起こす確率(臨床的交差反応性)は~50%。
・硬骨魚類アレルギー→ほかの硬骨魚類アレルギー:~50%
→軟骨魚類アレルギー:<5%
・食事指導に魚の生物学分類は利用できるか? → No!
生物学分類表は魚のアレルゲン性と一致していない。
魚の生物学分類は真の進化の過程を反映していない。
見た目で(胸鰭に対する腹鰭の位置)分類されている。
▢ 魚除去食での栄養学的問題
・ビタミンD摂取不足→卵黄、きくらげ、干しシイタケで補充
もしくは、カツオの缶詰やメカジキが食べられれば補うことができる
・n-3系多価不飽和脂肪酸(EPAやDHA)の摂取不足
・カルシウム不足→牛乳などで補充
▢ 症状の出やすい魚
・タイやカレイが高率…PA高値
・カジキ、カツオ、ツナ缶は低率…PA低値
・多魚腫に反応する場合もPAが原因であることが多く、カツオ、カジキ、マグロ、ツナ缶などから試すのがよい。
▢ 魚アレルギーの食事生活指導
・カツオ、いりこなどのだしの除去は不要なことが多い。
・ツナ缶は高温高圧処理で低アレルゲン化されており、多くの場合摂取可能である。
・学校行事で魚市場などへ行く際は、魚アレルゲンを吸入すると呼吸器症状を起こしうるので、マスク着用など防御対策が必要。
・カルシウム、ビタミンDの補充は前述
▢ エビアレルギーの診断に特異的IgEは信頼できない。
▢ エビアレルギーの原因はトロポミオシンファミリーであり、相同性が高いが、
臨床的交差反応リスクとトロポミオシンのアミノ酸配列の相動性は一致しない。
▢ エビアレルギー患者の臨床的交差反応性:
・カニアレルギー:64.7%
・イカアレルギー:17.5%
・タコアレルギー:20.3%
・ホタテアレルギー:19.6%