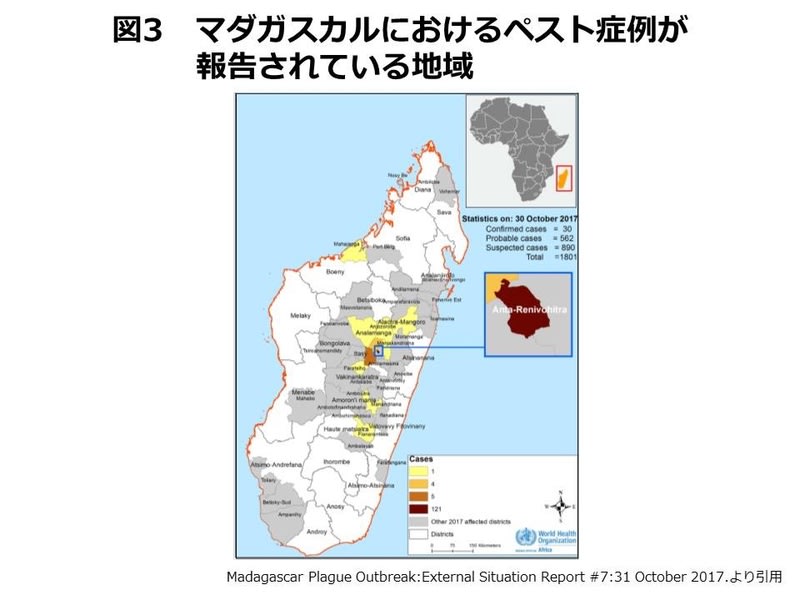「風邪薬は効かない」ことは当ブログでは何度も取りあげてきましたが、
今回は、米国の学会の見解が発表されたという記事を紹介します。
■ 「風邪による咳に効く薬はない」米学会が見解
(2017年11月25日:medy)
(HealthDay News 2017年11月8日)
市販されているさまざまな咳止めの薬から米国で「風邪に効く」とされているチキンスープといった民間療法まで、あらゆる治療法に関して米国胸部医学会(ACCP)の専門家委員会が文献のシステマティックレビューを行ったところ、効果を裏付ける質の高いエビデンスがある治療法は一つもなかったという。
これに基づき同委員会は指針をまとめ、「風邪による咳を抑えるために市販の咳止めや風邪薬を飲むことは推奨されない」との見解を示した。
このシステマティックレビューと指針はACCP専門家委員会の報告書として「Chest」11月号に掲載された。
筆頭著者で米クレイトン大学教授のMark Malesker氏によると、数多くの米国人が風邪による咳に対して市販薬を使用しており、2015年の米国における市販の風邪薬や咳止め薬、抗アレルギー薬の販売額は95億ドル(約1兆700億円)を超えていたという。
今回、同氏らはさまざまな咳に対する治療法の効果を検証したランダム化比較試験(RCT)のシステマティックレビューを実施した。
その結果、抗ヒスタミン薬や鎮痛薬、鼻粘膜の充血を緩和する成分が含まれる風邪薬に効果があることを示す一貫したエビデンスはなかった。
また、ナプロキセン(ナイキサン®)やイブプロフェン(ブルフェン®)などの非ステロイド性抗炎症薬(NSAID)の試験データの分析からも、これらの効果を裏付けるエビデンスはないことが分かった。
ACCPがこのトピックについてシステマティックレビューを実施したのは2006年に発表した咳ガイドライン以来だが、 「残念ながら2006年以降、風邪が原因の咳に対する治療の選択肢にはほとんど変化がない」と同氏らは説明している。
では、眠れないほどつらい咳にはどう対処すればよいのだろうか。
Malesker氏によると、1歳以上の小児に対しては蜂蜜にある程度の効果があることを示した複数の研究があるという。
ただし、1歳未満の小児に蜂蜜は与えるべきではないとしている。
また、成人の咳には亜鉛トローチが有効であるとの弱いエビデンスがあるが、使用を推奨するには不十分で、亜鉛には副作用もあるため注意が必要だとしている。
このほか、チキンスープやネティポット(鼻洗浄)といった民間療法についても強いエビデンスはなかった。
ただし、Malesker氏は「お気に入りのお茶やスープを飲んで気分が良くなるなら、そうするべき」と話す。
また、市販の風邪薬を試す場合、医師や薬剤師に相談することが望ましく、特に2歳未満の小児に薬を飲ませる場合にはかかりつけの小児科医に相談すべきだとしている。
さらに、市販されている風邪薬には眠気などの副作用があることに加え、咳止めのシロップに含まれていることの多いデキストロメトルファン(メジコン®)には乱用リスクがある点についても注意が必要だという。
米国立ユダヤ医療研究センターのDavid Beuther氏は「咳を止める効果的な手段がいまだに見つかっていないことにいら立ちを感じている。
風邪による咳は睡眠やQOL(生活の質)に影響することもある」とした上で、「そんな時は手っ取り早い方法を求めがちだが、休暇を取って安静にすることも必要だ」と助言している。
水分摂取も咳の原因となる粘液を洗い流すのに有効だという。
なお、頻繁に風邪をひく場合や咳が長引く場合は軽度の喘息や慢性副鼻腔炎などの疾患が隠れている可能性もあるため、医師に相談した方がよいとしている。
上記報告では「蜂蜜」がよいと記されていますが、近年この作用メカニズムも中枢性鎮咳薬と同じではないかとの研究発表もあり、今後の解析が臨まれます。
当院ではふつうの風邪薬で治りの悪い患者さんに漢方薬をお勧めしています。
例えば鼻水止め。
西洋薬では抗ヒスタミン薬しかありません。
しかし漢方薬では複数の方剤を使い分けます。
・風邪の初期のくしゃみ・鼻水には
小青竜湯
・数日後、鼻水が濁ってきて奥にたまってつらそうなら
葛根湯加川芎辛夷
・慢性化し、青っ洟がたくさん出続けるとき(蓄膿症・副鼻腔炎)は
辛夷清肺湯
等々。
西洋薬の風邪薬を処方後「あの薬が効いたので同じものをください」という方は滅多にいませんが、
漢方薬を処方後「あの薬が効いたので同じものをください」という方は少なからず存在して、皆さんリピーターになります。