そもそも、「解釈」という思考作業は、自分の都合(主義・主張、政治的立場、時の状況など)のいいように成される。
従って、程度の差はあれ、文言の本意から反れてしまいがちだ。そして、書かれている文言が、明快であるならば「解釈の相違」は小さいはずだが・・・他人が書いた、しかもメモ的な文言ならば、「解釈の相違の幅」はなお更広がるのが自然であろう。
今回、「日本国憲法は、日本国民(自分)が書いたものであるから、自己矛盾に陥らないように読んでいくことが大切である」という前提で国語的読解作業を行っている。その流れで、今有る「解釈論」について述べてみたい。
では、実際をみてみよう。
◎ 解釈の初っ端は、第90回帝国議会における吉田発言であろう。
彼は、「第一項で侵略戦争はしません。第二項で(一切の)戦力を持ちません。」と、第一項と第二項を切り離し、(余計な文字)を加えて答弁をした。「前項の目的のため」の文言を無視したのであった。
第二項は、第一項の方針(侵略戦争の放棄)を受けて、その具体策を述べており、第一項と第二項は、連続した(一つの)文章と見るべきである。従って正しくは、「侵略戦争の放棄を達するため、そのための戦力を保持しない。」と言うべきであったろう。
それで、以来、政府自身矛盾に陥ってしまい、後に「必要最小限の戦力は持てる」「戦力とは、近代戦を戦いうる戦力のことだ」などとワケのわからない詭弁を続けなければならなくなったのである。(尤も、彼がそう答弁せざるを得なかった当時の様々な状況はわかるが・・・)
2. 不可解な解説・・テレビによく出ていた東大法学部卒の憲法学者K教授は、ブログの中で、9条の説明箇所で、以下のように述べている。
「日本国憲法では、 憲法9条1項で戦争・武力行使が禁じられ、
2項では「軍」の編成と「戦力」不保持が規定される。
いかなる名目であれ、「武力行使」一般が原則として禁止されているのだ。」(原文のまま)と。
( はあ???) いかなる名目? 一般? 原則として?・・・・抽象的な専門用語の羅列であるが、一般の人が読むと「(わけくちゃわからん!)とにかく「全ての戦争、一切の戦力が禁止されている」のだなあ」と印象付けされるのではないだろうか?
内容を説明せず、字面のみをつまみ食いして、読者を誘導する話法は、専門的言い回し(?)による「つまみ食い解釈子供だまし論法」と言いたい。 (9条改正や集団的自衛権に反対している憲法学者や政治家、各種議員等の話を注意して聞いていると、話法は、みーんな上記のパターンである)注意が必要であろう。
3.改憲派の憲法学者さえも、「(すべての)戦力を保持しない」と解釈し、「前項の目的」を無視している人がいる。
政府の解釈に従ってのことだろうか?
さて、問題の二項の「戦力」について、・・・どっちなの?
A侵略戦争のための戦力を意味するのか?
B(一切の)戦力を意味するのか?
◎Aである。戦力が無いのだから自衛戦争もできない。結果として、一切戦争しないのだ、という主張について。
反論)ある条件下で出した結果を即全てに当てはめるというのは、論理的におかしいことだ。逆の条件から論じてみれば明らかだ。現実的にもおかしいことは明白である。
◎Bの主張について。
反論)「一切の戦力不保持」を主張するひとは、「前項の・・・」を無視しており、読み方としては不十分である。
ただし、メモ書きであるため、そう理解されやすいのは事実である。だからこそ、わかりやすい文言の条文に書き変える必要があるのである。ではメモ書きになった理由ですが、それは、GHQから原案をわたされ、それを写しただけのものであり、且つ、審議も不十分であったことに要因があるのです。
A と読まなければならない理由
1.第一項を書いているときは、頭の中は、侵略戦争について考えていますよね。
第二項を書くときは、第一項の方針を考えながら書いているのだから、その流れでメモったのだと考えるべきです。だから、その戦力とは、「侵略戦争のための戦力」だと、いえるのではないでしょうか。
2.そもそも主権を持ち自由な状況の中で自分(日本人)が憲法を書いたという前提なら、第二項を書いている段階で、(一切の戦力=戦争を否定する)のなら、第一項が条件付き戦争放棄の内容になっていることに気がつかなければならない。すぐ書き換えなければいけないはずである。そのままにしておくのは、自己矛盾であろう。
3.(中国は証人である)中国は、「自衛のための戦力をもつ可能性がある」と指摘した(既述)。一切の戦力(軍隊)を持たない、というのなら、軍人はいないはずだから、66条第2項の文民条項がある、というのは矛盾であろう。矛盾を解消するには、「侵略戦争のための戦争」と読まなければならないのである。(西修教授が同意のことを著していることがわかり、心強く思う)
以上から、「(侵略戦争をするための)戦力」と読むことによって、9条に関わる疑問は全てすっきりと解消する。
9条は、すっきり条項であった!
次回は、「交戦権」について。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◎追加)お母さん方へ。
憲法9条を理解するために 、次のように 言葉を置き換えてみました(太字箇所)
「憲法9条 私は、家族の笑顔を希求し、刃物の使用は、他人との言い争いを解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第二項 前項の目的を達するため、出刃包丁や菜切り包丁などは、これを保持しない。(以下略)」
さて、お母さん方にお伺いします。
「出刃包丁や菜切り包丁など」を(すべて)保持することを止めますか?
それじゃあ困りませんか? 可愛い坊やに美味しい料理を作ってあげられませんよね。
理由1) でも・・・ご安心ください。第一項で、「他人との言い争いを解決する手段としては」と条件がついています。
ですから、それ以外の条件では包丁を持つことは可能ですよ。
理由2)あなたが二項を書き始めた時は、一項のこと(条件付き放棄論)に頭は集中していたはずです。だが、書いた文言は、メモ書きになってしまった・・・・ということではないでしょうか。
理由3)<包丁は、・・・・どっち?>
包丁で人を殺すこともできます。だから、「包丁は殺人の道具だ」と決めつけて、放棄しますか?
包丁は、料理(平和的)にも使えます。この目的のためだけに使いたいですよね。
要は、「包丁は、物を切るという機能を持っただけの道具」です。それをどのように使うかを決めるのは「あなた」ですよね。
包丁は意思の無いただの道具であって、その使い方次第なんです。
自衛隊を「暴力装置」と言って、問題を起こしたM党のS議員がおりましたが、自衛隊は平和な暮らしをもたらしてくれる女神でもあるんです。戦車も大砲も、自衛のために使えば良いのです。
これで、お分かりでしょう?第一項と二項を繋げる文言が「前項の目的の実現のため」であり、それを切り離して読むことは正しい理解の仕方ではないのです。
これで、あなた(スッキリ!)みーんな(´∀`*)












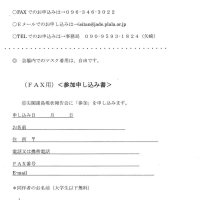
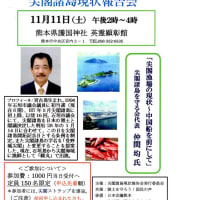


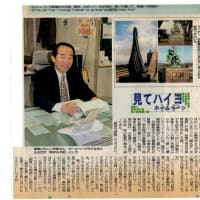
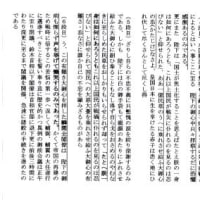
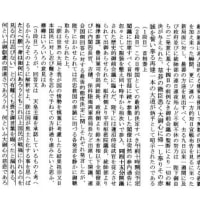

助動詞の “ will ”が付いているので
“ will ”を取るまで永遠に未来の条文。
だから、
第二項 前項の目的を達するため、出刃包丁や菜切り包丁などは、
将来これを保持しない予定である。
となり、
現在の武装は問題無しと成る?
日本滅亡まで“ will ”を付けとけば超ザル法?