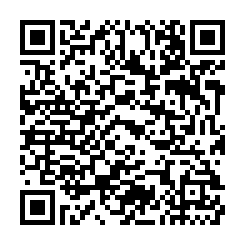音楽の三要素、メロディ、リズム、ハーモニーを最低限満たす、ギター、ベース、ドラムスのスリーピースバンド。
その中でも、クリーム、ジミ・ヘンドリクス・エクスペリエンス、グランド・ファンク・レイルロードはロック史上、特筆すべきスーパーバンドだ。
シンプルかつダイナミックで、ロックバンドの編成はコレに尽きる。
余分なものがないだけに、それぞれのプレーヤーには標準以上のテクニックが求められる。
クリームは三人の力量が拮抗し、その演奏は鬼気迫るバトルそのものだった。
ジミヘンとGFRは突出したギタリストのワンマンバンドで、他の二人は縁の下の力持ち的な存在だ。
高校時代、我が家は田舎の一軒家だったこともあり、この3バンドをセパレートステレオのボリュームをMAXにして聴いていた。まさにロックと対峙するという気概を持って拝聴していたのだ。
リードとサイドに分かれたギターや、キーボード、管楽器などが入ると厚みや広がりは増すが、本来のロックのテンションは薄められてしまう。
ロックバンドがサポートメンバーも含め大編成になり、デジタル機器による音響操作が容易になった現在では、あの頃のような本来のハードロックは昔の音源で聴くしかない。
その中でも、クリーム、ジミ・ヘンドリクス・エクスペリエンス、グランド・ファンク・レイルロードはロック史上、特筆すべきスーパーバンドだ。
シンプルかつダイナミックで、ロックバンドの編成はコレに尽きる。
余分なものがないだけに、それぞれのプレーヤーには標準以上のテクニックが求められる。
クリームは三人の力量が拮抗し、その演奏は鬼気迫るバトルそのものだった。
ジミヘンとGFRは突出したギタリストのワンマンバンドで、他の二人は縁の下の力持ち的な存在だ。
高校時代、我が家は田舎の一軒家だったこともあり、この3バンドをセパレートステレオのボリュームをMAXにして聴いていた。まさにロックと対峙するという気概を持って拝聴していたのだ。
リードとサイドに分かれたギターや、キーボード、管楽器などが入ると厚みや広がりは増すが、本来のロックのテンションは薄められてしまう。
ロックバンドがサポートメンバーも含め大編成になり、デジタル機器による音響操作が容易になった現在では、あの頃のような本来のハードロックは昔の音源で聴くしかない。