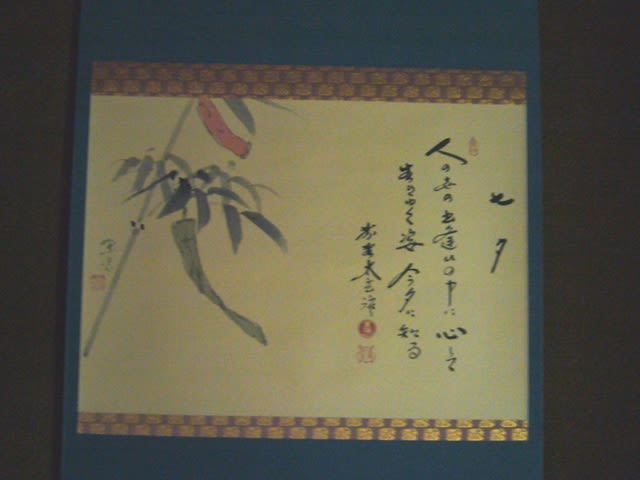炭所望は亭主の所望により客が炭をつぐ作法です
炉の季節に行うきまりになっています

半田にぬれ灰を入れて平らにならします

底取りで左巴に書いていきます

中心部は少し力を入れて巴にする
中央に長火箸を置きその上に斜めに底取りを置いて準備終了
点前 炭取りを持ち出し釜を上げ、勝手つきに引き環をはずす
炭取りを炉近くいつも釜を上げるところに移動する
水屋に戻り巴半田を持ち出して炉近くに置きつける

炉中の大きな炭からあげていきます

細かい下火は炉中の真ん中に集め底取りで
向こうより手前にすくいとって半田に上げます
灰の山を崩し、四隅よりかき上げ半田より
大振りな下火を3個ほど炉中に入れます。灰をまき
胴炭をつぎ正客に炭つぎの所望をいたします
2007の稽古