*「なぜ油絵を描くのは難しいのか」(2016-07-27 の記事) もよかったら、読んでみて下さい。
前回の記事では、油絵を描く上での根本的な問題について書きました。いわば本質論です。それに対して今回は、油絵を描く上での実際的な問題、画材について書きます。表面論です。
つまり、油絵制作は、本質的にも、表面的にも、非常に困難を伴っているのです。では早速始めましょう。
国内外を問わず、油絵を描いている人は、例えそれが趣味であれ、日曜画家であれ、プロ画家であれ、皆、あやふやなままで描いているのです(私もそのうちの一人です)。ということは日本だけでなく、欧米を含めた世界中の油絵制作者ということになりますが、実際にそうなのです。
これが水彩なら、それが透明水彩であれ、グアッシュ(不透明水彩)であれ、何の問題もありません。支持体は紙ですし、顔料をアラビアゴムで練ったのが水彩絵具ですし、水で溶いて書きます。
ところが油絵では、こうはいかないのです。「えっ!? だって支持体はカンバスだし、顔料を油で練ったのが油絵具だし、乾性油(と揮発性油)で溶いて描くんでしょう?」と言われそうですが、では具体的に、何をどう使うのかが問題なのです。
確かに支持体はカンバスです。でも種類が水性地(吸収性)、エマルジョン(半吸収性)、油性(非吸収性)と3つもあります。また板に描くこともできます(昔はよく板を使った)。
顔料を油で練ったのが油絵具ですが、リンシード、ポピー、サフラワー、ウォルナット、どれで練るのか。これらの乾性油を加工したサンシックンドでも練れます。
一般に日本では油絵具は市販のチューブ入りを使いますので、つまりは自作する人が少ないので、この問題で悩む必要はありませんが、そうなると大抵はリンシードかポピーで練られたものを使うことになります。
溶き油は、揮発性油にはテレピンとぺトロールがあり、乾性油には上記のリンシード、ポピー、サフラワー、ウォルナットなどがあり、加えて、これらを加工した、サンシックンド、スタンド、ボイルドなどがあり、どれを使うのか。
実際には揮発性油と乾性油を混ぜたものを使いますが、どれを選び、どう配合するのか。またこの溶き油にさらに樹脂を混ぜるのが良しとされ、樹脂には、天然のマスチック、ダンマル、コーパルの他、合成樹脂もあります。
溶き油を最初から自作するのは、自作しろと言われても何をどうしていいのかよくわからないので、油絵初心者のために市販の調合溶き油、いわゆるペインティング・オイルが用意されています。
さて「カンバスは油絵・アクリル共用を、油絵具は市販のチューブ入り、溶き油はペインティング・オイルを使えば、問題ないだろ」ということになるんですが、それは初心者の話。
だんだん描き慣れて中級者以降になると、さまざまな事情で自作をすることになりますが、そこで問題が発生します。一体何をどうすればいいのか。
ここで混ぜっ返すようで恐縮ですが、そもそも油絵は油絵具だけで描かれていませんでした。当初は板にテンペラ(顔料を卵で溶いた絵具)で描き、その上から油絵具で描いていた。これを油絵と言っていたんです。
ところがヨーロッパでは、油絵具だけで描くようになってすっかりこの事実を忘れ、これを思い出したのが(つまりは美術史家や学者が研究で明らかにしたのが)、何と!20世紀の初頭だそです(さぞ混乱したでしょうな、当時の日本洋画界は)。
えーっと話を戻しまして、カンバスなり、油絵具なり、溶き油なりを自作するとして、「そんなのさ、昔の資料が残っているとか、偉い学者さんの研究とかでわかるんじゃないの?」と普通は思うんですが、それがさっぱり当てにならない。
つまりは古典絵画の巨匠たちがどういう風に描いていたか、つまりどんな画材をどう使って、どんな制作過程を踏んでいたのかがわかっていないわけです。
だから「俺はそんなに難しいことをしようとしているんじゃない。ごく普通に描ければいいんだ。ちょっと趣味として油絵を楽しくやりたいだけなんだから、一般的な描き方を教えてくれればいいんだ」と言われるのが一番困るわけです。
油絵の大体の描き方はわかっているわけです。でも実際に描くには「大体」では困るわけで、具体的にはっきりとしていないといけないわけですが、それがそうなっていない。
要するに油絵制作については、理論的にわかっているだけで、実践するには不十分な状態にあるわけです。
また混ぜっ返すようですが、油絵具がチューブ入りで市販されるようになったのは産業革命以降であります。その過程で油絵具は変質し、いろんな混ぜ物が添加され、結果、腰が強いものになりました。ということは、もはや以前の油絵具とは別物になってます。
これは加工油についても同様で、市販のサンシックンドやスタンドオイルは、昔のもの(ルネサンス期から近代以前までのもの)とは別物だそうです。
おわかりいただけたでしょうか、油絵を描くというのは、初心者のうちはともかく、中級者以降、つまり枚数を描けば描くほど、画材について暗中模索せざるを得ない状況で、「道具もなければ、方法もわかない」ということになってます。
かく言う私も、地元の絵画教室に通っていた時、絵の先生に「溶き油については自分で研究しなさい」とあっさり言われました。別にこれは先生の手抜きではなく、先生もよくわからないということで、先生どころか、世界中の誰もがわからないのだから、仕方ないわけです。
現実的な話をしましょう。確かに画材店の油絵コーナーに行けば、実に様々な画材が用意されています。油絵具の色も豊富ですし、乾性油や加工油も揃っています。天然樹脂に合成樹脂、さまざまなペインティング・オイルも多数。
問題はこれらの組み合わせなのです。カンバスはどの種類を使うのか、油絵具はどの色を使うのか、ペインティング・オイルを自作するにはどれを使うのか。
そして更なる問題は、これらの画材を使ってどう描くのか。どういう手順で描き進めたらいいのか。
今、ここで話しているのは、巨匠ならではの秘密技法だったり、超絶技巧であったりするのではありません。ごく一般的な油絵の描き方の話です。
つまり油絵は一般的な描き方が確定されていない。欧米の人文書を読んでいると「一般化」という言葉が出てきますが、まさに「油絵制作は一般化されていない」わけです。
しかしながら、油絵制作は一般化できないという意見もあります。そもそも昔はそれぞれの画家が工房を構えており、多くの弟子を抱えていました。当時はもちろん、画材は市販されてなどいませんから、全て工房内で作られていました。ですから各工房で、画材は微妙にあるいは大きく違っていた可能性は大いにありますし、制作過程も同様です。
まとめると、油絵をどう描いたらいいのかおおよそはわかっており、それに従って何となく作品を仕上げることはできます。ですが、いつまでもこのあやふやなままでは良くないので、あれこれ調べて自分なりにやろうとすると、途端に困難に直面します。
それでも皆、プロ、アマ問わず、油絵を描いてます。私はこれを格闘と表現しています。そう「油絵と格闘している」のです。
最後に、私自身はどうなのかというと、市販のカンバスに下塗りを重ね、独自の下地にしていることが、私の油絵の工夫です。ペインティング・オイルは確かに自作していますが、正直あまり自信がないですし、パレット(油絵具の色の選択)も国内メーカーです。制作過程でのこだわりは、常に下層の色が突き抜けてくるように努めていることぐらいです。
今回、ここで書いている内容は、油絵をずっと描いている人なら、誰もが抱えている悩みです。残念ながら、解決の目処は立たなさそうです。最新の科学機器で名画の分析は進んでいますが、制作過程までは解明されないでしょう。
ごく普通に描けない、それが油絵。そんなところでしょうか。
前回の記事では、油絵を描く上での根本的な問題について書きました。いわば本質論です。それに対して今回は、油絵を描く上での実際的な問題、画材について書きます。表面論です。
つまり、油絵制作は、本質的にも、表面的にも、非常に困難を伴っているのです。では早速始めましょう。
国内外を問わず、油絵を描いている人は、例えそれが趣味であれ、日曜画家であれ、プロ画家であれ、皆、あやふやなままで描いているのです(私もそのうちの一人です)。ということは日本だけでなく、欧米を含めた世界中の油絵制作者ということになりますが、実際にそうなのです。
これが水彩なら、それが透明水彩であれ、グアッシュ(不透明水彩)であれ、何の問題もありません。支持体は紙ですし、顔料をアラビアゴムで練ったのが水彩絵具ですし、水で溶いて書きます。
ところが油絵では、こうはいかないのです。「えっ!? だって支持体はカンバスだし、顔料を油で練ったのが油絵具だし、乾性油(と揮発性油)で溶いて描くんでしょう?」と言われそうですが、では具体的に、何をどう使うのかが問題なのです。
確かに支持体はカンバスです。でも種類が水性地(吸収性)、エマルジョン(半吸収性)、油性(非吸収性)と3つもあります。また板に描くこともできます(昔はよく板を使った)。
顔料を油で練ったのが油絵具ですが、リンシード、ポピー、サフラワー、ウォルナット、どれで練るのか。これらの乾性油を加工したサンシックンドでも練れます。
一般に日本では油絵具は市販のチューブ入りを使いますので、つまりは自作する人が少ないので、この問題で悩む必要はありませんが、そうなると大抵はリンシードかポピーで練られたものを使うことになります。
溶き油は、揮発性油にはテレピンとぺトロールがあり、乾性油には上記のリンシード、ポピー、サフラワー、ウォルナットなどがあり、加えて、これらを加工した、サンシックンド、スタンド、ボイルドなどがあり、どれを使うのか。
実際には揮発性油と乾性油を混ぜたものを使いますが、どれを選び、どう配合するのか。またこの溶き油にさらに樹脂を混ぜるのが良しとされ、樹脂には、天然のマスチック、ダンマル、コーパルの他、合成樹脂もあります。
溶き油を最初から自作するのは、自作しろと言われても何をどうしていいのかよくわからないので、油絵初心者のために市販の調合溶き油、いわゆるペインティング・オイルが用意されています。
さて「カンバスは油絵・アクリル共用を、油絵具は市販のチューブ入り、溶き油はペインティング・オイルを使えば、問題ないだろ」ということになるんですが、それは初心者の話。
だんだん描き慣れて中級者以降になると、さまざまな事情で自作をすることになりますが、そこで問題が発生します。一体何をどうすればいいのか。
ここで混ぜっ返すようで恐縮ですが、そもそも油絵は油絵具だけで描かれていませんでした。当初は板にテンペラ(顔料を卵で溶いた絵具)で描き、その上から油絵具で描いていた。これを油絵と言っていたんです。
ところがヨーロッパでは、油絵具だけで描くようになってすっかりこの事実を忘れ、これを思い出したのが(つまりは美術史家や学者が研究で明らかにしたのが)、何と!20世紀の初頭だそです(さぞ混乱したでしょうな、当時の日本洋画界は)。
えーっと話を戻しまして、カンバスなり、油絵具なり、溶き油なりを自作するとして、「そんなのさ、昔の資料が残っているとか、偉い学者さんの研究とかでわかるんじゃないの?」と普通は思うんですが、それがさっぱり当てにならない。
つまりは古典絵画の巨匠たちがどういう風に描いていたか、つまりどんな画材をどう使って、どんな制作過程を踏んでいたのかがわかっていないわけです。
だから「俺はそんなに難しいことをしようとしているんじゃない。ごく普通に描ければいいんだ。ちょっと趣味として油絵を楽しくやりたいだけなんだから、一般的な描き方を教えてくれればいいんだ」と言われるのが一番困るわけです。
油絵の大体の描き方はわかっているわけです。でも実際に描くには「大体」では困るわけで、具体的にはっきりとしていないといけないわけですが、それがそうなっていない。
要するに油絵制作については、理論的にわかっているだけで、実践するには不十分な状態にあるわけです。
また混ぜっ返すようですが、油絵具がチューブ入りで市販されるようになったのは産業革命以降であります。その過程で油絵具は変質し、いろんな混ぜ物が添加され、結果、腰が強いものになりました。ということは、もはや以前の油絵具とは別物になってます。
これは加工油についても同様で、市販のサンシックンドやスタンドオイルは、昔のもの(ルネサンス期から近代以前までのもの)とは別物だそうです。
おわかりいただけたでしょうか、油絵を描くというのは、初心者のうちはともかく、中級者以降、つまり枚数を描けば描くほど、画材について暗中模索せざるを得ない状況で、「道具もなければ、方法もわかない」ということになってます。
かく言う私も、地元の絵画教室に通っていた時、絵の先生に「溶き油については自分で研究しなさい」とあっさり言われました。別にこれは先生の手抜きではなく、先生もよくわからないということで、先生どころか、世界中の誰もがわからないのだから、仕方ないわけです。
現実的な話をしましょう。確かに画材店の油絵コーナーに行けば、実に様々な画材が用意されています。油絵具の色も豊富ですし、乾性油や加工油も揃っています。天然樹脂に合成樹脂、さまざまなペインティング・オイルも多数。
問題はこれらの組み合わせなのです。カンバスはどの種類を使うのか、油絵具はどの色を使うのか、ペインティング・オイルを自作するにはどれを使うのか。
そして更なる問題は、これらの画材を使ってどう描くのか。どういう手順で描き進めたらいいのか。
今、ここで話しているのは、巨匠ならではの秘密技法だったり、超絶技巧であったりするのではありません。ごく一般的な油絵の描き方の話です。
つまり油絵は一般的な描き方が確定されていない。欧米の人文書を読んでいると「一般化」という言葉が出てきますが、まさに「油絵制作は一般化されていない」わけです。
しかしながら、油絵制作は一般化できないという意見もあります。そもそも昔はそれぞれの画家が工房を構えており、多くの弟子を抱えていました。当時はもちろん、画材は市販されてなどいませんから、全て工房内で作られていました。ですから各工房で、画材は微妙にあるいは大きく違っていた可能性は大いにありますし、制作過程も同様です。
まとめると、油絵をどう描いたらいいのかおおよそはわかっており、それに従って何となく作品を仕上げることはできます。ですが、いつまでもこのあやふやなままでは良くないので、あれこれ調べて自分なりにやろうとすると、途端に困難に直面します。
それでも皆、プロ、アマ問わず、油絵を描いてます。私はこれを格闘と表現しています。そう「油絵と格闘している」のです。
最後に、私自身はどうなのかというと、市販のカンバスに下塗りを重ね、独自の下地にしていることが、私の油絵の工夫です。ペインティング・オイルは確かに自作していますが、正直あまり自信がないですし、パレット(油絵具の色の選択)も国内メーカーです。制作過程でのこだわりは、常に下層の色が突き抜けてくるように努めていることぐらいです。
今回、ここで書いている内容は、油絵をずっと描いている人なら、誰もが抱えている悩みです。残念ながら、解決の目処は立たなさそうです。最新の科学機器で名画の分析は進んでいますが、制作過程までは解明されないでしょう。
ごく普通に描けない、それが油絵。そんなところでしょうか。











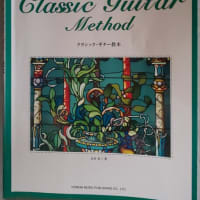




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます