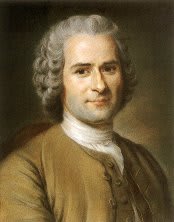今もワールドカップは順調に進行しているようだ。だが、日本は残念ながら対オーストラリア戦で惨めな敗北を味わった。特に試合終了間際に、なし崩しに得点されたのを見ても、日本サッカーがまだ多くの問題を抱えていることを示している。そして、アルゼンチンやスペインやブラジルなどの世界的な強豪チームの試合を見るにつけても、多くの点で日本チームが、まだ国際的な水準にすら立ちえていないことが明らかになってきている。
将来、民主主義が人類の支配的な国家形態となり、剣を鋤に打ち代えて、国家と国家の間の戦争の止む時が来ないとも限らない。そんな時には、戦争に代わって、こうしたスポーツ大会を戦場にして、国家や民族が威信をかけて戦うようになることだろう。ワールドカップ大会もその一つになることは間違いない。
日本のJリーグが生まれてからも、すでに十余年が経過しているが、ブラジルのロナウジージョのような世界的にも数本の指に入るような選手はまだ日本には生まれていないようである。しかし、これまでのワールドカップに参戦することすらおぼつかなかった一昔に比べれば、世界大会に常連になりつつあるのはそれなりに選手たちの実力が向上してきているからだろう。
経済の領域では、日本は最近はアジアの隣国、中国や韓国の追い上げに、アジアでも多少影が薄くなりつつあるとはいえ、国際的にはG8国の一国に収まるなど、相応の地位を築いてきたといえる。しかし、民族や国家の評価というのは、単に経済の分野での小さな成功のみで決まるのではなく、サッカーのようなスポーツ、芸術、宗教、学問、科学、道徳などの総合的な文化の水準によって、その価値が決まるというのは、個人の場合と同じではないだろうか。サッカーのワールドカップ大会などでは、サッカーのイレブンたちが代表して、文字通り世界中の人々の眼の前に、国家や民族の具体的な現象をさらすことになる。
先の対オーストラリア戦における日本チームの敗北からも、多くの問題や事実が読み取れると思う。このサーカー戦を観戦して、感じたこと考えたことを書いてみたいと思った。
特にサッカーの試合のようなものには、時の利、地の利など試合の勢いというものがあるから、その時々の試合の勝敗の結果は必ずしも実力と一致しない。しかし、もちろん、実力というのは、客観的にきっちりと評価出来るものである。試合の回数が多くなればなるほど、その実力の差は、はっきりと客観的に現れてくるだろう。
サッカーの試合も国家間の総力戦も、いずれも戦争という本質においては変わりはない。おりしも、アメリカチームが「ワールドカップで戦争に来た」と発言したとかで、イタリア人がアメリカチームに反発しているらしいが、子供じみた態度だと思う。ワールドカップをアメリカチームのように一つの戦争として捉えること自体悪いことではないし、また、そうした認識をもつことに意義もある。むしろ国家意識の薄く弱い日本国民を代表する日本チームに、どれだけ国家の威信を賭けているのだという自覚があるのか、それが問題にされてもよいと思う。
それはとにかく、サッカーも勝負を賭した一つの戦いである以上、そこには、戦争やその他の勝負事に共通する論理がある。そこには、戦術と戦略の総合的な実現の場として、試合が存在している。それは、柔道や剣道などの個人の格闘技などとも、論理的な構造は同じである。
ただ、サッカーのような集団戦の場合は、勝敗に決定的な要素としては二つある。一つは、チームを構成する選手一人一人の資質と能力、もう一つ、チーム全体としての組織力、この二つである。その二者は有機的な相互関係にある。
つまり、あらゆる有機体がそうであるように、部分と全体がどのようにかみ合い、調和しあって一つのより高い戦力を構成するかが課題である。そのためには選手一人一人の戦闘能力を高めるとともに、それが、チーム全体の組織力に生かされなければならない。
対オーストラリア戦の敗北では、選手の個人としての能力が十分に高められていなかったのみならず、チーム全体としても組織的な戦術や戦略も高められていなかったように思う。というよりも、チームとしての戦術や戦略といった確固たるものが日本チームには見られなかった。場当たり的な対応に終始していたように思う。その弱点が出たと思う。これでは日本チームは、武器を持たないで戦争するようなもので、到底勝てない。
チームとしての戦術や戦略が、一つの論理として選手一人一人に自覚され、かつ、様々な事態や戦況に対応できるように、選手一人一人の身体に記憶されるまでトレーニングされていなければならないが、そのためには、まず、一つの組織として戦争を戦うには、どのような武器が必要で、その武器をどのように駆使しなければならないかという問題意識が選手のみならず、監督やコーチに必要である。
しかし、統一した戦術や戦略を選手たちが共有するまでトレーニングされているようには思えなかった。パス送りによる正面突破戦術や、サイドロングパスによる、サイドからの攻撃など、サッカーとしての戦術の基本を十分に駆使ししえていると感じられたのは、オーストラリアチームの方だった。また、グランドの後方に布陣したために攻め込まれ、受身となって「攻撃は最大の防御なり」ということわざの真理を日本チームは実現できているようには思えなかった。先の試合を見る限り、日本18位、オーストラリア42位という、FIFAの評価は、明らかに正当な評価ではないように思われる。
企業や国家間の競争や戦争と同じく、サッカー戦においても、最終的に勝敗の帰趨を決めるのは、選手一人一人の資質と能力と、それを、指導し指揮する監督、コーチの資質と能力である。
ジーコ監督は、個人的な選手能力としては、まぎれもなく世界一級であるだろうが、それはジーコ監督自身が自らの個人的な資質と能力と努力によって形成し、獲得してきたものである。しかし、ジーコ監督は、その能力を十分に論理化して、それを改めて選手たちに、戦いのための武器として、日本選手たちに共有化させていることに成功しているとは思えない。むしろ、監督やコーチ自身に本当に必要なものは、きわめて高度な論理的な能力なのである。
さらに一般的に、日本の文化の特徴としても、物事を論理化して自覚する傾向は弱い。その必要についての自覚もなく、その問題意識も弱く、その能力も低い。サッカーというスポーツにおいても、その他の生活現場と同様に相変わらず、精神主義的根性論が強いのではないだろうか。
この傾向は、先般ベストセラーになった『国家の品格』の著者、藤原正彦氏らにも典型的に見られる。国家間の戦争にしてもサッカーの試合にしても、その勝敗を最終的に決するのは、個人や組織や民族や国家の持っている「物事を論理化して把握する能力」、理論的な能力だと思う。これは科学する能力である。しかし、この論理能力の決定的で深刻な重要性について、藤原正彦教授をはじめとして、ほとんど自覚がないようである。今日の学校教育の現場でもそうである。
理論のない本能的で盲目的なトレーニング。つまり、論理の分析のない、非科学的なトレーニングや戦術では、本当の意味では強くなれない。究極的には、「情の民族」は「理の民族」には勝てない。日本人の民族としての弱点は、そのまま、サッカーにおける日本チームの弱点ではないだろうか。
だから、本当は「論理軽視の文化」では絶対に駄目で、民族の骨の髄まで、論理偏重ぐらいにまでに、それを我が民族の体質としてゆく必要がある。それなのに、藤原氏のように、しかも数学者でありながら、日本の過剰な「美的情緒感受性」文化を、民族の弱点としてさえ自覚する問題意識がほとんどない。それが現状ではないだろうか。この弱点を本質的に克服することなくして、日本サッカーは永遠に欧米のチームには勝てないのではないかと危惧するのは杞憂だろうか。
日本サッカーチームが、真の意味で強くなるために必要なことは何か。そのためには、たとえば、世界的な半導体の研究者といわれる、元東北大学学長の西沢潤一氏ような、できれば工学系や自然科学系の優れた学者を召集して、サッカーをあらゆる側面から研究させるのである。
もちろん、単にサッカーの勝負の構造という観点からのみならず、その国民文化に与える影響、健康や教育的効果から、サッカーの試合の勝敗の論理の解明、そして、個々の選手たちのトレーニング法とそのためのツールの開発にいたるまでを、サッカー協会の中枢に、文化を含めた総合的なサッカー研究学校を設立して研究させるのである。そして、その研究の成果を、全国に散らばるクラブチームの拠点を通じて、全国に青少年から浸透させてゆくのである。優れたコーチ陣の自覚的な育成も重要である。W杯にようやく再登場したオーストラリアチームもそうして強くなったはずである。
その能力訓練の目的と核心は、選手一人一人が青少年の頃から始める「論理的な能力」、「理論的能力」の開発と向上である。そのために選手たちに、研究論文を実践的な練習と平行して書かせてゆくぐらいのことも始めるべきだ。それは、サッカーを入り口とする現代日本の教育と文化の革命にならなければならない。そうして、まず身体能力以前に「頭」を鍛えなければ、本当には強くはなれない。
日本チームの対オーストラリア戦の敗北を観戦して思ったことだった。
2006年06月17日