山本常朝 ――『葉隠』の死生観
人間は文化的な生物である。だから、その成育の環境と伝統のなかで「教育」を受けてはじめて人間になる。教育や伝統などの文化的な環境が人格形成に決定的な影響を及ぼす。人は誰でも、両親を第一として、故人であれ、また海外であれ、青年の頃から多くの人格に接することを通じて人格形成を行う。そして、多くの人がそうであるように、私もまた、様々な出来事や人格から何らかの影響を受けながら、意識的にかあるいは無自覚的に自分の人格を形成してきたといえる。
その中にも、もちろんその影響の強弱はある。人格の中にも、強い影響力、感化力を持つものとさほどでもないものがある。
最近でこそ特に関わることもないけれども、二十歳前後の青年時代に触れる機会があって、かなり強い印象を残した人格に山本常朝という人間がいる。常朝とは、いうまでもなく『葉隠』の語り部である。私はそれを当時刊行されていた「江戸史料叢書」の中の上下本として読んだ。
『葉隠』といい山本常朝といえば、その武士道の主張で戦前の右翼思想家のイデオロギー形成に寄与したことから、左翼からは批判的な眼で見られることも多いようである。けれども、それは山本常朝自身の責任ではない。常朝自身の考え方には、右翼とか左翼とかいった狭い範疇を越えた普遍的な真実がある。
常朝の思想の核心は、武士の身分として「死の決意をもって主君に奉じる」ということにあった。武士の生き方としての死の覚悟である。彼の人生観、死生観はそれに貫かれている。
「毎朝毎夕改めては死に死に、常住死身に成りて居る時は、武道に自由を得、一生落ち度なく家職を仕果たすべき也」と語っている。
ある意味では彼は最高の「モラリスト」であるとも言え、少なくとも江戸、明治期には、我が国にこうした人格は少なくなかったのだろうと思われる。そして、まさにそれと対局にあるのが、戦後民主主義の人間群像なのだろう。
常朝自身は、また、それなりに風流人であったようである。彼の言葉の節々にも、詩人的な風格が香ってくる。彼自身は仏道修行や風雅の道は隠居や出家者の従事することとして、無学文盲を称して、奉公一篇に精を出したが、詩人としての気質に不足はなかった。「恋の至極は忍ぶ恋と見立て候」というのもそうである。彼自身がきわめて聡明であったことはその発言からもわかるが、また、なかなか美男子であったようだ。しかし、器量がよく、利発者であっても、それが表に出るようでは人が受け取らぬ事をよく知っていた。それで毎日、常朝は鏡に自分の顔を映して自分の器量を押さえたのである。
江戸と今日の平成の御世では大きく異なるのは言うまでもないが、それでも本質的に共通する部分もある。そこに、『葉隠』が今日にも普遍的に通用する真理を語っている一面も少なくない。たとえば彼は「武篇は気違ひにならねばされぬ者也」と言う。
現代の私たちが、ふつうに暮らしていても、特に男子には日常的にその誇りを試される場合が多い。その誇りを守る必要があれば、いつでも狂い死にせよ、と常朝は教えるのである。
だから、その配偶者は、いつ何時でも彼女の夫が街の路頭で狂い死にすることがあったとしても、その死には何らかの事情があることを思う必要がある。人生の伴侶として、その覚悟を求められるだろう。昔の武士の妻たちは皆そのことは心得ていたはずである。
また、常朝は次のような言葉も残している。「人間一生誠に僅かの事也。好ひた事をして暮らすべき也。夢の間の世の中にすかぬ事計りして、苦を見て暮らすは愚か成る事也。此の事はわろく聞きて害になる事故、若き衆などへ終に語らぬ奥の手也。」












![ヘーゲル『哲学入門』 中級 第二段 自己意識 第三十一節 [自己と他者の自由について]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/1a/f5/817b90d3f8ac7b90d39847a479009217.jpg)

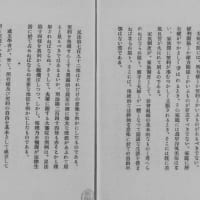

![ヘーゲル『哲学入門』第二章 義務と道徳 第三十七節 [衝動と満足の偶然性について]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/0f/b9/ae7fc3fa05eeda789aa4d9d112b37d72.jpg)

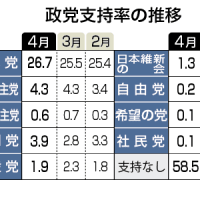










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます