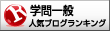朝日新聞における文章修行
脳科学者の茂木健一郎氏が朝日新聞の文章批判をおこなっていることを、池田信夫氏のブログで 知りました。文章を書くうえで、「他山の石」とすべきかとも思い、記録しておきます。果たして朝日新聞の論考が本当に受験小論文の練習に参考になるので しょうか。論理的な文章、科学的な文章はどうあるべきかについて、さらに考えてゆきたいと思います。こうした記事が多くの人に読まれて、日本国民の国語 能力がより高まってゆくことを期待したいものです。
>><<
2012年9月27日(木)付 朝日新聞
http://www.asahi.com/paper/column.html
天声人語
3年前の秋、自民党は落ち武者集団を見るようだった。政権を明け渡し、「自民党という名が国民に嫌われている」と党名を変える動きもあった。「和魂党」やら「自由新党」やら、まじめに考えていたらしい▼支援団体は離れ、陳情は減り、食い慣れぬ冷や飯のせいか無気力と自嘲さえ漂った。その斜陽から、新総裁が次期首相と目される党勢の復活である。「ある者の愚行は、他の者の財産である」と古人は言ったが、民主党の重ねる愚行(拙政)で、自民は財産(支持)を積み直した▼とはいえ総裁に安倍晋三元首相が返り咲いたのは、どこか「なつメロ」を聴く思いがする。セピアがかった旋律だ。当初は劣勢と見られたが、尖閣諸島や竹島から吹くナショナリズムの風に、うまく乗ったようである▼1回目の投票で2位だった候補が決選投票で逆転したのは、1956年の石橋湛山以来になる。その決選で敗れたのが安倍氏の祖父の岸信介だったのは因縁めく。「もはや戦後ではない」と経済白書がうたった年のことだ▼以降の自民党は、国民に潜在する現状維持意識に根を張って長期政権を保ってきた。人心を逸(そ)らさぬ程度に首相交代を繰り返してきたが、3年前に賞味期限が切れた▼思えば自民は、原発を推し進め、安全神話を作り上げ、尖閣や竹島では無為を続け、国の借金を膨らませてきた。景気よく民主党を罵倒するだけで済まないのは、よくお分かりだと思う。たまさかの上げ潮に浮かれず、責任を省みてほしい。
>><<
茂木健一郎(@kenichiromogi)さんの連続ツイート
第728回「天声人語の文体で、政治を論じるのはやめてほしい」
http://togetter.com/li/380308
連続ツイート第728回をお届けします。文章は、その場で即興で書いています。本日は、今朝読んだある文章について。
kenichiromogi 2012/09/27 09:12:17
kenichiromogi
てせ(1)英語のessayは、日本語の「随筆」とは似て非なるものである。前者は、例えばEconomistの文章に見られるように、evidenceに基づくcritical thinkingの結晶であり、科学論文にもつながる。後者は感性に基づく主観の文章であって、曖昧さの本質がある。
kenichiromogi 2012/09/27 09:14:31
kenichiromogi
てせ(2)もちろん、日本語の「随筆」にも美質がないわけではない。枕草子や、徒然草、漱石の「思い出す事など」は「随筆」の傑作であって、生きることの中で私たちが感じる心の揺れ、動きをとらえる。私自身も、「生きて死ぬ私」や「脳と仮想」などの随筆を書いてきた。
kenichiromogi 2012/09/27 09:16:03
kenichiromogi
てせ(3)「随筆」の文体は、日本の一つの財産であるが、すべてのテーマを論じるのに適切ではない。例えば、政治的課題については、evidenceとcritical thinkingに基づく英語のessayの文体で論じるのがふさわしい。ところが、日本では「随筆」で政治を論じてきた。
kenichiromogi 2012/09/27 09:17:41
kenichiromogi
てせ(4)「随筆」の文体で政治を論じることの愚、悪影響、不幸を、今朝の天声人語(http://t.co/unbYa9Ox)を読んで改めて思う。安倍晋三さんが自民党総裁になられたことを論じているが、全体として意味不明。主観や曖昧さの羅列で、何を主張しているのか一向に伝わってこない。
kenichiromogi 2012/09/27 09:19:18
kenichiromogi
てせ(5)思いついて朝刊紙面で添削してたら、紙面が真っ赤になった。まず、「党名を変える動き」から論じることが適切だとは思わぬ。「和魂党」や「自由新党」が検討されたというが、どれくらいsignificantな動きだったのか。ニュースバリューを検討するバランス感覚がない。
kenichiromogi 2012/09/27 09:20:40
kenichiromogi
てせ(6)「斜陽」という言葉で下野を論じているが、ナンセンス。そもそも、健全な議会制民主主義の下では野党になるのは当たり前。必ずと言っていいほど、数年後には政権に返り咲く。実際、今の流れはそうなっている。「斜陽」という感性的、主観的表現は、政治プロセスの本質にかすってもいない。
kenichiromogi 2012/09/27 09:22:17
kenichiromogi
てせ(7)さらに、天声人語は、安倍氏の再登場を「なつメロ」と表現する。小学生でも考えつくような、陳腐な表現だ。読者に提供されるべきは、再登場の背景分析だろう。さらに、「ナショナリズムの風に、うまく乗った」という表現は失礼だ。「うまく」という言葉に、筆者の対象蔑視と低俗さが表れる。
kenichiromogi 2012/09/27 09:24:16
kenichiromogi
てせ(8)その後の文章も、感性に流され支離滅裂。「人心を逸らさぬ程度に」は、政治的プロセスを論じる表現としては不適切である。あげくの果てが、結語の「たまさかの上げ潮に浮かれず、責任を省みてほしい」。自分を何様だと思っているのか。何を安倍氏に期待しているのか、全く伝わってこない。
kenichiromogi 2012/09/27 09:26:06
kenichiromogi
てせ(9)今朝の天声人語の筆者には、以上の失礼をお詫びするが、考えてみていただきたいのは、朝日新聞の一面に載っている以上、天声人語には、公共性があるということである。この文体とスタンスが、日本の政治を語る時の精神風土を作る。その事の罪を、よくよく考えていただきたい。
kenichiromogi 2012/09/27 09:27:25
kenichiromogi
てせ(10)テレビの政治討論番組でも、使われる言語が(特に政治評論家と呼ばれる方々において)感性的、情緒的であることの責任の一端は、天声人語にあるのではないか。このようなスタイルで政治を論ずることの愚に、もうそろそろ朝日新聞、および天声人語の筆者は気づいてほしい。
kenichiromogi 2012/09/27 09:28:37
kenichiromogi
てせ(11)もちろん、天声人語にも、良い回はある。「花鳥風月」や「社会事象」を論じた回である。そのような時には、文体と対象がはまる。天声人語は、もし今のまま継続するならば、政治を論じることをやめるか、あるいは政治を論じる時には硬質な文体で議論する、第二の創業を目指してはどうか。
kenichiromogi 2012/09/27 09:30:18
kenichiromogi
てせ(12)「脳トレ」で天声人語を書き写すという動きがあるようだが、特に政治を論じた回については、今のままではますます日本人の思考が情緒的かつ非論理的になるので、私は絶対反対である。再読、未読に耐えるような文章に、特に政治について書かれた天声人語はなっていない。
kenichiromogi 2012/09/27 09:31:56
kenichiromogi
てせ(13)吉田兼好流の「随筆」ではなく、論理と証拠に基づく「essay」の伝統を、日本でも根付かせるしかない。新聞は、多くの読者が触れる公器として、日本の言論空間を前に進める社会的責務がある。新聞の顔である一面に、情緒的政治論を載せるのは、いい加減やめて欲しい。
kenichiromogi 2012/09/27 09:33:47
kenichiromogi
てせ(14)最後に。橋下徹氏のツイッターでの文章は、時に論敵への烈しい言葉などがあり十分に伝わっていないかもしれぬが、日本語で政治的事象を論ずるスタイルの一つのイノベーション。冷静に読めば、論理的に緻密な構成になっていることがわかる。政治の季節は、ふさわしい言葉で語りたい。
kenichiromogi 2012/09/27 09:35:34
kenichiromogi
以上、連続ツイート第728回「天声人語の文体で、政治を論じるのはやめてほしい」でした。
>><<終わり
※
茂木氏は12回目で「味読」(精読?)とすべきところを「未読」と転換ミスしているようなので、老婆心までに。










 在日米海軍司令部 @CNFJ
在日米海軍司令部 @CNFJ 上下逆さまつげ @kitayokitakita
上下逆さまつげ @kitayokitakita shuzo ati @soratine
shuzo ati @soratine