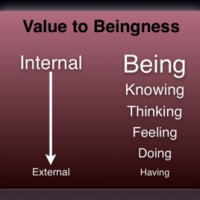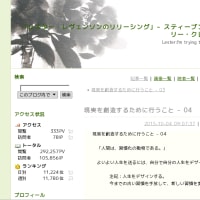仏陀の教え - 参考サイト - 02
前の内容:
仏陀の教え - 参考サイト - 01
仏陀の教えに
「 今 」を生かせ
未来にあなたを縛ることをするな!
過ぎ去った過去に囚われるな!
そうしたら( 逆に )物事はうまく回転していくことでしょう。
とOoi (黄慧音 )氏は語っています。
参考サイト:
釈迦仏教の根本思想について - Yahoo!ブログ
釈迦仏教の根本思想とは何か? (仏教 心理学 哲学)
関連リンク:
第5章 釈迦と死後の世界について
2012/8/23(木) 午後 7:53
さらに付言して言えば、最初期の仏教においては、ニルヴァーナ(中村元氏はニルヴァーナを「安らぎ」であると訳している)は死後に得られるものではなく、今ここに、現世において体現されるものであることが説かれている。
最古の経典(パーラーヤナ篇)に登場する釈迦は、次のように言っている。
『師が答えた、
「メッタグーよ。伝承によるのではなくて、いま眼のあたりに体得されるこの理法を、わたしはそなたに説き明かすであろう。その理法を知って、よく気をつけて行ない、世間の執著を乗り越えよ。」』(Sn.1053)
『師は言われた、
「ドータカよ。伝承によるのではない、まのあたりに体得されるこの安らぎを、そなたに説き明かすであろう。それを知ってよく気をつけて行ない、世の中の執著を乗り越えよ。」』(Sn.1066)
最初期の仏教においては、ニルヴァーナは、現世において眼のあたりに体現されるものであったが、時代の経過とともに、ニルヴァーナは死後に起こるものだと考えられ、ニルヴァーナとは聖者の死を意味するようになったのである。(『中村元選集・第13巻・P.368 参照)
「6.釈迦と形而上学的難題について」に続く・・・↓↓
続きます。仏陀の教え - 参考サイト - 02
6.釈迦と形而上学的難題について
第6章 釈迦と形而上学的難題について
2012/8/23(木) 午後 8:03
ここでもう一つ、中村氏の解説を引用してみようと思う。
『・・・・ゴータマ・ブッダは、当時の諸哲学説と対立する何らかの特殊な哲学説の立場に立って新たな宗教を創設したものでもなく、また新しい形而上学を唱導していたのではない。かれは二律背反に陥るような形而上学説を能う限り排除して、真実の実践的認識を教示したのである。それは「法を観る」立場である。それは人生の如実相を教えるとともに、人間の実践すべき真実の道であることを標榜している。』(『中村元選集・第13巻・P.46)
さらに、中村氏は、次のように言っている。
『仏教以外の当時の諸哲学宗教は、精神・霊魂であるとか絶対者であるとか物質であるとか、その他何らかの実体的原理を認めて、その上に思想体系を構成していた。ところが仏教のみはいかなる実体的原理をも認め
なかった。そもそも形而上学的企図を否認した。そうして実践的真理のみを問題としようとする。』(『中村元選集・第14巻・P.38)
『最初期の仏教は、当時議論されていた形而上学的な問題について解答を与えることを拒否した。』(『中村元選集・第18巻・P.149)
『釈尊は諸々の学者の無益な論争を離れて心の安らぎを得るべきことを説いた。』 スッタニパータ784,785,885-888,834 (『中村元選集・第16巻・P.198)
「第7章 アートマンについて」に続く・・・↓
第7章 アートマンについて
2013/6/15(土) 午後 9:16
つまり、これらを集約すれば、歴史的人物としてのゴータマ・ブッダのとった手法とその他の多くの宗教の手法との最大なる相違とは、多くの宗教が何ものかによって想定された形而上学的見解を前提として成り立っているのに対して、釈迦のとった手法とは、諸々の形而上学的見解から離れることによって成し得たものなのである、ということである。
そういった意味においても、想いからの解脱において解脱した人(=ブッダ)にとっては、生きているうちには容易には知ることができない「死後の行方」つまり「アートマンの存在」あるいは、「死後の意識の存続」の有無などの諸々の形而上学的な思索・考究に関しては「無記」なのであり、釈迦の時代には、修行者の間においては、おそらく人間及び悟った人の「死後の議論」はもちろんのこと、「形而上学的な議論」をすること自体が禁止されていたであろうと私は推測している。
『かれはここで、両極端に対して、種々の生存に対して、この世についても、来世についても願うことはない。諸々の事物に関して断定を下して得た固執の住居(すまい)は、かれには何も存在しない。』(Sn.801)
『想いを知りつくして、激流を渡れ。聖者は、所有したいという執著に汚されることなく、(煩悩の)矢を抜き去って、つとめ励んで行ない、この世もかの世も望まない。』(Sn.779)
言うまでもないか、最初期の仏教で説かれていたことは、「苦の終滅」である。「苦の終滅」とは、如何なる境遇に直面しても決して動ずることはなく、さらには「不安の概念」なといったものが微塵も入り込む余地のない境地なのだろう。
そして、釈迦時代の仏教のとった手法とは、根本的に人間の本能に対して強く反逆していると思う。
つまり、仏教で言う真理とは、人間の本能とは逆の方向線上あり、それが、安らぎの境地を実現させるためにゴータマ・ブッダの行き着いた結論であったに違いない。
「何か特定の思想こそが真理とし、他の思想を間違ったものとするならば、それは偏見である。同時に、その特定の思想にこだわっていることになる。
わたしたちはさまざまなことを経験し、学び、考え、慣れたりするが、それらのうちの一つ、ないしはいくつかを重視して、よいものとしているならば、それもまた偏見が含まれたこだわりなのである。
この道を行くなら、こだわりを棄てなければならない。
戒律や道徳にすらこだわってはならない。
何にも執着せずにおり、何か集団にも依存してはならない。」
「スッタニパータ第4章」
『超訳 仏陀の言葉』白取春彦・幻冬舎 P.157
「第8章 無我について」に続く・・・・・・・↓
第8章 無我について
2013/1/23(水) 午後 8:13
さらに、古い詩句は、「無我」(非我)の「我」(=私)というものに関して、次のように語っている。私は、この『スッタニパータ』の「矢」という経は、先に引用した詩句と併せて、最初期の仏教の根幹を語っているものであると思っている。(以下、『スッタニパータ』Sn.547~593より引用)
『この世における人々の命は、定まった相なく、どれだけ生きられるかも解らない。惨ましく、短くて、苦悩をともなっている。
生まれたものどもは、死を遁れる道がない。老いに達しては、死ぬ。実に生ある者どもの定めは、このとうりである。
熟した果実は早く落ちる。それと同じく、生まれた人々は、死なねばならぬ。かれらにはつねに死の怖れがある。
たとえば、陶工のつくった土の器が終りにはすべて破壊されてしまうように、人々の命もまたそのとうりである。
若い人も壮年の人も、愚者も賢者も、すべて死に屈服してしまう。すべての者は必ず死に至る。
かれらは死に捉えられてあの世に去って行くが、父もその子を救わず親族もその親族を救わない。
見よ。見まもっている親族がとめどもなく悲嘆にくれているのに、人は屠所に引かれる牛のように、一人ずつ、連れ去られる。
このように世間の人々は死と老いとによって害われる。それ故に賢者は、世のなりゆ
きを知って、悲しまない。
汝は、来た人の道を知らず、また去った人の道を知らない。汝は(生と死の)両端を見きわめないで、わめいて、いたずらになき悲しむ。
迷妄にとらわれて自己を害なっている人が、もしもなき悲しんでなんらかの利を得ることがあるならば、賢者もそうするがよかろう。
泣き悲しんでは、心の安らぎは得られない。ただかれにはますます苦しみが生じ、身体がやつれるだけである。
みずから自己を害いながら、身は痩せ醜くなる。そうしたからとて、死んだ人々はどうにもならない。嘆き悲しむのは無益である。
人が悲しむのをやめないならば、ますます苦悩を受けることになる。亡くなった人のことを嘆くならば、悲しみに捕らわれてしまったのだ。
見よ。他の(生きている)人々はまた自分のつくった業にしたがって死んで行く。かれら生あるものどもは死に捕らえられて、この世で慄えおののいている。
ひとびとがいろいろと考えてみても、結果は意図とは異なったものとなる。壊れて消え去るのは、このとうりである。世の成りゆくさまを見よ。
たとい人が百年生きようとも、あるいはそれ以上生きようとも、終には親族の人々すら離れて、この世の生命を捨てるに至る。
だから(尊敬されるべき人)の教えを聞いて、人が死んで亡くなったのを見ては、「かれはもうわたしの力の及ばぬものなのだ」とさとって、嘆き悲しみを去れ。
たとえば家に火がついているのを水で消し止めるように、そのように知慧ある聡明な賢者、立派な人は、悲しみが起こったのを速やかに滅ぼしてしまいなさい。──譬えば風が綿を吹き払うように。
已が悲嘆と愛執と憂いとを除け。已が楽しみを求める人は、已が(煩悩の)矢を抜くべし。 (煩悩の)矢を抜き去って、こだわることなく、心の安らぎを得たならば、あらゆる悲しみを超越して、悲しみなき者となり、安らぎに帰する。』
さらに、古い経典の詩句は、次のようにも語っている。(以下『ダンマパダ』より引用)
『花を摘むのに夢中になっている人を、死がさらって行くように、眠っている村を、洪水が押し流して行くように、―
花を摘むのに夢中になっている人が、未だに望みを果たさないうちに、死神がかれを征服する。』(47~48)
『大空の中にいても、大海の中にいても、山の中の洞窟にいても、およそ世界の何処にいても、死の脅威のない場所は無い。』(128)
そして、仏教においての死に対する姿勢は、『ダンマパダ』の次の言葉によって、集約できるであろう。
『「われらは、ここにあって死ぬはずのものである」と覚悟しよう。―このことわりを他の人々は知っていない。しかし、このことわりを知る人があれば、争いはしずまる。』(1・6)
つまり、経典には、人は、自らの「死」から逃れられない、人は死ぬものである、ということ、そして、「私」が「私のもの」であると思い込んでいる「私の所有物」もまた、いずれは無くなってしまうというこの理(ことわり)を真に知ったならば、心は静まりかえり、争いはなくなる、ということが説かれているのである。
さらに、『スッタ・ニパータ』において「想念を焼き尽して」(Sn.7)と言われるように、想いから解脱す(解き放たれ)ること、そして、想いから解脱する、という想いからも解脱するということ、すなわち、それらを総称して、我執をなくす、ということが最初期の仏教で説かれるところの「無我」(非我)の根幹であると、私は思っている。
「第9章 釈迦と輪廻について」に続く・・・・・↓
第9章 釈迦と輪廻について
第9章 死後の輪廻について
2012/9/15(土) 午後 7:53
要するに、ブッダにとっては、死後においての意識(識別作用)の存続を含めた輪廻の存在の有無については、有という想いもなく無という想いさえもない、ということなのだろうと私は思っている。それは、ブッダの究極の境地においては、死後の議論は存在しないのであり、そういった論点自体が問題として挙がってこないのであろう。
つまり、ブッダの究極の境地においては、死後の輪廻が真実かどうか、具体的に言えば、死後において自らの識別作用が存続するのか否か、死後に断滅するのか永久に行き続けるのか、などといったことについては相手にしない、そして、最終的には、輪廻転生が真実であるのか方便であるのか、そういった想いからも離れる、そして、そういった想いから離れる、という想いからも離れる、ということになるのだろう。
そしてもちろん、死後の世界(天界や地獄など)の存在を否定することは釈迦の姿勢ではなく、あくまでブッダのその勝義においては、あらゆる形而上学説について沈黙する、つまり問題としない、という手法がとられたのであろう。
なお、パーラーヤナ篇(Sn.1073~1076)と「中部経典63」においての死後に関しての質問者の問いが、「人(人間)の死後の行方」ではなく「如来の死後の行方」となっているのは、経典の編纂者の強い配慮があったに違いないと私は思っている。
なぜなら、その質問の問いが「如来の死後の行方」ではなく「人」(人間)の死後の行方についてであるのなら、経典の論点自体が人間一般の形而上学的な領域について触れることになり、さらにはそのことが断滅説と曲解される要素を含むと思うからである。
このことを裏を返して言えば、仏教の修行者が自らの死後の行方に関して有という想いや無という想いを持ち続けたままでは輪廻を繰り返すことになる、具体的に言えば、ニルヴァーナに至ること、つまり輪廻から解脱することは困難となるだろうと私は思っている。
『10.「異説の徒」について』に続く・・・・↓
10.「異説の徒」について
第10章 「異説の徒」について
2013/4/11(木) 午後 8:57
では、一体何ゆえに、最初期の仏教の<修行者向けの教え>においては、「すべての見解」が捨て去られることが説かれていのだろうか?
それに対する私の解釈は、次のとおりである。
釈迦の存命中、多くの宗教者や思想家たちは、自らが打ち立てた見解(それらの見解の大部分が、形而上的見解に関するものであった)を基に、その反対説の論者たちと論争に至り、その結果として争いや摩擦を引き起こしていたのであるが、釈迦の基本的なスタンスとは、いくら論じても決着の着かない形而上学的な議論から離れる、ということであり、さらには、一切の見解を捨て去ったところに、言い換えれば、想いからの解脱によって解脱した境地において、安らぎ<ニルヴァーナ>を見いだしたのであったと私は思っている。
スッタ・ニパータに登場するブッダは次のように言う。
【 『わたくしはこのことを説く』、ということがわたくしにはない。】(Sn.837)
それは、最初期の仏教においては、何らかの特定の教義(特殊な見解)が説かれていたのではなく、一切の見解(想い)から解き放たれることが推奨されていた、ということを意味しているのであろう。(在家者には「死後の天生-応報の思想」が説かれていた。)
正直に言って、これらのことは、「史実としてのゴータマ・ブッダが修行者に対して何を説いたのか?」という、ことを探る際に、看過できない根本的な問題であると私は思っている。
もちろん、私は、「梵網経」で説かれている仏教独自の(おそらく後代の仏教教学者が創作したであろう)第63番目の形而上学的見解を「悪しき見解」であるとして頭ごなしに否定しているのではない。
ただ、仏教は、時の経過と共に、「ブッダの神格化」が進み、思想的な変容が起こっていったことは間違いない事実であると思う。
要約すれば、後代(少なくともアショーカ王統治時代以降)に編纂された経典の記述の多くは、最古の経典であるパーラーヤナ篇やアッタカ篇などに説かれているブッダの教えと矛盾する内容が散見するのであるが、おそらく新しい層の経典が書かれた時代に思想的変容が起こっていった可能性を勘案すれば、これらの理由(最古層の経典と新しい層の経典との矛盾)が容易に氷解されてくるのである。
いずれにしても、最古層の経典に書かれている内容を理解し共感する人は、究めて稀であると私は思っている。
多くの人は、やはり、超越的(超感覚的)なものに憧れるのだろう。
そうであるからこそ元々人間であった釈迦には、空中や水中を自由自在に飛びかったり、壁を通り抜けたり、あるいは前世や来世の世界を見通せるといったような超人的な属性が付加されるようになっていったのだろう。
もちろん、それらを信じることには、私は、何も問題はないとも思っている。
「11.部分的真理について」↓に続く・・・・
11.部分的真理について
第11章 部分的真理について
2012/12/3(月) 午後 9:21
私は「部分的真理」というものを考えてみたときに、経典の次の言葉を思い出した。(引用開始)
『修行僧らよ、われは世間と争わない。しかし世間がわれと争う。法を語る人は、世間の何人とも争わない。
世間の諸の賢者が「無し」と承認したことを、われも「無し」と語る。世間の諸の賢者が「有り」と承認したことを、われもまた「有り」と語る。
世間の諸の賢者が「無し」と承認したことを、われも「無し」と語るとは何のことであるのか?常住・常恒・永久にして変滅をうけることのない物質的なかたちなるものは存在しない、と世間の賢者によって承認されているが、われもまた、それは存在しない、と語るのである。』(SN.Ⅲ,p.138 f.)
『真理は一つであって、第二のものは存在しない。その(真理)を知った人は、争うことがない。かれらはめいめい異なった真理をほめたたえている。それ故に諸々の<道の人>は同一の事を語らないのである。』(Sn.884)(引用終わり)
私は「諸々の<道の人>は同一の事を語らない」ということには、大まかに言えば、二つの意味があると思っている。
その一つとは、今まさに述べた「部分的真理」であり、他説の中にも部分的に真理が存在し、それを承認している境地においては、同一の事を語らない、ということであり、もう一つは、囚われる想念から解き放たれた境地においては、一切の見解に依拠することがない故に、同一の事を語ることもない、ということであるのだろう。
「ブッダの教え」(理法)というものは、敢えて言うなれば、次の経典の言葉で集約できるのだろうと思った。
「『わたくしはこのことを説く』、ということがわたくしにはない。諸々の事物に対する執著を執著であると知って、諸々の偏見における(過誤を)見て、個執することなく、省察しつつ内心の安らぎをわたくしは見た。」(Sn.837)
いわゆる最初期の仏教においては、特定の教義なるものは殆ど説かれていなかった、ということであるのだろう。
『 もしも人が見解によって清らかになり得るのであるならば、あるいはまた人が知識によって苦しみを捨て得るのであるならば、それは煩悩にとらわれている人が(正しい道以外の)他の方法によっても清められることになるであろう。このように語る人を「偏見ある人」と呼ぶ。』(Sn.789)
『(真の)バラモンは、(正しい道の)ほかには、見解・伝承の学問・戒律・道徳・思想のうちのどれによっても清らかになるとは説かない。かれは禍福に汚されることなく、自我を捨て、この世において(禍福の因を)つくることがない。』(Sn.790 )
『かれははからいをなすことなく、(何物かを)特に重んずることもなく、「これこそ究極の清らかなことだ」と語ることもない。結ばれた執著のきずなをすて去って、世間の何ものについても願望を起すことがない。』(Sn.794)
さらにここで、私は、龍樹の『中論』から、おなじみの言葉を再度引用してみようと思う。
『〔ニルヴァーナとは〕一切を認め知ること(有所得)が滅し、戯論が滅して、めでたい〔境地〕である。いかなる教えも、どこおいてでも、誰のためにも、ブッダは説かなかったのである。』(第25章・24)
ブッダは何も説かなかった。繰り返して言うが、私は龍樹のこの言葉は、仏教の核心を表わしている一句であると思っている。
「第12章 想いからの解脱について」に続く・・・↓
第12章 想いからの解脱について
2011/1/18(火) 午後 11:41
何度も繰り返すが、最古層の経典に登場する釈迦は、「私には、これを説く、ということがない」と言う。
見解も主張もないところには、人と人との「争い」や「確執」「摩擦」は存在しない。
さらには、その見解にも主張にも一切の例外はなく(後代の仏教では数々の例外を想定していったのではあるが)、これがまさにゴータマ・ブッダ(釈尊)が到達した結論なのだろう。
『Sn.894 一切の(哲学的)断定を捨て去ったならば、人は世の中で確執を起こすことはない。』
そういった意味合いを含めて、初期経典を総合的に観るなら、私は、「輪廻からの解脱」の「輪廻」とは当然のこととして方便である可能性が高いと思っている。もちろんそれは修行者向けの教えに限定した話である。
そしてさらに究極に言えば、釈迦の境地においては、経典に書かれている「輪廻からの解脱」の「輪廻」が真実であるか方便であるか、という想いからも離れる(解き放たれている)、ということでもあるとも思っている。
つまり、「想いからの解脱において解脱した」人(=悟った人、如来)においては、「輪廻からの解脱」の「輪廻」が真実であるか方便であるか、という問いの解答は、究極に言えば「無記」である、ということになるのだろう。なぜなら、「想いからの解脱において解脱した」人には、死後の輪廻の世界の存在の有無についての見解から解脱して(解き放たれて)いるからである。
釈迦の手法とは、究極に言うなら、やはり、本能への反逆であると思う。
そういった意味において、後代の仏教は、人間においての根源的な世俗的欲求に対して、何らかの折り合いをつけていったところから始まったと見做してよいと思う。
最終的には、理をもって理から離れる、ということ、釈迦のとった手法とは、まさに、そういうことになるのだろう。
注記:これで、終了しています。
前の内容:
仏陀の教え - 参考サイト - 01
仏陀の教えに
「 今 」を生かせ
未来にあなたを縛ることをするな!
過ぎ去った過去に囚われるな!
そうしたら( 逆に )物事はうまく回転していくことでしょう。
とOoi (黄慧音 )氏は語っています。
参考サイト:
釈迦仏教の根本思想について - Yahoo!ブログ
釈迦仏教の根本思想とは何か? (仏教 心理学 哲学)
関連リンク:
第5章 釈迦と死後の世界について
2012/8/23(木) 午後 7:53
さらに付言して言えば、最初期の仏教においては、ニルヴァーナ(中村元氏はニルヴァーナを「安らぎ」であると訳している)は死後に得られるものではなく、今ここに、現世において体現されるものであることが説かれている。
最古の経典(パーラーヤナ篇)に登場する釈迦は、次のように言っている。
『師が答えた、
「メッタグーよ。伝承によるのではなくて、いま眼のあたりに体得されるこの理法を、わたしはそなたに説き明かすであろう。その理法を知って、よく気をつけて行ない、世間の執著を乗り越えよ。」』(Sn.1053)
『師は言われた、
「ドータカよ。伝承によるのではない、まのあたりに体得されるこの安らぎを、そなたに説き明かすであろう。それを知ってよく気をつけて行ない、世の中の執著を乗り越えよ。」』(Sn.1066)
最初期の仏教においては、ニルヴァーナは、現世において眼のあたりに体現されるものであったが、時代の経過とともに、ニルヴァーナは死後に起こるものだと考えられ、ニルヴァーナとは聖者の死を意味するようになったのである。(『中村元選集・第13巻・P.368 参照)
「6.釈迦と形而上学的難題について」に続く・・・↓↓
続きます。仏陀の教え - 参考サイト - 02
6.釈迦と形而上学的難題について
第6章 釈迦と形而上学的難題について
2012/8/23(木) 午後 8:03
ここでもう一つ、中村氏の解説を引用してみようと思う。
『・・・・ゴータマ・ブッダは、当時の諸哲学説と対立する何らかの特殊な哲学説の立場に立って新たな宗教を創設したものでもなく、また新しい形而上学を唱導していたのではない。かれは二律背反に陥るような形而上学説を能う限り排除して、真実の実践的認識を教示したのである。それは「法を観る」立場である。それは人生の如実相を教えるとともに、人間の実践すべき真実の道であることを標榜している。』(『中村元選集・第13巻・P.46)
さらに、中村氏は、次のように言っている。
『仏教以外の当時の諸哲学宗教は、精神・霊魂であるとか絶対者であるとか物質であるとか、その他何らかの実体的原理を認めて、その上に思想体系を構成していた。ところが仏教のみはいかなる実体的原理をも認め
なかった。そもそも形而上学的企図を否認した。そうして実践的真理のみを問題としようとする。』(『中村元選集・第14巻・P.38)
『最初期の仏教は、当時議論されていた形而上学的な問題について解答を与えることを拒否した。』(『中村元選集・第18巻・P.149)
『釈尊は諸々の学者の無益な論争を離れて心の安らぎを得るべきことを説いた。』 スッタニパータ784,785,885-888,834 (『中村元選集・第16巻・P.198)
「第7章 アートマンについて」に続く・・・↓
第7章 アートマンについて
2013/6/15(土) 午後 9:16
つまり、これらを集約すれば、歴史的人物としてのゴータマ・ブッダのとった手法とその他の多くの宗教の手法との最大なる相違とは、多くの宗教が何ものかによって想定された形而上学的見解を前提として成り立っているのに対して、釈迦のとった手法とは、諸々の形而上学的見解から離れることによって成し得たものなのである、ということである。
そういった意味においても、想いからの解脱において解脱した人(=ブッダ)にとっては、生きているうちには容易には知ることができない「死後の行方」つまり「アートマンの存在」あるいは、「死後の意識の存続」の有無などの諸々の形而上学的な思索・考究に関しては「無記」なのであり、釈迦の時代には、修行者の間においては、おそらく人間及び悟った人の「死後の議論」はもちろんのこと、「形而上学的な議論」をすること自体が禁止されていたであろうと私は推測している。
『かれはここで、両極端に対して、種々の生存に対して、この世についても、来世についても願うことはない。諸々の事物に関して断定を下して得た固執の住居(すまい)は、かれには何も存在しない。』(Sn.801)
『想いを知りつくして、激流を渡れ。聖者は、所有したいという執著に汚されることなく、(煩悩の)矢を抜き去って、つとめ励んで行ない、この世もかの世も望まない。』(Sn.779)
言うまでもないか、最初期の仏教で説かれていたことは、「苦の終滅」である。「苦の終滅」とは、如何なる境遇に直面しても決して動ずることはなく、さらには「不安の概念」なといったものが微塵も入り込む余地のない境地なのだろう。
そして、釈迦時代の仏教のとった手法とは、根本的に人間の本能に対して強く反逆していると思う。
つまり、仏教で言う真理とは、人間の本能とは逆の方向線上あり、それが、安らぎの境地を実現させるためにゴータマ・ブッダの行き着いた結論であったに違いない。
「何か特定の思想こそが真理とし、他の思想を間違ったものとするならば、それは偏見である。同時に、その特定の思想にこだわっていることになる。
わたしたちはさまざまなことを経験し、学び、考え、慣れたりするが、それらのうちの一つ、ないしはいくつかを重視して、よいものとしているならば、それもまた偏見が含まれたこだわりなのである。
この道を行くなら、こだわりを棄てなければならない。
戒律や道徳にすらこだわってはならない。
何にも執着せずにおり、何か集団にも依存してはならない。」
「スッタニパータ第4章」
『超訳 仏陀の言葉』白取春彦・幻冬舎 P.157
「第8章 無我について」に続く・・・・・・・↓
第8章 無我について
2013/1/23(水) 午後 8:13
さらに、古い詩句は、「無我」(非我)の「我」(=私)というものに関して、次のように語っている。私は、この『スッタニパータ』の「矢」という経は、先に引用した詩句と併せて、最初期の仏教の根幹を語っているものであると思っている。(以下、『スッタニパータ』Sn.547~593より引用)
『この世における人々の命は、定まった相なく、どれだけ生きられるかも解らない。惨ましく、短くて、苦悩をともなっている。
生まれたものどもは、死を遁れる道がない。老いに達しては、死ぬ。実に生ある者どもの定めは、このとうりである。
熟した果実は早く落ちる。それと同じく、生まれた人々は、死なねばならぬ。かれらにはつねに死の怖れがある。
たとえば、陶工のつくった土の器が終りにはすべて破壊されてしまうように、人々の命もまたそのとうりである。
若い人も壮年の人も、愚者も賢者も、すべて死に屈服してしまう。すべての者は必ず死に至る。
かれらは死に捉えられてあの世に去って行くが、父もその子を救わず親族もその親族を救わない。
見よ。見まもっている親族がとめどもなく悲嘆にくれているのに、人は屠所に引かれる牛のように、一人ずつ、連れ去られる。
このように世間の人々は死と老いとによって害われる。それ故に賢者は、世のなりゆ
きを知って、悲しまない。
汝は、来た人の道を知らず、また去った人の道を知らない。汝は(生と死の)両端を見きわめないで、わめいて、いたずらになき悲しむ。
迷妄にとらわれて自己を害なっている人が、もしもなき悲しんでなんらかの利を得ることがあるならば、賢者もそうするがよかろう。
泣き悲しんでは、心の安らぎは得られない。ただかれにはますます苦しみが生じ、身体がやつれるだけである。
みずから自己を害いながら、身は痩せ醜くなる。そうしたからとて、死んだ人々はどうにもならない。嘆き悲しむのは無益である。
人が悲しむのをやめないならば、ますます苦悩を受けることになる。亡くなった人のことを嘆くならば、悲しみに捕らわれてしまったのだ。
見よ。他の(生きている)人々はまた自分のつくった業にしたがって死んで行く。かれら生あるものどもは死に捕らえられて、この世で慄えおののいている。
ひとびとがいろいろと考えてみても、結果は意図とは異なったものとなる。壊れて消え去るのは、このとうりである。世の成りゆくさまを見よ。
たとい人が百年生きようとも、あるいはそれ以上生きようとも、終には親族の人々すら離れて、この世の生命を捨てるに至る。
だから(尊敬されるべき人)の教えを聞いて、人が死んで亡くなったのを見ては、「かれはもうわたしの力の及ばぬものなのだ」とさとって、嘆き悲しみを去れ。
たとえば家に火がついているのを水で消し止めるように、そのように知慧ある聡明な賢者、立派な人は、悲しみが起こったのを速やかに滅ぼしてしまいなさい。──譬えば風が綿を吹き払うように。
已が悲嘆と愛執と憂いとを除け。已が楽しみを求める人は、已が(煩悩の)矢を抜くべし。 (煩悩の)矢を抜き去って、こだわることなく、心の安らぎを得たならば、あらゆる悲しみを超越して、悲しみなき者となり、安らぎに帰する。』
さらに、古い経典の詩句は、次のようにも語っている。(以下『ダンマパダ』より引用)
『花を摘むのに夢中になっている人を、死がさらって行くように、眠っている村を、洪水が押し流して行くように、―
花を摘むのに夢中になっている人が、未だに望みを果たさないうちに、死神がかれを征服する。』(47~48)
『大空の中にいても、大海の中にいても、山の中の洞窟にいても、およそ世界の何処にいても、死の脅威のない場所は無い。』(128)
そして、仏教においての死に対する姿勢は、『ダンマパダ』の次の言葉によって、集約できるであろう。
『「われらは、ここにあって死ぬはずのものである」と覚悟しよう。―このことわりを他の人々は知っていない。しかし、このことわりを知る人があれば、争いはしずまる。』(1・6)
つまり、経典には、人は、自らの「死」から逃れられない、人は死ぬものである、ということ、そして、「私」が「私のもの」であると思い込んでいる「私の所有物」もまた、いずれは無くなってしまうというこの理(ことわり)を真に知ったならば、心は静まりかえり、争いはなくなる、ということが説かれているのである。
さらに、『スッタ・ニパータ』において「想念を焼き尽して」(Sn.7)と言われるように、想いから解脱す(解き放たれ)ること、そして、想いから解脱する、という想いからも解脱するということ、すなわち、それらを総称して、我執をなくす、ということが最初期の仏教で説かれるところの「無我」(非我)の根幹であると、私は思っている。
「第9章 釈迦と輪廻について」に続く・・・・・↓
第9章 釈迦と輪廻について
第9章 死後の輪廻について
2012/9/15(土) 午後 7:53
要するに、ブッダにとっては、死後においての意識(識別作用)の存続を含めた輪廻の存在の有無については、有という想いもなく無という想いさえもない、ということなのだろうと私は思っている。それは、ブッダの究極の境地においては、死後の議論は存在しないのであり、そういった論点自体が問題として挙がってこないのであろう。
つまり、ブッダの究極の境地においては、死後の輪廻が真実かどうか、具体的に言えば、死後において自らの識別作用が存続するのか否か、死後に断滅するのか永久に行き続けるのか、などといったことについては相手にしない、そして、最終的には、輪廻転生が真実であるのか方便であるのか、そういった想いからも離れる、そして、そういった想いから離れる、という想いからも離れる、ということになるのだろう。
そしてもちろん、死後の世界(天界や地獄など)の存在を否定することは釈迦の姿勢ではなく、あくまでブッダのその勝義においては、あらゆる形而上学説について沈黙する、つまり問題としない、という手法がとられたのであろう。
なお、パーラーヤナ篇(Sn.1073~1076)と「中部経典63」においての死後に関しての質問者の問いが、「人(人間)の死後の行方」ではなく「如来の死後の行方」となっているのは、経典の編纂者の強い配慮があったに違いないと私は思っている。
なぜなら、その質問の問いが「如来の死後の行方」ではなく「人」(人間)の死後の行方についてであるのなら、経典の論点自体が人間一般の形而上学的な領域について触れることになり、さらにはそのことが断滅説と曲解される要素を含むと思うからである。
このことを裏を返して言えば、仏教の修行者が自らの死後の行方に関して有という想いや無という想いを持ち続けたままでは輪廻を繰り返すことになる、具体的に言えば、ニルヴァーナに至ること、つまり輪廻から解脱することは困難となるだろうと私は思っている。
『10.「異説の徒」について』に続く・・・・↓
10.「異説の徒」について
第10章 「異説の徒」について
2013/4/11(木) 午後 8:57
では、一体何ゆえに、最初期の仏教の<修行者向けの教え>においては、「すべての見解」が捨て去られることが説かれていのだろうか?
それに対する私の解釈は、次のとおりである。
釈迦の存命中、多くの宗教者や思想家たちは、自らが打ち立てた見解(それらの見解の大部分が、形而上的見解に関するものであった)を基に、その反対説の論者たちと論争に至り、その結果として争いや摩擦を引き起こしていたのであるが、釈迦の基本的なスタンスとは、いくら論じても決着の着かない形而上学的な議論から離れる、ということであり、さらには、一切の見解を捨て去ったところに、言い換えれば、想いからの解脱によって解脱した境地において、安らぎ<ニルヴァーナ>を見いだしたのであったと私は思っている。
スッタ・ニパータに登場するブッダは次のように言う。
【 『わたくしはこのことを説く』、ということがわたくしにはない。】(Sn.837)
それは、最初期の仏教においては、何らかの特定の教義(特殊な見解)が説かれていたのではなく、一切の見解(想い)から解き放たれることが推奨されていた、ということを意味しているのであろう。(在家者には「死後の天生-応報の思想」が説かれていた。)
正直に言って、これらのことは、「史実としてのゴータマ・ブッダが修行者に対して何を説いたのか?」という、ことを探る際に、看過できない根本的な問題であると私は思っている。
もちろん、私は、「梵網経」で説かれている仏教独自の(おそらく後代の仏教教学者が創作したであろう)第63番目の形而上学的見解を「悪しき見解」であるとして頭ごなしに否定しているのではない。
ただ、仏教は、時の経過と共に、「ブッダの神格化」が進み、思想的な変容が起こっていったことは間違いない事実であると思う。
要約すれば、後代(少なくともアショーカ王統治時代以降)に編纂された経典の記述の多くは、最古の経典であるパーラーヤナ篇やアッタカ篇などに説かれているブッダの教えと矛盾する内容が散見するのであるが、おそらく新しい層の経典が書かれた時代に思想的変容が起こっていった可能性を勘案すれば、これらの理由(最古層の経典と新しい層の経典との矛盾)が容易に氷解されてくるのである。
いずれにしても、最古層の経典に書かれている内容を理解し共感する人は、究めて稀であると私は思っている。
多くの人は、やはり、超越的(超感覚的)なものに憧れるのだろう。
そうであるからこそ元々人間であった釈迦には、空中や水中を自由自在に飛びかったり、壁を通り抜けたり、あるいは前世や来世の世界を見通せるといったような超人的な属性が付加されるようになっていったのだろう。
もちろん、それらを信じることには、私は、何も問題はないとも思っている。
「11.部分的真理について」↓に続く・・・・
11.部分的真理について
第11章 部分的真理について
2012/12/3(月) 午後 9:21
私は「部分的真理」というものを考えてみたときに、経典の次の言葉を思い出した。(引用開始)
『修行僧らよ、われは世間と争わない。しかし世間がわれと争う。法を語る人は、世間の何人とも争わない。
世間の諸の賢者が「無し」と承認したことを、われも「無し」と語る。世間の諸の賢者が「有り」と承認したことを、われもまた「有り」と語る。
世間の諸の賢者が「無し」と承認したことを、われも「無し」と語るとは何のことであるのか?常住・常恒・永久にして変滅をうけることのない物質的なかたちなるものは存在しない、と世間の賢者によって承認されているが、われもまた、それは存在しない、と語るのである。』(SN.Ⅲ,p.138 f.)
『真理は一つであって、第二のものは存在しない。その(真理)を知った人は、争うことがない。かれらはめいめい異なった真理をほめたたえている。それ故に諸々の<道の人>は同一の事を語らないのである。』(Sn.884)(引用終わり)
私は「諸々の<道の人>は同一の事を語らない」ということには、大まかに言えば、二つの意味があると思っている。
その一つとは、今まさに述べた「部分的真理」であり、他説の中にも部分的に真理が存在し、それを承認している境地においては、同一の事を語らない、ということであり、もう一つは、囚われる想念から解き放たれた境地においては、一切の見解に依拠することがない故に、同一の事を語ることもない、ということであるのだろう。
「ブッダの教え」(理法)というものは、敢えて言うなれば、次の経典の言葉で集約できるのだろうと思った。
「『わたくしはこのことを説く』、ということがわたくしにはない。諸々の事物に対する執著を執著であると知って、諸々の偏見における(過誤を)見て、個執することなく、省察しつつ内心の安らぎをわたくしは見た。」(Sn.837)
いわゆる最初期の仏教においては、特定の教義なるものは殆ど説かれていなかった、ということであるのだろう。
『 もしも人が見解によって清らかになり得るのであるならば、あるいはまた人が知識によって苦しみを捨て得るのであるならば、それは煩悩にとらわれている人が(正しい道以外の)他の方法によっても清められることになるであろう。このように語る人を「偏見ある人」と呼ぶ。』(Sn.789)
『(真の)バラモンは、(正しい道の)ほかには、見解・伝承の学問・戒律・道徳・思想のうちのどれによっても清らかになるとは説かない。かれは禍福に汚されることなく、自我を捨て、この世において(禍福の因を)つくることがない。』(Sn.790 )
『かれははからいをなすことなく、(何物かを)特に重んずることもなく、「これこそ究極の清らかなことだ」と語ることもない。結ばれた執著のきずなをすて去って、世間の何ものについても願望を起すことがない。』(Sn.794)
さらにここで、私は、龍樹の『中論』から、おなじみの言葉を再度引用してみようと思う。
『〔ニルヴァーナとは〕一切を認め知ること(有所得)が滅し、戯論が滅して、めでたい〔境地〕である。いかなる教えも、どこおいてでも、誰のためにも、ブッダは説かなかったのである。』(第25章・24)
ブッダは何も説かなかった。繰り返して言うが、私は龍樹のこの言葉は、仏教の核心を表わしている一句であると思っている。
「第12章 想いからの解脱について」に続く・・・↓
第12章 想いからの解脱について
2011/1/18(火) 午後 11:41
何度も繰り返すが、最古層の経典に登場する釈迦は、「私には、これを説く、ということがない」と言う。
見解も主張もないところには、人と人との「争い」や「確執」「摩擦」は存在しない。
さらには、その見解にも主張にも一切の例外はなく(後代の仏教では数々の例外を想定していったのではあるが)、これがまさにゴータマ・ブッダ(釈尊)が到達した結論なのだろう。
『Sn.894 一切の(哲学的)断定を捨て去ったならば、人は世の中で確執を起こすことはない。』
そういった意味合いを含めて、初期経典を総合的に観るなら、私は、「輪廻からの解脱」の「輪廻」とは当然のこととして方便である可能性が高いと思っている。もちろんそれは修行者向けの教えに限定した話である。
そしてさらに究極に言えば、釈迦の境地においては、経典に書かれている「輪廻からの解脱」の「輪廻」が真実であるか方便であるか、という想いからも離れる(解き放たれている)、ということでもあるとも思っている。
つまり、「想いからの解脱において解脱した」人(=悟った人、如来)においては、「輪廻からの解脱」の「輪廻」が真実であるか方便であるか、という問いの解答は、究極に言えば「無記」である、ということになるのだろう。なぜなら、「想いからの解脱において解脱した」人には、死後の輪廻の世界の存在の有無についての見解から解脱して(解き放たれて)いるからである。
釈迦の手法とは、究極に言うなら、やはり、本能への反逆であると思う。
そういった意味において、後代の仏教は、人間においての根源的な世俗的欲求に対して、何らかの折り合いをつけていったところから始まったと見做してよいと思う。
最終的には、理をもって理から離れる、ということ、釈迦のとった手法とは、まさに、そういうことになるのだろう。
注記:これで、終了しています。