
《ゴマが育てている桃太郎トマト(ミニトマトのアイコも作ってるよ~)
 》
》連日の猛暑の中、ゴマは去年に引きつづき、今年も市民農園を借りて野菜作りにはげんでいます。
とはいえ、メキメキ向上するはずの体力はあまり変わらず、一動作ごとに立ちくらむ現象が頻発しているのです(……なぜだ
 )
)そんなこんななので、今が旬のトマトを収穫するときも、フラ~っとして青い実つきの隣の枝までバッサリいってしまうという失態つづき

泣く泣く捨てようとした青いトマトでしたが、
「青いのは、ピクルスにするといいよ
 」とのお得情報を得、さっそく作ってみました。
」とのお得情報を得、さっそく作ってみました。……なんていうと、「やだ、ゴマちゃんたら、ピクルスをサクサク作れるなんて、料理上手なのね~
 」という称賛の声が上がりそうですが、さにあらず……
」という称賛の声が上がりそうですが、さにあらず……
今はスーパーで『ピクルスの素』が売ってるんだぞー

トマトをテキトーに切って、素をぶっこんで2日ほどしたら、ハイ、出来あがり

ほほほほ~


《軽井沢に行ったとき売っていた青トマトのピクルス。おいしそうだったけど、ビンボーなゴマにはちょいとお高めだったので、後ろ髪ひかれつつあきらめたあこがれの品》
てなことで、今日はわが国におけるトマトの歴史について調べてみたのです

まずはウィキさんによると、
「トマト(学名:Solanum lycopersicum)
南アメリカのアンデス山脈高原地帯(ペルー、エクアドル)原産のナス科ナス属の植物。
多年生植物。果実は食用として利用。緑黄色野菜の一種。
日本語では唐柿(とうし)、赤茄子(あかなす)、蕃茄(ばんか)、小金瓜(こがねうり)、珊瑚樹茄子(さんごじゅなす)などの異称もある」
ほかにも『六月柿』という異称があります。

《アイコ(例のすり替えられたあの子のことじゃないよ
 )》
)》トマトが栽培されはじめたのは、8世紀初頭、南米のアステカ・インカの人々によってでした。
そして、今現在、世界には8000種類以上もの品種が存在しており、日本では、農林水産省に品種登録されたものだけでも190種類以上あるそうです

南アメリカで細々と栽培されていたトマトは、16世紀に、あの野蛮&残虐なスペイン人が南アメリカに侵略してきた際、トウガラシやトウモロコシ・ジャガイモなどのタネとともにヨーロッパに持ち帰られ、広まっていきました。
しかし、当初ヨーロッパでは、
「おい、なんかコレ、ベラドンナ(有毒
 )に似てっぺ? んじゃあ、これにも毒があるにちげぇーねーずら
)に似てっぺ? んじゃあ、これにも毒があるにちげぇーねーずら  」(どこの言葉だよ
」(どこの言葉だよ  )と言われ、食用ではなく、観賞用として普及したのです。
)と言われ、食用ではなく、観賞用として普及したのです。ところが、イタリア(のビンボーな人)の中に、
「いんや、きっと食えるはず……
 」と考える人がいて、200年にもおよぶ研究・改良の結果、18世紀には食用となりました。
」と考える人がいて、200年にもおよぶ研究・改良の結果、18世紀には食用となりました。以後、食用トマトはおもにイタリア、ポルトガル、スペインで栽培されはじめ、やがてフランス・南イタリアでトマトソースが作られたり、イタリアではパスタや肉のトマト煮込みなどの料理が考案されたりして、いろいろなトマト料理が誕生し、トマちゃんはメジャー化していきました。
さて、わが国には17世紀半ばころに伝わってきたようです。
文献に残る最古の記述では、江戸前期の儒学者・貝原益軒の大和本草(1709年)の中に、「唐ガキ」と紹介された一文が見られます。
ちなみに中国では、現在もトマトのことを「西紅柿」と呼んでいたりします。
かの狩野探幽も、1668年に『唐なすび』の絵を描いています


しかし、江戸期に入ってはきたものの、最初はヨーロッパ同様に観賞用植物としてしか見られておらず、食用とされたのは明治以降でした。
これは、文明開化の流れの中で、キャベツ・タマネギ・アスパラガス・にんじんなど、他の西洋野菜といっしょに欧米から『食べられるもの』としてあらためて入ってきてからです。
その後、日本人の味覚に合う品種改良・育成を経て、ようやく昭和に入ってからトマトが日本人の食卓に上るようになったのです。
トマト栽培がはじまった当初は、春に種をまいて夏に収穫するのが一般的でしたが、現在はハウス栽培により年間を通してトマトが食べられるようになったのです。
……とはいえ、毎日20個くらいずつ取れると、さすがにどうしていいか悩むけどね

ナスもバカみたいに取れるしさ……ぶつぶつ……毎日トマト&ナス……ナス科食材ばっか











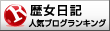



 ここはどこ~
ここはどこ~
 )
) (エライ
(エライ
 キリスト教では、パンはキリストの肉体、ぶどう酒はキリストの血だとされ(=「聖餐論」)、この儀式で口にするパンとぶどう酒は「聖体」と呼ばれる
キリスト教では、パンはキリストの肉体、ぶどう酒はキリストの血だとされ(=「聖餐論」)、この儀式で口にするパンとぶどう酒は「聖体」と呼ばれる )
)
 マントウ:小麦粉に酵母を加えて発酵させた後、蒸して作る蒸しパン。日本のマンジュウのルーツとも)
マントウ:小麦粉に酵母を加えて発酵させた後、蒸して作る蒸しパン。日本のマンジュウのルーツとも) )
)

 )
) )
) )
)

 」
」




