
775年息子の皇太子と共に謀殺された井上内親王(光仁天皇皇后)陵 (宇智陵 うちのみささぎ)
「日本三大怨霊」の平安朝前期の菅原道真の百年前、平安朝末期の平将門・崇徳天皇の3百年前。今から1300年前の奈良時代の政争に関連した史上最強の「祟り神」を恐れた桓武(かんむ)天皇は住み慣れた平城京を捨て長岡京を造営、結果的に奈良から遠い京都の平安京に遷都する最大の原因だったのが、当時最も高齢62歳で即位した光仁天皇の皇后で奈良県五條市御山町に陵墓がある井上(いのえ)内親王の謀殺だった。
吉野川(紀ノ川)と丹生川の合流点の南西側の丘陵地の頂上付近にあり、現在は新しくできた農免道路北側に面している(★注、本来なら遷都は重大ごとであり必ず何か大きな理由がある。ところが平安遷都では日本国の歴史教科書も触れないし歴史学者も語りたくないタブー中のタブー「祟り神」井上内親王を挙国一致で闇に葬る歴史改竄「隠蔽工作」だったのである)

光仁天皇皇太子 他戸(おさべ)親王墓。井上(いのえ)内親王陵(宇智陵)から北東500メートルにあるが道が細すぎて直接行くことは出来ない。周囲は柿畑の中の小高い丘の上にあり後ろには地元自治体の比較的広い墓地が広がっている(★注、陵墓への標識や道路案内の類が一切ないので事前に下調べが必要だ)

光仁天皇皇太子 他戸親王墓

井上内親王の第3子火雷神の霊を慰めるための「火雷(ほのいかずち)神社」
普通の神社とは違い、ここは「祟り神」を祀っているので社殿は柵で囲まれて、前面にある拝殿が木製の格子で封鎖(ヒトと神とを分離)されているので近ずく事が出来ない。他戸親王墓北東500メートルにあり集落から離れた田圃の中の細い道を辿ると吉野川と丹生川合流点の南側の河畔にある小さな神社。後ろ側は吉野川の崖(★注、丹生川を隔てて怨霊神社本宮から直線で200メートル東にある)
奈良県五條市は藤原南家ゆかりの地で、「流配」時に内親王は懐妊しており、男児を出産し、母と兄の怨みを晴らす為、雷神となったと言い伝えられている。五條市にはJR五条駅北側とJR二見駅西側の二か所に井上内親王が出産時に産湯を沸かした窯を埋めたとする釜窪の地名がある。
井上内親王は36歳(38歳説もある)で第1子を、45歳で第2子を産んでいるが、いくら何でも50歳代後半での第3子の懐妊や出産は物理的に不可能なので、これは史上最強の「祟り神」の恨みの深さや超自然的脅威、多くの人々の畏怖を強調するために作られた伝承

同じく出産した場所だと言われる「産屋峰」の宮前霹靂神社(五條市西久留野町)がある。「青天の霹靂」の霹靂は雷のことで、「カントケ(神解け)」とも読み、突然の落雷を意味します。
「祟り神」井上内親王を祀る怨霊神社(本宮)五條市霊安寺町

大幅に永久保存ランクが低い県指定の重要文化財
「御霊大明神御縁起」には、怨霊に追われるように奈良から長岡京、平安京へと遷都した桓武天皇は平安朝初期の西暦800年に怨霊神社とその神宮寺の「霊安寺」を建立。宇智郡(旧五條市と大淀町佐名伝)全域を神域としたと伝えています。宇智郡一円に怨霊信仰が広まった平安朝末期の800年前ごろに、宇智郡内全域に御霊神社が分祀(宮分け)され霊安寺町の本宮を含めて「御霊神社」が23社祀られている。
何度かの兵火で焼け落ちたので、現在の「御霊神社」本宮の建物は江戸時代初期に再建されたものだが永久保存の国の重要文化財資格十分だ。しかし何故か保護の順番や歴史的価値が大幅に低い「県の重要文化財」にとどまっているので国道168号線の邪魔だと一と二の鳥居が撤去され、現在の場所に一の鳥居が移築される。
明治元年に跡形もなく破壊された怨霊神社本宮神宮寺「霊安寺」
 民家の庭先に基石だけが残るだけの「霊安寺」
民家の庭先に基石だけが残るだけの「霊安寺」
「霊安寺」(りょうあんじ)の文字が文献で最初に見られるのは、日本後紀の延暦24年(805)2月6日。霊安寺の創建は定かではありませんが、この時にはすでに存在していて、伝承では葛井王が宇智郡に遣わされた延暦19年(800年)に創建されたといわれているので「御霊神社」も同時に創建されたことになります。

近親結婚と女帝と、
持統天皇の異母妹なので甥の草壁親王と近親結婚した第43代元明天皇とその娘の第44代元正天皇は女帝(★注、後世とは違い、男の天皇より大幅に女帝の方が多かった奈良朝)
持統天皇の父親は天智天皇なの叔父と姪で近親結婚したことになる(大海人皇子と天智天皇は兄弟では無かったとの説がある)が、井上内親王の長女酒人内親王は異母兄の山部親王(井上内親王失脚後の皇太子、後の桓武天皇)と近親婚で朝原内親王を生む。(朝原内親王は桓武天皇の第一皇女なのに母親や祖母と同じ伊勢の斎宮に卜占され若くして死んでいる)
悲運な悲劇が連続する皇女井上内親王(藤原4家の政争に巻き込まれ天智系消滅。天武系も有力皇族が次々失脚)
天武天皇系の井上内親王は大仏建立で有名な奈良朝三代目で最初の男子の天皇第45代「聖武天皇」の長女として生まれたが母親の県犬養広刀自(あがたいぬかいのひろとじ)は皇族ではなく身分が低かった。何かとスキャンダルが多い孝謙天皇(重祚して称徳天皇)の異母姉。
弓削道鏡との浮名を流した異母妹とは大違いで5歳の時に卜占で伊勢神宮の斎宮(恋愛禁止の未婚の皇女)に選ばれ11歳から遠い伊勢に出向、17年後の28歳でやっと平城京に帰り、その後、酒乱で無能を装って過激な政争を搔い潜って生き延びた(冤罪の自分の妻や子供を助けなかったので、本当に無能だった可能性が高い)白壁王(しらかべおう、天智天皇の孫、施基皇子の第六子)58歳と結婚、754年に38歳の高齢出産で第一子の酒人内親王を生む。761年(天平宝字5年)井上内親王は超高齢出産の45歳で、他戸(おさべ)親王を産んだが政治とは離れて平穏に暮らしていた。
本当は天皇になる気が無かった白壁王(49代光仁天皇)
転機は異母妹称徳天皇崩御(770年)相次ぐ政争に巻き込まれて、天武系の長屋王など能力が優れた有力な皇族が一層されていて、あとを継ぐべき人材が枯渇した。
仕方なく政治に全く無関心。身の危険を感じて酒浸りになり、腑抜けを装っていた白壁王が62歳の即位持の最高年齢記録で奈良朝最後の第49代光仁(こうにん)天皇に即位したので自動的に妻の井上内親王は54歳で皇后になり、翌年正月に他戸(おさべ)親王も11歳で皇太子になる。
しかし、今までの成り行きを考えれば当然だが、2年後の772年井上内親王は天皇を呪詛したとの大逆罪で皇后の位を剥奪。他戸親王も母に連座して皇太子の位を剥奪され、廃太子になったが、翌773年和国宇智郡(五條市須恵)の没官の館に監禁され、その1年半後の775年(宝亀6年)4月27日井上内親王は59歳、他戸親王は15歳の若さで死亡。井上内親王母子の謀殺が疑われるが、政変に関与した藤原式家「藤原百川」の策略だったと言われている。
母親が百済系渡来人(外国人とのハーフ)なので、本来なら天皇になる資格が無かった50代桓武天皇
謀殺と怨霊伝説と遷都
奈良時代末期、桓武天皇の信任が厚く、それまでの奈良の平城京から遷都して京都南部の長岡京造営の最高責任者だった中納言藤原種継が785年(延暦4年)に長岡京内で何者かが放った矢で殺された、不審な暗殺事件が今回の「消えた弾丸」安倍殺しに少し背景が似ているのである。2023年07月16日 |
政治・外交、憲法と天皇制 「消えた弾丸」安倍殺しの動機?
平安遷都の最大要因なのに、・・日本史から完全に消された「歴史上最強の祟り神」井上内親王
井上内親王母子謀殺時の政変では、他戸親王の代わりに皇太子となったのが第50代桓武天皇で、他戸親王と同じ異母兄弟の早良親王を皇太子にするも矢張り785年謀殺される。(★注、怨霊神社の御神体は主神が桓武天皇の義理の母親の井上内親王(光仁天皇皇后)、自分の異母兄弟の他戸親王と早良親王の何れも不審死した二人の皇太子の3人を祀る)
自分に一番近い身内が次々と不審死する。これでは桓武天皇が怨霊の祟りを恐れ平城京を逃げ出したのは、当時の常識としては当然の正しい判断だったのである。
霊安寺町の御霊神社は平安時代初期の800年(延暦19年)に霊安寺(りょうあんじ)とともに創建
第45代・聖武天皇第1皇女で、第49代・光仁天皇皇后・井上内親王は呪詛の罪で他戸(おさべ)親王と共に大和国宇智郡(奈良県五條市)に配流されて暗殺された後の天変地異や悪疫が流行。井上内親王・他戸親王の祟りを恐れた第50代・桓武(かんむ)天皇の第12皇子の勅使・葛井親王が派遣されて霊安寺・御霊神社が創建された。(★注、戦乱で焼失。現在の怨霊神社本宮は江戸時代初期に再建されたもの)
現存する、最も古い五條市中之町「怨霊神社」(鎌倉時代前期の1238年霊安寺町の本宮から分霊「宮分け」)

平安朝末期に怨霊神社本宮から分祀された奈良県五條市中之町1765番の御霊神社の見どころはいずれも重要文化財に指定されている本殿・他戸神社本殿・早良神社本殿です。本殿・他戸神社本殿・早良神社本殿は室町時代中期の1472年(文明4年)に建立されました。

国道310号に沿って鎮座。玉垣で囲われた境内は社叢が鬱蒼としており、入口には朱塗りの両部鳥居が東向きに建っています。(★注、JR五条駅から2kmで徒歩なら30分程度)

井上内親王が火雷神を生んだとき、産湯に使ったという釜を埋めた「釜塚」があります。(★注、JR五条駅に一番近く国道310号線四つ辻には案内看板もあるが住宅密集地なので怨霊神社に特徴的な長い参道がない)
すべての「御霊神社」の拝殿は丈夫な木製の格子で厳重に塞がれている
この画像では読めないが中央には「開けた者は必ず閉めるように」との注意書きが小さな文字で書いてあるイノシシ除けのステンレスの丈夫な金網の「柵」(高さ7尺、2・1メートル)が参道の入り口(横幅3尺)を塞いでいる。
「祈」(いのり)の一文字以外、史上最強の「祟り神」井上内親王を祀る「怨霊神社」であるとの道路案内や説明看板が何処にも無いので普通の都会人なら入るのを躊躇する
(何度も「入り口」の柵の前を通ったのだが、・・ (^_^;)
一番発見するのが難しかった奈良県五條市六倉町217の御霊神社。たぶん歴史上もっとも恐ろしい「祟り神」井上内親王を祀る、怨霊神社である事実を地元住民が隠したかったのだろう。知らんけど \(^o^)/
六倉町と島野町の境に架かる大昭橋の近く、六倉(むつくら)の集落と道路を挟んだ反対側の小山に鎮座しています。
道路から北側擁壁にある狭い切込みの間の、細長いコンクリートの階段の「長い参道」を上がると灯篭や鳥居が現れます。(★注、ただし、道路にも境内にも標識の類が何も無い。怨霊神社を示す一切の説明文も看板もない。もちろん鳥居の扁額も無い徹底ぶりには驚くやら呆れるやら)

石の鳥居に「御霊神社」の扁額を掲げる
吉野川南岸にある二番目に見つけるのが困難な牧の怨霊神社は、宮前池の上にある宮山と呼ばれる丘陵地に鎮座。境内には井戸も掘られている(★注、県道137号にある牧の地元案内板には「宮前池」はあるが肝心の「御霊神社」の表記が何処にも無い)
本殿の扉には正装した武人が描かれていたといいます。
平安時代末期の「宮分け」で牧の集落はホウキとスダレを持って帰ってきたが、スダレは小島に譲り、小島にも御霊神社が建てられたそうです。(★注、参道や境内の社叢は鬱蒼とした針葉樹林や照葉樹林が多く陰気臭いが、周りが広大な柿畑など果樹園の牧の怨霊神社は落葉広葉樹なので冬には明るくて快適)

一番標高が高い(標高差が大きい)ので見つけにくいだけではなく、体力が必要な小和町の御霊神社
200段の階段の上に社殿があります。
元はこの階段の下にあり、明治初年に移転しました。基本的に怨霊神社の本宮から「宮分け」された「御霊神社」は村の守り神的存在(村の鎮守さま。産土神)なので集落の外れに長い参道を持つ構造になっている。
ところが、小和町だけ「御霊神社」が随分離れている位置にあり、これは明治元年の怨霊神社本宮神宮寺である霊安寺の破壊運動(水戸国学などが推進した廃仏毀釈)と関係していると思われる。日本三大「祟り神」の菅原道真や平将門、崇徳院とは違い主神の「祟り神」が女性皇族の井上内親王であることが水戸国学など右翼国粋主義的な偏狭で男尊女卑のイデオロギーに抵触していたので歴史から消されたのである
宮分けの時、小和村の役人が真っ先に駆けつけ、すばらしく立派な御神像を背負って逃げました。
これを知った人々は取り返そうと、あとを追ってきました。
吉野川まで逃げてきましたが捕まりそうになってしまいました。
そのとき、五條村の人が役人に代わって御神像を背負って川を渡りました。
役人は御神像を村まで持って帰り、ほっと一息ついて「(追っ手が)もう来ん」と言ったため、そこに建つ鳥居をモウコン鳥居と呼んだそうです。(★注、この愉快なモウコン伝説は小和の地元では有名で「うちの神さんは霊安寺町の本宮から『盗んできた』ものだ。」との言い伝えがある)

宇智郡内で五條市ではなく唯一大淀町佐名伝(さなて)にある「御霊神社」
寺院が2軒もある100戸ほどの集落北側の田圃を抜けた丘陵地入り口に佐名手の「御霊神社」の石の鳥居が立っている(★注、ただし、六倉と同じで鳥居の扁額も無いし境内にも「御霊神社」の文字も主神の「祟り神」井上内親王の案内表記も何も無い。幕末か明治期の組織的な歴史改竄が疑われる)
佐名伝の歴史
佐名手の荘(さなてのしょう)
佐名伝の「御霊神社」(ごりょうじんじゃ)が、佐名伝に分祀されたのが鎌倉時代と考えられます。
嘉禎四年(1238年)何かの機縁があり、宇智郡一帯に「御霊神社」が十数ヶ所に分祀されたと言われていて、その中の一つが村の鎮守として祀られている「御霊神社」であると考えられます
神社が祀られるということは、「井上内親王」の縁起よりも、村に農耕が定着していて一定の農業生産が行われていて、自然の恩恵に畏敬の念と感謝を抱いていたことから神社を祀られたと思われます。
と言っても、現在のような神社ではなく素朴な社であったことでしょう。宗教的に施設が出来たことは、そこに住む人々の帰属意識や郷土への愛着が高まってのことと考えられます。
村の鎮守
村の鎮守である「御霊神社」は、「井上内親王」を祀っています。
「井上内親王」の読み方は、「いのうえ・いのえ・いかみ」とあるようですが、私たちは「いのうえないしんのうさま」と仰いでいます。
「井上内親王」は717年(養老元年)中央では平城に都が造られ新しい時代の幕開けのころ、第45代天皇の聖武天皇と懸犬養広刀自(あがたいぬかいのすくねとじ)の子として誕生されました。
11歳を迎えた井上内親王は伊勢神宮に仕え、白壁王の后となり、白壁王が光仁天皇に即位されると皇后となられました。
しかし、時は移り、772年(宝亀二年)三月皇后の井上内親王は大逆の罪により皇后から下され、同じく五月に皇太子の他戸(おさべ)親王も皇太子から下され、
そして十月、二人とも大和国宇陀郡に幽閉されました。
そして、年変わり宝亀四年四月、井上内親王と他戸内親王は獄死されたのでした。
この事件は、皇位継承の争乱によるところがあり、早くから二人の死を弔うとともに祟りを恐れるほどの事件であったと言えます。
「井上内親王」を慕い、その流れの皇位継承を願っていた吉野の地方豪族たちは、親王なきあと、各地の山稜に神社を設け「吉野皇太后」として読経の奉納が行われ
ました。村の鎮守・御霊神社は、その一つと言えます。今日に至っては村の鎮守の神様としてお祀りされ親しまれています。
今日村の安穏を祈願し、折にふれて村人・宮座講により参詣の行事を行っています
お正月の年賀の参詣・自治会主催の成人式・夏・秋の大祭りをはじめ。毎日、村人の参詣があり、当番により定期的な清掃も行われています。
特に秋のお祭りに際しては、旧大阿太村の各地と同じように「お仮屋」建てが行われています。各地により建て方や資材に違いがあり、佐名伝独自の「お仮屋」
が例年、宮座講によって建てられています。
(佐名手自治会ホームページから抜粋)
700年ほど前の鎌倉時代初期に宮分けした「怨霊神社」では大淀町「佐名手」だけがホームページを持っており五條市霊安寺町の本宮とは今では関係が無くなっている模様である
嘉禎4年(1238)、本宮から宇智郡内の22村に分祀され、新たに御霊神社が建てられたり、その地にあった神社に併せ祀ったりしたことを「宮分け」と言い、各地にその伝説が残っています。
おもしろいのは、現在のように正式に勧請、あるいはお祭りをして神霊を祀るということではなく、御神像をはじめいろんな物を奪い合っていることです。
しかも、数社が御神像を持って帰ったといわれています。

国道168号線に面した(五條市丹原町宮山473)御霊神社(★注、怨霊神社本宮の一の鳥居と二の鳥居がR168号線建設時に取り壊されたように丹原にも参道が無い)
丹原町 …… 当時の神官が真っ先に行って宝冠を着けた鋳造の像をもらってきました。
これが本物の御神像であるといわれています。
滝町 …… 鬼八という人物が簀子の下に隠れていて、太鼓の合図とともに木像4体を背負って逃げました。
足が速い鬼八はどんどん逃げて、追っ手が来なくなったので、芝崎の岩の所で御神像を下して休みました。
それで、この岩は明神岩と呼ばれるようになり、明神岩は境を守る岩となったといわれています。
南阿田の人が「土地を提供するので、うちの氏神さんとしても拝ませてほしい」と申し出たので、現在の地に合祀したといわれています。
山田町 …… 馬に乗った御神像を頒けてもらったといわれています。
大深町 …… 大深は機先を制して真っ先に剣と御幣、谷奥深は船に乗った女神像、
田殿は一番あとにやってきて薦をもらって帰りました。
中之町はミソコシとホウキ、小島町はスダレ、中牧・市塚町・二見はホウキ、岡町は御幣を持って帰ったといわれています。
古代の祭祀では玉箒や幣に神霊が依りつくとされ、現在のホウキとは意味が全く違うものです。

御霊神社 黒駒・落杣神社

式内社。御霊神社・落杣神社の2枚の額が並んでかかっています。(★注、平城京を捨てる原因となった史上最強、しかも他に類例がない女の「祟り神」である井上内親王を祀る「御霊神社」は他の無難な神様と合祀される例が多い)
本殿は平成21年より大修理を行い、23年に竣工しました。
神社の東側に磐座があり、その前に小祠を置いて祀られているのが落杣神社です。
現在は御霊神社に合祀されています。
この近くには黒駒古墳もあります。
宮分けの時、御神体を馬に乗せて犬飼町へ運ぼうとしたところ、馬の脚が止まり、押せど引けど動かなくなりました。
それで、御霊さんはこの地に留まることをお望みだと思い、ここに祀ったといわれています。
御神体は箒であったと伝わっています。
(★注、吉野川南岸の丘の上にある黒駒町の「御霊神社」は井上内親王陵(宇智陵)の北東700メートル、光仁天皇皇太子 他戸親王墓の東700メートルほどで、悲運の井上内親王母子の陵墓からは一番近い位置にある)

霊安寺町の怨霊神社本宮に一番近い御霊神社 二見
秋祭りに新町の御旅所にお渡りをした帰り、桜の木を回る「回り桜」の風習が残っています。霊安寺町の怨霊神社本宮に一番近い位置の「御霊神社」で吉野川北岸にあり神社の後ろが崖になっている

皇室の先祖神(アマテラス)を祀っているのに壬申の乱の持統天皇以来、明治天皇まで歴代天皇が誰も参拝しなかった伊勢神宮
歴代天皇が「1000年以上訪れなかった伊勢神宮」の謎 アマテラスの正体とは?
2024年01月12日 デイリー新潮
なぜ天皇家の祖神アマテラスは、実在の初代王と言われる崇神天皇によって、伊勢に追いやられたのか。歴代天皇は明治になるまで千年以上もの間、アマテラスを祀る伊勢神宮を訪れなかったのはなぜか。(★注、天照大神を伊勢に追いやったとの伝承や、第10代崇神天皇の存在自体が神話の範囲。歴史的事実とはみなされない)
こうしたことの背後には、朝廷の権力を独占してきた藤原氏の暗躍がある、というのが歴史作家の関裕二氏「スサノオの正体」の見方
ただし、皇太子時代の桓武(かんむ)天皇(山部親王)は、体調不良を理由に伊勢神宮に詣でている。
桓武天皇は順調に皇位継承候補になったわけではない。本当の皇太子を死に追いやって、権利を獲得している。
父・光仁天皇の正妃は井上内親王で、二人の間の長子が他戸(おさべ)親王。光仁は天智系で、天武系の称徳(しょうとく)天皇の崩御を受けて、即位した。この時、皇位をめぐって天武系と天智系はもめたが、天武系の井上内親王を皇后に、その子の他戸親王を皇太子に立てることで、親天武派を説得し丸く収めたのだろう。ところが、井上内親王が光仁天皇を呪詛したという理由で、母子は幽閉。これを受けて、山部親王が皇太子に立てられた。しばらくして、母子は幽閉先で同じ日に同じ場所で亡くなってしまった。密殺されたのだろう。邪魔者は皇族でもワナにはめて抹殺するのが、藤原政権の手口である(ワナと言うよりもでっちあげ)。
いわゆる「御霊信仰(祟り封じ)」は、井上内親王と他戸親王の事件がきっかけだったと考えられている。山部親王は他戸親王が死ななければ皇太子になれなかったのだから、やましい気持があったのだろう。井上内親王と他戸親王の祟りが体調不良の原因と信じ、あわてて、伊勢の神にすがったわけである。
問題は、なぜ祟り封じのために伊勢の神を選んだのかだ。山部親王は自らの行動によって、「伊勢の神は病をもたらす恐ろしい祟り神」であることを証明してしまったわけである。
(抜粋)
1月12日 デイリー新潮
「祟り神」としてのアマテラス
デイリー新潮で「スサノオの正体」著者の歴史作家関裕二は、出雲(大国主)神話の荒ぶる神スサノオと、皇室の先祖神を祭祀する伊勢神宮のアマテラス(スサノオの姉)とが何時の間にか入れ替わった(伊勢神宮が祀っているのはアマテラスではなく「祟り神」のスサノオだった)との仮説を主張している。(★注、外国の太陽神は常に男だが我が日本だけは例外で女性。しかも記紀の記述から分かることは日本神話の最高神アマテラス自身が最初から「守り神」であると同時に恐ろしい「祟り神」としての相反する性格を併せ持っていた)
「怨霊」を封じるための神社
天皇家の先祖神のアマテラス自身が、井上内親王と同じ恐るべき「祟り神」だったので御所では祭ることが出来ないので遠い地の果ての伊勢に放逐して封印していたらしい。
平城京を捨てて、最後には平安京に遷都した桓武天皇が心底怯えた、恐ろしい怨霊神社「御霊神社」のシステムに一番近いのが小学校の修学旅行に良く使われる「伊勢神宮」で、恐ろしい「祟り神」を封印する拝殿や、神社の神域の広さに不釣り合いな長すぎる参道などの構造も伊勢神宮と「御霊神社」とは非常に似ている。
王殺しの伝統がある怖ろしい日本の歴史 『伊勢神宮に参拝しなかった歴代天皇の不思議』
国家神道の総本山的な皇室の先祖神である天照大神を祀る伊勢神宮ですが、実は、何故か明治天皇以前の歴代天皇は誰も参拝していない。
大海人皇子(天智天皇の皇太子。天武天皇)が吉野を逃れて岐阜で兵を挙げる前に伊勢神宮に参拝したとあるが、大海人皇子は天智天皇の子供(跡継ぎ)の大友皇子(明治時代に『弘文天皇』という名で追諡)を殺す壬申の乱を起こしている。伊勢神宮ですが、天皇家(皇室)にとって歴史的に祈りの場所であるよりも呪とか穢れの禍々しい神を封じる恐ろしい場所らしい。(だから京から遠く離れた、地の果ての伊勢だったのである)
日本書紀によるとヤマトタケルの第二子で第14代天皇の仲哀天皇は神託に従わなかった(アマテラスに逆らった)ので殺され、二番目の妃の神功皇后が代わり朝鮮に侵攻、第15天皇の応神天皇を生む、怖ろしい『王殺し』の歴史書である。
ゾルレンのためにザインの天皇を殺す偽右翼
2018年10月15日 | 政治・外交と天皇制 2019年02月26日 | 宗教 うろんな「二・二六事件」日本的クーデター

八咫烏の神話や、熊野水軍の本拠地で日本独自の修験道(仏教と神道が融合した山岳宗教)の総本山でもあった熊野本宮大社の参詣曼荼羅。(★注、熊野本宮大社は明治22年(1889年)の大水害までは熊野川の中洲の大斎原にあった)
伊勢神宮よりも天皇家の信仰心が篤かった神仏融合の熊野権現
『日本書紀』によると日本武尊(ヤマトタケルノミコト)の子供の仲哀天皇(第14代天皇)は九州の熊襲征伐の途中に妻(神功皇后)が神がかっって『朝鮮征伐の神託』を受けるが、仲哀天皇が神託に従わなかったため神(アマテラス)に殺されたとの恐ろしい記述がある。
宗教学者の島田裕巳は、天皇の住む京都御所内にはアマテラスを祀っていないとか、明治天皇以前の歴代天皇は誰一人も伊勢神宮にお参りしないなど、天皇家の先祖神としての天照大御神(伊勢神宮)の意味が何とも不可解である。
壬申の乱で大海人皇子(後の天武天皇)が吉野から伊勢神宮(天照大御神)に参拝して必勝を祈願、岐阜で挙兵して天智天皇の息子の大友 皇子(弘文天皇)を殺しているなど何とも血なまぐさい歴史がある。(★注、クーデターを成功させた天武天皇の妻の持統天皇が伊勢神宮を整備修復して、天皇として最後の参拝をした事実は「壬申の乱」の史実からは当然な政治的処置。何の不思議もない)
長い間、天皇の未婚(処女)の内親王が都から遠く離れた伊勢神宮に斎王として派遣される仕来たりは万葉集などでも『悲劇』として歌われている(天皇家の守り神というよりアマテラスには『祟り神』の要素が強いらしい)
このため歴代の上皇(法皇)や女院は伊勢神宮ではなくて紀伊半島南部の熊野本宮大社(那智大社など熊野三山)を参拝していた。京都から1カ月もかけ『中辺路』の山道を使って熊野詣を歩いている。2021年10月25日 | 政治・外交、憲法と天皇制 女性天皇待望論の必然性
(おまけ)
小島町「御霊神社」
隣にある大きなモンベル五條店(吉野川のカヌー競技基地)で聞いたが全員、誰一人も知らなかった謎の怨霊神社
 格子の栄山寺境内の北東端に南面して鎮座。
格子の栄山寺境内の北東端に南面して鎮座。
もとは藤原氏の氏神である春日社を祀っていたと考えられています
宮分けで井上内親王が祀られました。
いずれにしても寺を護持する鎮守であったと思われます。
何故か賽銭箱がない拝殿の閉じられた格子の向こうに見えるのが史上最強の「祟り神」井上内親王を祀る本殿
村社にして小島一円の氏神(産土神)。
井上皇后を祀る。
嘉禎4年(1238年)、宇賀郡霊安寺御霊神社より分祀。
この社は、もとは興福寺の支配下にあった栄山寺では鎮守の春日神社と呼ばれた。
安土桃山時代に興福寺の支配から脱すると御霊神社と称するようになった。
国宝を所有するので拝観料を徴収する栄山寺の境内社ですが、(人が少なすぎて)イノシシ除けの柵としては低すぎて境内の湿地がヌタ場になったのは当然の成り行き
拝殿の格子から見上げる「祟り神」井上内親王を祀る本殿







 民家の庭先に基石だけが残るだけの「霊安寺」
民家の庭先に基石だけが残るだけの「霊安寺」

























 格子の
格子の







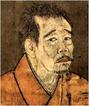

明治帝以降、日本の帝室が伊勢を尊重するのと同様に。
《宝亀九年(七七八)十月丁酉【廿五】》○丁酉。
皇太子向伊勢。
とあるなら、
何故タイトルが意識的に読者を間違いに誘導する「桓武天皇参詣」になるのでしょうか。?
実に不思議です。普通なら誰も間違いません。致命的に注意力や判断力が不足しています。
ちなみに今回の主役の史上最強の「祟り神」井上内親王(光仁天皇の皇后)と他戸親王(皇太子)の二人が失脚したのが772年。謀殺されたのが775年なので桓武が皇太子になってから6年後。母子が殺されてから3年後に伊勢に参拝している。
ちなみに桓武の父親は天皇だが母親が百済系渡来人なので本来なら次期天皇の皇太子にはなれないのです
ところが、何しろ当時の先進国百済系なので、本人は官僚としての資質を持っていたが、同時に朝鮮半島には陰陽五行説など道教の卜占や呪いには深く染まっていたので、北と東西の3方向が山に囲まれ南に水が流れる平安遷都になったらしい。毎日新聞ソウル支局長によれば今でも韓国では与野党とも風水頼み。日本でも多分自民党は創価学会の政治部公明党と同じでカルト
そして伊勢神宮に行幸した持統天皇は帝位11年の間に43回も都を離れて行幸している。なんとも異様過ぎるのです
そのうち31回という、吉野行幸の頻度を考えると、吉野に「政治的軍事的な勢力があった」と考える方が辻褄が合います。大海人皇子が決起したのは岐阜だが、天智天皇へのクーデターを決意したのは吉野での出来事です。
吉野は日本独自の山岳宗教修験道の総本山であり、平安貴族とか上皇の熊野詣でも修験道と関係している。神仏混交の修験道は真言と天台の密教の流れなので有名な比叡山の僧兵は修験道の荒法師。弁慶の伝説など軍事力そのもの
伊勢よりも、高野山の方が皇族がお参りしているかもしれませんよね・・・
崇徳院の墓なり社が、讃岐から京都に移されたのは、明治になってから。前の東京五輪の時も東京からわざわざ勅使を崇徳院の墓に報告に行かせたとか。
余りに「妙」な気がします・・・
まあ天皇だから、天皇の呪いが怖いのでしょうが・・
後醍醐天皇が女装して吉野辺りに逃げ込んだりしてるように、政変に敗れた貴族たちは吉野熊野に亡命政府でも作ってたのでしょうか。また、海を隔てる四国にも御霊信仰が盛んですが、四国や熊野の森深い土地に政変で貴族や王家が逃げて祟り神化するのが神道史の一部であり、天皇制からされる前の天皇の仕事とは、それらの霊を慰撫する事だったのではないでしょうか。
天武の子孫たちが自滅して、天智直系の新王朝というべき桓武体制は先進的な渡来人勢力に支援されていた。
中国由来の律令体制の根幹である儒教原理からすれば、女性である天照大神を祀る伊勢神宮を天皇が参拝することはとうてい許容できないだろう。
究極的には国家神道を指向する明治体制は、儒教原理と別個の水戸学や平田国学など日本固有の原理に支えられる必要があった。
明治天皇になって伊勢神宮に参拝したのはそうした因果ではなかろうか。
私が「奈良に高鴨神社というのがありますが、加茂氏と関係あるのですか?」と質問したところ、
その方のお返事「あります。加茂氏は元々は奈良で勢力を蓄え、その後、今の京都の方へきた。元から京都周辺にいた勢力を糾合した、ということだろうとされています」
私は今日(5月15日)上賀茂神社で、葵祭を見学してきましたが、京都の上賀茂・下賀茂両社は皇室とも、抜きんでた関係を続けてきたところだという事でした。
高鴨神社のHPより「当神社は全国鴨(加茂)社の総本宮で弥生中期より祭祀を行う日本最古の神社の一つです。」
加茂氏は、渡来系ですが、皇室を盛り立ててきた系統です。
なにか関連があるかもしれないですね。
軍事をつかさどるのが物部氏で天皇家(大王家)と同じ、独自の天孫降臨神話神話を持っているのですが
物部氏の氏神とする石上神宮(奈良県天理市)とか、奈良県桜井にある三輪山(みわやま)の大物主大神を祀る大神神社など、奈良には出雲神話の神々を祀るが、たぶん金剛山の山麓の高鴨神社も同じ系列だと思われます。
高鴨神社の北にある一言主神社も同じで大国主系の、一言主神は日本書紀などによると雄略天皇と争ったと記されており、しかも場所が神仏混交の日本独自の修験道の開祖役小角の大和葛城山の山麓と色々と面白い歴史がてんこ盛り。奈良に高鴨神社の社殿は板葺きなのに驚いた。
ところが、よく見かける檜皮葺とは違い板葺きなので20年程度で新しくする必要があるらしいが伊勢神宮とは違い、何の説明も無い。伊勢神宮の太陽神アマテラスの弟が出雲神話の先祖のスサノオなので、奈良県内に多くの出雲系列の神社が多いのは頷けるが、逆に考えると飛鳥など長く都があったなr県内に、皇室の先祖神アマテラスを祀る神社が少なすぎるように思います。史上最強の「祟り神」井上内親王と同じで、アマテラスとは天皇家の先祖神(守り神)の性格よりも、「祟り神」の性格の方が強いのでしょう。
3月26日、堀川潤氏の講演を聞きました。氏は
「賀茂十六流に属する上賀茂神社旧社家の家柄。始祖は5世紀にまで遡る。先祖は代々上賀茂神社の神職を務め、朝廷とのかかわりが強かった。」
「平成28年より、八咫烏(賀茂建角身命)を祖とする賀茂一族の団体である賀茂県主同族会の理事長を務めている。」ということです。
賀茂祭(葵祭)は、明治17年(1884)「春日大社の春日祭・石清水八幡宮の石清水祭と共に三勅祭として」「斎行されることに」と。
今年5月15日の賀茂祭(葵祭)には皇族の彬子さんが、昨年に続き参加(主催者的にはご臨席)。何か素人には分かりませんが、神事では大切な役割があるのでしょう。
八咫烏はご存じのように、想像上の神武天皇を助けた一族です。熊野大社にも八咫烏の像があります。(コロナ禍の頃にはくちばしにマスクが)
賀茂氏は、渡来人ではないですね。思い違いでした。
あと、大国主には、たくさんの別名(大物主大神などなど)がありますが、これらは、たくさんのいわゆる「国つ神(国津神)」の1グループをまとめたものではないでしょうか。
しかし通常の20年程度で代替わりしていたと考えれば、ピッタリ中国の最初の統一王朝秦の始皇帝時代にあたり、それなら、
日本書紀「神武東征」神話にピッタリとシンクロ。ほぼ一致する司馬遷「史記」徐福神話
全国各地に多数ある徐福が日本に初めて上陸したとの伝説があり
秦の始皇帝の求めた『不老不死』は不可能だが、
日本の歴史家では魏志倭人伝(動乱の3世紀末)の卑弥呼は大好きで史実だと思っているが、なぜか前漢時代の歴史家司馬遷(紀元前145~紀元前87)の『史記』の徐福は大嫌いで『史実ではない』と長いあいだ完全無視している。ところが日本以外では女王卑弥呼よりも、史記の徐福が蓬莱で国王になった話の方が有名であり関心も高い。(★注、そもそも日本国内でも卑弥呼神社など卑弥呼の民間伝承はゼロだった。ところが、対照的に徐福の伝承は日本中に多数存在している)
何故日本では史記の徐福を歴史家が排除するかの謎ですが、日本の高度な禁忌(タブー)に抵触するからでしょう。
記紀に出てくる天皇は百歳以上の長命だが、普通に在位期間20年程度で換算すると徐福が東方へ出帆して蓬莱島で王となった時期と初代天皇の神武が即位したのが同じ時期となる。
何故、日本だけは徐福伝説を歴史家が取り上げないかの謎ですが、司馬遷の史記の徐福伝説の話と、日本の記紀の記述(紀伊半島の熊野に上陸して大和で即位)とが妙に一致するのですね。徐福の話は、やはり不味かったのでしょう。
神武即位と徐福渡来が同時期であることは、日本の歴史学者は戦前から気づいていたらしいが、命が惜しいので間違っても口には出せない。
2023年02月14日 | 文化・歴史
建国記念制定から150年目
https://blog.goo.ne.jp/syokunin-2008/e/e3d696a2fe987faf20b7efd93c508fe5
大国主は大和からの国譲りの使者を篭絡して味方に付けるので、仕方なく武力行使を行うと脅したが、
大国主は「長男に聞いてくれ」とのらりくらりと誤魔化すが、同じく長男も「次男に聞いてくれ」と答えない優柔不断でのらりくらり。
そこで大和側は次男を乗っていた船ごと攻撃してコテンパンに打ち負かして、大国主の次男坊が逃げた先が諏訪湖。武田信玄の守り神の諏訪大社の御神体が出雲から逃げてきた大国主の次男坊、諏訪大社の祭りが荒々しいはずです