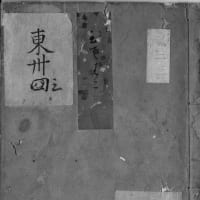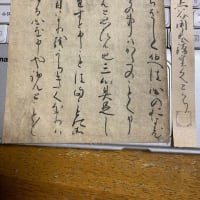14:00から主任会。その前に「五郎八」で牡蠣南蛮を食う。

大ぶりの牡蠣がたくさん入っている。広島産なのだそうだ。梅干しが1個添えられていたので、何の意味か尋ねると、食後の口直しだとか。牡蠣はくどいから、さっぱりさせる効果があるのだと。若旦那のアイデアらしい。私は牡蠣と女はくどいのが好きなんだがね…と女将に冗談を言う。そうでしょうね、おほほほほ…とあしらわれる。BGMにクリスマスソングがかかっていた。次はリリー・マルレーン。女将の趣味だという。戦時中の歌ですがな。さすが、軍人恩給を支給されている人は違いますな。
主任会の議題書を一見すると、ほとんど何もない。しめた、早く終わるぞと喜んだのは甘かった。例の気の重い問題について一渡りの報告があり、そのあとの判定事項はささっと済んだが、カリキュラム改変に向けての設計業務に関する説明と質疑が長引いて、結局17:00近くまでかかった。
今の学部のカリキュラムを調整したのは、実は私である。それが、専門課程の所定単位数が少な過ぎるというので、2012年度(実際には2012年度に入学し2013年度専門課程に進級する学生から適用)に向けて改変作業に入ることになった。ところが、我が学部はコースごとに考え方がバラバラで、およそ統一感というものが無い。それを、さらにバインドをきつくするというのだから、もう全体のカリキュラムを把握できる人は、誰もいなくなるに相違ない。
簡単にいえば、体系性を有しているコースと、学生を教員個人に配したいコースに分かれると思う。我が所属コースは、典型的な前者であり、しかも規模が大きい方だから、今度のカリキュラム改変は実に簡単な作業。そもそも、演習の数を増やす必要を認めないからだ。5分もあれば設計図が仕上がるはず。
斜め前にポン史コースのAB澤主任が座っておいでなので、オタクはどうなさるのですか?とお尋ねすると、選択講義の指定科目数と履修単位を増やすだけだとおっしゃり、既に該当科目にはチェックが入っている。ウチとまったく同じ考えだ。
質疑を聴いていると、文学部はもうおしまいなんじゃないかなあと、真実思った。『文学部がなくなる日』という新書本も出ているしなあ。演習単位を増大させるって、どういう料簡なのか、今もって私には理解できない。我がコースは学部改編以前から、やや講義重視だったということも関係するかもしれない。もともとの調整の時からそうだったが、今のカリキュラムは半期制であって、セメスター制ではないから、学生が留学した場合や、配当学年・学期に単位を落とした場合への想定・配慮を、まったく欠いている。だから、この間の教授会のような、何でもありの救済措置が提案されたりする。
副学部長殿や教務主任殿は、事態の本質を、実はどうも十全に理解されていないように思われるのだ。副学部長殿が言葉につまったから、仕方が無いので助け船を出した。ついでに、この改変自体、コース側・教える側の都合本位で、受講する学生側の立場はちっとも考慮されていない、留学したり、単位を落としたり、延長生になったりする学生たち(そうした学生があんなに大勢生じるのに)をどうするか、設計に当たっては十分考えるべきだと、捨て台詞的な発言をしておいた(それ自体無責任と言わば言え)。今回のカリキュラム改変は、絶対に失敗する。どこもかしこも、特殊ローカルルールだらけになって、カリキュラムの全体像が分からなくなり(事務所の担当者の方だってどんどん異動していく)、数年で破綻すると断言しておきたい。その原因は、中長期的な学部運営ができない我々の体質だが、皺寄せを蒙るのは、すべて学生なのだ。だいたいカリキュラム委員会は、何をしておるのだ? こんな事態を、本当に認めたのだろうか?
現行の教務委員会とは、学生担当の事案に関わる諮問機関だが、こうなると、教務担当教務委員会というのを立ち上げないと、大変なことになると思うがね。今の教務主任殿は、主任会・教授会の議案書を、本当に、本当に全部ご自身で書いていらっしゃるのだろうか?
…やはり私は、今の教務に辛辣かなあ。ただし、協力する気は、毛頭なし。もう引退だもの。