みなさま、おはようございます。海風おねいさんです。
少し遅くなりましたが、今日は七草粥をUPしておきます。
日本には、いろんな季節行事があり、いろんな行事食がありますね。
便利な世の中になるとともに、季節感がどんどん薄れ、
行事食も学校給食でいただくだけでは、寂しい気がします。
ご家庭でもぜひ行事食を作り、四季の恵みに感謝していただきながら、
それにまつわる話題ができたらいいですよね。
本年は、年間通して、行事食も取り上げてまいりますね。

「七草粥」
なんともいわれぬ薬膳の香りいっぱいの春の七草粥です。
身体にとってもいい香り。この風味、最高です。
わが家の七草粥は、生姜と押し麦が入ってるのが特徴。
生姜は風邪予防にもなり、香りを増して食欲をそそります。
生姜を入れただけのお粥も家ではよく作ります。
(生姜は食べません)

「春の七草」
七草 クリック
クリック
子どもの頃に学校で習いましたね。春の七草、覚えてますか?
本来なら、あちこちを散策し、七草を集めてくるものなんでしょうが、
いまはなかなかその環境も望めませんで、便利な七草セットを使いました。

わが家はお米と押し麦を半量ずつでお粥を炊きます。
半分ほど炊けてきたところで生姜のスライスと、
すずな=かぶ、すずしろ=大根の刻んだものを入れて炊きます。

炊き上がる少し前に、せり、 なずな=ぺんぺん草、ごぎょう= 母子草、
はこべら=はこべ、ほとけのざ=こおにたびらこの刻んだものを散らします。
わが家は、このくらいたっぷりと入れますよ。

ひと混ぜして、ひと煮立ちして、完成。とろとろにおいしそうに炊けました。
お節やお正月のご馳走で疲れた胃腸を休め、冬場に不足しがちなビタミンを補う
春の七草粥。昔からの人々の生活の知恵が行事食となります。

 追記(1/13)
追記(1/13)
七草の起源を調べてみましたら、詳しく書かれたサイトがありましたので、
参考までに転載します。
「人日の節句」(じんじつのせちく)から・・。中国の古俗に、元日から六日までは鶏(にわとり)、狗(いぬ)、羊(ひつじ)、猪(いのしし)、牛(うし)、馬(うま)という家畜を占い、七日には「人」を占うというものがあり、この日を「人日」と呼びました。「人日」には七種菜羹(ななしゅさいよう、又はしちしゅさいのかん)を食して無病息災を祈念したのだそうです。
日本では、平安時代の延喜式(えんぎしき)という書物に、正月十五日の供御(くご)の粥(かゆ)、又、即位後の解斎(げさい:物忌みを解いて平常に戻る)の粥(かゆ)などが見られ、いずれも節目、節目にお粥を食して身を清めたようです。
また、平安時代の人気行事として、正月最初の子(ね)の日には郊外に出かけて若菜を摘むという、今で言うピクニックのようなものがあり、この3つの行事がごちゃまぜになって「七草かゆ」の風習が出来上がってきたようです。
以上 AJINOMOtO.メルマガ・コラムより転載
少し遅くなりましたが、今日は七草粥をUPしておきます。
日本には、いろんな季節行事があり、いろんな行事食がありますね。
便利な世の中になるとともに、季節感がどんどん薄れ、
行事食も学校給食でいただくだけでは、寂しい気がします。
ご家庭でもぜひ行事食を作り、四季の恵みに感謝していただきながら、
それにまつわる話題ができたらいいですよね。
本年は、年間通して、行事食も取り上げてまいりますね。


「七草粥」
なんともいわれぬ薬膳の香りいっぱいの春の七草粥です。
身体にとってもいい香り。この風味、最高です。
わが家の七草粥は、生姜と押し麦が入ってるのが特徴。
生姜は風邪予防にもなり、香りを増して食欲をそそります。
生姜を入れただけのお粥も家ではよく作ります。
(生姜は食べません)

「春の七草」
七草
 クリック
クリック
子どもの頃に学校で習いましたね。春の七草、覚えてますか?
本来なら、あちこちを散策し、七草を集めてくるものなんでしょうが、
いまはなかなかその環境も望めませんで、便利な七草セットを使いました。

わが家はお米と押し麦を半量ずつでお粥を炊きます。
半分ほど炊けてきたところで生姜のスライスと、
すずな=かぶ、すずしろ=大根の刻んだものを入れて炊きます。

炊き上がる少し前に、せり、 なずな=ぺんぺん草、ごぎょう= 母子草、
はこべら=はこべ、ほとけのざ=こおにたびらこの刻んだものを散らします。
わが家は、このくらいたっぷりと入れますよ。

ひと混ぜして、ひと煮立ちして、完成。とろとろにおいしそうに炊けました。
お節やお正月のご馳走で疲れた胃腸を休め、冬場に不足しがちなビタミンを補う
春の七草粥。昔からの人々の生活の知恵が行事食となります。

 追記(1/13)
追記(1/13)七草の起源を調べてみましたら、詳しく書かれたサイトがありましたので、
参考までに転載します。
「人日の節句」(じんじつのせちく)から・・。中国の古俗に、元日から六日までは鶏(にわとり)、狗(いぬ)、羊(ひつじ)、猪(いのしし)、牛(うし)、馬(うま)という家畜を占い、七日には「人」を占うというものがあり、この日を「人日」と呼びました。「人日」には七種菜羹(ななしゅさいよう、又はしちしゅさいのかん)を食して無病息災を祈念したのだそうです。
日本では、平安時代の延喜式(えんぎしき)という書物に、正月十五日の供御(くご)の粥(かゆ)、又、即位後の解斎(げさい:物忌みを解いて平常に戻る)の粥(かゆ)などが見られ、いずれも節目、節目にお粥を食して身を清めたようです。
また、平安時代の人気行事として、正月最初の子(ね)の日には郊外に出かけて若菜を摘むという、今で言うピクニックのようなものがあり、この3つの行事がごちゃまぜになって「七草かゆ」の風習が出来上がってきたようです。
以上 AJINOMOtO.メルマガ・コラムより転載

















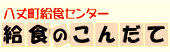







申し訳ないですw
正月ボケでどうにもロクな料理を作っておらず…
今年,季節のものはできるだけ食そうと
生まれて初めて七草粥を作って食べました。
実家では七草粥を食べる習慣がなかったのですが
あっさり,七草の風味が良くおいしかったです。
久々のTBの送らせていただきますので
よろしくお願いしますね♪
写真を撮らなかったのが悔やまれますぅ。
子供達が大人になって「それ、知ってるよ」って言える行事食、この先幾つ体験させてやれるかしら。
ちゃんと考えてある愛情料理作ってるじゃないの、大丈夫よ!
七草の風味、ほんとにおいしいよねぇ。
これぞ日本のハーブだと、ハーブカテゴリに入れました。
今年は行事食を順次UPしていくので、TB材料の目安になるかも。
近頃では家庭で行事食を作る家が少ないので、
学校給食で行事食を知る子も多いとか。
ゆなちゃんは、学給と重なっちゃうかもしれないけど、
作ったらぜひTBお願いね。
いつも学校給食と重なるのを不満に思ってたの。
子どもが同じメニューを続けて食べることになるので。
でも、その件を以前に食の掲示板で話題にしたら、
作らない家庭が多いのだから、仕方がないという意見が多かった。
季節を感じながら食事をし、その行事を話題にして子に伝えていくことは、
とても豊かな心持ちになれる。
それで、僭越ながら今年はできる限り行事食をUPして、
みなさまにも作っていただきたいと提案していくことといたしました。
ぜひ一緒に作っていきましょう♪
七草粥の写真残念です。見たかったわ。
次回ぜひよろしくね。