11分間の、いろんな人の出来事をばらばらと描いた映画らしい、くらいの情報で
でも、オムニバス的な映画好きなので、見に行ってみたら
わーお!なにこれ!このラスト数分間の衝撃といったら!
よく考えたら、ありがちなまとめ方ではあるんだけど、でもですねぇ、
ラストに至るまでの、複数の人たちの11分の描き方が
時系列やら場所や事柄も、なんかシャッフルされててスムーズじゃないので
大きな流れではなく、細切れの意識を研ぎ澄ませて観てたんですよ。
そこから突然プチンとスイッチが入って、それからはもう、ザ・怒涛!
としかいいようのないラストの収束の仕方がすごすぎ、それまでの世界と遠すぎて、
予想もしないことがどんどん起こったような、あっと息を呑み続ける数分だった。
いやはや。これはうまい。”怒涛”の終わり頃には、すっかり舌を巻いていました。
そこへ至るまでは特に暴力的な描写はなく、サスペンスフルなものもないのに、
見ている気持ちはサスペンスなんです、
どこか不穏で、むき出しではない緊張感が隠れてる。
冒頭のカメラのぶんぶん揺れる感じ(酔いそうになった)や
忙しいカット割りで何が何だかわからないし、
カメラの視点が変わっても誰の視点かわからないまま次のカットへいくし、
それ以外にも、いくつもの謎があって、なんだか難しい映画のようです。
空に見えていたものはなんなのか?
数回啓示的に出てくる言葉はなんなのか?
登場人物の背景も目的もほとんど説明されないままつぎはぎで見せられる。
そういう謎の置き方や説明のなさも塩梅がいいです。うまい感じにもやもやする。
登場人物それぞれのわずかな接点も、結局オチはなく、
ラストで強引にひと束になるのだけで、このオチのなさも、またいい。
いろいろと説明のない答えのないシーンを細かく積み上げるので、
登場人物への共感も、あまり許さない作り方です。表面的にしか描かれてないし、
何しろ人やことや場所や時間がばらばらすぎるし、
ひとつひとつのつぎはぎも、わかりやすくは撮られていない。でも、
人はわかりやすい答えがない時、意識をより尖らせ、より注意深く見るものです。
それで、なんだかよくわからないそれらを、集中してみてきた細々した全部を、
ラストの大仕掛けで、一気に、その大仕掛けに釣り合う何かにしてしまった。
78歳の監督イエジー・スコリモフスキはポーランド映画の大巨匠だそうですが、
「心から信じられる話になるか、逆に信じられない話になれば心強い。」
と言ってて、まさにそういう映画。
観終わって思ったのは、
どこかで意味なくすれ違ってるだけの11人の人たちの11分が、
最後は一つ点に収束するようなことになるわけですが、
これはむしろ、最後の出来事から逆回しに見ていったものを
編集した、というような感じがするなぁということ。
時系列を逆回しに見て行くと、もっとわかりやすく、
謎には必然があるかもしれないし、それなら説明のなさも理解できる。かも。
面白い映画でした、
最後のエンドロールの、幾つもの風景がモザイク状になり
最後はドットになっていくシーンもうまい。












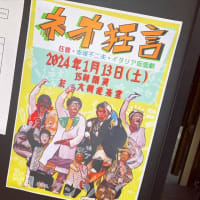





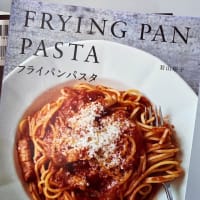

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます