1975年の第47回アカデミー賞でドキュメンタリー長編賞を受賞し、数多くのベトナム戦争映画に多大な影響を与えたドキュメンタリー。さまざまな証言や取材映像を通し、ベトナム戦争の真実に迫っていく。監督は、ジャーナリスト、ドキュメンタリー作家として幅広い活動を続けているピーター・デイヴィス。ジョンソン元大統領の政策補佐官が出演シーンの削除を求めて裁判ざたになるなど、上映妨害行為も相次いだ衝撃の内容が見どころだ。
映画に関しては、いくつかのレビューを拾ったものを下に貼り付けときます。
わたしがダラダラ説明するより正確だから。(するけど。笑)
映画で戦闘や死体は日常的に目にするレベルだけど
これはドキュメンタリーで、この中で撃たれたりして倒れて死ぬ人は
本当に、その場で死んだ人なのだと思うと、不思議な気分になってから
ショックが襲ってくる。
前に見ていた→報道写真の写真集も同様で、カメラの目の前で、
撮影している人の目の前で、その時本当に起こったことの記録なのです。
写真もショックだったけど、動画で見るとわたしには重くて重くて、
なんども嗚咽をこらえきれなくなった。何十年も前の終わった戦争の映像だけど。
「ベトナム戦争は最初で最後の自由な報道が許された戦争だった」と
この映画の中でも言われてるけど、今こういう報道は難しいだろうし
こういう自由が許される空気が、もうだんだんなくなっていってるように思う。
映画は、ベトナム戦争を声高に糾弾する姿勢はなく、
当時の大統領の映像から、名もなきベトナム人、退役軍人、アメリカ人脱走兵まで
ベトナム戦争に関係のあるたくさんの人たちの取材やニュース映像を
かなり満遍なく多角的に集めて編集してあります。
わたしは、映画として良質なドキュメンタリーというのは、
ある一方向へのプロパガンダに終始するのではなく
多面的な視点を持つことで、問題を浮き彫りにしていくものだと思いますが
この映画は、それに当てはまる優れた正統派ドキュメンタリーだと思う。
結果的には、ベトナム戦争に批判的な方向の作品になってはいるのですが、
違う方向の意見や発言も、きちんとした形で扱われています。
人間というものはそれぞれ、立場も思想も多様で、個人レベルでは、
アメリカ人にも被害者はいて、ベトナム人にも加害者はいて、
大国のエゴの犠牲になった、と一言で言いきっては漏れてしまう部分も
丁寧に拾っているように見えます。
だからといって大義や利益のために蹂躙する大国と、翻弄される小国という構図に
なにもかわりはないんだけど、
そういう割り切れない小さなひとりひとりが切ない存在で
その総体として戦争を見ると、ただ悲しいことだなぁと思う。
・ストレートな被害者であるベトナム民間人の怒りや、
家族を亡くしたベトナム人の子供の泣き崩れる姿のシーン。
・ベトナムで捕虜経験のある元軍人の帰郷パレードは華やかで、その後
いろんなところで誇らしげに講演し、小学生くらいの子どもたちに
国のため正義のため戦える人間になれ、というようなことを説くシーン。
・アジア人の命は軽い、人数が多いから一人一人の命が安いのだという
偉い人。
・戦闘機からの爆撃はすごく楽しいと無邪気に笑うパイロット
(その爆撃で大勢の民間人やその家が燃えているんだけど・・・)
・過酷な戦争体験の後遺症に悩む元軍人。
・アウトドア派のスポーツマンだったのに、足を亡くし恋人をなくしても
(あるいは失くしたからこそ?)ベトナム戦争を否定したくない元軍人。
・兵役拒否した脱走兵が、もう逃げるのは嫌だと
公聴会で自分のこの戦争に対する考えを述べるシーン。
・戦争でお金儲けをする南ベトナムのベトナム人実業家のシーン。
・そして政治家たち
本当に多種多様な人のいろいろな証言や意見を見ることができます。
見ているうちに、どの戦争も同じことだなぁと思う部分が多すぎて、
どれだけ戦争しても人も世界も何も学ばないことに絶望しそうになる。
とりあえず、これは学生たちみんなに見せるといいと思った。
YouTubeに、全編アップされてたのでここに貼っておきます。
字幕はないけど、わりと分かりやすい英語かな。2時間弱です。
ベトナムの現状を歪曲し、国民を欺き続ける政権。プロパガンダによって強化される反共主義や愛国心、東洋人に対する差別意識。精神的・肉体的に深い傷を負った帰還兵や軍を告発する脱走兵。北爆で家族を奪われた人々の嘆きと怒り。私欲に走る南ベトナムの政治家や銀行家。南ベトナム政府と米軍に農地を奪われ、サイゴンのような大都市に流れ込み、窮乏生活を余儀なくされる難民。多様な視点から戦争の実態が掘り下げられていく。
その実態はイラク戦争と重ねてみることができる。アメリカは軍事介入や侵攻の口実を得るために、ベトナムではトンキン湾事件をでっち上げ、イラクでは大量破壊兵器に関する信憑性の低い情報に飛びついた。ジエムやチャラビという亡命ベトナム人やイラク人を担ぎ、アメリカ中心の資本主義的な世界秩序を構築する足がかりにしようとした。そして、政治的な欠陥を埋めるために圧倒的な軍事力に頼り、ゲリラ戦に翻弄されることになった。
アメリカはベトナムから何を学んだのか。その答えはひとつではない。ネオコンはベトナムのトラウマがあるからこそ、アメリカが再び弱体化することを恐れ、権力を握って世界を変えようとした。ベトナムとイラクを繋げてみると、その病巣の深さが鮮明になる。(大場正明)
ちなみに世の中にはベトナム戦争が題材かまたは主人公がベトナム帰還兵という映画は198本あるらしく、その中で「ランボー者またはランボー物」と総称できるヒロイックな映画は100本以上を占めるそうです。
1975年アカデミー長編ドキュメンタリー賞受賞時に、ベトナム戦争とアメリカの良心について語り始めたプロデューサーに対してゴリゴリタカ派のフランク・シナトラが「アカデミー賞に政治を持ち込むな」と抗議したところ、「映画は真実を見つめて平和に貢献しなければならない」と反論して女を上げたシャーリー・マクレーン。
わずかな救いは戦争をしたのはアメリカだけど、取材や報道を許し、こんなドキュメンタリーが作られるのもアメリカだという事。












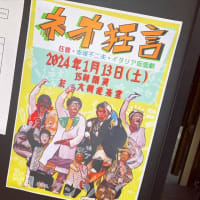





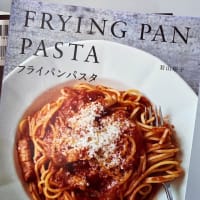

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます