西アフリカ、マリ共和国の、世界遺産芋登録された古都ティンブクトゥ近くが舞台。
ある日イスラム過激派が乗り込んできて一帯を支配するようになり、
厳格なイスラム法により、娯楽や美術、スポーツや音楽も禁止される。
厳格なイスラム法というより、支配者たちの都合とわがままにより、という感じ。
たとえば、街で見かけたある少女を、ある兵士が娶りたいと少女の親に言う。
親が拒否すると、せっかく平和的に申し込んでやったのにと
力づくで少女を連れ去り妻にしてしまう。
親の訴えで、昔からある村のイスラム寺院の指導者が、兵士たちと話し合うけど
保護者の同意がないのにと責められると、
町の支配者は自分たちだから自分たちが保護者であり
従ってこの結婚は認められていてイスラム法的に何の問題もないと言い張る。
なんでもこの調子で、自分たちの都合だけで勝手な支配をして、
銃と暴力で人々を苦しめるのです。
と、まあ、そういう映画かと思ってドキュメンタリー見るように見ていたら
そういうテーマにあまり関係の無い物語がメインになってて、
ちょっと焦点がボケると言うか意味わかんない映画になってるかもしれない。
ドキュメンタリー風の、恐怖政治の支配とそこの人々に関する描写は、
ディテールもよく映像も美しく、それだけならいい映画だったんだけどなぁ。
特に川のシーンいくつか、超望遠で俯瞰で撮ったシーン、
息をのむ美しさでした。
(以下ちょっとネタバレあります)
物語は、町外れに住む少女と、その両親、そして牛飼いの少年。
牛飼いの少年は親が兵士で殺された孤児らしいんだけど
一緒に仲良く暮らしてます。
その少年が大事にしていた牛を、川で漁をする男に殺されてしまう。
でもそれ、殺したのはやりすぎだけど、この男もなんども警告してるんです。
牛たちを自分の網のところまで来させるな、網を壊すな、近寄るなと。
あらかじめ警告されていたのに、牛が暴走して網を壊し、
怒った男に殺される。
少年が子供だから仕方ない部分はあるけど、あれだけ警告されてたのに
暴走する前に、網の近くに行かないようになんで気をつけないのか。
なんでわざわざそこに、水飲ませに行くのか、その辺わからない。
少女の父親がそれを聞いて怒り、川の男のところに銃を持っていく。
もみ合ううちに銃が暴発して川の男を殺してしまう。。。
この父親、こそシーンの前までは本当にやさしく穏やかで
娘と家族を何より愛している頼もしい素敵なお父さんなんだけど、
ここから急に行動が幼稚で馬鹿っぽくなっていくので、愛想が尽きてしまった。
むしろ川の男の方が気の毒になりました・・・。
結局父親は支配者たちのイスラム法によって裁かれるのですが、
父親と漁師の決闘という、この一連の物語は、
過激派支配による抑圧された日常、というテーマに全然関係ないですよね。
テーマの悲劇と物語の悲劇に相関がないところが、なんかちぐはぐというか
変な感じで、一体どう見ればいいのかわからない。
「人間の『赦し』とは何かを描いた壮大な叙事詩」とあるけど
叙事詩と言っていいくらいの映像美の方はあるのですが、
赦しについて何か描かれていたか、そういう映画か?とういうとノー!です。
いい加減なコピー書くなぁ、ほんとに。見てないんじゃないの?と思う。
でも、物語を忘れて、テーマ(と思われること)と映像だけを見ると、
とてもいい映画なんですけどね。
丁寧に作られているディテールはどれもいいです。
音楽を愛する人々、指導者たちの中にもある心の揺らぎや弱さ、
奔放に自分を貫き笑うカラフルな装いの狂女。
でも予告にもあるエアサッカーのシーンは、きれいだしエモーション煽るけど
ちょっとやりすぎ、嘘っぽい作り事だよなぁと思ってしまった。
サッカーが禁じられてて、ボールなしでサッカーに興じ、
兵士たちが来ると知らん顔して柔軟体操してたりするんだけど、
ボールなしのエアサッカーってありえないでしょ。複数で。
みんなに一つの同じボールが見えてないと、ゲームとして無理だから。
ただ、シーンとしてはとてもきれいで盛り上がるり感動的なので
嘘っぽさをわかってても入れちゃったんだろうなぁ。
それともあえて、なのかもしれませんね。












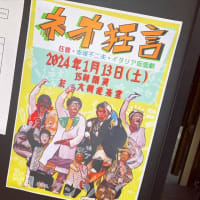





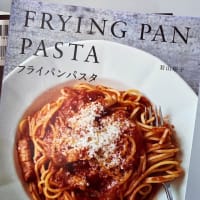

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます