地球へのラブレターと言う言葉は映画の中でも出てくるけど
本当の原題は「地の塩」(英:The Salt of The Earth/仏:Le sel de la terre)
こっちの方が好きですが、日本では馴染みがないのかもしれない、
新約聖書中のイエス・キリストの言葉ですね。
映画の中で、最初の方で、人間は結局地の塩である、というところがあって、
これは希望の感じられる言葉で、一度絶望にうちのめされたサルガドが
最後のプロジェクトでまた希望を見出したことを表しているのでしょうか。
ストーリーより、そこに写されている写真のひとつひとつの出来事に
大いに心動かされるドキュメンタリーです。
特に前半の、報道写真家時代の写真は、目を背けたくなるような
凄惨な場面がたくさん出てきます。
死体もゴロゴロ出てくる。子供も大人も男も女も。
この辺はかなりきつくて、サルガドの絶望がわかります。
そして、すでに有名だった報道写真家から
自然を撮る写真家に方向転換したわけだけど、
それを「逃げたのだ」とは誰も言わず、
新たな希望を探して、と周りも言い本人も思うところは
彼の人徳だろうか、あるいは有無を言わせない才能だろうか、
どっちにしてもポジティブだなぁと、個人的には思う。
そもそも途方もなく運のいい男だなと、わたしは思いました。
ジャングルでも戦場でも出向いてサバイバルできる屈強な身体と
強い意志と好奇心、使命感を持ち、それらを遺憾なく発揮して撮った写真は
美しく力強く静かで雄弁。
もうひとつ思ったことは、サルガドってひとりの天才写真家というより、
優れたパートナーとのユニットだな、むしろ、ということ。
彼が15歳で都会に出て出会った、一目惚れの初恋の女性が
彼の生涯のパートナーとなったのですが、
それが、生涯尊敬し、助け合い高め合い続ける相手になったなんて
やっぱり運がいいと思ってしまう。
天才はそれに見合った人と出会う、という運命的なものだと思ってしまう。
(わたしあんまり運命論者ではないんだけど。笑)
写真家になるきっかけも妻のカメラだったし、
その後安定した仕事を捨てて写真家になった時も、そのあともずっと、
ふたりで一緒にプロジェクトを考え達成してきたようです。
家族を置いての長い旅の数々も、それによって撮れた写真も、
その写真集や写真展などあらゆる企画が
彼女なしには別のものになってしまったことだろうと思う。
そういえばブラジルの、サルガドの育った、父の森を再生させたのも、
彼女の一言が発端だった。
聡明で、忍耐力、行動力があり、現実的な問題処理能力にも優れる一方
柔軟で愛情、感性豊かな素晴らしい女性なんだろうな。
サルガド自身も、ただの天才肌の芸術家ではなく
バランス感覚を持った大人の部分のある人ですが。
まあとにかく、写真が本当に素晴らしいですから
できれば、映画館で大きなスクリーンで見てください。
・・・・・・・・・・・・・・・・
以下ストーリー。ネタバレありますが、まあドキュメンタリーだし、
ストーリーを追う映画ではないけど、でも嫌な方は読まないで。笑
セバスチャン・サルガドはブラジルで15歳まで生まれ育ちます。
姉妹が7人いる中の唯一の男子だったようで、きっと大事にされたことでしょう。
家は、当時かなり余裕のある家だったようで、高校からは都会に出ます。
父親は法律家にしたかったのですが、とりあえず経済学を納めて大学を出て
エコノミストとしてパリやロンドンで働き始めます。
報道写真家としての彼の世界の問題を見る目、テーマを選ぶ力は
あまり気が進まなかった?経済学の基礎が役になったようです。
その後、カメラに夢中になり、写真家となり、世界を旅します。
世界の悲惨な現実、飢餓や病気や内紛や虐殺の現場に飛び込み
素晴らしい写真を撮りますが、エチオピアやルワンダでの
現実のあまりの悲惨さに、もう絶望しかないと感じます。
人間の歴史は戦争の歴史だ、というナレーションは
監督のヴェンダースのものだったかサルガドのものだったか
覚えていないけど、そういう気持ちになるでしょうね。
そこで、サルガドが新たにスタートさせたプロジェクトが「ジェネシス」
これがタイトルにもなっている地球へのラブレター的な写真たちです。
地球に残されている森や砂漠や氷原や、そこの動物達、少数民族たち。
一方では、干ばつですっかり荒地になった父親の広大な土地に
200万本もの木を植え森を再び生き返らせます。
そうして自然の偉大さに触れることで、希望を取り戻していく、
と、そういう感じのドキュメンタリー。












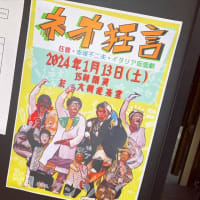





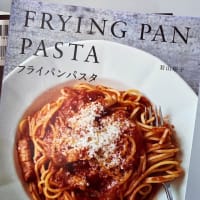

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます