A.能・狂言という世界
今年になってから、なぜか「能」というものに興味が湧いて、いくつかDVDになっている能楽を見ている。きっかけは小泉文夫氏の『日本の音』で解決されていた能・狂言の音楽的側面を、日本の伝統芸能の一ジャンルとして考察するという問題だった。ぼくはこれまで、西洋音楽そして西洋近代のアート全般について自分なりにいろいろ考えて文章も書いてきたのだが、今まで抜け落ちていたのが、日本の芸能・アートのことだった。西洋近代とはまったく異なる文化的伝統から受け継がれた音楽、美術、建築、芸能。とくに中世に世阿弥によって完成された能というユニークな芸は、音楽的要素、演劇的要素、舞踊的要素、そして文学的要素が融合し結晶した能は、狂言とも相まってその後も長く武家の式楽として上演されてきた。
能については、30年ほど前に一度見てみようと思って、千駄ヶ谷の国立能楽堂で見たのだが、途中で寝てしまって、その演目が何であったかも覚えていない。そんないい加減な経験しかないので、基本的に知らないことが多い。そこで、勉強を兼ねてなにか基本テキストを読もうと思ったのだが、いわゆる能のテキストとしての謡曲集をいきなり読んでも、能がどういうものかはわからない。そこで、世阿弥直伝の26世観世流宗家の観世清和氏の解説と、武道家で思想家としても知られる内田樹氏の共著『能はこんなに面白い!』小学館2013年、が読みやすそうなので読んでみる。内田氏は、能や謡の稽古を17年やっているということは知らなかったが、能楽の世界を外から眺める視点がおもしろそうである。入門編としてはこれがいいだろう。
まずは、第一話 能から見た日本の原点(観世清和氏執筆)から。
「能の源流を辿りますと、大きく二つのものがあります。一つは、奈良時代にさかのぼる「散楽(さんがく)」と呼ばれるものです。これはその当時大陸から渡ってきた芸能で、歌謡や物真似、曲芸など、さまざまなものを含んでいました。やがて日本に定着して「猿楽(さるがく)」と呼ばれるようになり、専門の一座もいくつか誕生しました。奈良・大和地方には、「結崎(ゆうざき)座」など四座があったといわれ、観阿弥はこの結崎座に所属していました。これらは総称して「大和猿楽」と呼ばれています。
他方、農村の素朴な芸能から発展した「田楽」やお寺の密教的な行法から生まれた「呪師芸(しゅしげい)」なども盛んに行われ、互いに交流・影響しあっていたようです。
こうした猿楽や田楽の諸座が芸を競う中、南北朝の時代に、先ほどご紹介した大和猿楽の結崎座に名手、観阿弥が登場しました。観阿弥は、物真似芸委が主体であった猿楽に、田楽や当時「曲舞」とよばれていた歌舞的な趣向の強いものを大胆に取り入れて改革し、さらにそれを息子世阿弥が受け継ぎ、手を加えて、今日の能楽をつくりあげていったのです。
世阿弥は、わずか十二歳であった時に十七歳の将軍、足利義満の目に止まり、その寵愛を受けることになりました。それを頼もしい後ろ盾として、能を優美な舞台芸術として確立してゆきます。その完成が今から約六百年ほど前のことです。以来能は、一度も途切れることなく、徳川幕府のときには「式楽」、つまり公式の舞楽として庇護を受け、また明治以降は、日本の最も古い伝統芸能の一つとして多くの人々の支持のもとに受け継がれてきました。
シテ方には、観世、宝生、金春、金剛、喜多の五流があり、各流儀の能楽堂や国立能楽堂、全国の能舞台やホールを会場に、公演を続け、多くのお客さまにご覧いただいております。
能舞台
舞台にはまず主役である「シテ」がおります。そして、そのシテと語りあいをしながら、時に舞台の進行役となる「ワキ」がおります。さらに笛、小鼓、大鼓、時には太鼓も加わる囃子方、総勢八名で構成される地謡がおります。
これですべてと申し上げたいところですが、実は舞台上にはもう二人、「後見」と呼ばれる者が、舞台向かって左奥に控えております。じっと座って、時折シテのそばに進み、装束の乱れを直したり、あるいは舞いの中でシテが手から放した小道具を、邪魔にならないように片付けたり、ごく稀ではありますが、演者が謡の詞章を忘れて絶句するようなことがあれば、即座に小声で助け船を出して、シテを支えるといったこともいたします。
こうした動きを見ていると、後見は黒子であり、“縁の下の力持ち”のような存在に見えます。しかし、そしてそのような補佐役ではありません。
実はその日、その舞台で行われることのすべてに責任をもち、その一曲を無事終わらせることを任務とし、そうかんとくをつとめるのが、この後見なのです。
したがって、もしシテが舞台上で倒れるといった万一のことがあれば、後見は即座に立ちあがって、中断したところから後を引き継ぎ、平然とシテの代役を務めて無事一曲を終わらせるということもいたします。つまり貢献は、シテと同等、あるいはそれ以上の力を備えている存在です。貢献には、何事にも動ずることのない、心の準備と判断力、上演中の一曲を中途からでも引き継ぎ、舞い納める高い技量が求められています。
おそらくあらゆる演劇において、主役が倒れるという不慮の事態への対応は、舞台袖に控えたプロデューサーが、緞帳を降ろせと指示することではないでしょうか。そしてその日の舞台はそこで中止となるでしょう。またそのことに、客席から疑問の声が上がることもないと思います。
ところが、能だけはどんな場合にも舞台を中断させないために、高い技量を持ったものを舞台上に控えさせるのです。実際には、シテが急病で倒れるなどということは、まずありません。ですから、代役としての出番は、実際にはほとんどないといってもいいと思います。そして装束の乱れを直す程度のことなら、こなせる者はいくらでもおります。しかし、能は約束として貢献を必ず置きます。いったん始まった能に、中止があってはならない。その覚悟と備えを持った演劇が能なのです。
日本の演劇に、あるいは世界の演劇に、このような用意をしているものがあるでしょうか?寡聞にして私は知りません。
ではなぜ、能だけがそのような用意をするのか。
内田樹先生は、このことについて「能が演じられている舞台には霊が降りて来ているからではないか」また「能には人を供養する要素がある」という趣旨のことをおっしゃっています。
私もそのように思います。もともと能は、神を招き、神にみていただく素朴な舞いが、その源流の一つとなっています。後には、現世に未練を残し、成仏できずにいる死者の霊を慰めるものとしても曲作りが行われ、演じられました。神や霊の存在が能舞台を色濃く覆っていることは間違いないのです。だからこそ能は、いったん始められた以上、必ず舞い納めなければなりません。途中でやめてしまったら、そこで始まった神や霊との対話は中断し、失われてしまうからです。こうした決意を明確に示したものこそ、後見の存在ではないでしょうか。能は、大変神に近いところで、もちろん神といっても、西洋でいう一神教の、いわゆるゴッドではありませんが、この地上に遍在する神々や霊と共にある。それが大きな特徴の一つなのではないかと思います。
このことは、能舞台の変遷を見ても明らかです。
今皆さんがお出かけになる能楽堂は、建物の中にすっぽりと能舞台が収まっております。今ではこの形が当たり前ですが、しかし、このようになりましたのは、明治時代の半ば頃のことで、能楽の七百年近い歴史からみれば、比較的最近のことに過ぎません。それまで能舞台は屋外にありました。今も京都・西本願寺の北能舞台や南能舞台、宮島・厳島神社の能舞台など、屋外の能舞台が残っています。
このうち国宝にもなっております北能舞台は、天正九年、1581年以前に建立されたことが当時の記録からわかります。今から四百三十年以上も前のもので、現存する能舞台として最古のものです。因みに1581年といえば、翌年に本能寺の変があり、織田信長が明智光秀に追いつめられて自害した年であり、羽柴秀吉がいわゆる「中国大返し」で大軍を京都に上らせ、光秀を討った年でもありました。まさに騒然とした戦国の世でした。その頃の建立ということになります。
それはともかく、歴史をさらにさかのぼれば、この屋外の舞台も、ごく初期のものは、ただ土を盛っただけであったり、床を組み、そこに屋根を葺いただけの簡素なものであったと思われます。実際その例は奈良・春日大社の舞台や同じく奈良・丹生神社の舞台に残っております。そしてそのいずれもが、観客席を持たず、神殿に向かって設けられているのです。つまり、その発生においては、観客は存在せず、演者はただ神様に向かって演じていました。能は、その初期において、まだそれを能とは呼んではいなかったと思いますが、人に見せるためのものではなく、神に捧げるものでした。それが初期の舞台から見て取ることができます。
それは『翁』から始まった
少し歴史を振り返りますと、六世紀に聖徳太子が「申楽(さるがく)舞(まい)」をつくり秦河勝(はたのかわかつ)に教え、十世紀半ばに秦元安と村上天皇が中興の祖となり天下泰平のご祈禱に用いた。これが「式三番」の元であるという記述が、世阿弥の『風姿花伝』の中にあります。
ここで語る『式三番』とは、現在も舞われている『翁』のことです。同じではありませんが、現在の原型というべき曲で、そのエッセンスは受け継がれています。『翁』は能の原型を伝え、能がいかに神の世界に近い存在であるかを証明するものの一つといえるのではないでしょうか。
今も『翁』は、年の初めや祝賀の能などで演じられ、一般の能とは区別されていますが、能の原点を示す貴重な演目であると思います。『翁』は、能の他の曲目とは大きく趣を異にしています。それは神事という性格を強くもち、天下泰平・五穀豊穣を祈る儀式に近いものだからです。現在『式三番』とも呼ばれており、翁、千歳(せんざい)、三番叟(さんばそう)(三)の三役が舞台に立ちます。
『翁』には、通常の演目とは異なる決まりごとが数多くあります。例えば、主役である翁は、公演の数日前から「水垢離」と呼ばれる精進潔斎を行います。近年は少し簡略化される傾向にありますが、今も行っています。また、舞台当日の朝は「別火(べつか)」といって、家族が煮炊きするのとは別の火を用いた食事をとります。さらに楽屋には、翁面を飾った「翁飾り」と呼ばれる祭壇が設けられ、出演者全員がその前で車座になり、洗米(せんまい)、塩、お神酒(みき)を口に含みます。その後、後見が打つ切り火に送られて舞台に進み出る約束になっています。
舞台上の所作や進行も『翁』は独特です。翁を勤めるシテは素顔で登場し、舞台上で面(おもて)を掛け、舞いが終わると、その場で面を外して退場します。その面は「白式尉(はくしきじょう)」「肉式尉(にくしきじょう)」と呼ばれ、後に三番叟が用いるものは「黒式尉(こくしきじょう)」と呼びますが、これらの面はいずれも顎の部分が切り離され紐で結ばれたいわゆる「切り顎」と呼ばれるもので、雅楽の面などにはありますが、能面では、他に例がありません。
やがて千歳が露払いとして舞い、その間に面を掛けた翁が、後を受けて天下泰平を祈って荘重に舞い、舞い終えると千歳を引き連れて退場。その後、三番叟が「揉之段」「鈴之段」と呼ばれる二つの舞を待って終わります
おそらく、面を掛けることで翁には神の霊が降臨し、翁自身が神となって、天下泰平を祈るのでしょう。
元々は六十六番もの演目を持っていたというこの翁芸が、大きな源流となり、呪術的で儀礼的だったものにさらにさまざまなエンターテインメント要素が加わり、田楽や曲舞のエッセンスも取り込まれ肥大化していく中で、呪術的なものから少しずつ離れ、観客に見せて楽しむ興行としての能が生まれたと、大きくいえるのではないかと思います。
その歩みを定かに示す資料などはないのですが、私はその歩みを促した背景として、二つのきっかけがあったのではないかと思っています。それらは端的に言えば、仏教徒の出会いです。もし、猿楽が仏教と出会わなければ、それはそのまま当初の神事の舞いであり、それから派生した曲芸や物真似芸、あるいは滑稽な寸劇といったものにとどまったかもしれません。」観世清和・内田樹『能はこんなに面白い!』小学館、2013年。pp.22-33.
能はやはり舞台で見なければなにも感じないしわからないと思うので、今度能楽堂に行くことにした。これを読みながら、能の奥深さを体験してみよう。
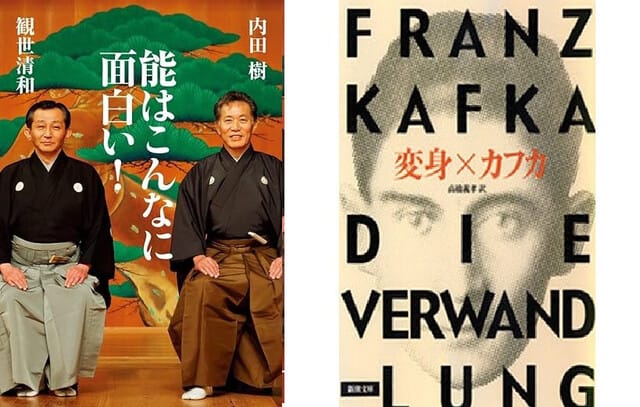
B.カフカ没後100年
フランツ・カフカ(Franz Kafka、チェコ語: František Kafka、1883年7月3日 - 1924年6月3日)は、現在のチェコ出身の小説家。プラハのユダヤ人の家庭に生まれ、法律を学んだのち保険局に勤めながら作品を執筆した。どこかユーモラスな孤独感と不安の横溢する、夢の世界を想起させるような独特の小説作品を残した。その著作は数編の長編小説と多数の短編、日記および恋人などに宛てた膨大な量の手紙からなり、純粋な創作はその少なからぬ点数が未完であることで知られている。生前は『変身』など数冊の著書がごく限られた範囲で知られるのみだったが、死後中絶された長編『審判』『城』『失踪者』を始めとする遺稿が友人マックス・ブロートによって発表されて再発見・再評価をうけ、特に実存主義的見地から注目されたことによって世界的なブームとなった。その後もドゥルーズ=ガタリの著作などにもカフカに関する物があるなど、現代思想においても影響がある。現在ではジェイムズ・ジョイス、マルセル・プルーストと並び20世紀の文学を代表する作家と見なされている。(以上、Wikipediaより)
「大波小波:理由を説明しないのだ。朝起きたら虫に変っていた布地の販売員、いつまでも目的の城に辿り着けない測量士、ある日いきなり逮捕された銀行員。因果関係が不明のまま作品は読者に委ねられる。
フランツ・カフカ没後100年だ。彼は法学博士で堅い職場に勤めながら小説を書き、40歳で亡くなった。生前に出版されたのは『変身』のほかわずか数点。残された原稿は焼却を依頼された友人が出版した。カフカ文学の特徴は不条理と不安でカミュ、ベケットと並び実存主義文学といわれた。彼らの作品の登場人物に起きる事象には理由がなく不安をよぶ。だが条理をわかりやすく説くのが文学ではない。そもそも人間の生は不確定であり、不条理な局面に立ち会うこともある。
日本でも安部公房をはじめ、実存主義文学の勢いがあったが最近は影を潜める。だが商業誌が検証すべきこのテーマに一石を投じたのが『江古田文学』(江古田文学会)。特集として「日本実存主義文学」を編んだ。日大の学生たちに読むきっかけづくりの心意気やよし。
一方今の政治。理(ことわり)に合わないことばかり。説明もせず原因も究明しない。まさか政治家の手本はカフカではあるまい。 (K)」東京新聞2024年3月4日夕刊5面。
『変身』を読んだのは高校生の頃だったと思う。不思議な小説だと思った。そして『城』。映画になり芝居にもなったので見た。やはりユニークな文学だと思った。こういうものを人知れず書く人が、日常生活ではごく真面目な官吏として勤務していたということも、強く印象に残った。ベルリンの壁が壊れた翌年、プラハに行ったとき、なるほどこれがカフカの生きた町かと感慨が沸いた。
今年になってから、なぜか「能」というものに興味が湧いて、いくつかDVDになっている能楽を見ている。きっかけは小泉文夫氏の『日本の音』で解決されていた能・狂言の音楽的側面を、日本の伝統芸能の一ジャンルとして考察するという問題だった。ぼくはこれまで、西洋音楽そして西洋近代のアート全般について自分なりにいろいろ考えて文章も書いてきたのだが、今まで抜け落ちていたのが、日本の芸能・アートのことだった。西洋近代とはまったく異なる文化的伝統から受け継がれた音楽、美術、建築、芸能。とくに中世に世阿弥によって完成された能というユニークな芸は、音楽的要素、演劇的要素、舞踊的要素、そして文学的要素が融合し結晶した能は、狂言とも相まってその後も長く武家の式楽として上演されてきた。
能については、30年ほど前に一度見てみようと思って、千駄ヶ谷の国立能楽堂で見たのだが、途中で寝てしまって、その演目が何であったかも覚えていない。そんないい加減な経験しかないので、基本的に知らないことが多い。そこで、勉強を兼ねてなにか基本テキストを読もうと思ったのだが、いわゆる能のテキストとしての謡曲集をいきなり読んでも、能がどういうものかはわからない。そこで、世阿弥直伝の26世観世流宗家の観世清和氏の解説と、武道家で思想家としても知られる内田樹氏の共著『能はこんなに面白い!』小学館2013年、が読みやすそうなので読んでみる。内田氏は、能や謡の稽古を17年やっているということは知らなかったが、能楽の世界を外から眺める視点がおもしろそうである。入門編としてはこれがいいだろう。
まずは、第一話 能から見た日本の原点(観世清和氏執筆)から。
「能の源流を辿りますと、大きく二つのものがあります。一つは、奈良時代にさかのぼる「散楽(さんがく)」と呼ばれるものです。これはその当時大陸から渡ってきた芸能で、歌謡や物真似、曲芸など、さまざまなものを含んでいました。やがて日本に定着して「猿楽(さるがく)」と呼ばれるようになり、専門の一座もいくつか誕生しました。奈良・大和地方には、「結崎(ゆうざき)座」など四座があったといわれ、観阿弥はこの結崎座に所属していました。これらは総称して「大和猿楽」と呼ばれています。
他方、農村の素朴な芸能から発展した「田楽」やお寺の密教的な行法から生まれた「呪師芸(しゅしげい)」なども盛んに行われ、互いに交流・影響しあっていたようです。
こうした猿楽や田楽の諸座が芸を競う中、南北朝の時代に、先ほどご紹介した大和猿楽の結崎座に名手、観阿弥が登場しました。観阿弥は、物真似芸委が主体であった猿楽に、田楽や当時「曲舞」とよばれていた歌舞的な趣向の強いものを大胆に取り入れて改革し、さらにそれを息子世阿弥が受け継ぎ、手を加えて、今日の能楽をつくりあげていったのです。
世阿弥は、わずか十二歳であった時に十七歳の将軍、足利義満の目に止まり、その寵愛を受けることになりました。それを頼もしい後ろ盾として、能を優美な舞台芸術として確立してゆきます。その完成が今から約六百年ほど前のことです。以来能は、一度も途切れることなく、徳川幕府のときには「式楽」、つまり公式の舞楽として庇護を受け、また明治以降は、日本の最も古い伝統芸能の一つとして多くの人々の支持のもとに受け継がれてきました。
シテ方には、観世、宝生、金春、金剛、喜多の五流があり、各流儀の能楽堂や国立能楽堂、全国の能舞台やホールを会場に、公演を続け、多くのお客さまにご覧いただいております。
能舞台
舞台にはまず主役である「シテ」がおります。そして、そのシテと語りあいをしながら、時に舞台の進行役となる「ワキ」がおります。さらに笛、小鼓、大鼓、時には太鼓も加わる囃子方、総勢八名で構成される地謡がおります。
これですべてと申し上げたいところですが、実は舞台上にはもう二人、「後見」と呼ばれる者が、舞台向かって左奥に控えております。じっと座って、時折シテのそばに進み、装束の乱れを直したり、あるいは舞いの中でシテが手から放した小道具を、邪魔にならないように片付けたり、ごく稀ではありますが、演者が謡の詞章を忘れて絶句するようなことがあれば、即座に小声で助け船を出して、シテを支えるといったこともいたします。
こうした動きを見ていると、後見は黒子であり、“縁の下の力持ち”のような存在に見えます。しかし、そしてそのような補佐役ではありません。
実はその日、その舞台で行われることのすべてに責任をもち、その一曲を無事終わらせることを任務とし、そうかんとくをつとめるのが、この後見なのです。
したがって、もしシテが舞台上で倒れるといった万一のことがあれば、後見は即座に立ちあがって、中断したところから後を引き継ぎ、平然とシテの代役を務めて無事一曲を終わらせるということもいたします。つまり貢献は、シテと同等、あるいはそれ以上の力を備えている存在です。貢献には、何事にも動ずることのない、心の準備と判断力、上演中の一曲を中途からでも引き継ぎ、舞い納める高い技量が求められています。
おそらくあらゆる演劇において、主役が倒れるという不慮の事態への対応は、舞台袖に控えたプロデューサーが、緞帳を降ろせと指示することではないでしょうか。そしてその日の舞台はそこで中止となるでしょう。またそのことに、客席から疑問の声が上がることもないと思います。
ところが、能だけはどんな場合にも舞台を中断させないために、高い技量を持ったものを舞台上に控えさせるのです。実際には、シテが急病で倒れるなどということは、まずありません。ですから、代役としての出番は、実際にはほとんどないといってもいいと思います。そして装束の乱れを直す程度のことなら、こなせる者はいくらでもおります。しかし、能は約束として貢献を必ず置きます。いったん始まった能に、中止があってはならない。その覚悟と備えを持った演劇が能なのです。
日本の演劇に、あるいは世界の演劇に、このような用意をしているものがあるでしょうか?寡聞にして私は知りません。
ではなぜ、能だけがそのような用意をするのか。
内田樹先生は、このことについて「能が演じられている舞台には霊が降りて来ているからではないか」また「能には人を供養する要素がある」という趣旨のことをおっしゃっています。
私もそのように思います。もともと能は、神を招き、神にみていただく素朴な舞いが、その源流の一つとなっています。後には、現世に未練を残し、成仏できずにいる死者の霊を慰めるものとしても曲作りが行われ、演じられました。神や霊の存在が能舞台を色濃く覆っていることは間違いないのです。だからこそ能は、いったん始められた以上、必ず舞い納めなければなりません。途中でやめてしまったら、そこで始まった神や霊との対話は中断し、失われてしまうからです。こうした決意を明確に示したものこそ、後見の存在ではないでしょうか。能は、大変神に近いところで、もちろん神といっても、西洋でいう一神教の、いわゆるゴッドではありませんが、この地上に遍在する神々や霊と共にある。それが大きな特徴の一つなのではないかと思います。
このことは、能舞台の変遷を見ても明らかです。
今皆さんがお出かけになる能楽堂は、建物の中にすっぽりと能舞台が収まっております。今ではこの形が当たり前ですが、しかし、このようになりましたのは、明治時代の半ば頃のことで、能楽の七百年近い歴史からみれば、比較的最近のことに過ぎません。それまで能舞台は屋外にありました。今も京都・西本願寺の北能舞台や南能舞台、宮島・厳島神社の能舞台など、屋外の能舞台が残っています。
このうち国宝にもなっております北能舞台は、天正九年、1581年以前に建立されたことが当時の記録からわかります。今から四百三十年以上も前のもので、現存する能舞台として最古のものです。因みに1581年といえば、翌年に本能寺の変があり、織田信長が明智光秀に追いつめられて自害した年であり、羽柴秀吉がいわゆる「中国大返し」で大軍を京都に上らせ、光秀を討った年でもありました。まさに騒然とした戦国の世でした。その頃の建立ということになります。
それはともかく、歴史をさらにさかのぼれば、この屋外の舞台も、ごく初期のものは、ただ土を盛っただけであったり、床を組み、そこに屋根を葺いただけの簡素なものであったと思われます。実際その例は奈良・春日大社の舞台や同じく奈良・丹生神社の舞台に残っております。そしてそのいずれもが、観客席を持たず、神殿に向かって設けられているのです。つまり、その発生においては、観客は存在せず、演者はただ神様に向かって演じていました。能は、その初期において、まだそれを能とは呼んではいなかったと思いますが、人に見せるためのものではなく、神に捧げるものでした。それが初期の舞台から見て取ることができます。
それは『翁』から始まった
少し歴史を振り返りますと、六世紀に聖徳太子が「申楽(さるがく)舞(まい)」をつくり秦河勝(はたのかわかつ)に教え、十世紀半ばに秦元安と村上天皇が中興の祖となり天下泰平のご祈禱に用いた。これが「式三番」の元であるという記述が、世阿弥の『風姿花伝』の中にあります。
ここで語る『式三番』とは、現在も舞われている『翁』のことです。同じではありませんが、現在の原型というべき曲で、そのエッセンスは受け継がれています。『翁』は能の原型を伝え、能がいかに神の世界に近い存在であるかを証明するものの一つといえるのではないでしょうか。
今も『翁』は、年の初めや祝賀の能などで演じられ、一般の能とは区別されていますが、能の原点を示す貴重な演目であると思います。『翁』は、能の他の曲目とは大きく趣を異にしています。それは神事という性格を強くもち、天下泰平・五穀豊穣を祈る儀式に近いものだからです。現在『式三番』とも呼ばれており、翁、千歳(せんざい)、三番叟(さんばそう)(三)の三役が舞台に立ちます。
『翁』には、通常の演目とは異なる決まりごとが数多くあります。例えば、主役である翁は、公演の数日前から「水垢離」と呼ばれる精進潔斎を行います。近年は少し簡略化される傾向にありますが、今も行っています。また、舞台当日の朝は「別火(べつか)」といって、家族が煮炊きするのとは別の火を用いた食事をとります。さらに楽屋には、翁面を飾った「翁飾り」と呼ばれる祭壇が設けられ、出演者全員がその前で車座になり、洗米(せんまい)、塩、お神酒(みき)を口に含みます。その後、後見が打つ切り火に送られて舞台に進み出る約束になっています。
舞台上の所作や進行も『翁』は独特です。翁を勤めるシテは素顔で登場し、舞台上で面(おもて)を掛け、舞いが終わると、その場で面を外して退場します。その面は「白式尉(はくしきじょう)」「肉式尉(にくしきじょう)」と呼ばれ、後に三番叟が用いるものは「黒式尉(こくしきじょう)」と呼びますが、これらの面はいずれも顎の部分が切り離され紐で結ばれたいわゆる「切り顎」と呼ばれるもので、雅楽の面などにはありますが、能面では、他に例がありません。
やがて千歳が露払いとして舞い、その間に面を掛けた翁が、後を受けて天下泰平を祈って荘重に舞い、舞い終えると千歳を引き連れて退場。その後、三番叟が「揉之段」「鈴之段」と呼ばれる二つの舞を待って終わります
おそらく、面を掛けることで翁には神の霊が降臨し、翁自身が神となって、天下泰平を祈るのでしょう。
元々は六十六番もの演目を持っていたというこの翁芸が、大きな源流となり、呪術的で儀礼的だったものにさらにさまざまなエンターテインメント要素が加わり、田楽や曲舞のエッセンスも取り込まれ肥大化していく中で、呪術的なものから少しずつ離れ、観客に見せて楽しむ興行としての能が生まれたと、大きくいえるのではないかと思います。
その歩みを定かに示す資料などはないのですが、私はその歩みを促した背景として、二つのきっかけがあったのではないかと思っています。それらは端的に言えば、仏教徒の出会いです。もし、猿楽が仏教と出会わなければ、それはそのまま当初の神事の舞いであり、それから派生した曲芸や物真似芸、あるいは滑稽な寸劇といったものにとどまったかもしれません。」観世清和・内田樹『能はこんなに面白い!』小学館、2013年。pp.22-33.
能はやはり舞台で見なければなにも感じないしわからないと思うので、今度能楽堂に行くことにした。これを読みながら、能の奥深さを体験してみよう。
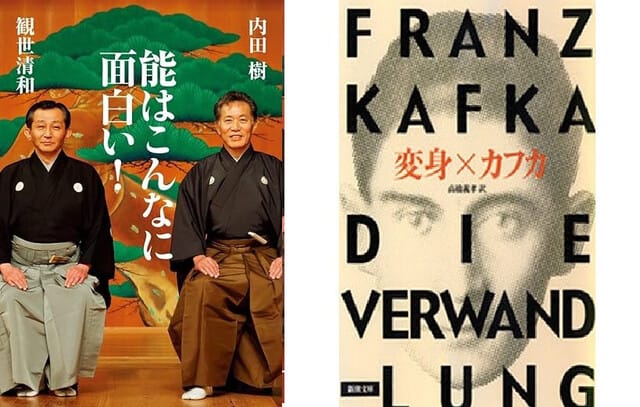
B.カフカ没後100年
フランツ・カフカ(Franz Kafka、チェコ語: František Kafka、1883年7月3日 - 1924年6月3日)は、現在のチェコ出身の小説家。プラハのユダヤ人の家庭に生まれ、法律を学んだのち保険局に勤めながら作品を執筆した。どこかユーモラスな孤独感と不安の横溢する、夢の世界を想起させるような独特の小説作品を残した。その著作は数編の長編小説と多数の短編、日記および恋人などに宛てた膨大な量の手紙からなり、純粋な創作はその少なからぬ点数が未完であることで知られている。生前は『変身』など数冊の著書がごく限られた範囲で知られるのみだったが、死後中絶された長編『審判』『城』『失踪者』を始めとする遺稿が友人マックス・ブロートによって発表されて再発見・再評価をうけ、特に実存主義的見地から注目されたことによって世界的なブームとなった。その後もドゥルーズ=ガタリの著作などにもカフカに関する物があるなど、現代思想においても影響がある。現在ではジェイムズ・ジョイス、マルセル・プルーストと並び20世紀の文学を代表する作家と見なされている。(以上、Wikipediaより)
「大波小波:理由を説明しないのだ。朝起きたら虫に変っていた布地の販売員、いつまでも目的の城に辿り着けない測量士、ある日いきなり逮捕された銀行員。因果関係が不明のまま作品は読者に委ねられる。
フランツ・カフカ没後100年だ。彼は法学博士で堅い職場に勤めながら小説を書き、40歳で亡くなった。生前に出版されたのは『変身』のほかわずか数点。残された原稿は焼却を依頼された友人が出版した。カフカ文学の特徴は不条理と不安でカミュ、ベケットと並び実存主義文学といわれた。彼らの作品の登場人物に起きる事象には理由がなく不安をよぶ。だが条理をわかりやすく説くのが文学ではない。そもそも人間の生は不確定であり、不条理な局面に立ち会うこともある。
日本でも安部公房をはじめ、実存主義文学の勢いがあったが最近は影を潜める。だが商業誌が検証すべきこのテーマに一石を投じたのが『江古田文学』(江古田文学会)。特集として「日本実存主義文学」を編んだ。日大の学生たちに読むきっかけづくりの心意気やよし。
一方今の政治。理(ことわり)に合わないことばかり。説明もせず原因も究明しない。まさか政治家の手本はカフカではあるまい。 (K)」東京新聞2024年3月4日夕刊5面。
『変身』を読んだのは高校生の頃だったと思う。不思議な小説だと思った。そして『城』。映画になり芝居にもなったので見た。やはりユニークな文学だと思った。こういうものを人知れず書く人が、日常生活ではごく真面目な官吏として勤務していたということも、強く印象に残った。ベルリンの壁が壊れた翌年、プラハに行ったとき、なるほどこれがカフカの生きた町かと感慨が沸いた。















