3時間内に安否確認半数だけ 震災直後それでも携帯通話86%
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2012041102000232.html
昨年の東日本大震災発生後、首都圏に住む家族や職場に安否確認をした人は81%に上り、三時間以内に連絡がついた人は半数程度にとどまっていたことが、警視庁の警備心理学研究会のアンケートで分かった。安否確認の方法は携帯電話を使った通話が86%(複数回答)と圧倒的に多く、災害時につながりにくくなる携帯電話に頼る傾向が浮き彫りになった。
安否確認の方法では、携帯電話の通話に次いで、携帯やパソコンのメールが47%、自宅の電話が33%、公衆電話が9%だった。携帯で利用できる災害用伝言板は5%、災害用伝言ダイヤル(171)は2・5%にとどまった。ツイッターを活用した人は3%だった。
(サイトから引用)
--
こうした災害の実態を想定した上での連絡手段確保が望まれますね。
わが家の場合は伝言板でしょう。
ただ伝言板の場合、相手の携帯電話番号を知らないと、確認できないのです。
ふだんメールばかりしている聴覚障害者、相手の電話番号は知らないことが多いので、ちょっと意外な落とし穴かもしれません。今後は相手の携帯端末の電話番号も教えてもらいましょう。直接メールもできますし。(小川)
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2012041102000232.html
昨年の東日本大震災発生後、首都圏に住む家族や職場に安否確認をした人は81%に上り、三時間以内に連絡がついた人は半数程度にとどまっていたことが、警視庁の警備心理学研究会のアンケートで分かった。安否確認の方法は携帯電話を使った通話が86%(複数回答)と圧倒的に多く、災害時につながりにくくなる携帯電話に頼る傾向が浮き彫りになった。
安否確認の方法では、携帯電話の通話に次いで、携帯やパソコンのメールが47%、自宅の電話が33%、公衆電話が9%だった。携帯で利用できる災害用伝言板は5%、災害用伝言ダイヤル(171)は2・5%にとどまった。ツイッターを活用した人は3%だった。
(サイトから引用)
--
こうした災害の実態を想定した上での連絡手段確保が望まれますね。
わが家の場合は伝言板でしょう。
ただ伝言板の場合、相手の携帯電話番号を知らないと、確認できないのです。
ふだんメールばかりしている聴覚障害者、相手の電話番号は知らないことが多いので、ちょっと意外な落とし穴かもしれません。今後は相手の携帯端末の電話番号も教えてもらいましょう。直接メールもできますし。(小川)











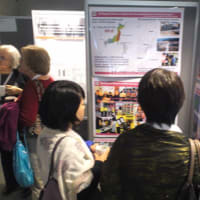
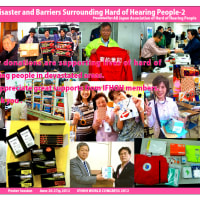
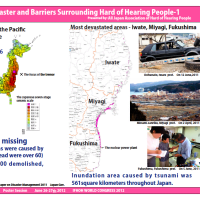






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます