■■何でもできる「平均的優等生」をめざすか、それとも一点突破の突出をめざすか■■
前にもこのブログで書いたことだが、
小学校で初等の英語教育を施せば、日本人がコミュニケイション手段としての英語を使いこなすレヴェルに達することができる…というような安易な発想。
これまで中学・高校、そして大学の10年間で英語を学んできても、英語を使いこなせない(と自ら思い込んでいる)日本人がどれほど多いか…と、エリート文部官僚が悩んで、行き当たりばったりに出した方針=制度が、それなんだろう、と私は思う。
しかし、私見では、日本人が――失敗=恥を恐れず、堂々と――外国語でコミュニケイションを取ることに挑戦しない心理障壁となっている最大の原因は、まさに「平均的優等生」を大量生産してきた学校教育にある。
学校=「学びの場」としてのスクールは、まさに失敗を許される場であって、子どもや若年層が失敗を恐れず試行錯誤し、狭い自分を表現しぶつけ合う場(相手と品位の尊重の上に)でなければならない。
にもかかわらず、目先の成績評価の物差しに怯え、周囲や教師などの目を恐れて、「優等生の虚像」であろうと振る舞いたがる人間をつくり出してきたのが、日本の学校ではないか。「上から目線」をどこまで除去できるかが、学びの場の優劣の尺度ではなかろうか。
ところが、学校は、上下秩序(権威への服従)のインプリントの場となっている。
学舎と集団馴致との混同は、19世紀の骨董だと思う。
思考力や学問的能力の向上のためには、上下秩序はむしろ邪魔である。というのも、思考や学問は、古い知識の権威や価値観の批判と破壊(部品としての取り込み・受容)である場合が多いから。
学校の本分は、失敗が恥(汚点=マイナス評価)となるような環境を排除して、自分さがしの試行錯誤となることだ。
譬えでいえば、全体的に丸いボールのような平均的優等生をつくるよりも、コンペイトウのように突出した部分とへこんだ部分がある個性人をつくるのか、という選択肢の前に立っているのだ。
前置きはこのくらいにして、本題に入ろう。
■言葉の原点から学ぶ■
私たちは、日常生活や学びの場でアルファベットを使わないことで、教育=学習のチャンスをかなりの程度失っている。
このハンディキャップをカヴァーするために、科目の多くの用語(専門用語)を学ぶときには、ギリシア語・ラテン語(グレコ=ローマン教養と呼ぶ)を基礎とするヨーロッパ語教養を、興味のある子たちには手引きすべきだ。
たとえば、生物史で人類への進化の歩みのなかで〈ピテカントゥロプス〉という生物(言葉)を学ぶとする。
〈pithecanthropus〉のことだ。なかなか覚えにくいカタカナ語だ。
ここで、グレコ=ローマン教養を使うのだ。以下では、できる限りカタカナ表現を使うことにする。
〈ピテカントゥロプス〉は、2つの用語の合成からなる。〈ピテクス〉+〈アントゥロプス〉ということだ。
〈ピテクス〉は「猿」、〈アントゥロプス〉は「人間・人類」という意味だ。してみると、この合成語は「猿人(類)」という意味をつくることになる。ひらがなで表現すれば、「さるにんげん」なのである。
グレコ=ローマン教養がある欧米人には、要するに〈ピテカントゥロプス〉という語は、そういう意味の響きを持つ言葉にすぎない。
学校で教える場合には、〈ピテカントゥロプス〉というラテン語表記の学術専門用語を教える方法と〈さるにんげん〉という平易な日本語で教える方法があるわけだ。ところが、日本の専門家や教師には、後者の方法はまったく意に介されない。
なぜだろう。いかにも学問をしたという「重み」を感じさせるためだろうか。
しかし、生物進化論を理解するためには、〈さる+にんげん〉は、人類が現生の猿類と共通の祖先から人類が進化してきたという本質的な文脈を示すうえで、決定的に重要な言葉表現である。
ところが、〈ピテカントゥロプス〉では、いきなり目の前に途方もなく高い壁が立ちはだかることになる。
小学校で「さるにんげん、猿はピテクス、人はアントゥロプス」「ピテクス・たす・アントゥロプスはピテカントゥロプス」というふうにすれば教えられる。言葉遊びだ。
「アウストラロピテクス」は「南方の猿」。
そうすると、子どもらはやがて、グレコ=ローマン用語法(統辞法)では、〈ピテクス〉の〈ス〉を取り去って、母音から始まる〈アントゥロプス〉をつなげることができることを感じ取るだろう。いや、言葉の合成にさいには、前の語の最後を母音にするという高度な方法まで直観的に理解するかもしれない(つまり可能性を開く)。
そして、いつか〈アントゥロポロギー:anthropologie〉(アントゥロプス+ロゴス)が「人類学」「人間学」、つまり「ヒトの科学」であることを知るだろう。〈フィラントゥロピー:philanthropy(ie)〉(フィロス(フィルス)+アントゥロプス〉が「人類愛、博愛主義・慈善行為」であることも。
さらに、〈アンドロイド〉が「人間型機械・人類がた生物」であることにさえつながるかもしれない。ヨーロッパ語では〈th〉⇔〈d〉の変移がしばしばだ。
欧米のエリート中等学校(中学・高校、ことにイングランドのパブリックスクールやドイツのギュムナジウム)では、大学進学希望者には14歳くらいからギリシア語・ラテン語の講座を必修としている。ことに理学・化学、医学、法学系では、ことに重要視される。
高等教育機関では専門学術用語(学名)がグレコ=ローマン語で表記されるからだ。
日本ではそういうことがない。で、私は大学(学部・大学院)で専門原書を読むたびに、グレコ=ローマン教養がないことの弱点を思い知ることになった。欧米の学者たちは、論文でとりわけ大事な論点を提示するところで、自分の見解を権威づけるためにラテン語を使う場合があるからだ。
■専門原語は理解の役に立つ■
私は高校に入りたての頃に化学でつまづいた。化合物の化学式から(たとえば連立法式を立てて)分子量や当量を計算する方法がなかなか理解できなかった。それに慣れたと思ったら、今度は有機化学(炭水化合物)の化学式や構造モデルを覚えなければならなくなった。
ものぐさで暗記が嫌いだった私は、何とか単純な基礎や原理から系統的に結論(化学式や構造式)を引き出す方法がないものかと悩んだ。もちろん、赤点から逃れるためだ。
テクストを読んでいるうちに、「そうだ、用語で覚えればいいのだ!」ということに気がついた。もちろん、最低限度のことは記憶しなければならないのだが、その最低限度のこととか、複合的なことについて、用語を原語で覚えることが非常に役に立つことに思い至った。
それはまた物理学でも役立つことなどを。
で気がついついたこととは、
・学名は元素番号表を手がかりに、元素のラテン語名を覚えれば、化学式や構造式をだいたい思い描けること
たとえば、「ヒドロ」は水素、「オクシ」は酸素、「カルボ」は炭素、「クロロ」が塩素、「イソ」がヨウ素、「ニトゥロ」が窒素、そのほか「フェロ」が鉄が化合していることを示す。
・ラテン語で1、2、3、4、5、6、7、8、9、10を覚える必要があること。そのうち有機化学では、メタ、エタ、プロパ、ブタまでが変則で、あとはラテン語どおりに、ペンタ、ヘクサ、セプタ、オクタ、ノナ、デカとなり、大きな数では100=ヘクタ、1000=キロ、1000万=メガ、10億=ギガ、1兆=テラ…などとなること
・小さな数値では、10分の1=デシ(デキ)、100分の1=センティ、1000分の1=ミリ、100万分の1=マイクロ、10億分の1=ナノ、1兆分の1=ピコ…などとなること
・ある同じ分子や原子が2つ結合していると「ディ」:〈di〉、3つが「トゥリ」:〈tri〉、4つが「テトゥラ」:〈tetra〉、5つが「ペンタ」:〈penta〉・・・という接頭辞がその原子や分子の名前の直前につくこと
たとえば、「ディクロロエタン」は、エタン(C2H6)という原基に塩素が2つ結合していることが名前からすぐにわかる。
・有機化合物で炭素が環型(円環式)に結合している場合、シクロ〈cyclo〉(ツィクロ)という形容語が前につくこと。「シクロ」は英語読み「サイクロ」で「円環」である。
・そのさい、5角形に結合しているものは「シクロペンタ(ン)…」〈cyclopenta(ne)…〉となり、6角形のときには「シクロヘクサ(ン)」〈cyclohexa(ne)…〉と表記されること
だから、「シクロペンタ…」ときたら、五角形のC5Hxを、「シクロヘクサ…」ときたら、C6Hxを思い描けばいいことになる。
などだった。これらのことは、すでに理解している個別の知識を系統的に整理するうえでも役立った。
しかも、これらのことは、SFでも読むつもりでしょっちゅう考えていれば、自然に覚えられる。そして、やがて英単語の組み立ての理解にも役立った。暗記しないで、素材となっている部品から意味を取ればいいのだと。
もちろん、こういう覚え方・理解の仕方には好き嫌いがあって、向いている人と向いていない人とがいる。けれども、片端から暗記で覚え込むよりはずっと楽だと思う。
でも、興味を持った小さな男子たちが恐竜などの古生物の名前をすぶに覚えてしまうことからすると、かなり低年齢の頃から、興味をわかせるやり方で学ばせれば、わりかた効果的ではなかろうか。
しかも、こういう方法は、ヨーロッパ史や生物学(生物史)にもそのまま適用できる。何より、語学のセンスを培えるのがいい。
■言葉からの想像と遊び■
言葉(原語)を素材にして、アカデミックな想像力をはばたかせる遊び(連想ゲイム)をすることもできる。
たとえば「地中海」という言葉。
北アフリカとヨーロッパとのあいだにある海洋であり、西は大西洋から東は黒海やアナトリア(トゥルコ)、中東方面、スエズ運河にいたる「中海」だ。
英語では〈Mediterranean Sea〉(仏語:mēditerranēe)。ラテン語では〈mare internum nostorum〉〈mare medium terra〉。
ラテン語の「マーレ・インテルヌム・ノストルム」は「われら仲間のものである内海」、「マーレ・メディウム・テッラ」は「大陸のなかに入り込んだ内海」という意味になるだろう。
英語もラテン語をもとにできている。「メディ」とは「メディウム」「メディウス」から来た語で「中間の、内部の」、「テラ(ネア)」は「大陸(の)、大地(の)」。というわけで、大陸に囲まれた内海、大陸群の内部に入り込んだ海、内陸海という意味になる。
世界地図を見れば、そのとおりの位置、形状だ。
で、北アフリカとエスパーニャとのあいだは狭い海峡で、ジブラルタルではわずか20キロメートルもない狭い水路で大西洋からの水路と連絡している。そして、もちろん地中海という言葉ができた頃には、スエズ運河はないから、大西洋から大陸の奥地にまで入り込んでいる巨大な内海だと見られていたことだろう。
余談だが、ブリテンがその世界覇権を維持するために、ジブラルタルとスエズの海軍基地の維持に執拗にこだわったのも、むべなるかなという地理的環境ではないか。この世界峡谷を抑えれば、地中海の制海権の大半がそれだけで構築できるのだから。
古代ローマ帝国時代には、この海洋を取り囲むようにローマと支配下の植民地が形成されていたことから、われらのものなる(=ノストルム)内海(=マーレ・インテルヌム)と意識されていたのだろう。
で、やがてローマ人たちは西はエスパニア、北はブリタニアまで遠征して植民地や軍駐屯地を築いた。となると、場合によっては北大西洋とか北海を見ることになるので、「われらが内海」は、じつは大陸の内部に入り込んでいる海洋であることに気づく。
要するに、母なるローマの狭い空間意識から、ヨーロッパや中東、北アフリカを含むコスモロギー(世界観)を持つことになっただろう。
それから800年後、北イタリア人たちによる世界貿易ネットワークの組織化が始まる。大西洋、黒海、紅海、インド洋、バルト海=北海をまたにかけた遠距離貿易組織を形成する。このときになると、明確に「大陸の内部に入り込んだ内海」という地理意識ができ上がる。
南にはヨーロッパよりもはるかに先進的なムスリムの太守国家群、東には中央アジア、インドやペルシア、東アジア、アフリカ東部に続く交易路、北にはキリスト教の君主国家群(ヨーロッパ)。まさに文明の十字路で、交易の恩恵が絶大な空間だった。
この時代、イタリア人たちはヨーロッパの大地を〈terra firma(ferma)〉と呼んだ。今では「大陸」と訳されるが、確固としてどこまでも続く大地というほどの意味だっただろう。海や湖沼に浮かぶ「島」との対比であろうか。
やがてフランスやブリテンで〈continent〉という言葉が生まれる。生まれたての頃、コンティネント(コンティナン)は、〈firma〉に対応して「確固として永続する」というような意味だっただろう。やがて、この語だけで「大陸」という意味合いを帯びて、やがてそれだけの意味になる。
氷河期が終焉した直後には、氷床の下に深く沈んでいた幅広い低地=海や湿地がまだ残っていて、地中海は、黒海やカスピ海、ウラル海までずっと続いていたのかもしれない。大西洋から中央アジアまでの海や水路があったかもしれない。
中学の時の地理学で、「地中海」という語の意味を少しでも考えさせたら、それだけでも、日本人の少年少女たちは豊かな世界観への一歩を踏み出すのではなかろうか。
■言葉の連想遊びをもうひとつ■
英語で日本語の「蒸気機関車」にあたる言葉に〈the steam locomotive〉がある。
ところが、英語としてのこの言葉自体には「蒸気機関車」という意味はない。つまりは、ロコモティヴを機関車とするのは、意訳でしかない。〈the steam engine cart(+locomotive cart/vehicle)〉とすれば、蒸気機関車となるだろう。
で、ロコモティヴは〈loco〉+〈motive〉からなる造語=合成語である。
ロコは原語が〈locus〉で〈local〉〈location〉のもととなった語だ。ロークスとは、地上の場所、局地・現地・地方とか二次元平面や立体(三次元)空間での位置や場所(座標)を示す語である。
またモウティヴは、原動力とか動機、動性という意味で、ここから〈move〉〈motion〉などの語が派生していった。
そうすると、ロコモティヴとは、「地上の場所を移動する能力・原動力、運動性」とでもいうような意味になる。18世紀後半のブリテン人(機械工学ではスコットランド人たちが活躍した)は、蒸気機関車を離れた場所を機動的に移動できる能力、すなわち旅客・運輸機能に着目して、そんな名前をつけたのかもしれない。
これは、蒸気機関車がもたらす効果について着目した発想だ。「産業革命」開始期の経済的効果や機能に期待しての名称となる。
ところで、数学や理工学に詳しい人なら、ロークス(ロウカス)という語には、平面や空間上の座標集合、つまり軌跡(軌道)という意味があることをご存じだろう。
だから、もしその当時、蒸気機関の命名者が数学や理工学に詳しい人ならば、「軌道(レイル上)を走る原動力」という文脈で名前をつけたのかもしれない。
これは、物理的構造や性格から見て名前をつける視点だ。
250年も前のブリテン人たちが、いずれの発想で命名したのか、考えると楽しい。
■さらに、さらに■
さて、やはり英語で夕方、日没時を表す〈(the) evening〉という言葉がある。そして、それと反対語の〈morning〉という言葉もある。
両方ともに〈ing〉がついているので、本来は、現在分詞(現在進行形または分子形容詞)か動名詞であって、そのもとになった動詞(不定詞=動詞原形)があるはずだ。
イーヴニングの方は〈even〉、モーニングの方は〈morn/mourn〉という動詞がもとになっている。
イーヴンには対等、水平という意味があって、水平線とか地平面という意味になる。ということはつまり、イーヴンという動詞は、太陽の位置が水平線や地平線とイーヴン(対等)になるということだ。
「太陽が深く傾き、地平線や水平線と並ぶ位置に来る」という形容語が、イーヴニングの本来の意味なのである。〈the〉という定冠詞をつけて日没時間帯=夕刻という意味に転じてきたわけだ。
でモーアン(モーン)だが、これは英語の古語・雅語(簡単な辞典には掲載されていない)で、「日が昇る、夜が明ける」という意味を持つ。だから、モーニングは「日が昇る、夜が開ける」という形容語で、定冠詞をつけると「日の出時間帯、夜明け時」という意味になる。
英語を習いたての子どもたちのなかには、イングがつくので、現在進行形(現在分詞)だろうかと思う子もいるだろう。それは、すごく正しい直感で、深い洞察力のきっかけになる。小学校では、ぜひそういう言葉の成り立ちみたいな材料として教えてほしいものだ。
外国語に深まっていく大事な契機となるから。
こうして、歴史や地理、科学史などをからめて、日本語の言葉の構造の学習と英語(ヨーロッパ語)の成り立ち論理の研究に進む道が開けるのだ。複数の語学について、並行して論理的組み立てを学ぶ機会になるのだから。
■身近なラテン語について■
いま私たちは、ヴィジュアルとかヴィディオ、ヴィジョン、ヴィジブルとか言う用語に慣れっこになっている。
これらの言葉は、もともとラテン語(古代ローマ語)である。
ラテン語では、子音として〈d〉(ドゥ)は人称や格の変化によって〈s〉に変化する。
つまり、ある人称には「見る」は「ヴィデイオ」となるが、別の人称では、「ヴィズ」「ヴィズィ」となるのだ。したがって、「ヴィディ」は「ヴィズ」に置き換わるのだ。
もっとも、古代ローマでは人称代名詞が未発達だったから、動詞の人称変化によって主語となる名詞の人称を見極めなければならないのだが。主語表記なしに動詞などが続いていく文を見ることになる。
たとえば、〈video〉なら「私」が主語だし、〈visi〉なら「彼」あるいは「カエサエル」が主語となっていると判断することになる。
もちろん、アルファベットの表記がそういう風に変化するのだが、その時代の表音・発音は不明である。
今の日本人が、鎌倉時代や平安時代の人びとの発音をまったく理解できないのと同じだ。その時代のインテリは、中国大陸に渡ってすぐに向こうの発音をマスターできる発音=口舌(と耳)の構造であったのだという。
話を戻すと、
ヴィディ、ヴィズというラテン語は、対象を視覚的に知覚する(像として認知する)という意味を持っていた。
アメリカ風の英語発音が正しく、基準的だという発想は、だから、捨てたほうがいい。その発音がアメリカのどこの場所かで、「ネイティヴ発音」はかなり異なる。したがって、そんなものは、第二義的以下の問題だ。
むしろ、言葉の論理、語法、書法、文法こそが決定的に重要なのだ。共通のプロトコルを理解しないで、発音を意識しても、まったく無駄である。
このほかにも、「ディスク」がある。ラテン語で「皿、円盤」などを意味する語だ。
〈discus〉〈disc〉から英語の〈dish〉に変異していくことは、容易に想像できる。
身近な外来語から、いろいろと想像し調べてみるのが、思考力や言語理解への着実な道となることも多いのだ。
前にもこのブログで書いたことだが、
小学校で初等の英語教育を施せば、日本人がコミュニケイション手段としての英語を使いこなすレヴェルに達することができる…というような安易な発想。
これまで中学・高校、そして大学の10年間で英語を学んできても、英語を使いこなせない(と自ら思い込んでいる)日本人がどれほど多いか…と、エリート文部官僚が悩んで、行き当たりばったりに出した方針=制度が、それなんだろう、と私は思う。
しかし、私見では、日本人が――失敗=恥を恐れず、堂々と――外国語でコミュニケイションを取ることに挑戦しない心理障壁となっている最大の原因は、まさに「平均的優等生」を大量生産してきた学校教育にある。
学校=「学びの場」としてのスクールは、まさに失敗を許される場であって、子どもや若年層が失敗を恐れず試行錯誤し、狭い自分を表現しぶつけ合う場(相手と品位の尊重の上に)でなければならない。
にもかかわらず、目先の成績評価の物差しに怯え、周囲や教師などの目を恐れて、「優等生の虚像」であろうと振る舞いたがる人間をつくり出してきたのが、日本の学校ではないか。「上から目線」をどこまで除去できるかが、学びの場の優劣の尺度ではなかろうか。
ところが、学校は、上下秩序(権威への服従)のインプリントの場となっている。
学舎と集団馴致との混同は、19世紀の骨董だと思う。
思考力や学問的能力の向上のためには、上下秩序はむしろ邪魔である。というのも、思考や学問は、古い知識の権威や価値観の批判と破壊(部品としての取り込み・受容)である場合が多いから。
学校の本分は、失敗が恥(汚点=マイナス評価)となるような環境を排除して、自分さがしの試行錯誤となることだ。
譬えでいえば、全体的に丸いボールのような平均的優等生をつくるよりも、コンペイトウのように突出した部分とへこんだ部分がある個性人をつくるのか、という選択肢の前に立っているのだ。
前置きはこのくらいにして、本題に入ろう。
■言葉の原点から学ぶ■
私たちは、日常生活や学びの場でアルファベットを使わないことで、教育=学習のチャンスをかなりの程度失っている。
このハンディキャップをカヴァーするために、科目の多くの用語(専門用語)を学ぶときには、ギリシア語・ラテン語(グレコ=ローマン教養と呼ぶ)を基礎とするヨーロッパ語教養を、興味のある子たちには手引きすべきだ。
たとえば、生物史で人類への進化の歩みのなかで〈ピテカントゥロプス〉という生物(言葉)を学ぶとする。
〈pithecanthropus〉のことだ。なかなか覚えにくいカタカナ語だ。
ここで、グレコ=ローマン教養を使うのだ。以下では、できる限りカタカナ表現を使うことにする。
〈ピテカントゥロプス〉は、2つの用語の合成からなる。〈ピテクス〉+〈アントゥロプス〉ということだ。
〈ピテクス〉は「猿」、〈アントゥロプス〉は「人間・人類」という意味だ。してみると、この合成語は「猿人(類)」という意味をつくることになる。ひらがなで表現すれば、「さるにんげん」なのである。
グレコ=ローマン教養がある欧米人には、要するに〈ピテカントゥロプス〉という語は、そういう意味の響きを持つ言葉にすぎない。
学校で教える場合には、〈ピテカントゥロプス〉というラテン語表記の学術専門用語を教える方法と〈さるにんげん〉という平易な日本語で教える方法があるわけだ。ところが、日本の専門家や教師には、後者の方法はまったく意に介されない。
なぜだろう。いかにも学問をしたという「重み」を感じさせるためだろうか。
しかし、生物進化論を理解するためには、〈さる+にんげん〉は、人類が現生の猿類と共通の祖先から人類が進化してきたという本質的な文脈を示すうえで、決定的に重要な言葉表現である。
ところが、〈ピテカントゥロプス〉では、いきなり目の前に途方もなく高い壁が立ちはだかることになる。
小学校で「さるにんげん、猿はピテクス、人はアントゥロプス」「ピテクス・たす・アントゥロプスはピテカントゥロプス」というふうにすれば教えられる。言葉遊びだ。
「アウストラロピテクス」は「南方の猿」。
そうすると、子どもらはやがて、グレコ=ローマン用語法(統辞法)では、〈ピテクス〉の〈ス〉を取り去って、母音から始まる〈アントゥロプス〉をつなげることができることを感じ取るだろう。いや、言葉の合成にさいには、前の語の最後を母音にするという高度な方法まで直観的に理解するかもしれない(つまり可能性を開く)。
そして、いつか〈アントゥロポロギー:anthropologie〉(アントゥロプス+ロゴス)が「人類学」「人間学」、つまり「ヒトの科学」であることを知るだろう。〈フィラントゥロピー:philanthropy(ie)〉(フィロス(フィルス)+アントゥロプス〉が「人類愛、博愛主義・慈善行為」であることも。
さらに、〈アンドロイド〉が「人間型機械・人類がた生物」であることにさえつながるかもしれない。ヨーロッパ語では〈th〉⇔〈d〉の変移がしばしばだ。
欧米のエリート中等学校(中学・高校、ことにイングランドのパブリックスクールやドイツのギュムナジウム)では、大学進学希望者には14歳くらいからギリシア語・ラテン語の講座を必修としている。ことに理学・化学、医学、法学系では、ことに重要視される。
高等教育機関では専門学術用語(学名)がグレコ=ローマン語で表記されるからだ。
日本ではそういうことがない。で、私は大学(学部・大学院)で専門原書を読むたびに、グレコ=ローマン教養がないことの弱点を思い知ることになった。欧米の学者たちは、論文でとりわけ大事な論点を提示するところで、自分の見解を権威づけるためにラテン語を使う場合があるからだ。
■専門原語は理解の役に立つ■
私は高校に入りたての頃に化学でつまづいた。化合物の化学式から(たとえば連立法式を立てて)分子量や当量を計算する方法がなかなか理解できなかった。それに慣れたと思ったら、今度は有機化学(炭水化合物)の化学式や構造モデルを覚えなければならなくなった。
ものぐさで暗記が嫌いだった私は、何とか単純な基礎や原理から系統的に結論(化学式や構造式)を引き出す方法がないものかと悩んだ。もちろん、赤点から逃れるためだ。
テクストを読んでいるうちに、「そうだ、用語で覚えればいいのだ!」ということに気がついた。もちろん、最低限度のことは記憶しなければならないのだが、その最低限度のこととか、複合的なことについて、用語を原語で覚えることが非常に役に立つことに思い至った。
それはまた物理学でも役立つことなどを。
で気がついついたこととは、
・学名は元素番号表を手がかりに、元素のラテン語名を覚えれば、化学式や構造式をだいたい思い描けること
たとえば、「ヒドロ」は水素、「オクシ」は酸素、「カルボ」は炭素、「クロロ」が塩素、「イソ」がヨウ素、「ニトゥロ」が窒素、そのほか「フェロ」が鉄が化合していることを示す。
・ラテン語で1、2、3、4、5、6、7、8、9、10を覚える必要があること。そのうち有機化学では、メタ、エタ、プロパ、ブタまでが変則で、あとはラテン語どおりに、ペンタ、ヘクサ、セプタ、オクタ、ノナ、デカとなり、大きな数では100=ヘクタ、1000=キロ、1000万=メガ、10億=ギガ、1兆=テラ…などとなること
・小さな数値では、10分の1=デシ(デキ)、100分の1=センティ、1000分の1=ミリ、100万分の1=マイクロ、10億分の1=ナノ、1兆分の1=ピコ…などとなること
・ある同じ分子や原子が2つ結合していると「ディ」:〈di〉、3つが「トゥリ」:〈tri〉、4つが「テトゥラ」:〈tetra〉、5つが「ペンタ」:〈penta〉・・・という接頭辞がその原子や分子の名前の直前につくこと
たとえば、「ディクロロエタン」は、エタン(C2H6)という原基に塩素が2つ結合していることが名前からすぐにわかる。
・有機化合物で炭素が環型(円環式)に結合している場合、シクロ〈cyclo〉(ツィクロ)という形容語が前につくこと。「シクロ」は英語読み「サイクロ」で「円環」である。
・そのさい、5角形に結合しているものは「シクロペンタ(ン)…」〈cyclopenta(ne)…〉となり、6角形のときには「シクロヘクサ(ン)」〈cyclohexa(ne)…〉と表記されること
だから、「シクロペンタ…」ときたら、五角形のC5Hxを、「シクロヘクサ…」ときたら、C6Hxを思い描けばいいことになる。
などだった。これらのことは、すでに理解している個別の知識を系統的に整理するうえでも役立った。
しかも、これらのことは、SFでも読むつもりでしょっちゅう考えていれば、自然に覚えられる。そして、やがて英単語の組み立ての理解にも役立った。暗記しないで、素材となっている部品から意味を取ればいいのだと。
もちろん、こういう覚え方・理解の仕方には好き嫌いがあって、向いている人と向いていない人とがいる。けれども、片端から暗記で覚え込むよりはずっと楽だと思う。
でも、興味を持った小さな男子たちが恐竜などの古生物の名前をすぶに覚えてしまうことからすると、かなり低年齢の頃から、興味をわかせるやり方で学ばせれば、わりかた効果的ではなかろうか。
しかも、こういう方法は、ヨーロッパ史や生物学(生物史)にもそのまま適用できる。何より、語学のセンスを培えるのがいい。
■言葉からの想像と遊び■
言葉(原語)を素材にして、アカデミックな想像力をはばたかせる遊び(連想ゲイム)をすることもできる。
たとえば「地中海」という言葉。
北アフリカとヨーロッパとのあいだにある海洋であり、西は大西洋から東は黒海やアナトリア(トゥルコ)、中東方面、スエズ運河にいたる「中海」だ。
英語では〈Mediterranean Sea〉(仏語:mēditerranēe)。ラテン語では〈mare internum nostorum〉〈mare medium terra〉。
ラテン語の「マーレ・インテルヌム・ノストルム」は「われら仲間のものである内海」、「マーレ・メディウム・テッラ」は「大陸のなかに入り込んだ内海」という意味になるだろう。
英語もラテン語をもとにできている。「メディ」とは「メディウム」「メディウス」から来た語で「中間の、内部の」、「テラ(ネア)」は「大陸(の)、大地(の)」。というわけで、大陸に囲まれた内海、大陸群の内部に入り込んだ海、内陸海という意味になる。
世界地図を見れば、そのとおりの位置、形状だ。
で、北アフリカとエスパーニャとのあいだは狭い海峡で、ジブラルタルではわずか20キロメートルもない狭い水路で大西洋からの水路と連絡している。そして、もちろん地中海という言葉ができた頃には、スエズ運河はないから、大西洋から大陸の奥地にまで入り込んでいる巨大な内海だと見られていたことだろう。
余談だが、ブリテンがその世界覇権を維持するために、ジブラルタルとスエズの海軍基地の維持に執拗にこだわったのも、むべなるかなという地理的環境ではないか。この世界峡谷を抑えれば、地中海の制海権の大半がそれだけで構築できるのだから。
古代ローマ帝国時代には、この海洋を取り囲むようにローマと支配下の植民地が形成されていたことから、われらのものなる(=ノストルム)内海(=マーレ・インテルヌム)と意識されていたのだろう。
で、やがてローマ人たちは西はエスパニア、北はブリタニアまで遠征して植民地や軍駐屯地を築いた。となると、場合によっては北大西洋とか北海を見ることになるので、「われらが内海」は、じつは大陸の内部に入り込んでいる海洋であることに気づく。
要するに、母なるローマの狭い空間意識から、ヨーロッパや中東、北アフリカを含むコスモロギー(世界観)を持つことになっただろう。
それから800年後、北イタリア人たちによる世界貿易ネットワークの組織化が始まる。大西洋、黒海、紅海、インド洋、バルト海=北海をまたにかけた遠距離貿易組織を形成する。このときになると、明確に「大陸の内部に入り込んだ内海」という地理意識ができ上がる。
南にはヨーロッパよりもはるかに先進的なムスリムの太守国家群、東には中央アジア、インドやペルシア、東アジア、アフリカ東部に続く交易路、北にはキリスト教の君主国家群(ヨーロッパ)。まさに文明の十字路で、交易の恩恵が絶大な空間だった。
この時代、イタリア人たちはヨーロッパの大地を〈terra firma(ferma)〉と呼んだ。今では「大陸」と訳されるが、確固としてどこまでも続く大地というほどの意味だっただろう。海や湖沼に浮かぶ「島」との対比であろうか。
やがてフランスやブリテンで〈continent〉という言葉が生まれる。生まれたての頃、コンティネント(コンティナン)は、〈firma〉に対応して「確固として永続する」というような意味だっただろう。やがて、この語だけで「大陸」という意味合いを帯びて、やがてそれだけの意味になる。
氷河期が終焉した直後には、氷床の下に深く沈んでいた幅広い低地=海や湿地がまだ残っていて、地中海は、黒海やカスピ海、ウラル海までずっと続いていたのかもしれない。大西洋から中央アジアまでの海や水路があったかもしれない。
中学の時の地理学で、「地中海」という語の意味を少しでも考えさせたら、それだけでも、日本人の少年少女たちは豊かな世界観への一歩を踏み出すのではなかろうか。
■言葉の連想遊びをもうひとつ■
英語で日本語の「蒸気機関車」にあたる言葉に〈the steam locomotive〉がある。
ところが、英語としてのこの言葉自体には「蒸気機関車」という意味はない。つまりは、ロコモティヴを機関車とするのは、意訳でしかない。〈the steam engine cart(+locomotive cart/vehicle)〉とすれば、蒸気機関車となるだろう。
で、ロコモティヴは〈loco〉+〈motive〉からなる造語=合成語である。
ロコは原語が〈locus〉で〈local〉〈location〉のもととなった語だ。ロークスとは、地上の場所、局地・現地・地方とか二次元平面や立体(三次元)空間での位置や場所(座標)を示す語である。
またモウティヴは、原動力とか動機、動性という意味で、ここから〈move〉〈motion〉などの語が派生していった。
そうすると、ロコモティヴとは、「地上の場所を移動する能力・原動力、運動性」とでもいうような意味になる。18世紀後半のブリテン人(機械工学ではスコットランド人たちが活躍した)は、蒸気機関車を離れた場所を機動的に移動できる能力、すなわち旅客・運輸機能に着目して、そんな名前をつけたのかもしれない。
これは、蒸気機関車がもたらす効果について着目した発想だ。「産業革命」開始期の経済的効果や機能に期待しての名称となる。
ところで、数学や理工学に詳しい人なら、ロークス(ロウカス)という語には、平面や空間上の座標集合、つまり軌跡(軌道)という意味があることをご存じだろう。
だから、もしその当時、蒸気機関の命名者が数学や理工学に詳しい人ならば、「軌道(レイル上)を走る原動力」という文脈で名前をつけたのかもしれない。
これは、物理的構造や性格から見て名前をつける視点だ。
250年も前のブリテン人たちが、いずれの発想で命名したのか、考えると楽しい。
■さらに、さらに■
さて、やはり英語で夕方、日没時を表す〈(the) evening〉という言葉がある。そして、それと反対語の〈morning〉という言葉もある。
両方ともに〈ing〉がついているので、本来は、現在分詞(現在進行形または分子形容詞)か動名詞であって、そのもとになった動詞(不定詞=動詞原形)があるはずだ。
イーヴニングの方は〈even〉、モーニングの方は〈morn/mourn〉という動詞がもとになっている。
イーヴンには対等、水平という意味があって、水平線とか地平面という意味になる。ということはつまり、イーヴンという動詞は、太陽の位置が水平線や地平線とイーヴン(対等)になるということだ。
「太陽が深く傾き、地平線や水平線と並ぶ位置に来る」という形容語が、イーヴニングの本来の意味なのである。〈the〉という定冠詞をつけて日没時間帯=夕刻という意味に転じてきたわけだ。
でモーアン(モーン)だが、これは英語の古語・雅語(簡単な辞典には掲載されていない)で、「日が昇る、夜が明ける」という意味を持つ。だから、モーニングは「日が昇る、夜が開ける」という形容語で、定冠詞をつけると「日の出時間帯、夜明け時」という意味になる。
英語を習いたての子どもたちのなかには、イングがつくので、現在進行形(現在分詞)だろうかと思う子もいるだろう。それは、すごく正しい直感で、深い洞察力のきっかけになる。小学校では、ぜひそういう言葉の成り立ちみたいな材料として教えてほしいものだ。
外国語に深まっていく大事な契機となるから。
こうして、歴史や地理、科学史などをからめて、日本語の言葉の構造の学習と英語(ヨーロッパ語)の成り立ち論理の研究に進む道が開けるのだ。複数の語学について、並行して論理的組み立てを学ぶ機会になるのだから。
■身近なラテン語について■
いま私たちは、ヴィジュアルとかヴィディオ、ヴィジョン、ヴィジブルとか言う用語に慣れっこになっている。
これらの言葉は、もともとラテン語(古代ローマ語)である。
ラテン語では、子音として〈d〉(ドゥ)は人称や格の変化によって〈s〉に変化する。
つまり、ある人称には「見る」は「ヴィデイオ」となるが、別の人称では、「ヴィズ」「ヴィズィ」となるのだ。したがって、「ヴィディ」は「ヴィズ」に置き換わるのだ。
もっとも、古代ローマでは人称代名詞が未発達だったから、動詞の人称変化によって主語となる名詞の人称を見極めなければならないのだが。主語表記なしに動詞などが続いていく文を見ることになる。
たとえば、〈video〉なら「私」が主語だし、〈visi〉なら「彼」あるいは「カエサエル」が主語となっていると判断することになる。
もちろん、アルファベットの表記がそういう風に変化するのだが、その時代の表音・発音は不明である。
今の日本人が、鎌倉時代や平安時代の人びとの発音をまったく理解できないのと同じだ。その時代のインテリは、中国大陸に渡ってすぐに向こうの発音をマスターできる発音=口舌(と耳)の構造であったのだという。
話を戻すと、
ヴィディ、ヴィズというラテン語は、対象を視覚的に知覚する(像として認知する)という意味を持っていた。
アメリカ風の英語発音が正しく、基準的だという発想は、だから、捨てたほうがいい。その発音がアメリカのどこの場所かで、「ネイティヴ発音」はかなり異なる。したがって、そんなものは、第二義的以下の問題だ。
むしろ、言葉の論理、語法、書法、文法こそが決定的に重要なのだ。共通のプロトコルを理解しないで、発音を意識しても、まったく無駄である。
このほかにも、「ディスク」がある。ラテン語で「皿、円盤」などを意味する語だ。
〈discus〉〈disc〉から英語の〈dish〉に変異していくことは、容易に想像できる。
身近な外来語から、いろいろと想像し調べてみるのが、思考力や言語理解への着実な道となることも多いのだ。










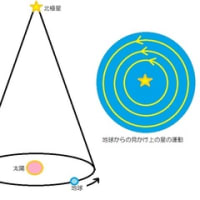
我が国は、東西文化の橋渡しになるべき国であり、世界もそれを期待している。
しかるに、我が民族は、思考力と表現力に乏しい。
英語は、自分の考えを伝える言葉である。内容がある。正確に伝わっているかが問題になる。
日本語は、相手に考えを委ねる言葉である。内容がない。どう見られるか (考えられるか) が問題である。
日本人が英米流の高等教育を習得できれば、自己の考え方を全世界に伝えることが可能になる。
ただし、フィリピン流の英語の普及では、我々は12歳のメンタリィティを脱することはできない。
http://www11.ocn.ne.jp/~noga1213/
http://3379tera.blog.ocn.ne.jp/blog/