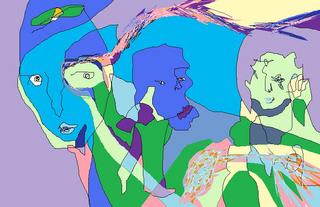
日々、熊本の片田舎で地域医療に勤しんでいます。
そろそろ親もウィーンとかから帰ってくる予定。豚インフルエンザ騒動で、国際空港は出入国が厳しそうだなー。
地域医療をやっていると、患者さんも個性的で学ぶことがとても多い。
基本的に外来もゆっくり時間があるので、時間があるときは患者さんと何気ない世間話をするようにしている。
色々感じたことに関して、せっかくなので忘れないうちに書き記しておきたい。
■戦争経験者
80歳後半~90歳の戦争経験者のおじいさんが何人もいる。
彼らは姿勢もよく、声も大きい。誰が見ても元気そのもののおじいさんが多い。
そして、戦争当時のことを詳細に覚えていて、ふとした話でそういう話になる。(耳が聞こえなくなったのは機関銃が原因だ。おなかの傷は戦争中に米軍に撃たれた跡だ。・・・)
僕は時間が許す限りその話を聞くし、非常に興味深く聞いてしまう。
シベリアで抑留された話、命からがら逃げてきた話、死ぬ気で海を泳いだ話、戦友が何人も死んで自分だけが生き残った話・・・・・・・・。エピソードは無限にある。
戦争を、細かいことを切り捨てて悪だと命名することは容易い。
昨今では、金融資本主義やサブプライム問題や金儲けを、細かいことを切り捨てて悪だと命名することは容易い。
全体を見渡すとプラスマイナスで悪だったのかもしれないが、だからと言ってその全体を形成していた部分部分が、一様に総じて悪だということにはならない。
寧ろ、部分自体には善悪という概念すら存在せず、自分の幸せ、アナタの幸せ、そんな短期的で身近なものを願いながら生活していただけで、そんな無数の部分を大きく包む「場」が、プラスマイナスすると悪の方向寄りに向いていたから、時間軸を含めて考えた上で結果として悪になったということなのだろうと思う。
そこが時間という流れの不思議なところ。
短期的(時間・日単位)に見ると、善の方向性をしているように思える。
長期的に(年単位)で見ると、悪の方向性をしていたように思える。
さらに、地球の寿命くらいの視点で見ると、善悪を超えて、そんな概念すら埃のように消えてしまうようにも思える。
この世は諸行無常だから、常に他者や世界の影響の下で、自分も常に変化しながら生きている。
全てにおいて常なるものが無い「無常」の世界を生きているから、短期的な視点と長期的な視点で結論が180度反転することを経験する。
戦争経験者のおじいさんの話を聞いていると、戦争という大きな悪の中に包まれているように感じていて、少し複雑な表情で話すことも多い。
「戦時中は散々英雄だって誉められたばってん、戦後には散々人殺し扱いばされて、辛い時もありましたばい。」
「みんな周りは死んだり殺されたりしとるけん、何で自分だけ生きとるのかよく分からんとですよ。だけんこそ、何か自分にも役割があるとは思うとっとですとよ。でも、もう年寄りだけん、社会からは用無しですたいね。」
戦争経験者のおじいさんの話は、色んな脚色が入って事実と変容していることもあるだろう。
でも、自分としては眼の前にあるその言葉を、偏見もなく、善悪もなく、そのまま聞きたい。
「先生」とは、「先に生まれた」人のことだと、自分は感じている。
■農業
熊本は農業大国ということもあって、農家の人は多い。
農家の人は毎日土を触り、自然と共に一体化して生活しているように見える。
農家のおじいさんおばあさんと接していると、自我の発想を無くし、全て自然の世界に委ねて生きている人たちのように見える。
これは、『有限の自己を捨て、無限の他者へ。』(2009-04-20)の視点で言うなら、有限の自己を捨て、無限の自然という他者を中心に、全てを捉えている人だと思う。
自然の天候、雨がふったり、晴れたり、人間の力ではどうしようもできない。害虫の発生もそうだ。
もちろん、科学技術という自意識が過剰に発達すると、天候も科学の力でコントロールしよという発想になるし、害虫も科学の力で管理しようと思い始める。
自然と共に生きている農家の人々の話を聞く。
農業で過剰なお金を稼ごうなどとは微塵も思っていない。おそらく、資本主義的発想をしている農家の人は少数派なのだろう。声が大きいからよく聞こえてくるだけなのだろう。
そんな質素な農家である大勢の人たちは、自分が食べる分だけ、そして自分の周りにいる『ワタシとアナタ』の近い関係性を持つ人の分だけに、農作物を作っている。
そして、『ワタシとアナタ』の関係性を結んでいる縁の中で、農家の患者さんから今日スイカをもらったし、昨日は別の人からネギをもらったし、その前は別の人からキャベツをもらった。
話を聞いていると、害虫に対しても無駄な殺生はしない。
虫も人間も、同じように自然に生かされていると考えている。
そこに境界線を引いて分けていない。
人間VS害虫と境界線を引いているのは、近代的な発想なのだと気付かされる。
「害」虫という命名も、自意識中心の近代的な発想なのだと気付かされる。
そこには、「自分たちの食べもの」のような縄張り意識や、そんな境界自体が存在していないし、食べ物は自然からの贈り物であり、人間が食べさせてもらえるるときもあれば、虫が食べることもある。単にそれくらいしか考えていない。
それこそが、海の幸、山の幸という発想で、「幸」という概念が自然に出てくる。
自然の法則に自分の身を全て委ねて、そんな「ドーナツの穴のような何もない自分」から全てを発想しているから、「生かされている」という感覚が非常に強い。話の端々から「生かされている」という絶対的に受け身の発想法が滲み出てくる。
その受身の発想法からは、「ありがとう」という感謝の言葉が、何の抵抗もなく自然に滑り出てくるのを見る。
だから、僕ら医者にも「ありがとう」、看護士にも「ありがとう」、みんなに「ありがとう」と、惜しげなく放射状に言葉と態度を発しながら、いつも病院を出て行く。
「ありがとう」という言葉を何十回も聞く。
自分は、そこにこそ、『有限の自己を捨て、無限の他者へ』で書こうとした世界観の一例を見る。
そういう生き方をしているお年寄りは、短期的には振り込め詐欺で騙されてしまったり、連帯人保証で騙されたりすることもあるのかもしれない。勝手にそういう心配をしてしまう。
でも、そういう「騙された」とか「損した」っていうのは、まだ未熟な自分が捉われている短期的な自意識中心の発想であり、彼らのように無限の自然に自己を委ねて生きている人には、そんな概念すらないのかもしれない。
ある境界線を作って、そんな概念を作って閉じているのは、まだ未熟な若造の自分から見える世界なのかもしれない。
彼ら自然に生きている人たちは、開かれた自然の発想で生きているように見える。
そこに、患者さんという一人の人と同時に、無限の自然そのものを見る。
農業を生業にして、自然に自己を委ねて生きているお年寄りの後ろ姿にこそ、医学の研鑽よりも自分としては学ぶことが多い。
そんな、日々です。
そろそろ親もウィーンとかから帰ってくる予定。豚インフルエンザ騒動で、国際空港は出入国が厳しそうだなー。
地域医療をやっていると、患者さんも個性的で学ぶことがとても多い。
基本的に外来もゆっくり時間があるので、時間があるときは患者さんと何気ない世間話をするようにしている。
色々感じたことに関して、せっかくなので忘れないうちに書き記しておきたい。
■戦争経験者
80歳後半~90歳の戦争経験者のおじいさんが何人もいる。
彼らは姿勢もよく、声も大きい。誰が見ても元気そのもののおじいさんが多い。
そして、戦争当時のことを詳細に覚えていて、ふとした話でそういう話になる。(耳が聞こえなくなったのは機関銃が原因だ。おなかの傷は戦争中に米軍に撃たれた跡だ。・・・)
僕は時間が許す限りその話を聞くし、非常に興味深く聞いてしまう。
シベリアで抑留された話、命からがら逃げてきた話、死ぬ気で海を泳いだ話、戦友が何人も死んで自分だけが生き残った話・・・・・・・・。エピソードは無限にある。
戦争を、細かいことを切り捨てて悪だと命名することは容易い。
昨今では、金融資本主義やサブプライム問題や金儲けを、細かいことを切り捨てて悪だと命名することは容易い。
全体を見渡すとプラスマイナスで悪だったのかもしれないが、だからと言ってその全体を形成していた部分部分が、一様に総じて悪だということにはならない。
寧ろ、部分自体には善悪という概念すら存在せず、自分の幸せ、アナタの幸せ、そんな短期的で身近なものを願いながら生活していただけで、そんな無数の部分を大きく包む「場」が、プラスマイナスすると悪の方向寄りに向いていたから、時間軸を含めて考えた上で結果として悪になったということなのだろうと思う。
そこが時間という流れの不思議なところ。
短期的(時間・日単位)に見ると、善の方向性をしているように思える。
長期的に(年単位)で見ると、悪の方向性をしていたように思える。
さらに、地球の寿命くらいの視点で見ると、善悪を超えて、そんな概念すら埃のように消えてしまうようにも思える。
この世は諸行無常だから、常に他者や世界の影響の下で、自分も常に変化しながら生きている。
全てにおいて常なるものが無い「無常」の世界を生きているから、短期的な視点と長期的な視点で結論が180度反転することを経験する。
戦争経験者のおじいさんの話を聞いていると、戦争という大きな悪の中に包まれているように感じていて、少し複雑な表情で話すことも多い。
「戦時中は散々英雄だって誉められたばってん、戦後には散々人殺し扱いばされて、辛い時もありましたばい。」
「みんな周りは死んだり殺されたりしとるけん、何で自分だけ生きとるのかよく分からんとですよ。だけんこそ、何か自分にも役割があるとは思うとっとですとよ。でも、もう年寄りだけん、社会からは用無しですたいね。」
戦争経験者のおじいさんの話は、色んな脚色が入って事実と変容していることもあるだろう。
でも、自分としては眼の前にあるその言葉を、偏見もなく、善悪もなく、そのまま聞きたい。
「先生」とは、「先に生まれた」人のことだと、自分は感じている。
■農業
熊本は農業大国ということもあって、農家の人は多い。
農家の人は毎日土を触り、自然と共に一体化して生活しているように見える。
農家のおじいさんおばあさんと接していると、自我の発想を無くし、全て自然の世界に委ねて生きている人たちのように見える。
これは、『有限の自己を捨て、無限の他者へ。』(2009-04-20)の視点で言うなら、有限の自己を捨て、無限の自然という他者を中心に、全てを捉えている人だと思う。
自然の天候、雨がふったり、晴れたり、人間の力ではどうしようもできない。害虫の発生もそうだ。
もちろん、科学技術という自意識が過剰に発達すると、天候も科学の力でコントロールしよという発想になるし、害虫も科学の力で管理しようと思い始める。
自然と共に生きている農家の人々の話を聞く。
農業で過剰なお金を稼ごうなどとは微塵も思っていない。おそらく、資本主義的発想をしている農家の人は少数派なのだろう。声が大きいからよく聞こえてくるだけなのだろう。
そんな質素な農家である大勢の人たちは、自分が食べる分だけ、そして自分の周りにいる『ワタシとアナタ』の近い関係性を持つ人の分だけに、農作物を作っている。
そして、『ワタシとアナタ』の関係性を結んでいる縁の中で、農家の患者さんから今日スイカをもらったし、昨日は別の人からネギをもらったし、その前は別の人からキャベツをもらった。
話を聞いていると、害虫に対しても無駄な殺生はしない。
虫も人間も、同じように自然に生かされていると考えている。
そこに境界線を引いて分けていない。
人間VS害虫と境界線を引いているのは、近代的な発想なのだと気付かされる。
「害」虫という命名も、自意識中心の近代的な発想なのだと気付かされる。
そこには、「自分たちの食べもの」のような縄張り意識や、そんな境界自体が存在していないし、食べ物は自然からの贈り物であり、人間が食べさせてもらえるるときもあれば、虫が食べることもある。単にそれくらいしか考えていない。
それこそが、海の幸、山の幸という発想で、「幸」という概念が自然に出てくる。
自然の法則に自分の身を全て委ねて、そんな「ドーナツの穴のような何もない自分」から全てを発想しているから、「生かされている」という感覚が非常に強い。話の端々から「生かされている」という絶対的に受け身の発想法が滲み出てくる。
その受身の発想法からは、「ありがとう」という感謝の言葉が、何の抵抗もなく自然に滑り出てくるのを見る。
だから、僕ら医者にも「ありがとう」、看護士にも「ありがとう」、みんなに「ありがとう」と、惜しげなく放射状に言葉と態度を発しながら、いつも病院を出て行く。
「ありがとう」という言葉を何十回も聞く。
自分は、そこにこそ、『有限の自己を捨て、無限の他者へ』で書こうとした世界観の一例を見る。
そういう生き方をしているお年寄りは、短期的には振り込め詐欺で騙されてしまったり、連帯人保証で騙されたりすることもあるのかもしれない。勝手にそういう心配をしてしまう。
でも、そういう「騙された」とか「損した」っていうのは、まだ未熟な自分が捉われている短期的な自意識中心の発想であり、彼らのように無限の自然に自己を委ねて生きている人には、そんな概念すらないのかもしれない。
ある境界線を作って、そんな概念を作って閉じているのは、まだ未熟な若造の自分から見える世界なのかもしれない。
彼ら自然に生きている人たちは、開かれた自然の発想で生きているように見える。
そこに、患者さんという一人の人と同時に、無限の自然そのものを見る。
農業を生業にして、自然に自己を委ねて生きているお年寄りの後ろ姿にこそ、医学の研鑽よりも自分としては学ぶことが多い。
そんな、日々です。










熊本で、
また新しい自分を発見したり振り返ったり前を見つめたり。
いなばさんより多少なりとも歳を重ねてきた自分としては、いなばさんが身近なお年寄りや農家の方々とお話したりしている様子を知り、これからを担う若者が地に足をつけて謙虚になろうとしていることを嬉しく思います。
世にいう、偉い人々だけではなく、ごく普通に身近に暮らしている人々こそなくてはならない大切な存在なのですよね。
そんな当たり前のことさえ忘れてしまいそうな殺伐とした日々に埋没しそうな時、自然の中に身を置いてみるとそこから大切なものが見えてくるような気がします。
私は、庭に萌える木々や草花、小鳥達に目をやりながら、毎日、そんな小さな自然から、生きているすがすがしさをもらっています。
いなばさんが熊本でいろんな年代の方々とお話しし、境界を持たずに自分を開こうとしているのが伝わってきます。
あと、私の祖母が般若心経をよくよんで(声を出して)くれていたので、私もよむようになりました。
初めは意味もよく分からず、解説を照らし合わせながらよんでいました。
今でもまだ正確には理解できていないとは思いますが、感じていることがあります。
祖母からよんでもらっていたとばかり思い込んでいましたが、実際に自分がよんでいると「これは、誰かのためによんでいるんじゃなくて、自分のためなのかも…」と感じています。
p.s.見田宗介の社会学ゼミナール1回目の報告、近いうちにコメント投稿しますね。
矢継ぎ早に更新されていて
読むのに忙しくするのは、どこか嬉しいです。
戦時をくぐりぬけたご老体が
コンビニで「温めてください」など注文して
いる瞬間
その後ろに並びながら、ひとり混乱します。
芋の汁も足りないちゃぶ台から、マイクロウェーブのレジ前へ。よく錯乱せずに消化してこられたなと。驚きを禁じえない。淘汰されてしまった方も多かったことでしょうか。
また、他県のご仁に「復帰のときはだいぶ尽力したよ」と話しかけられることが幾度かあり、謝辞を述べるべきなのかと困惑もしました。
聴くことを重ねていく所存だよ。
個人的には
善は、現在から未来に向う細く短いベクトルでも気づかれやすく
悪は、ベクトルがよっぽど長くないと気づきにくいな
振り返ってみると、悪が鮮やかにうつるな
「全体を見渡すとプラスマイナスで悪だったのかもしれないが、だからと言ってその全体を形成していた部分部分が、一様に総じて悪だということにはならない」
この箇所は、ここ数年社会人をやってきてずっと考えてきたことです。言い換えると、最善と思われた部分の総和が最悪の結果を引き起こす様を目の当たりにしてきたからだと思います。
それでも我々には全体を見通すことは出来ない。戦争という一言で切ることのできないイベントを通過した老人の方々がいま「なぜ自分が生きているのかわからない」と述懐するのはもっとも誠実な回答なのかもしれません。(その判断すら僕には出来ないのですが)
ちょうど自分の考えていたこととシンクロしていたので思わず。
雨音様
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
熊本にいると、東京がいかに時間の流れが速いかって痛感しますねー。
なんか急かされちゃうというか、みんなが駅をイソイソと歩くから、それに吊られて自分も自然に早足になっちゃう。そんな感じです。
人と話したり、本読んだり、音楽聴いたり、家の掃除したり、・・・
そんな単純なことで日々は過ぎていくし、少し前まで一日中病院のカテーテル室で心臓の冠動脈という2-3mmレベルのことだけを追求していた日々と大違い。
同じ時間をすごしているとは思えません。
ただ、熊本でも、東京でも、お年寄りは明らかに自分とは違う時間の密度を生きているのを感じます。
そういう意味で、やはり長く生きている人には学ぶことが多いですね。
偉い人や教科書に出ている人からも色んなものを学びましたが、今はジャンルを閉じず、自分の心に響く全てのものから吸収しています。
それは、「学ぼう」「吸収しよう」と前のめりになっているわけではなくて、心を開いていたり、自己中心の発祥から他者中心の発想に移行してから、ごく自然に自分の心持がそうなっているので、いかに自分の視点次第で世界が反転しうるかという不可思議を感じています。
雨音さんがおっしゃる『庭に萌える木々や草花、小鳥達』っていうのは、自然そのものであって、登山をしていたときから自然のよさには一々感動していた人間ではありますが、最近は開かれた存在でもあり、この世に遍く存在している、そんな自然というものの底知れなさを感じています。
この辺の自然論に関しても、色々思うところはあるので、ふと書きたい気分になったら書くかもしれません。
般若心経!いいですよね。
僕もつい最近までは、あのお経を真面目に聞いたこともなかったんですが、ひょんなとこから仏教の世界観を知るようになってから、
『大般若波羅蜜多経』600巻と『摩訶般若波羅蜜経』のエッセンス集ですもんねー。
般若心経の「心」が、サンスクリットで心臓(=重要な物)を意味するっていうのを聞いてから、心臓を専門にする自分としては不思議な縁も感じましたね。
僕は『現代語訳 般若心経』玄侑宗久(ちくま新書)を読んで、般若心経は面白いなーって思い出しました。
みうらじゅんの『アウトドア般若心経』っていうのもギャグで味付けしてあって面白いです。さすがみうらじゅん。
見田宗介の社会学ゼミナール、是非教えてくださーい。
Is君は見田LOVERですしね。
僕は見田宗介『社会学入門』は面白い!って思えましたが、直接の公演聞いた時がイマイチだったので笑、直接話を聞くよりテキストで味わう人がいいのかなーなんて感じちゃいました。
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
H.P.様
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
無駄に更新してます。笑
また6月から仕事するようになったら更新頻度も落ちると思いますけど。
まあできれば週に2回、可能なら週に1回程度はコンスタントに更新したいですね。
ブログって、自分を開くプロセスと同期させるとかなりいいツールだと思い始めてきているので、書く衝動に襲われたときにとても便利です。H.P.先生も、お時間あるようならブログも是非。
確かに、お年寄りとコンビニの風景は違和感ありますね。
僕らの価値観に無理やり合わせているのが申し訳なく思います。
いつも得意のミスチルの歌詞から引用すると、
最新アルバムSuperMarketFantasyの『東京』っていう曲があって、
http://www.youtube.com/watch?v=2P5i1Ftoi08
***********************
『東京』
歌詞:桜井和寿
東京を象徴しているロボットみたいなビルの街
目一杯の 精一杯の
働く人で今日もごった返してる
信号待ち。足を止めて誰かが口笛を吹いてる
とぎれとぎれの旋律だけど
なぜかしら 少しだけ癒されてる
描いた夢
それを追い続けたって 所詮
たどり着けるのはひとにぎりだけの人だけだと知ってる
「それならば何のために頑張ってる?」
とか言いながら分かってる
この街に大切な人がいる
東京は後戻りしない
老いてく者を置き去りにして
目一杯の 手一杯の
目新しいモノを抱え込んでく
思い出がいっぱい詰まった景色だって また
破壊されるから 出来るだけ執着しないようにしてる
それでも匂いと共に記憶してる
遺伝子に刻み込まれてく
この胸に大切な場所がある
バイパスに架かる歩道橋からよく見える
ベランダに咲いた彩とりどりの花
甘い匂いがこの胸にあふれ出す
あの人に手紙でも書こうかなぁ?
描いた夢
それを追い続けたって 所詮
たどり着けるのはひとにぎりだけの人だけど
あと少し頑張ってみようかな
それでもいつか可能性が消える日が来ても
大切な人はいる
思い出がいっぱい詰まった景色だって また
破壊されるから 出来るだけ執着しないようにしてる
それでも匂いと共に記憶してる
遺伝子に刻み込まれてく
この胸に大切な場所がある
この胸に大切な人がいる
*****************
この曲の中の、
『東京は後戻りしない
老いてく者を置き去りにして』
って部分を特に思い出しちゃいました。
特に、H.P.先生がおられる沖縄は、日本の戦争での負の歴史がいっぱい詰まっているし、複雑に絡み合った糸を解きなおす作業が必要なんだと思いますけどね。
まあそうなると、沖縄の米軍基地だとか、自衛隊とか、憲法9条とか。
まあ深めていくべきテーマはいっぱいあるんでしょうし。
(この辺は朝まで生テレビになっちゃう?)
善、悪とありますが、僕らは過去を振り返って悪に見えたことに引きづられすぎる傾向にあるんだけど、それと同時に善のことも救い上げないといけないと思いますね。
それは、『ワルイものをワルイと言うこと』であり、『イイものをイイと言うこと』。
そういう単純なことから始めていきたいものです。
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
RYM様
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
ブログ上ではお久しぶり!
ちょい前のNHKスペシャル見た?
<シリーズ マネー資本主義> っていうやつ。
http://www.nhk.or.jp/special/onair/090419.html
1970年頃にソロモンブラザーズが債券市場を作り出してから、企業の補助役であった投資銀行が過激な競争社会に入っていく過程を伝えていて、僕ら素人にはすごく面白かったよー。
<シリーズ マネー資本主義>
■第1回 “暴走”はなぜ止められなかったのか ~アメリカ投資銀行の興亡~
2009年4月19日(日)午後9時00分~ 総合
■第2回 超金余りはなぜ起きたのか ~検証 アメリカの金融政策~(仮)
2009年5月17日(日)午後9時00分~ 総合
■第3回 「老後の備え」もマネーゲームに踊った ~年金基金とヘッジファンド~(仮)
2009年6月14日(日)午後9時00分~ 総合
■第4回 天才たちが作り出した「禁断の果実」 ~金融工学・夢と暴走の軌跡~(仮)
2009年7月19日(日)午後9時00分~ 総合
■第5回 世界はバブルの誘惑を断ち切れるか ~世界の賢者に聞く~(仮)
2009年7月20日(月)午後9時00分~ 総合
7月まで続くシリーズみたいだね。
資本主義も、金融も、まあ昔から基本となるものはあったんだろうけど、インターネット社会とか国際的な交通網の発達で、どんどん有り様も変質しているんだろうし。
でも、やはり全世界ボーダレスになっていく社会(昔フラット化する社会って本あった気がするけど)は、恐ろしいってのはあるよね。もう自分が責任取れる範囲以上に対象が拡大していくし。
ネットで全世界とつながるっていう事自体も、時に恐ろしいと思う。こんな自体はさすがに今まで人類が経験していない事態だろうし。
まあその辺も含め、上の世代の言葉は当てにしないようにして、僕らの世代がウンウンうなって考えていかなきゃならん問題なんだと思う。
こんな混沌とした時代だからこそ、新しいものも生み出されるんだろうしね。
*******************
高村光太郎『道程』
僕の前に
道はない
僕の後ろに
道は出来る
ああ
自然よ
父よ
僕を
一人立ちさせた
広大な父よ
僕から目を離さないで
守る事をせよ
常に
父の気魄を僕に充たせよ
この遠い
道程のため
この遠い 道程のため
*******************
そして、そうやって感じたことを、ここに記してくれることで、空間を超えてそのほんの一部をもらうことができる。
実は、ぼくは最近ようやくドーナッツ理論のことがわかった気がしたんですよ。ちゃんとわかるのにやっぱり時間がかかってしまいました。
いくつかの実体験をしてみて、わかりました。自分とは何なのか、主体性という言葉が壁になって見えなかったのですが、それとはまた違う次元で超越した概念なのだとわかりました。
このエントリは、実にすばらしいです。世界に開いている様子が、実にすがすがしいというか、さわやかな風が心の中に吹いた気がしました。
ありがとう。
Shin.K様
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
最近は、『有限の自己を捨て、無限の他者へ。』(2009-04-20)を理論だけではなく実践から感じているので、すごく気分いいですねー。
そうなると、お年寄りの世代に、実はものすごいヒントが隠れていることがどんどん分かるようになってきました。
それは、『時間』の謎(と自分で思っているんだけど笑)にも関連する。
つまり、『未来』の概念です。
古典文学やクラシック音楽や古典映画の世界からつかまれた自分としては、『過去』という時間の概念を掴んでいた気がしたのですよね。
あとは『未来』だなーなんて思ってたんですけど、それはやはり『死』の概念と、『老い』の概念を考えるべきなのかもと最近は思う。
そういう意味で、釈迦が人間の四苦を『生老病死』として、そこに発想の起点を置いたのは本当にスゴイと思っている。仏教の古典とか、仏教の変遷からも多くのものを学び中です。
Shin.K氏は、きっとドーナツ理論分かると思うよー!
(→ドーナツ理論が何のことか意味不明な方は、吾がブログの『他者との出会い』(2009-04-04) を参照下さい)
Shin.K氏はいつも自然体だし、男性でありながら女性的な柔らかさがあって、男性のような直線に女性のような曲線の世界観も混在しているから、わしがイメージしている世界観に違う角度から照射してくると思うなー。お待ちしてます。
地面に穴を深く掘り続けると、そんな巨大地下大水脈にたどり着くと思います。
Shin.K氏に、『世界に開いている様子が、実にすがすがしいというか、さわやかな風が心の中に吹いた気がしました。』って言ってもらえるとうれしいなー。
自分も『開くこと、閉じること』の極意が分かってきたから、開くことで確かにさわやかな風がふいてくるのよねー。やっぱ換気は大事!
こちらこそ、読んでくれてアリガトウ!!