【さわやか自然百景「北海道 クッチャロ湖 冬」より】
日曜の朝は、NHKのTV番組「さわやか自然百景」が楽しみだ。
今週は「北海道 クッチャロ湖 冬」を観た。 北海道最北部のオホーツク海沿岸にあるクッチャロ湖では、湖が凍らない海の近くで、毎年約500羽のコハクチョウが越冬する。強いきずなで結ばれたコハクチョウの家族を見つめた。
きれいな映像に流れる、坂本竜一作曲のテーマ音楽が何とも言えない。ほとんど欠かさずに見ている「新日本紀行」(現在は「新日本紀行ふたたび」)や「小さな旅」も、そのテーマ音楽にはいつも心の底から癒されている。
ふと、5年前の闘病中のことを思い出した。ICUでの生死をさまよっていた約10日間、どう準備してくれたのか、いつまでも目ざめない私の耳元で、妻が繰り返し流してくれたのがこれらのテーマ音楽だった。あのときの幻覚は今も記憶に残っているが、懐かしの大好きなテーマ音楽は聴いた記憶がなかった。でも、思い出しても涙が出るほどの辛い病床で、意識の戻らない私の頭の片隅で繰り返し響いていたこの音楽が、私に生きる勇気を与えてくれたと今も信じている。
テーマ音楽の裏には、種々の豊かな映像や語りがあった。そうしたテーマ曲にいろいろ教えられ、こころ揺さぶられてきた。今、生かされてふたたび聴くこれらテーマ音楽は、特別な音楽となった。辛かったころを思い起こし、周囲に助けられて運良く九死に一生を得たこの命であれば、まず健康を大切にしなければと思っている。

日曜の朝は、NHKのTV番組「さわやか自然百景」が楽しみだ。
今週は「北海道 クッチャロ湖 冬」を観た。 北海道最北部のオホーツク海沿岸にあるクッチャロ湖では、湖が凍らない海の近くで、毎年約500羽のコハクチョウが越冬する。強いきずなで結ばれたコハクチョウの家族を見つめた。
きれいな映像に流れる、坂本竜一作曲のテーマ音楽が何とも言えない。ほとんど欠かさずに見ている「新日本紀行」(現在は「新日本紀行ふたたび」)や「小さな旅」も、そのテーマ音楽にはいつも心の底から癒されている。
ふと、5年前の闘病中のことを思い出した。ICUでの生死をさまよっていた約10日間、どう準備してくれたのか、いつまでも目ざめない私の耳元で、妻が繰り返し流してくれたのがこれらのテーマ音楽だった。あのときの幻覚は今も記憶に残っているが、懐かしの大好きなテーマ音楽は聴いた記憶がなかった。でも、思い出しても涙が出るほどの辛い病床で、意識の戻らない私の頭の片隅で繰り返し響いていたこの音楽が、私に生きる勇気を与えてくれたと今も信じている。
テーマ音楽の裏には、種々の豊かな映像や語りがあった。そうしたテーマ曲にいろいろ教えられ、こころ揺さぶられてきた。今、生かされてふたたび聴くこれらテーマ音楽は、特別な音楽となった。辛かったころを思い起こし、周囲に助けられて運良く九死に一生を得たこの命であれば、まず健康を大切にしなければと思っている。





















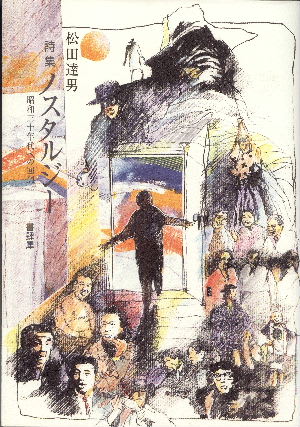


 母の作品のいくつかを壁に下げてある。本格的な額に入っている色紙をはずしスキャナーで取り込んだ。
母の作品のいくつかを壁に下げてある。本格的な額に入っている色紙をはずしスキャナーで取り込んだ。















