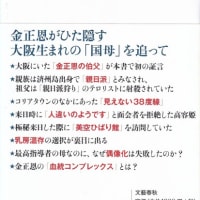新元号「令和」に関連して、黄文雄氏(文明史家)が興味深い一文を「台湾の声」に寄せている。
ここに転載をさせていただく。
【黄文雄】新元号を台湾に通知した日本に対し、中国は「中国の影響から逃れられない」
黄 文雄(文明史家)
【黄文雄の「日本人に教えたい本当の歴史、中国・韓国の真実」より転載
◆日本は他国と分け隔てなく台湾に新元号「令和」を通知
4月1日、新しい元号が「令和」に決定しました。早くも「令和」をモチーフにしたお菓子やT
シャツ、歌まで登場するなど、日本では大フィーバーが起こっています。また、諸外国でも、元号
決定について大きく報じられているようです。
日本政府は新元号について一斉に各国に通知しましたが、一部の台湾メディアでは、日本が承認
する195カ国に台湾は含まれないため、台湾には通知されないと報じていました。しかし、台湾外
交部は、日本の新元号が日本の対台湾窓口機関である日本台湾交流協会から台北駐日経済文化代表
処(大使館に相当)に通知されたと発表しました。
「自由時報」によると、台湾側に通知されたのは台湾時間で10時45分、つまり日本では11時45分
であり、菅官房長官が新元号を発表した時間とほぼ同じです。日本は即座に台湾にも通知していた
わけです。しかも通知内容も各国と完全に一致しており、日本政府は台湾を他国と分け隔てなく接
していたことがわかります。
このことを知った日本のネット民からは、「台湾にも告知されて嬉しい」「台湾は独立国家だ」
「台湾の皆さん、平成時代のご厚誼を感謝しています。日台の互助関係が続きますように」といっ
たメッセージが次々と発されました。
もちろん面白くないのは中国です。しかも、新元号はこれまでの中国の漢籍ではなく、初めて万
葉集という国書から取られたわけです。
中国共産党系の「環球時報」は当初、新元号が万葉集から取られたことについて、「初めての脱
中国」と速報しました。しかし、午後になって「万葉集は中国の古典文学の影響を受けている」と
いうことで、「『令和』は中国の影響を消し去ることができない」と記事の内容を修正しました。
いかにも中国は「いまだ日本は中国の影響下にある」ことを強調しようとしているわけで、非常
に滑稽です。いわゆる「中国のおかげ論」であり、文化すべてを中国が日本に下賜したというフィ
クションを語り、新たな「天朝朝貢冊封体制」を構築しようとしているわけです。
また、日本政府が台湾に通知したことも中国は気に食わないのでしょう。「日本は勝手に台湾に
新元号を通知したけれど、その元号は中国のお陰で生まれたものだ」と釘を刺したわけです。
たしかに漢字は中国から入りましたが、日本では音読み・訓読みに分け、さらに仮名を創出して
独自の使用法を展開してきました。9~11世紀ごろは、アジア諸国で独自の文字を創作することが
ブームになり、日本では仮名がつくられて、国風文化が花開きました。要するに、中国離れの末
に、独自文化が隆盛したわけです。894年に遣唐使が廃止になったのも無関係ではありません。
◆中国で使われる漢語の近代用語は7割近くが和製漢語
新元号の「令和」は、8世紀前半に太宰府の大友旅人の邸宅で開かれた「梅花の宴」で詠まれた3
2首の歌の序文から取られたものです。大宰府といえば、京の都から左遷された菅原道真(845~
903年)が祀られている太宰府天満宮が同地のシンボルとなっています。
道真は京の邸宅の梅の花を非常に大切にしていて、太宰府赴任にあたり「東風(こち)吹かば
にほひをこせよ 梅の花 主(あるじ)なしとて春な忘れそ(忘れるな)」という歌を詠んでいま
す。そして、道真によって可愛がられていた梅の木は、太宰府に赴任した道真を慕って、京の邸宅
から梅が飛んで来たという「飛梅」が有名です。
そして、894年に遣唐使を廃止したのは、まさに菅原道真であり、中国からの影響を排除したわ
けです。そのような由来からすると、漢籍ではなく、万葉集から「令和」という新元号が生まれた
のも、ある意味で歴史的転換なのかもしれません。
とはいえ、漢字については、多くの人が勘違いしています。確かに中国からもたらされたもので
すが、その表現の創造性には限界があり、約10世紀の唐末には、造語力のみならず拡散力も衰えま
した。
その結果、日本の仮名文字創出のように、アジア諸国で独自の文字創出が進み、東南アジアを中
心に、インドサンスクリット系の表音文字だけでも60前後が創出されています。
漢の天下崩壊によって、中華文化史は歴史の没落を迎えました。10世紀以後の文字史からする
と、仮名文字が主役となったわけです。
また、現在の中国で使われる漢語にしても、近代用語の7割近くが和製漢語となりました。加え
て、中華人民共和国の憲法は、75%以上も和製漢語が使われています。中国では和製漢語を「新
辞・新語」と称していますが、科学、哲学、経済、革命から、共産主義、共和国などに至るまで、
日本人が西洋の言葉を漢語に翻訳したものであり、現代中国もこの用語なしでは近代の概念を説明
できないのです。
中国政府が日本の新元号制定にあたり「中国の影響を消し去ることはできない」というなら、今
年で建国70周年を迎える「中華人民共和国」の名称こそ「日本の影響を消し去ることができない」
ものであり、「中国共産党」にしてもそれは同様なのです。
◆日本が独自の元号をつくった理由
今や元号を使っている国は日本のみですが、それは「万世一系」が続いているからです。宋の太
宗は日本からの留学僧・?然(ちょうねん)に謁見し、日本では皇統が途切れずに続いていること
を知って驚き、「これ蓋(けだ)し古の道なり」「これ朕の心なり」と羨ましがりました。
ちなみに元号の歴史ですが、東洋史の大家、宮崎市定博士の説によれば、それは漢の武帝からで
あり、秦始皇帝の天下統一からではなかったそうです。そのため、真の中国統一は漢の武帝だと宮
崎博士は説いていますが、私もそれに賛成します。
中国の制度は秦から始まったものが多いですが、秦はわずか3世で滅びてしまい、万世一系はで
きなかったのです。漢の時代に王莽が「新」という王朝をつくり、孔子が理想としたユートピアを
つくろうとしましたが、これも一代で滅びました。
日本の最初の元号は「大化」ですが、独自の元号をつくったのは、日本が中華王朝とは別の存在
であることを示すためであり、その意義は非常に大きいのです。
易姓革命によって王朝がころころ代わった中国では不可能だったことを、日本では現在に至るま
で続けているわけです。こうして考えると日本が「中国の影響下」にあるどころか、中国が日本を
羨み続けていることがわかります。
清末の戊戌維新にしても、明治維新をモデルに行おうとしたものですし、孫文を始めとする革命
の志士も、日本からの多大の援助があったことはよく知られています。中華人民共和国になってか
らも、日本からの巨額のODAが中国の近代化、経済大国化を支えました。
まさに近代中国は「日本がつくった」と言っていいほどなのです。中国が自慢する高速鉄道から
して、日本の新幹線の技術提供をそのまま「自国の独自技術」だとパクっているわけです。
そもそも中国は地名を国名にし、他国に「中国」の使用を禁止しました。日本に対しても中国地
方などの名称を変更するようにクレームをつけてきたことがありました。それは「中国」という表
記の独占を狙ったからです。
黄河流域の中原で王朝が樹立されるたびに、それらの王朝は「中国」を自称してきました。
◆「台北駐日経済文化代表処」の名称を早く「台湾」に変更すべき
アメリカ政府は最近、「台湾旅行法」「国防権限法」のみならず、北京にある大使館の土地面積
の10倍以上、99年の土地租借契約で台湾にAIT(米国在台湾協会)を設置しました。
日本政府も2017年の1月早々に、日本の駐台湾の外交機構である「交流協会」を「日本台湾交流
協会」に名称変更しました。
「台北駐日経済文化代表処」の名称も、「台北」ではなく「台湾」に早く変更すべきであり、日
台の有志に働きかけていくことが必要でしょう。そのことにもどかしさを感じている台湾人も少な
くありません。
もしアメリカが突如として台湾を国家承認した場合、日本はどうするでしょうか。また、もし中
国軍が台湾を占領して太平洋進出の基地とした場合、日本のシーラインはどうなるでしょうか。
いまだ代表処の名称が「台北」のままなのは、外務省のチャイナスクールの妨害があるのか、ま
たは総理府に問題があるのかはわかりません。しかし、「令和」を他国同様に台湾に告知したとい
うことで、日本の姿勢が確実に変わってきたことを信じたいと思います。
--
台湾の声