格安ツアーで、初めての韓国旅行に出かけた。ソウル3泊4日、日程表を見ると、一日中バスに乗り、史跡や土産物店巡り。半日間だけフリータイムはあるものの、3食付きというのは、あまりにも拘束感が強い。値段を考えれば、贅沢は言えないかも知れないが…。
3日目、午前中は「宋廟」などの史跡見学だったが、体調不良という理由でキャンセル。同行者はそのままツアーに出かけ、午後のフリータイムは38度線見学ツアーに行ってしまった。北朝鮮には興味はあるものの、それ以上にソウル市内に遺る日本統治時代の建築物を見たいと思っていた。
日本人向け観光バスで市内を巡っていても、ガイドさんは決して日本統治時代の話には触れない。たとえ、旧・朝鮮銀行(現・韓国銀行)の前を通っても、建物の由来を説明することはない。これは多分、お得意さんである日本人との無用な摩擦を避けようというのか、民族のプライドを傷つけられた時代のことは語りたくないのかのどちらかだろう。いずれにしても、私は「それはないだろう」と思う。
そこで「ひとり歩き」を実行。まず、ホテルのある鶴洞(ハクドン)から地下鉄7号線でソウル駅に向かった。途中、「総神大学前」という駅で地下鉄4号線に乗り換えるのだが、何とこの駅の実際の表示は「梨水」だったので、私は二つ先の「崇寶大入口」まで行ってしまった。ハングル文字の洪水の中で、似たような名前を識別するのはなかなか難しい。表示がこれでは不親切だなあと思う。
ようやくソウル駅に到着。目指すのは旧駅舎だったが、残念ながら工事中。シートを被った駅舎を遠目で眺めるに止まった。近くの博物館なども、月曜日なので皆休館日。これは不運だった。
ソウル駅をあとにして、「市庁」駅に。旧・裁判所(現在、ソウル市立美術館)に行ったが、ここも展示準備中で入れなかった。
南大門方面へ歩いていくと、旧・朝鮮銀行(現・韓国銀行)、旧・三越(現・新世界百貨店)、旧・第一銀行などがある広場へ。この広場の配置は、とても暗示的。朝鮮銀行と対面にある三越、第一銀行を民族英雄(?)やら革命家たちの銅像が遮るように建っている。これもお得意の「風水」を取り入れた配置なのだろうか。朝鮮総督府の建物が破壊されたとき、「日本帝国主義が韓国人の英気を奪うために、あの位置に建てたのだ」という説明があった。また、日本統治時代に南山に設置された測量の標準点(石)を同様の説明で非難したこともあるそうだ。日本人が「風水」で陰謀を図ったというお話なのだが、こういうトンデモ話のようなことで日本統治時代を非難するのはいつまで続くのだろうか? 当時の歴史を振り返れば、ことはそんな単純ではない。白色人種の欧米列強がアジア全域を植民地化する時代だったのだ。南下するロシアの脅威を李朝朝鮮が自力でくい止めることなどできたのだろうか?
朝鮮総督府をはじめとする日本統治時代の建造物の多くは、すでに破壊あるいは撤去されてしまった。韓国ではそれらは「反日」、憎しみの対象であっても、文化遺産ではあり得ない。
現存する旧・朝鮮銀行でも、その定礎石には文字が削り取られた跡が残っている。そこには「朝鮮総督府」という文字と設立の年月日(年号)が書かれていたはずだ。旧・裁判所(現・ソウル市立美術館)の定礎石には、かろうじて「朝鮮総督」の文字が残されていた。旧・三越だった新世界百貨店本館では、新しいプレートで「established 1930」とだけ表示している。このような行為は、日本人的な感覚を超えたものだ。日本人であれば、こういう記録は当時のまま保存するだろう。それが、明治維新を成し遂げた「近代精神」というものだ。だが、ソウルでは認めたくない史実は「なかったことにする」という、日本人とは全く異なる思考様式を目の当たりにした。韓流ドラマに夢中も結構だが、こういう隣人との付き合いは厄介で難しいことを知るべきだろう。
 (旧・朝鮮銀行=現・韓国銀行)
(旧・朝鮮銀行=現・韓国銀行)
 (旧・朝鮮銀行の定礎=朝鮮総督府や年号の文字が削り取られている)
(旧・朝鮮銀行の定礎=朝鮮総督府や年号の文字が削り取られている)
 (旧・朝鮮銀行 側面から撮影)
(旧・朝鮮銀行 側面から撮影)


(旧・三越本館 現・新世界百貨店本館)
 (旧三越の隣にある旧・第一銀行)
(旧三越の隣にある旧・第一銀行)
 (漢江大橋)
(漢江大橋)




(旧・裁判所 現・市立美術館 右側写真は、定礎石に刻まされた「朝鮮総督」の文字)


(1916年に造られたという洋館)
 (旧・ソウル市庁舎)
(旧・ソウル市庁舎)


(聖公会=英国国教会の教会)
 (「救世軍」本部)
(「救世軍」本部)


(改装工事中の旧・ソウル駅舎 右側が工事現場のフェンスに掲示されていた往時のソウル駅)











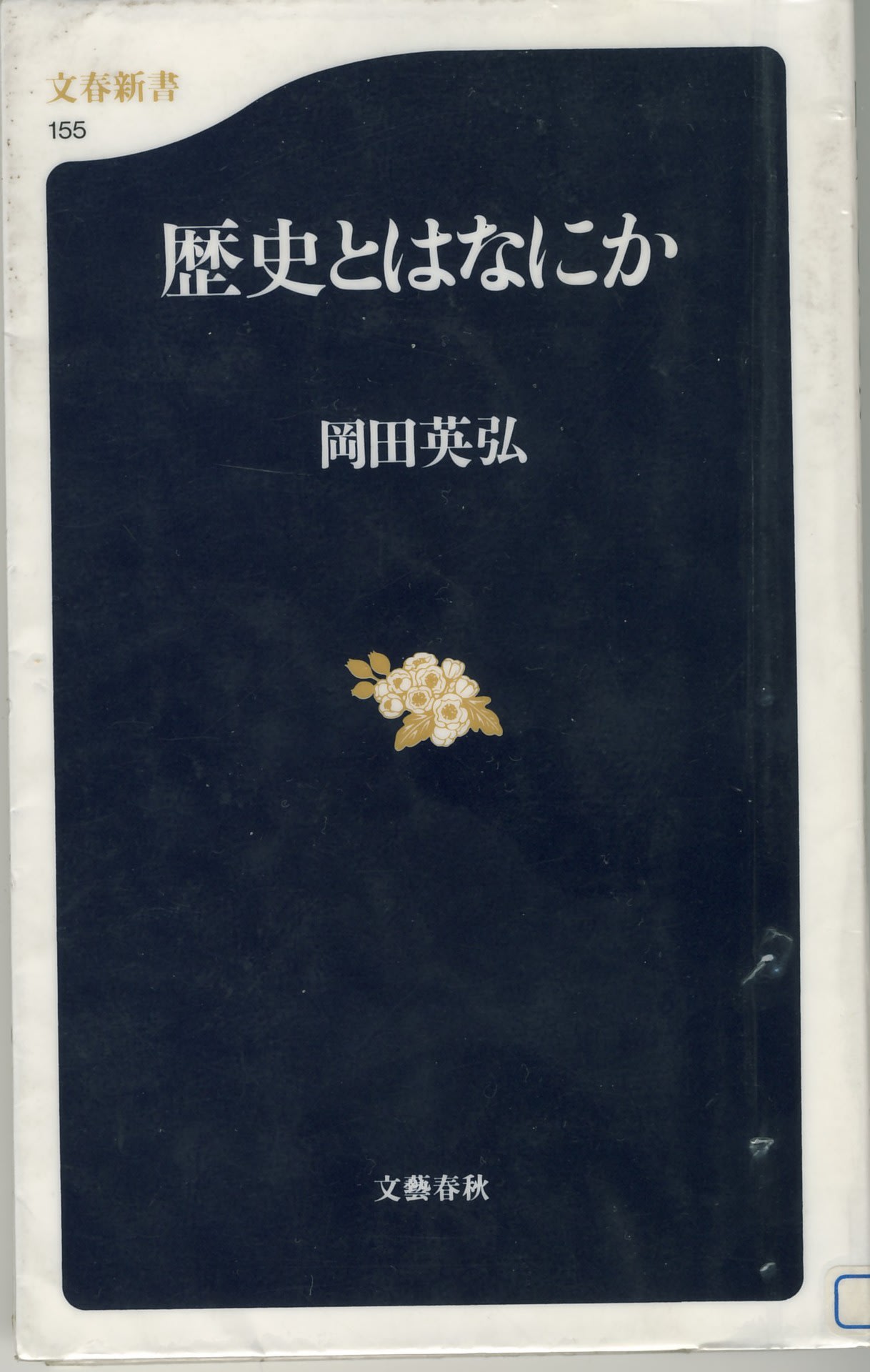





 (
(




 (
(
















米軍基地に占拠された沖縄から見れば、そのようなご意見が出るのかも知れませんが、中国に対する認識には疑問が残ります。そもそも、中国という名称、中国はひとつであるという脅迫観念が、これまでの中国観を曇らせてきたと考えます。
しかも現在の中国は、反日の中共一党独裁政権です。彼らが沖縄を併呑すれば、台湾の「二二八事件」(1947年)のような惨劇が起きると思います。明治国家が沖縄に対して行った行為は、現代の基準からすれば種々の問題がありますが、当時、列強はそれ以上のことをアジアに対してやっていたことを忘れてはならないと思います。
琉球の歴史にしてもかなり無知な状態で人生の半ばを過ぎて、見据えているお恥ずかしい現在です。二二八事件の捉え返しは本省人の李登輝総統の登場によってより光が当てられているのですね。昨今台湾から留学してきた学生が[中国人」ではなく「台湾人です」と発言したことにも驚いたのですが、台湾の戦後の歴史はとても興味深いです。琉球大の台湾や中国研究者のお話も身近で聴けるようになった現在ですが、台湾の方が沖縄を「琉球」の名称で呼んでいることも、沖縄の独立を台湾の将来の指針と兼ねて見ている視座を感じます。
コメントの中の「列強」がアジアに振るった植民地的政策の非情さは日本の比ではなかった、も確かにその通りかもしれません。アヘン戦争などみても、例えば中国の研究者もその戦争が中国の近代化への警笛で屈辱的な戦争だったと話していましたが、しかし、かといって日本が沖縄に振るった刃を全て正当化できるかは疑問ですね。
沖縄の米軍基地は植民地の象徴ですよね。それとそこからイラクやアフガニスタンにもアメリカの戦闘機が飛んでいってクラスター爆弾などが落とされ多くの子供たちが犠牲になっているのですよ。ベトナム戦争の時もそうでした!
上記のエッセイに関しては続きを改めて書きたいと思います。コメントありがとうございました!
Unknown (MONTY)
http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2010&d=1110&f=politics_1110_010.shtml
台湾では、「琉球」「琉球群島」という言葉が使われていますが、華夷秩序の復活を企むかのような中国とは、使う意味合いが異なります。「ひとつの中国」は、孫文が清朝の政治構造を換骨奪胎して作り上げた虚構です。その延長線上には、論理的に琉球は中国の属国だという主張が待っています。
どうも経済・軍事的に中国のパワーアップと比例して日本では中国脅威論が高まっていますが、昨今の尖閣諸島の動きも韓国の動きも同様、意図的に中国との対立を深めて日米同盟を強化しようとする日本のパワー・ポリティックスを逆に感じさせます。また琉球諸島を日本国の利害のために犠牲にしてもかまわないマジョリティー日本人の強固な意志さえ露わですよね。
日米が、沖縄を永久に無沈空母にせんとする企みは見え見えですよ。それは否定したいです!中国脅威論者は、例えば悪の基軸としてイラクやイランや北朝鮮を名指し、世界を騙して戦争に突入したアメリカに加担した視点で見ているのではないですか?大国と大国の間で今後琉球/沖縄がどう自らの方向性を選択していくか今問われています。暴力構造は例えば目取真俊の小説『虹の鳥』に暗喩として書かれています。そこに中国や台湾なども視野に入れて琉球諸島&東アジア全体の明日を考える必要があるのでしょう。
単純に一党独裁だから中国は怖いでも未来は切り開かれないでしょう。中国人の琉球人へのシンパシーはありますね。また琉球/沖縄の人間も中国にシンパシーを持っているのは間違いないでしょう。「痛み」の共感のようなものと、中国人の子孫の存在もあるのでしょうがーー。
先の戦争で日本人は三百万人以上犠牲になり、アジア諸国ではおよそ二千万人が犠牲になったと言われています。
琉球諸島の自決権は確保する必要があります!日米の植民地的現在、軍事要塞化を否定しない限り琉球/沖縄の未来は明るくならない、それが率直な思いです。
中国が、琉球諸島の自律権(自決権)を認め、軍事的に関与せず(併合や基地化をせず)、不可侵の平和な琉球弧を応援するならば、大いに結構ですね!
日米が、沖縄の軍事基地を全て撤去するならば、信頼できます。
一方で沖縄の作家のブログを見ると自衛隊配備を強固に推し進め、与那国や八重山、宮古、沖縄と全く琉球弧に多くの自衛隊とその家族を移住させて、沖縄をますます意のままに日本国の利害の生贄にするー過去の亡霊(日本国の防波堤)もまた迫出してきそうな雰囲気です。(これも先住民族を浄化する運動?)日米の軍事同盟が重要だと、管総理とオバマ大統領は対中国に強行路線を取る戦略を世界にアピールしました。つまり、いつまでもこの沖縄の戦前からの悪夢を上塗りせんとする意志が明らかです。
中国の怖さはアメリカの透明な民主主義(全体主義)の怖さと比例するのではないでしょうか?文字通り自由ということ、言論の自由、表現の自由が日常レベルで可能な点は確かにまだまだいいと言えるでしょう。政治批判もできます。それが許容された日本やアメリカ社会はまだ市民に優しいと言えますね。
しかし、中国を怖がってばかりいても、前に進みません。軍事力(一党独裁)で民衆を抑圧し自由を剥奪し、檻に閉じ込める。恐ろしいことです。中国内部から自由を求める運動と呼応した運動をこちらでも展開する必要があるのではないでしょうか?アメリカもかつてのソビエト連邦の解体のように中国の内部からの解体を目指していると、ネット・サイトから見えてきます。ボーダレス・グローバル経済が中国の一党独裁を解体させる必然などありえないでしょうか?
危惧するのは、中国の軍事的脅威に対して日本も軍隊(自衛隊)を増強する、という危険な兆候です。国際連合のより開かれたシステムを追求し、アメリカやNATO中心の平和維持軍ではなく幅広い世界の国々が共同で維持管理する平和構築システムを築く努力をする必要があるのでしょう、という前に努力はなされていますよね。
誤解されているのは、私は盲目的に中国を支持しているのではありません、貴方がご指摘の点を、じゃー、どう、いい方向へ持っていくか、その次のステップに取り組む必要があると考えます。戦時中、昭和3年生まれの母などは中国人をシナ人と呼びすて、差別的な言辞をしていたと話しています。認識なり教育、互いの理解度を深める多様な交流が問われています。
ハイティーンの者たちはネットで、たとえば、「日本鬼子」のプラカードに対して、およそ2000個の「ひのもとおにこ」の絵柄を創作してネットで展開するなど、大人の堅い構図とまた異なる交流をしています。
世界は一つに向かって、軍事的対立のない共栄圏を目指すビジョンなり夢は捨てたくないです。沖縄は独自に台湾や中国、韓国とも交流を深めていく必要があります。民衆はお互いに分かりあえると信じたい。政府や国の権力構造とは別にーー。
日本の国内植民地は返上したいですね。あなたがどこに住んでいるどなたか、よくわかりませんが、台湾の事情にお詳しい様子ですが、台湾から留学して博士論文など書いている学生からもいろいろとお話を伺いたいと思います。沖縄の歴史研究者や中国、台湾にお詳しい方々は、あまり本音でご意見を出されていません。それだけ問題は微妙で、流動的な現状なので、慎重な対応をされているのだと考えています。中国が大国意識丸出しで琉球/沖縄の自決権や意志を踏みにじるようなことは阻止しなければならないでしょう。
一方的に全否定したり全肯定するのは、いつでも危険なのかとも考えます。よりよき理解と共生・共同、戦争のない地球を目指していく、という事はどの国の民衆も同じ思いではないでしょうか?現状は厳しいーーー、それでも、よりよき未来を求めたい。
ご指摘の「簡単に中国を信じるな」は、胆に銘じたいと思います。
http://www.youtube.com/watch?v=wVTSSD8Anxo&feature=player_embedded
時代の変化の速さを感じます。21世紀がアジアの世紀と言われて久しいのですが、中国、インドを中心にどうダイナミックに展開していくのだろうか?日本はどうも浮き足立っていて、中国脅威論の中で軍国調になりつつあります。アメリカとニコニコ手を結んでその盾にされるのだろうか?
中国が戦略的に沖縄を自国の領土だと主張する度合いは増えてくるのでしょう。しかし、この琉球弧には住んでいる人間がいるのです。自立した独自の自治権を認知させるこちらからの発信が問われています。
日米が沖縄を踏みつけにする政策を変えない限
り、中国へのシンパシーは増えるのでは?あまり変わりばえのしない意見ですがーーー。しかし日本語で生活していますからねーー!
実は私も今、某国立大学で「東アジア国際関係史」を聴講しています。教授は近代中国史研究で著名の方ですが、専制国家である中国は数々の歴史捏造を行ったと指摘しています。少数民族の言語文化を奪い、「清帝国」の版図を「中国」の国土だとして漢民族が強権支配するというのが、中国共産党の企てる新たな「中華帝国」です。そこには沖縄も当然含まれています。「日本語で生活している」などというのは無関係、もし中国共産党が沖縄を占拠すれば、ただちに新たな「二二八事件」が起きます。蒋介石は、二万人の台湾人インテリ指導層を虐殺して、直ちに日本語、日本文化を禁止した。三人以上の集会も禁止です。その後、四〇年間、台湾人の言論は封殺された。その間、台湾の日本語世代は年老いていった。これと同じこと、いや共産党ですから、もっと残虐な支配が行われることは間違いないでしょう。
間違っても、華夷秩序下の清朝ー琉球王国との関係を現代に適応できるなどと思ってはなりません。
台湾の独立を支持します。香港の独立も支持したいのですが、現実は一国二制度の中の自由ですか?ただ国家という枠組みを超えたものを追求できないのが現実でしょうか?
「華夷秩序下の清朝ー琉球王国との関係を現代に適応できるなどと思ってはなりません」が貴方のポイントだと思います。琉球/沖縄の歴史を鑑みて、清王朝へのロマンティシズムはありますよね。今頃近代が迫ってきます。大城立裕氏の「さらば福州琉球館」について研究発表したのですが、当時の脱清人の動きなど、現在の沖縄のある者たちのメンタリティーに呼応するところがあるかどうか?ボーダレス、ディアスポラの要素はありえるか?結論はどうだったか、もっとじっくり見て論をまとめなければ、です。佐藤優にしても大城の小説『琉球処分』について意図的に宣伝しているのは、130年前の近代の世界地図を想起して、現代の問題を見ろというプロパンガンダだと言えるでしょう。そう思いませんか?
琉球大の高良倉吉先生などもあなたと同じことを話していたと記憶しています。琉球史を遅れて学ぶ者ですが、授業で三田剛史氏の「現代中国の琉球・沖縄観」について討議しました。琉球史を研究している前田舟子さんなど、北京語にも堪能ですから中国の研究者の論文も発表しました。また同じく台湾の研究をしている仲村春菜さんなども台湾側からの視点なども展開していたと記憶しています。(手元の資料を参考せず書いている。もし表記に間違いがあれば指摘よろしく!)私などは三田氏の指摘は面白いと感じました。
(1)中国に朝貢していた琉球王国は、中国の藩属国である。
(2)日本による琉球処分は軍事力を背景としたもので不当である。
(3)当時の国際情勢のため、清朝は琉球への権利を確保できなかった。
(4)中国は第二次世界大戦の連合国の一員であり、日本に対する戦後処理に関して、本来琉球の処遇に対する発言権を持つ。
(5)国共分裂、冷戦などの影響で、中国は琉球に対する権利を行使する機会を逸した。
以上ですが、現在の中国はその路線上で発言を強めている印象です。しかし三田氏は最後に「琉球の帰属について発言権があるのは、琉球の住民に他ならない」と当然ありうべき視点が欠落していると指摘しています。
確かに琉球/沖縄に住んでいる者たちの主権への配慮を欠いた(欠如した)論調になっていると思います。大国の傲慢さですね。その中で踏みにじられてきた者たちへの視線が弱いですね。日米も同じですがーー。
日本の知識人は欺瞞そのものですよ。自らの安寧は沖縄を踏みつけて成り立っているのですからね。どんな論調にも欺瞞が付きまとっています。麗しき日本国憲法は治外法権的に沖縄をアメリカに売り渡して成り立っているのですからね。(昭和天皇の発言も麗しく、沖縄をアメリカに長期リースしてOKです。その上でなりってきた日本の戦後の繁栄ですからね!日本の政治家、知識人のペテンの美しさよ!だから比嘉豊光が酔って【日本の知識人が書いた物はトイレットペーパーと同じ】と言っても、うなずけるのです。少し脱線!)
その点、琉球史や中国、台湾の権威ある研究者はしっかり現状を視座において論を展開してほしいものですね。中国脅威論がアメリカでも国内選挙を左右するほどに高まっている様子ですが、危険な色合いですね。EUでもロマの排除など、またイスラム系の人々への憎悪も膨らんでいるようで、世界はまた新たな民族間、宗教間の対立に向かっているようで、きな臭いです。
そんな現象があるからこそ、第三次世界大戦など引き起こさないために、地球人としての連帯間を深める、国境なき平和な今日・明日を求める運動が必要なのでは?と思います。
まず沖縄から基地をなくし、中国や近隣諸国の人々と友好関係を築けあげることをネットでもすべきなんでしょう。楽観的かもしれません。過去の残酷な経緯の方程式を未来にそのままあてはめることがない実践を今やることが大切だと考えます。
中国共産党の怖さですか?蒋介石の残酷さではなかったのですか?その辺はもっと学習する必要があるようです。漢民族と他の少数民族の関係がどうなっているかも知りたいですね。