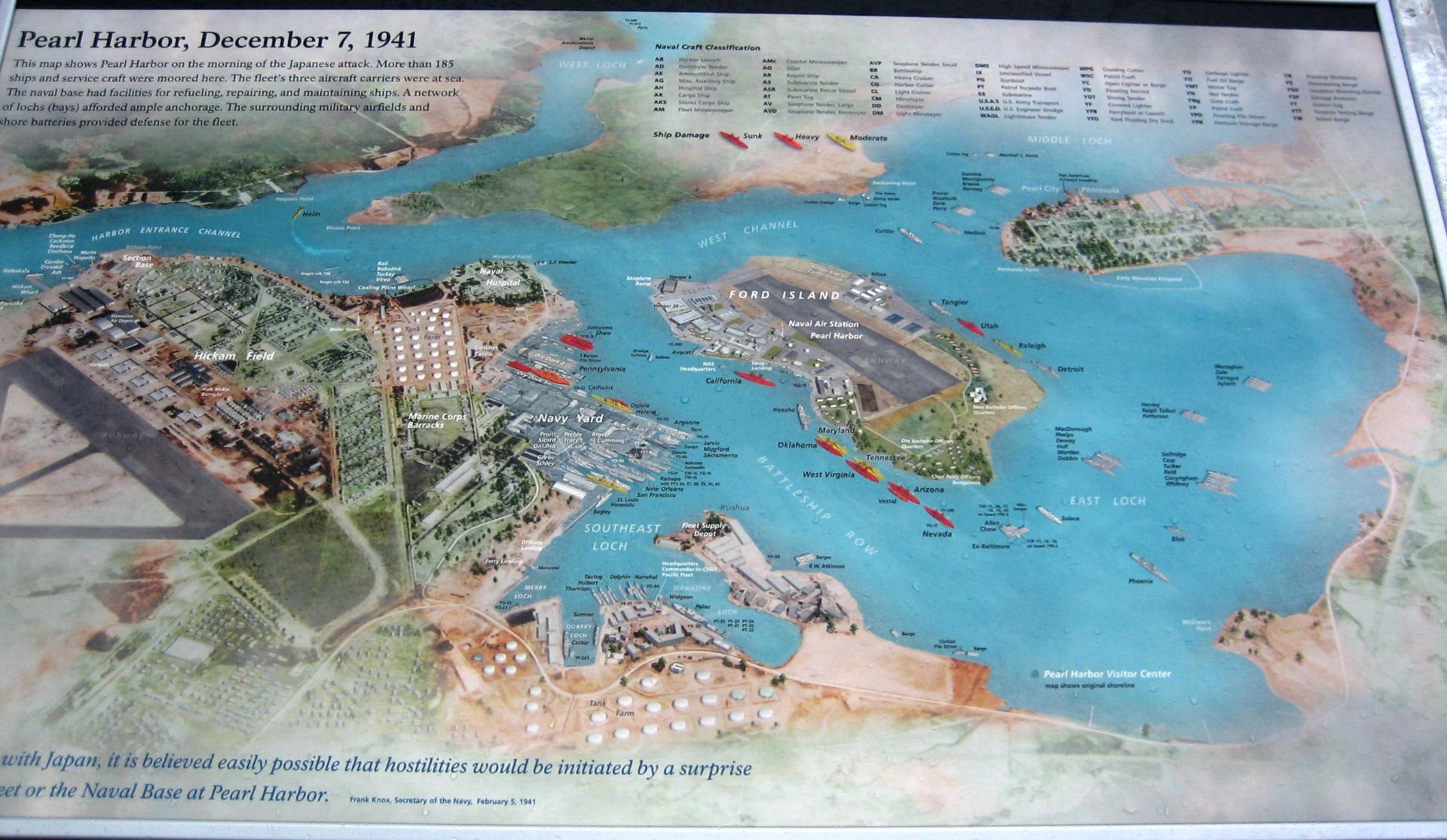季節がら、戦争を回顧するTV,ラジオ番組、新聞記事がいっぱい。中にはなるほどと納得するものもあるが、大半は現在の視点で過去の戦争を批判的に描くものばかり。「平和」「人権」「市民」「女性」などの概念で、あの戦争の実相を理解することができるのかどうか、はなはだ疑問が残る。とりわけ、現在国会で審議中の「安全保障法制」を批判するために、過去の戦争を持ち出すような態度は、不誠実と言わなければならないだろう。
そんな中で、驚くべき報道が登場した。1971年、「中国」の国連代表権問題が紛糾するなか、昭和天皇が「蒋介石支持」を佐藤栄作首相に促したというニュースだ。
日本国憲法のもとでは、天皇は象徴天皇であり、政治的発言は許されていない。だが、この「蒋介石支持」発言は、まぎれもなく政治的発言だ。1971年の時点でなお、このような発言をしたのなら、戦前、天皇が軍部の暴走に翻弄され、平和の意思を貫けなかったなどという通説は、都合のいい作り話としか思えなくなる。
おそらく昭和天皇は、蒋介石に対して「命の恩人」という意識があったのだろう。国連において「中国」を代表するのは中華人民共和国(大陸)か、中華民国(台湾)かというような議論よりも、敗戦の責任を問われず、自分の命を救ってくれた蒋介石個人にただただ恩義を感じていたのだろう。
毛沢東の中国共産党(=中共)と蒋介石の中国国民党は、「ひとつの中国」しか認めないという点で、同じ穴のムジナだった。中共は、権力掌握後、チベット侵攻を手始めにウイグル、内モンゴルなどの少数民族居住領域を制覇し、続いて大躍進運動、文化大革命などの暴政を推し進めた。一方、台湾に逃れた国民党は、二二八事件で台湾の知識層、指導層(台湾の日本語世代)を二万人以上虐殺し、以後40年以上にわたって「大陸反攻」を叫び、戒厳令を続けた。
昭和天皇は、かつて日本国民=臣民であった台湾人(日本語世代)が蒋介石の軍隊によって大虐殺された事実を知りながら、わが身を助けてくれたという理由だけで「蒋介石支持」発言をしたのだろうか。遺憾ながらここには、日本に「見棄てられた」台湾人(本省人)に対する思慮は全くうかがわれない。
昭和天皇の人間性を問われる重大ニュースだけに、今後の解明が待たれる。
昭和天皇「蒋介石支持を」=国連代表権問題、佐藤首相に促す―日米文書で判明
時事通信 7月30日(木)16時54分配信
蒋介石総統率いる中華民国(台湾)政府が国連の代表権を失う直前の1971年6月、佐藤栄作首相が米国のマイヤー駐日大使(共に当時)と会談した際、昭和天皇から「日本政府がしっかりと蒋介石を支持する」よう促されたと伝えていたことが分かった。
秘密指定解除された米国務省の外交文書で判明した。台湾の国連代表権維持への後押しを伝えたものとみられる。天皇の政治問題への関与発言が公になるのは極めて異例だ。
この問題について、日本の外交文書にも「陛下が(中国問題を)心配しておられた」というマイヤー大使に対する佐藤首相の発言が記載されている。昭和天皇の発言の背景には、蒋介石が終戦直後に中国に残った日本人の引き揚げや天皇制の尊重、対日賠償請求権の放棄など「以徳報怨」(徳をもって恨みに報いる)と呼ばれる寛大な対日政策を取ったことに「恩義」や「信義」を持ち続けていたことがあると思われる。しかし、国連代表権は71年10月、毛沢東主席の中華人民共和国(中国)政府に移った。
こうした経緯は、国連の中国代表権問題を詳しく検証した井上正也・成蹊大学法学部准教授(日本外交史)の研究で明らかになっている。「二つの中国」で揺れ動いた戦後70年の日中関係をめぐる「秘密折衝」の一幕が浮かび上がったが、井上氏は「蒋介石の行く末を案じた天皇の意向は、台湾擁護にこだわった佐藤の姿勢に少なからず影響を与えたのではないか」と解説する。
米外交文書によると、71年6月2日にマイヤー大使と会談した佐藤首相は「天皇は建前上、政治問題に関心を持たないのだが、(蒋介石)総統が過去において日本のために多くのことをやってくれたと述べた」とした上で、天皇による「蒋介石支持」の意向を大使に伝えた。日本側外交文書はこれほど明確ではないが、佐藤首相が大使に天皇の「心配」を伝え、「日本政府としては蒋介石総統に対する信義の問題ということもあり、本問題については慎重検討中である」と説明。「まず台湾の国連における議席を確保する要がある」と訴えた。
一方、秘密指定が解除された「佐藤首相・マイヤー大使会談」記録を保管する日本外務省の外交史料館(東京)では、「実は先刻陛下に御報告の際、通常陛下は政治問題には直接関与されないことになっているが、特にこの問題については心配しておられた」という佐藤首相の発言を黒塗りにして公開された。外務省は、天皇の政治関与発言が公になることに神経をとがらせているとみられる。
97年に発行された「佐藤栄作日記」によると、佐藤首相はマイヤー大使との会談に先立ち、宮中に参内し、「中国台湾問題」を奏上したと記している。
戦犯リストから消えた「天皇」=米国追随と共産化防止―蒋介石が早期決定・中国
時事通信 8月2日(日)15時29分配信
日本との戦争最終局面の1945年6月、当時中国を統治した中華民国・国民政府が作成した日本人戦犯リストのトップに「日皇裕仁」(昭和天皇)が掲げられたが、終戦直後の9月のリストからは消えていたことが分かった。
蒋介石主席の意向で決まったもので、連合国・米国に追随する方針のほか、共産主義の拡大防止という背景があった。米スタンフォード大学に保管される「蒋介石日記」でも同年10月下旬、「日本戦争犯罪人を既に裁定した」と記されており、終戦後の早い段階で「天皇免訴」が決定していた。
時事通信が中華民国の外交文書を公開する台湾の「国史館」や国民党史料を所蔵した「党史館」で入手した複数の戦犯リストや内部文書のほか、「蒋介石日記」の記述で判明した。
国民政府は終戦前から、戦犯リスト策定に着手しており、45年6月に軍令部が「侵戦(侵略戦争)以来敵国主要罪犯(犯罪人)調査票」を作成。戦犯トップに「陸海空軍大元帥」として「日皇裕仁」を掲げ、「侵略戦争の主犯・元凶」と明記した。日本の軍国主義による侵略の根源が天皇にあるとの見方は中国で根強く、議会に相当する民意機関「国民参政会」も7月17日、「天皇を戦争犯罪人に指名する」決議を可決した。
これに対して蒋介石は「日記」で9月21日、「当面の急務」として「戦争犯罪人(決定)」を挙げ、10月8日には「外交急務」として「日本軍戦争犯罪人の決定」と記した。同月14日に東条英機(元首相)ら12人を「特務工作の悪事を尽くした」として戦犯指定した。「日記」からは蒋介石の意向が選定に反映されていたことが分かり、9月の戦犯リストから天皇の名前は除外されていた。
蒋介石が「戦争犯罪人決定」を「急務」とした10月8日、国民参政会の決議に対し、戦犯問題を調査した司法行政部と外交部は天皇の戦犯認定について「蒋主席とトルーマン米大統領が、日皇の運命は日本の民意が自ら選択すべきであると共に表明した」と否定的な方向に傾いた。また当初、天皇を戦犯リストに掲げた軍令部は「皇室は将来的に日本の侵略国策を復活させる源泉だ」としつつ、「同盟国(連合国)によるポツダム宣言の円滑な命令執行と、共産主義勢力拡大の防止」のため、天皇免訴が必要だと方向転換した。
最終的には蒋介石の統括する国防最高委員会が45年12月28日、「日本問題処理の意見書」を決定。「同盟国の誤解と日本人の反感を回避」するため、「天皇と天皇制存廃の問題は、原則として同盟国の共同意見に従い処理する」との方針を確定した。
蒋介石政権は46年5月からの極東国際軍事裁判(東京裁判)に向け、東条ら計32人の戦犯リストを2回に分けて連合国軍総司令部(GHQ)に提出した。