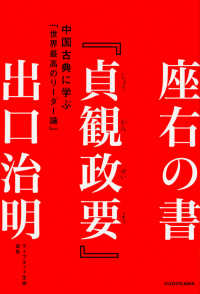SARS(サーズ)と比べコロナは致死率は低い?
識者の眼 日本医事新報
「新型コロナウイルス感染症はSARSに類似、厳重な警戒が必要」菅谷憲夫
菅谷憲夫 (神奈川県警友会けいゆう病院感染制御センターセンター長・小児科、慶應義塾大学医学部客員教授、WHO重症インフルエンザガイドライン委員)
2020年1月になって、中国武漢での2019 Novel Coronavirus(2019-nCoV)の流行が大きな問題となっている。しかし、日本政府の対策は遅れ、国内での人から人への感染が明らかになった時点でも、中国の感染地域からの団体観光旅行を放置したのは、2019-nCoVの感染性、重症度を過小評価したと考えられる。日本では、コロナウイルスの重症感染症である重症急性呼吸器症候群(SARS)や中東呼吸器症候群(MERS)の患者発生がなく、全く経験のなかったことも原因である。
日本のマスコミは、2019-nCoVの重症度は低いと報道してきた。典型的には以下のような報道がされてきた。例えば、「専門家らは、人から人への感染は限られていると指摘し、国内で感染が広がる危険性はほぼないと冷静な対応を求めている」とか、「国内の人は特別な対策は必要ない。手洗いやマスクなど、インフルエンザの予防策を取れば足りると話す」などである(1月20日時事ドットコムニュース)。このような論説が国内で流布したことは、わが国の対策の遅れに影響したと筆者は感じている。国民は、マスコミの断片的な報道に惑わされ、SARSクラスの重症感染症流行の危機的状況にあることを理解しないままに、国内で感染患者が続発している(2月2日現在)。
医療関係者は、確実な論文を基に、コロナウイルスについて理解、判断すべきであると考え、いくつかの論文内容を解説したい。
Lancet論文
最近、Lancet誌に、本年1月2日時点での武漢の2019-nCoV入院41例の詳細な報告があった。この論文の最も重要な内容は、武漢の2019-nCoV感染症は、臨床的に、かなりSARSに類似していると指摘している点である(Chaolin Huang, et al:Lancet. 2020.)。
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2820%2930183-5
言い換えれば、中国では、SARS類似疾患が大流行しているので、武漢のような大都市を封鎖してでも制圧を目指しているのである。中国が共産党政府だから、強制的な大規模な対策を取っているのではない。
論文で取り上げた入院患者41例は、全例が肺炎であった。平均年齢は49歳で、32%の患者が基礎疾患を持っていたが、高血圧も含まれ、日本で報道されているように、高齢者や重いハイリスク患者だけが感染、重症化するわけではない。
死亡者は6例で致死率は14.6%(6/41)であったが、これは、今後、確定診断法が普及して軽症例も明らかになれば、低下していくものと思われる。現在は数%であるが(2.2%、259/11791、2月2日現在)、それをもって、2019-nCoVの致死率が低いと報道されているのは誤りである。1918年の悪名高いスペインかぜ(インフルエンザのパンデミック)の致死率は、欧米諸国や日本では、1〜2%であった。2019-nCoVの致死率は、スペインかぜ並みに高いと報道するのが、医学的に正しい。
2019-nCoV症例はLancet論文ではSARSと似た症状を呈すると報告され、41例中13例(32%)がICU入院となっている。日本では、今のところ重症例が出ていないが、今後、日本でも症例数が増加するに従い、呼吸不全など重症例が出てくると思われる。マスコミ主導で、手洗い、マスク着用により、2019-nCoV感染が防げるような報道がされているが、そのような医学的な根拠は全くない。現状では、治療薬のないSARS類似の重症感染症と認識することが重要である。
初発症状は、発熱(98%)、咳(76%)、筋肉痛、全身倦怠などである。発症後8日で、22例(55%)が呼吸困難を訴えている。ICU入院や人工換気までは、発症後10.5日であり、急性感染症としては、比較的に長い経過で重症化することがわかる。日本では、病院へのアクセスが良いので、多くが発症早期に診断されると思われるが、早期症状が軽症であっても油断できない。
検査所見では、ウイルス感染の特徴である白血球減少症、リンパ球減少症が報告されている。プロカルシトニンは正常であった。入院時の肺炎が、細菌性ではなくて、ウイルス性であることがわかる。本論文では、2019-nCoV感染症の高率のICU入院率、致死率がSARSに類似していることが繰り返し述べられている。
医療関係者への感染も認められ、本論文では、2019-nCoV感染症患者の診察には空気予防策が必要で、N-95マスクなど個人用防護具の装備が強く勧奨されている。サージカルマスク着用だけの診察は危険である。現時点では、陰圧室を備えた環境での診療が、医療従事者への感染を防ぐために必須と筆者は考えている。なお本論文では、抗ウイルス薬の併用を治験していることが述べられている。
NEJM論文
New England Journal of Medicine誌にも、武漢の2019-nCoV肺炎の疫学的な検討論文が発表された(Qun Li, et al:N Engl J Med. 2020.)。
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2001316
2019年12月から本年1月の最初の425例を対象としている。患者の年齢は59歳(中央値)で、潜伏期間は平均5.2日(95%CI:4.1〜7.0)と報告された。また感染力を示す基本再生産数(Basic reproduction number、R0)は、2.2 (95%CI:1.4〜3.9)であった。
基本再生産数は今回、マスコミでも取り上げられているが、SARSやインフルエンザに近く、ワクチンや治療薬がない現在は、国内で流行が起きれば、多数の患者が発生することになる。マスク着用、手洗いを勧奨することは良いのだが、それで感染拡大を防げるという報道は誤りである。
さらに、同じNew England Journal of Medicine誌に、ドイツから潜伏期に感染した症例が報告されている。33歳の健康ドイツ人が1月24日に咳、発熱があり、一時39度まで発熱したが、26日には回復し1月27日に仕事に戻った。この時点で、2019-nCoVと診断された。この患者は1月20日、21日に上海から来たビジネスパートナーと会社で会った。ビジネスパートナーは、この会合時は無症状であり、翌日、ドイツから上海へ帰国の機内で発症し、1月26日に上海で2019-nCoVと確診された。1月28日には、ドイツで、さらに3名が発症した。
潜伏期といえども、発症の前日であり、感染性があるのは十分に理解できる。さらに2019-nCoVが強い感染力を持つことに驚かされる。上海からのビジネスパートナー(Index case)から、4名のドイツ人が発症している。また33歳のドイツ人の検体からは、仕事に戻った時点でも、108/mLと高濃度のコロナウイルスが検出されている。単純には比較できないが、成人のインフルエンザのウイルス排出に比べて、100倍か1000倍はウイルス量が高濃度である。臨床的に回復しても、かなりウイルスは残存し、感染性は残る可能性がある。
まとめ
世界保健機関(WHO)が、緊急事態を宣言するかどうかを検討した23日の会合で緊急事態を宣言しなかったことは、世界に対して、2019-nCoVは重大な感染症ではないという誤解を生み、各国の対策が遅れたのは残念であった。結局、1月30日、WHOは2019-nCoV流行を緊急事態と宣言した。
武漢の病院の状況を見ると、患者があふれ、まるで、新型インフルエンザの大流行を想像させる。実際、中国での2019-nCoV流行による混乱を見ると、1918年のスペインかぜ大流行と似た事態となっている。100年後の現代、医療体制の整備された中国の大都市でさえ、SARS類似の感染症が蔓延し、治療法も予防法もないとすれば、結局、スペインかぜ当時の混乱が再現されている。
米国でのスペインかぜ流行時、1918年10月から多くの都市で、学校、映画館、劇場、バー、教会までも閉鎖され、商店の開店時間も制限、集会も禁止された。衛生当局は、特に有効な対処法がないので、道路に消防車から絶え間なく水の散布を試みた。多くの町で、マスクを着用しないとバスなどの公共の交通機関には乗車できず、サンフランシスコではマスク着用を義務とし、従わない場合は逮捕された。全ての病院が満床となり、廊下に患者があふれ、多数の医師、看護師がインフルエンザに罹患した。患者を収容できないので、各地で、教会などの大きな建物は臨時の病院となった。これらの光景は、今、武漢周辺で実際に起きていることでもある。
中国では、2019-nCoVに対して、大規模な、そして徹底した都市の封鎖、外出禁止などが実施されている。ワクチンや治療薬がないからである。もしもインフルエンザ並みの感染力があり、SARS類似の重篤な疾患が流行すれば、わが国でも、手洗い、マスク着用だけではなく、感染地域からの入国禁止、集会、イベントの禁止など、強力な政府主導の対策が必要となるであろう。
スペインかぜでは、世界中で封鎖が実施されたが、大流行を抑えることはできず、世界で数千万人が死亡した。筆者が注目しているのは、武漢や中国各地で実施されている封鎖、外出禁止で2019-nCoV流行を抑えることができるかどうかである。
菅谷憲夫(神奈川県警友会けいゆう病院感染制御センターセンター長・小児科、慶應義塾大学医学部客員教授、WHO重症インフルエンザガイドライン委員)[新型コロナウイルス]