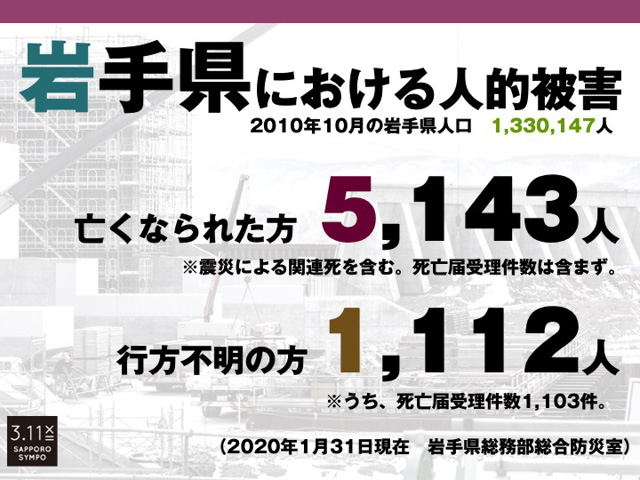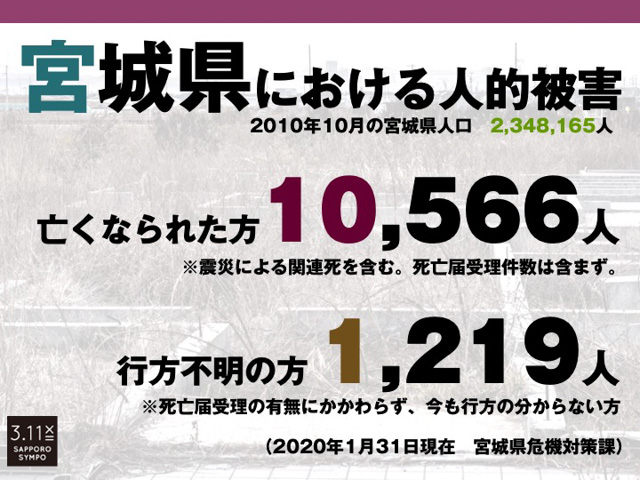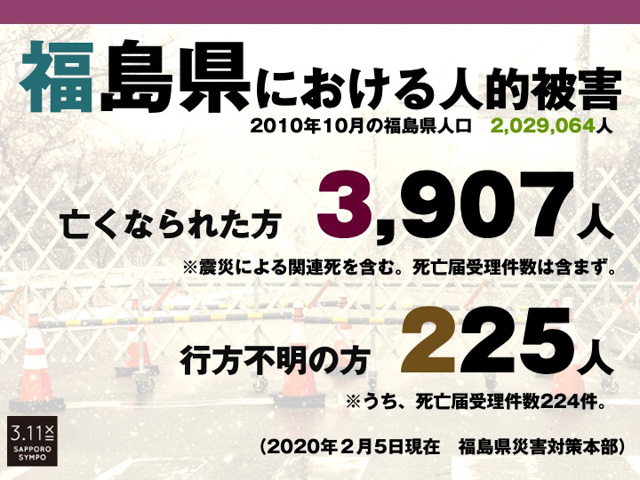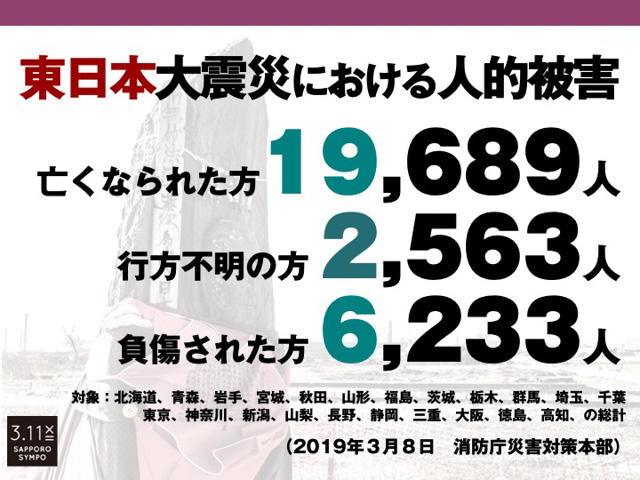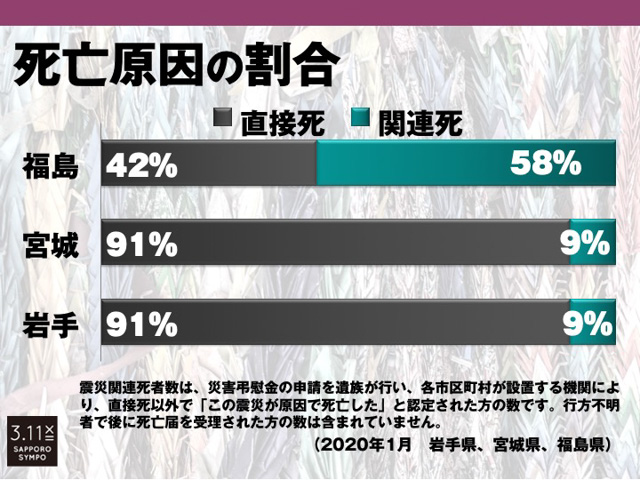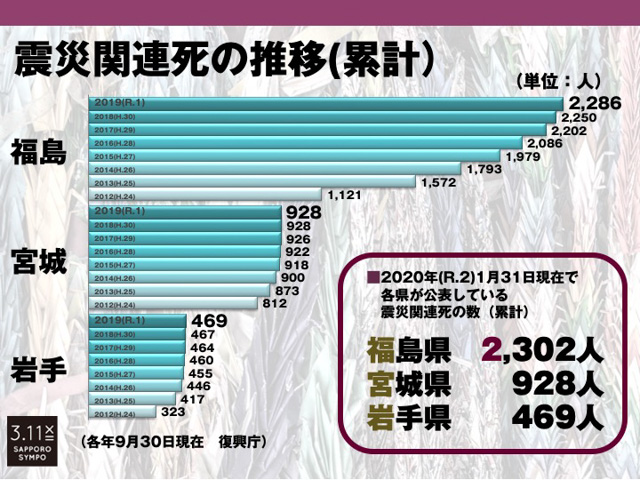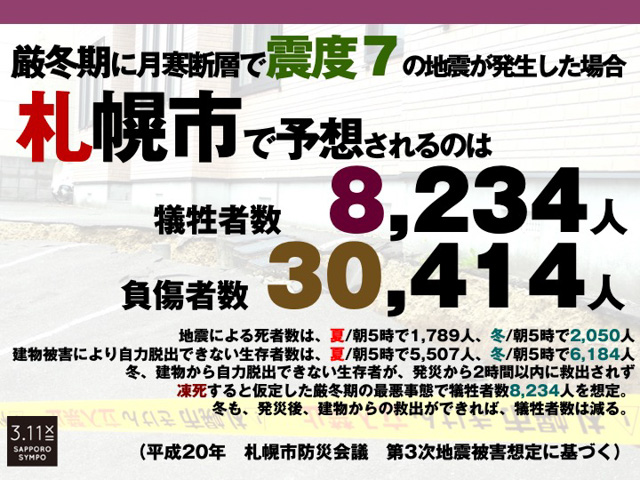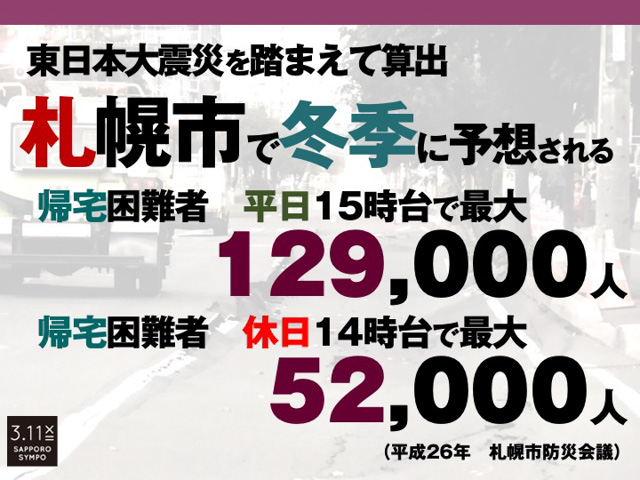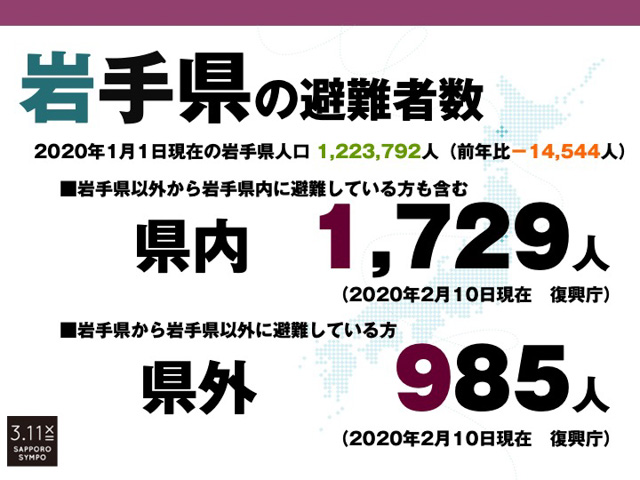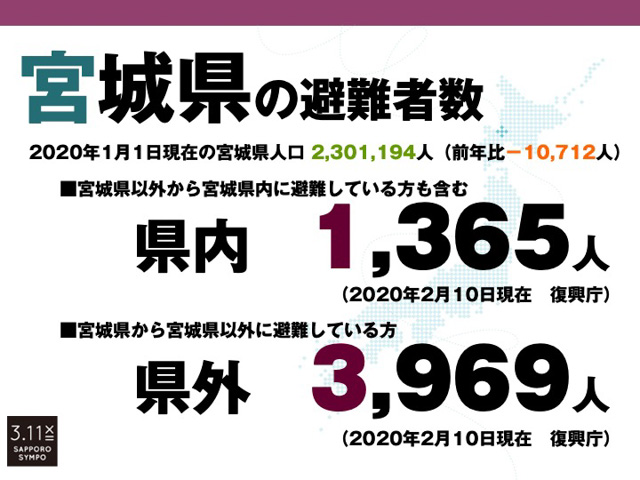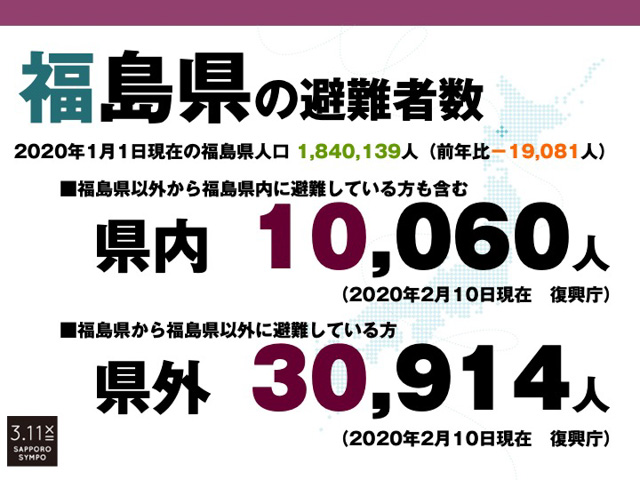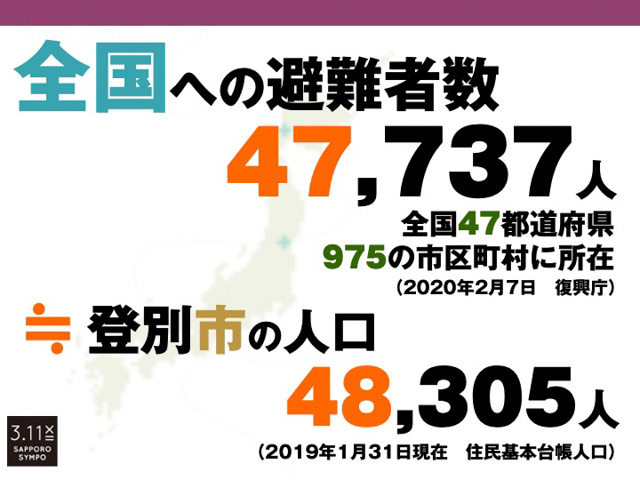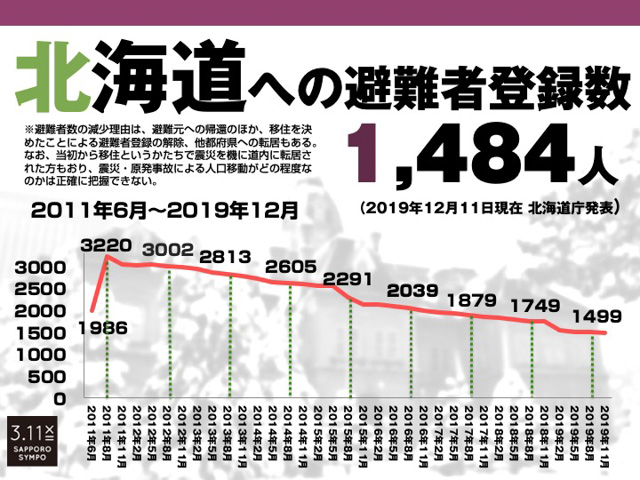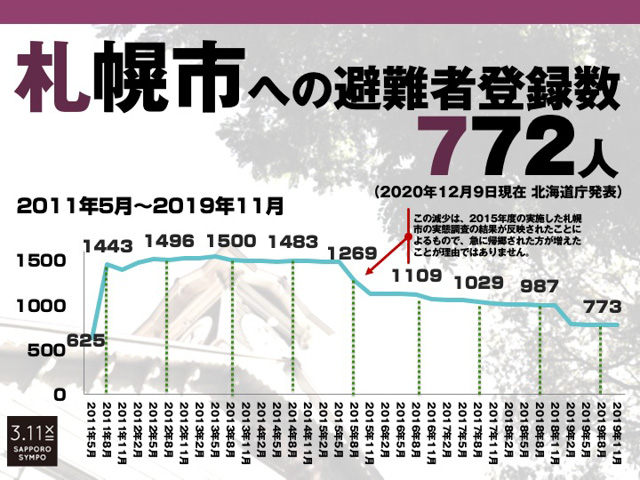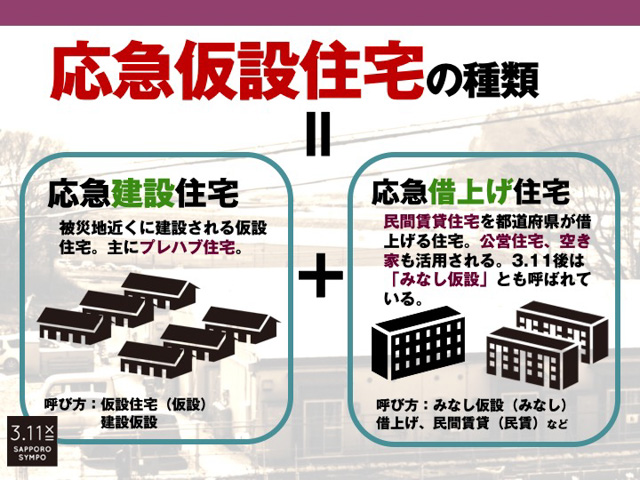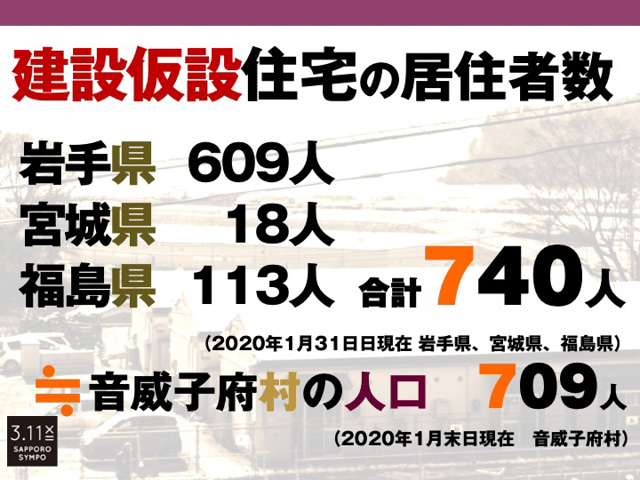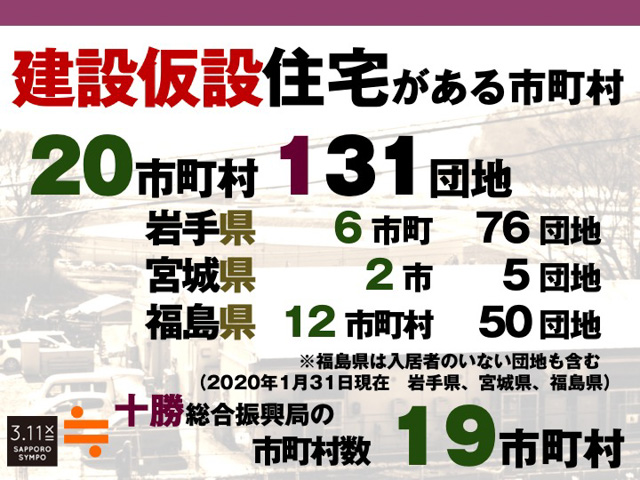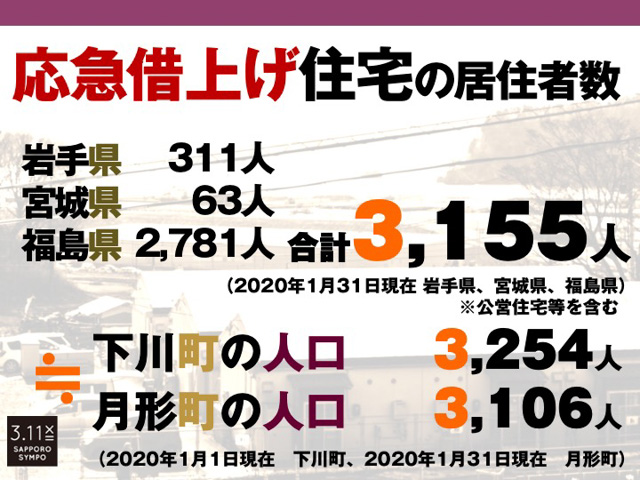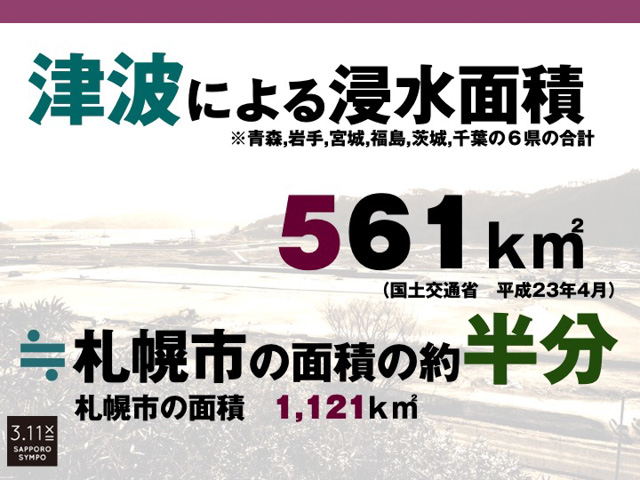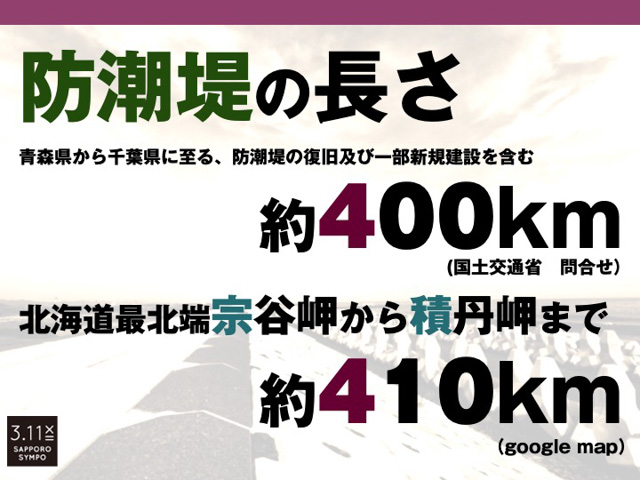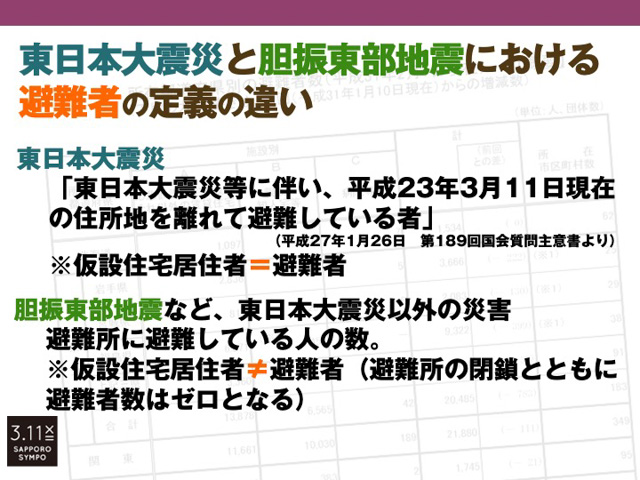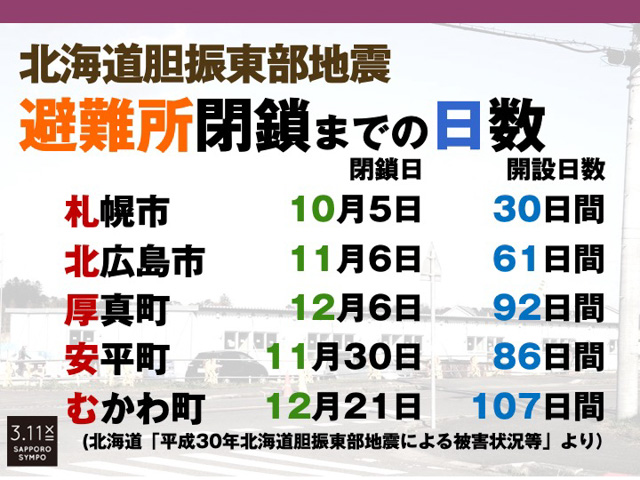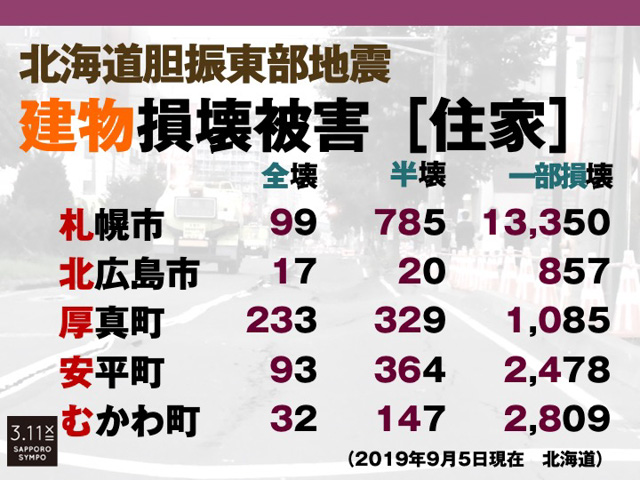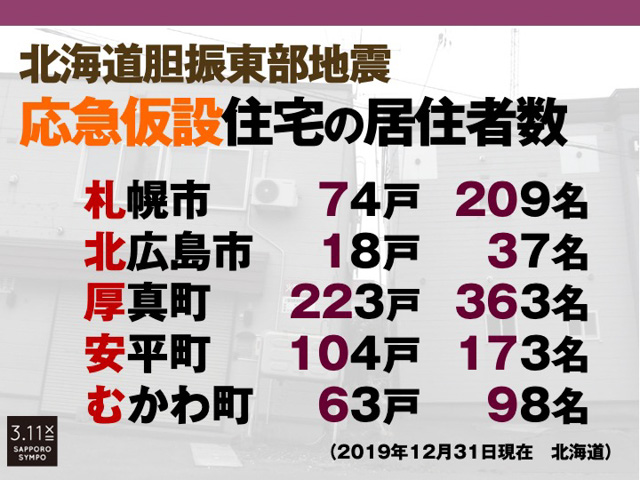この裁判は3年前、愛知県内で、父親が当時19歳の実の娘に性的暴行をした罪に問われたもので、1審の名古屋地方裁判所岡崎支部は娘の同意がなかったことは認めた一方、「相手が著しく抵抗できない状態につけ込んだ」という有罪の要件を満たしていないとして無罪を言い渡し、検察が控訴していました。
2審の名古屋高等裁判所では、検察が、娘は心理的・精神的に抵抗できない状態だったとして有罪とするよう求めた一方、被告の弁護士は改めて無罪を主張していました。
12日の判決で名古屋高等裁判所の堀内満裁判長は「被害者が中学2年生の頃から、意に反した性行為をくり返し受けてきたことや、経済的な負い目を感じていたことを踏まえれば、抵抗できない状態だったことは優に認められる」と指摘しました。
そして、「1審の判決は、有罪の要件である『抵抗できない状態』について、被害者の人格を完全に支配するような状態だということまで求めていて、要件を正当に解釈しなかった結果、誤った結論になっている」としました。
そのうえで「1審は、父親が子に対して継続的に行ってきた性的虐待の一環であるということを十分に評価していない。抵抗できない状態につけこみ、自分の性欲のはけ口にした卑劣な犯行で、被害者が受けた苦痛は極めて重大で深刻だ」と述べ、1審の無罪判決を取り消し、検察の求刑どおり、父親に懲役10年を言い渡しました。
この裁判をめぐっては、性暴力の被害者たちが、1審の無罪判決を受け、被害の実態が理解されていないとして各地で抗議のデモを行うなど波紋が広がり、2審の判断が注目されていました。
<section class="content--body">
有罪には2つの要件
日本の刑事裁判では、性行為を犯罪として処罰するには
▽「相手が同意していないこと」だけでなく、
▽「抵抗できない状態につけ込んだこと」が立証されなければなりません。
刑罰を科す対象が広がりすぎないようにするため特に悪質なケースを処罰するという趣旨で、
▽暴行や脅迫を加えたり
▽正常な判断ができない状況を利用したりして、
抵抗できない状態の相手に性行為をした場合に罪に問われます。
抵抗できない状態だったかどうかについては、「物理的・身体的」な原因があった場合だけでなく、
▽被害者が恐怖のあまり逆らえなかったり
▽拒否できないような立場や状況だったりするような「心理的・精神的」な
原因があった場合も含むとされています。
</section>
<section class="content--body">
1審が無罪とした理由
1審はなぜ無罪としたのか。
去年3月の判決で名古屋地方裁判所岡崎支部の鵜飼祐充裁判長は有罪の要件の1つ目の「娘が同意していなかった」ことについては認め、「極めて受け入れがたい性的虐待だった」としました。
また、父親は、娘が中学2年生の頃から性行為を繰り返し拒んだら暴力を振るうなど、父親という立場を利用して性的虐待を続けていたことも認め、「娘は抵抗する意思を奪われ継続的な性的虐待で精神的にも支配されていた」と指摘しました。
一方で、要件の2つ目の「抵抗できない状態につけ込んだ」とは認定せず、「拒否しようと思えばできる心理状態だったのに拒否しなかった」と判断しました。
その理由について1審は、娘が
▽過去に抵抗して拒んだことがあったことや、
▽一時、弟らに相談して性的暴行を受けないような対策をしていたこと、
▽アルバイト収入があり家を出て1人で暮らすことも検討していたことなどに触れ、
「人格を完全に支配され服従せざるをえない状態だったとは認めがたい」としました。
そして、「恐怖心から抵抗できなかった場合」や「行為に応じるほか選択肢がないと思い込まされていた場合」などと異なり、著しく抵抗できない状態には至っていなかったとして無罪を言い渡しました
。
</section>
<section class="content--body type-bottom">
無罪判決に広がった波紋
去年、性暴力をめぐって無罪判決が相次いだことを受け、被害者や支援者は「被害の実態が理解されていない」として各地で抗議のデモを始めました。
被害者に寄り添う気持ちを花で表現しようと「フラワーデモ」と名付けられ、偏見や二次被害を恐れて沈黙してきた被害者が、みずから声を上げる場にもなりました。
去年4月に東京と大阪で始まったデモは、その後、開催場所や人数を増やしながら毎月行われ、1年足らずで、延べ1万人以上が参加しました。
また、一連の無罪判決は、性暴力の被害者などが有罪の要件の撤廃などを求める動きにもつながりました。
去年5月、性暴力の被害者などでつくる団体は、「被害者が抵抗できたように思えるような状況でも、抵抗できない場合があることは心理学的に証明されている」として、法務省に対し、刑法の要件の見直しを求めました。
最高裁判所に対しては、「被害者が抵抗できなかったかどうかの認定にばらつきがある」として、被害者の心理について裁判官に研修を行うよう求めました
。
</section>
<section class="content--body type-bottom">
判決前に性暴力根絶訴え
2審の判決を前に、名古屋高等裁判所の前には、性暴力の被害の実態を反映した判決を求めようと、被害者や支援者およそ30人が花を手に集まり、「性暴力は許さない」などと書いたパネルを掲げ、被害の根絶を訴えました
。
</section>
<section class="content--body">
被害者弁護人「判決で初めて涙が出た」
被害者の弁護人の岩城正光弁護士は「弁護士として30年余りたつが、判決で涙が出たのは今回が初めてです。被害者のつらかった気持ちが、1審では厚い司法の壁で受け入れられることはなかったが、きょうの判決は被害者の気持ちに沿った常識的かつ良識的なものだった」と話しました。
</section>
<section class="content--body">
専門家「妥当な判断」
元刑事裁判官で、早稲田大学大学院法務研究科の稗田雅洋教授は「1審判決は、有罪の要件にあてはまるかどうかをかなり限定的に解釈していたが、2審判決は、これまでの裁判の実務に従ったもので、妥当な判断だと思う」と話しています。
そのうえで「裁判官は、法律の解釈にあたって、幅広い人の意見に耳を傾け、常識的な判断ができるように努力していくべきだ」と指摘しています。
</section>
<section class="content--body">
新型ウイルス感染拡大予防で傍聴席に制限
名古屋高等裁判所は、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、12日の判決で、傍聴席の数を制限する対応をとりました。
12日の法廷の傍聴席は96ありますが、報道機関向けなどを除く83席について、傍聴者が隣り合わないよう、間に2席ずつ空席を設けることとし、一般の席数は23となりました。
裁判所によりますと、23席に対し207人が並び、抽せんの倍率は9倍だったということです。
</section>
<section class="content--body">
伊藤詩織さん「ようやく回復への道たどれる」
性暴力の被害を訴え、刑事手続きでは相手が不起訴になり、民事裁判の1審で被害が認められたジャーナリストの伊藤詩織さんは、「女性の受けた傷は変わりませんが、今回の判決で、ようやく回復への道がたどれるのではないかと思います。長い道のりだと思いますが、今回、私たちが受け取った、考えるきっかけになるさまざまなバトンを、しっかり受け止めなくてはいけないと思います」と話しました。
</section>
<section class="content--body">
具ゆりさん「同じような経験持つ人たちを勇気づける判決」
裁判を傍聴した性暴力の根絶を訴えるデモの名古屋での呼びかけ人、具ゆりさんは、「まずは被害者の女性に『よく頑張ったね』と言ってあげたい。あなたの後ろにいる、同じような経験を持つ人たちを勇気づける判決だったと伝えたい」と話しました。
</section>
<section class="content--body">
被害者団体代表「法曹界全体にジェンダーバイアス」
父親から性暴力を受けた経験のある被害者団体の代表の山本潤さんは12日の判決を傍聴したあと、「性的虐待を受けた人の心理に基づいて判決を下してくれたうえ、1審の判決を誤ったものだと言ってくれて、うれしく思いました」と話しました。
そのうえで、「もともと法曹界全体にジェンダーバイアスがかかっていると思っています。男性が中心になって作った法律が男性によって運用されています。性犯罪が理解されにくいものだということを裁判官は認識し、バイアスを排除して公正な裁判を実現させてほしい」と求めました。
</section>
<section class="content--body">
北原みのりさん「同じような被害受けている人たちに心強い判決」
裁判を傍聴した、性暴力の根絶を訴えるデモの呼びかけ人で、作家の北原みのりさんは「同じような被害を受けている人たちにとって心強い判決になると思う。この1年間で、性暴力とは、どういう犯罪なのか、被害者から見たら、どういう暴力なのかということを、被害者自身が声を上げることで理解が深まったと思う。社会の空気が変わったし、声を上げたのは、むだではなかったと感じた」と話しました。
そして、1審と2審で判断が分かれたことについて、「なぜ1審で、この判決が出なかったのかということを、これからも問うていきたい。全く同じ事実を認めながらも、2審で全く違う視点の判決が出たという点が、非常に画期的だった」と話していました。
</section>