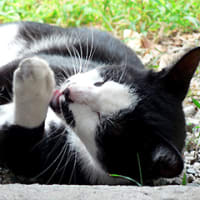1893年(明治26年)、当時鳥島には200人を越す労務者が従事していたが、島の一角に「玉置村」を設置し、「15年以上鳥島に定住し開拓事業に従事したものには500坪の土地を無償で与える」という口約束をしている。 しかし1902年(明治35年)鳥島は突如大爆発を起こし島に居た労務者125名全員が死亡、しかし半右衛門門一家は9年前にアホウドリの捕獲を島の責任者に任せ、東京に引き上げていて無事、 悪運が強いとしか言いようがない。 これで鳥島における半右衛門の事業は幕を下ろすが、15年間に殺戮したアホウドリの数は推定実に500万羽におよび、当然のことながら、鳥島における彼の事業はまったく評価されることなく現在に至っている。
大乱獲と噴火の結果、鳥島のアホウドリは絶滅したと思われていたが、昭和7年(1932年)の調査で僅かに50羽程度の生息が確認され、また2008年には推定2000羽まで繁殖が進んでいる。 しかし将来の噴火を考慮し、鳥島から南東に360km離れた小笠原諸島の聟島(むこじま)列島に少数の幼鳥を空輸し、移住・繁殖を進めているが、かってアホウドリが生息してた島々なので期待できそう。 鳥島での事業が軌道に乗っていた頃、半右衛門が次に眼をつけたのは「南大東島」。 沖縄本島の約400km東方に位置する大東諸島の島で、面積31平方kmサンゴ礁が隆起してできた周囲が断崖絶壁の孤島。 20世紀になるまで漂着者が着くだけの未開拓の地だったため、独自の生態系を保っていた。
僕がこの島を訪れたのは1500mの滑走路を備えた新空港が完成した1997年。 ここでの半右衛門は大東島諸島開発の偉人・英雄として銅像や記念碑まで建てられており、碑の側面には明治の地理学者・文化人の志賀重昂の文章で、「明治の一偉男子」と賞賛している。 しかし一方で鳥島の土地譲渡と同じく、この島の入植者にも同じ口約束が交わされていたという話も聞いた。 30年間開拓に従事すれば土地を無償で与えるという約束で、入植者にしてみればこの約束があったからこそ自作農の夢を見て、八丈島から1000キロも離れた無人島に入植する決心をしたのではないか・・・・この約束は結局反古にされ、口約束の有無が後にこの島をめぐる大きな問題へと発展していく。
南北大東島の貸与が許可されたのは1899年で半右衛門60歳、大実業家となった今、自ら開拓の指揮を執ることはなく入植者の乗った船を八丈で見送っただけで、事業は信頼する船長に任せる。 島の開墾作業は雑木や雑草を切り倒し、枯れた頃に焼くという焼畑農業で進められ、野菜やイモ類、綿や麦など何十種もの試作を重ねた結果、サトウキビが最も有望であることがわかり、島の主要産業に発展していく。 1902年頃になると島の事業も軌道に乗り道路や港の整備、今も島の観光名物となっている軽便鉄道(シュガートレイン)によるサトウキビ運搬も始められた。 また個人に土地が貸し与えられたが、島民が待ち望む譲渡ではなく小作人としてであり、作物の代金や賃金は玉置商会が発行する「玉置紙幣」で支払われたが、これは密出島を防ぐため。
1910年(明治43年)玉置半右衛門73歳で死去、創業者が亡くなると3人の息子達の出来が悪いこともあり、玉置王国は数奇な運命に翻弄される。 彼が死んで僅か6年後の1916年(大正5年)玉置商会は経営難から東洋精糖に事業売却、この時点で島の人口は3500人を超えている。 昭和に入ると東洋精糖が合併で大日本精糖に移り1945年(昭和20年)終戦。 そして1946年(昭和21年)一企業が支配する類い稀なる制度が、村制の施行により「東大東村」が生まれることで大きく変わる。 そして大日本精糖は本土に引き上げ、地元によって大東糖業社を設立される。 しかし土地は大日本製糖の所有のままで、島民との口約束は通用せず裁判にまで発展したが、それを解決したのはキャラウエイ高等弁務官の英断。 1964年(昭和39年)7月30日、農地や土地は無償で島民に譲渡される。 入植から64年、南大東島にとってこの日は歴史的な日となった。
大乱獲と噴火の結果、鳥島のアホウドリは絶滅したと思われていたが、昭和7年(1932年)の調査で僅かに50羽程度の生息が確認され、また2008年には推定2000羽まで繁殖が進んでいる。 しかし将来の噴火を考慮し、鳥島から南東に360km離れた小笠原諸島の聟島(むこじま)列島に少数の幼鳥を空輸し、移住・繁殖を進めているが、かってアホウドリが生息してた島々なので期待できそう。 鳥島での事業が軌道に乗っていた頃、半右衛門が次に眼をつけたのは「南大東島」。 沖縄本島の約400km東方に位置する大東諸島の島で、面積31平方kmサンゴ礁が隆起してできた周囲が断崖絶壁の孤島。 20世紀になるまで漂着者が着くだけの未開拓の地だったため、独自の生態系を保っていた。
僕がこの島を訪れたのは1500mの滑走路を備えた新空港が完成した1997年。 ここでの半右衛門は大東島諸島開発の偉人・英雄として銅像や記念碑まで建てられており、碑の側面には明治の地理学者・文化人の志賀重昂の文章で、「明治の一偉男子」と賞賛している。 しかし一方で鳥島の土地譲渡と同じく、この島の入植者にも同じ口約束が交わされていたという話も聞いた。 30年間開拓に従事すれば土地を無償で与えるという約束で、入植者にしてみればこの約束があったからこそ自作農の夢を見て、八丈島から1000キロも離れた無人島に入植する決心をしたのではないか・・・・この約束は結局反古にされ、口約束の有無が後にこの島をめぐる大きな問題へと発展していく。
南北大東島の貸与が許可されたのは1899年で半右衛門60歳、大実業家となった今、自ら開拓の指揮を執ることはなく入植者の乗った船を八丈で見送っただけで、事業は信頼する船長に任せる。 島の開墾作業は雑木や雑草を切り倒し、枯れた頃に焼くという焼畑農業で進められ、野菜やイモ類、綿や麦など何十種もの試作を重ねた結果、サトウキビが最も有望であることがわかり、島の主要産業に発展していく。 1902年頃になると島の事業も軌道に乗り道路や港の整備、今も島の観光名物となっている軽便鉄道(シュガートレイン)によるサトウキビ運搬も始められた。 また個人に土地が貸し与えられたが、島民が待ち望む譲渡ではなく小作人としてであり、作物の代金や賃金は玉置商会が発行する「玉置紙幣」で支払われたが、これは密出島を防ぐため。
1910年(明治43年)玉置半右衛門73歳で死去、創業者が亡くなると3人の息子達の出来が悪いこともあり、玉置王国は数奇な運命に翻弄される。 彼が死んで僅か6年後の1916年(大正5年)玉置商会は経営難から東洋精糖に事業売却、この時点で島の人口は3500人を超えている。 昭和に入ると東洋精糖が合併で大日本精糖に移り1945年(昭和20年)終戦。 そして1946年(昭和21年)一企業が支配する類い稀なる制度が、村制の施行により「東大東村」が生まれることで大きく変わる。 そして大日本精糖は本土に引き上げ、地元によって大東糖業社を設立される。 しかし土地は大日本製糖の所有のままで、島民との口約束は通用せず裁判にまで発展したが、それを解決したのはキャラウエイ高等弁務官の英断。 1964年(昭和39年)7月30日、農地や土地は無償で島民に譲渡される。 入植から64年、南大東島にとってこの日は歴史的な日となった。